
「現在進行形で悩んでいます」というママの声も多数
今回のアンケートでは、中間反抗期のときのうまい接しかたや声かけについてお聞きしましたが、「逆に教えてほしい!」というママの声もたくさん寄せられました。
何もうまいこと対応出来ていないので、なんとかしたい……。
仏の心が必要なのでしょうか? みなさんの回答、ぜひぜひ知りたいですーーー!!
どう対応してよいかわからず、タイムリーに悩んでいます。参考にさせてください。
なんとかしたい! どう対応したらいいかわからない! ママたちの切実な思いがひしひしと伝わってきます。
アンガーマネジメントの本を読んで、こちらのマインドから変えようとしたものの、本どおりにはうまくいかないのが現実です。
自分のマインドから変えようと努力してみたというママ。まずは拍手を送りたいです! うまくいかなくても、努力する姿勢そのものが素晴らしいと思います。
良くないと分かってますが、「なんでそんないいかたするの?」と毎回キレてしまう。いい結果になったことはありません。助けてください。
頭ではわかっていても、感情が先に出てしまう。そんな葛藤を抱えるママも多いのではないでしょうか。
先輩ママから届いた、あたたかいアドバイス&エール
最後に、先輩ママから届いたあたたかいアドバイス&エールをご紹介します。
5年生になって長男はびっくりするくらい落ち着いたんです。なので、終わりは来るし、そういうお年ごろなのねーと割り切ったほうが楽かもしれません。
そういう時期だと思って、受け流すしかないかと。でもあまりに酷いときは、怒ってしまいますよね。そんなときは赤ちゃんのころの写真を見返してました。
先輩ママからの「終わりは来る」という言葉には説得力があります。今は大変でも、これは誰しもがとおる成長の一過程。そう割り切ることで、少し気持ちが軽くなります。
怒ってしまった日は、赤ちゃんのころの写真を見返し、心を落ち着かせましょう。
「一緒に集中タイムしよー」と勉強や宿題のワードを出さないほうが怒りにくい気がする。親も一緒に本を読む、勉強するなどの姿勢が必要だが。あまりうるさくいわないが、やはりよい。
気に障りそうな言葉はいい換えて伝えるという、ママからのアドバイスです。ちょっとした言葉選びで、子どもの心にスッと届くこともあるようです。
今中間反抗期真っただなかといえばそうなのですが、母としては、あまり感情を出しすぎないのが1番だなと思います。「○○した?」と聞いて「してない」と返ってくると、「なんで!? 何回もいってるのに〜!!」と、怒りを返したくなるのですが、それをすると、子どももイライラしちゃうと思います。我が家では、「いつ宿題するん?」とシンプルに問いかけて、「16時」「おっけー」みたいな、すべてシンプルな会話で終わらすと、親子とも、イライラも少なく、なおかつ約束も決めれるので、次に声かけするまでの猶予ができ、こちらもやたらと気にする手間が省かれると思います。
シンプルな会話で終わらせることで、余計な争いを避け、なおかつ次の声かけまでの余白も確保できる。親子双方の負担を減らしつつ、すぐにでも実践できる方法ですね。我が家でも今日から取りいれたいと思います。
座談会に参加した20歳のお子さんを持つ先輩ママからはより長期的な視点でのアドバイスも。
中間反抗期で親の姿勢をしっかり見せておくと、大きくなってからの反抗期がほとんどなく、子どものほうから相談してくるようになります。黙ってやるのではなく、親を説得しなさい、というようにいっていたので、自分のやりたいことを認めてもらうプレゼンをするようになりました。ちゃんとやれば親はうんといってくれる関係性を作っておくとよいです。大きくなってから反抗されると、力もあるしお金もあるし、どこかに行ってしまうので、小学校中学年までにやっておくことがおすすめです。
中間反抗期のあとは思春期の反抗期……、子育ては続いていくものです。親子の信頼関係という「土台」を、いまのうちにしっかり築いておくことが大切なのかもしれません。
中間反抗期は親子それぞれのペースで乗り越えよう
今回の調査では、8割以上のママが中間反抗期にストレスを感じていることがわかりました。いっぽうで、ストレスを感じながらも「どう接したらいいのか」を考え、工夫しながら寄り添っているママたちの姿も印象的でした。
座談会のママからは「思春期の反抗期って放っておくのがベストかなと思うのですが、中間反抗期はママの関わりを求めているけど反抗もしたい! という感じなのかな、と実体験を通して感じます」という声があったように、中間反抗期は「甘えたい」と「ほっといてほしい」が入り混じる複雑な時期なのかもしれません。
一筋縄ではいかないからこそ、親子の信頼関係を築く大きなチャンスでもあります。完璧な対応を目指さなくても、向き合おうとするその気持ちこそが、きっとお子さんの未来の土台となるはずです。
※基本的にアンケート回答の原文をそのまま記載しています。ただし文字数の都合上、一部抜粋や主旨を損なわない範囲の要約・編集を行っている箇所があります。(明らかな誤字等は修正のうえ記載)
コクリコとAnyMaMa LIFESTYLE.Labが協働で、子育て課題解決×読書文化を目指すプロジェクト「コクリコラボ」。
ママの社会復帰を支援するサービス「AnyMaMa(エニママ)」で活躍するママたちのリアルな声を集めながら、新たなサービスや取り組み、ライフスタイルのアイデアを生み出していきます。













![尊い!「初産の出産祝い」に贈りたい絵本 おすすめ3冊[子どもの本専門書店・店長]が選んだワケ](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/034/010/large/e9628861-8b69-458d-b5c8-90bee1bc0022.jpg?1755431245)














































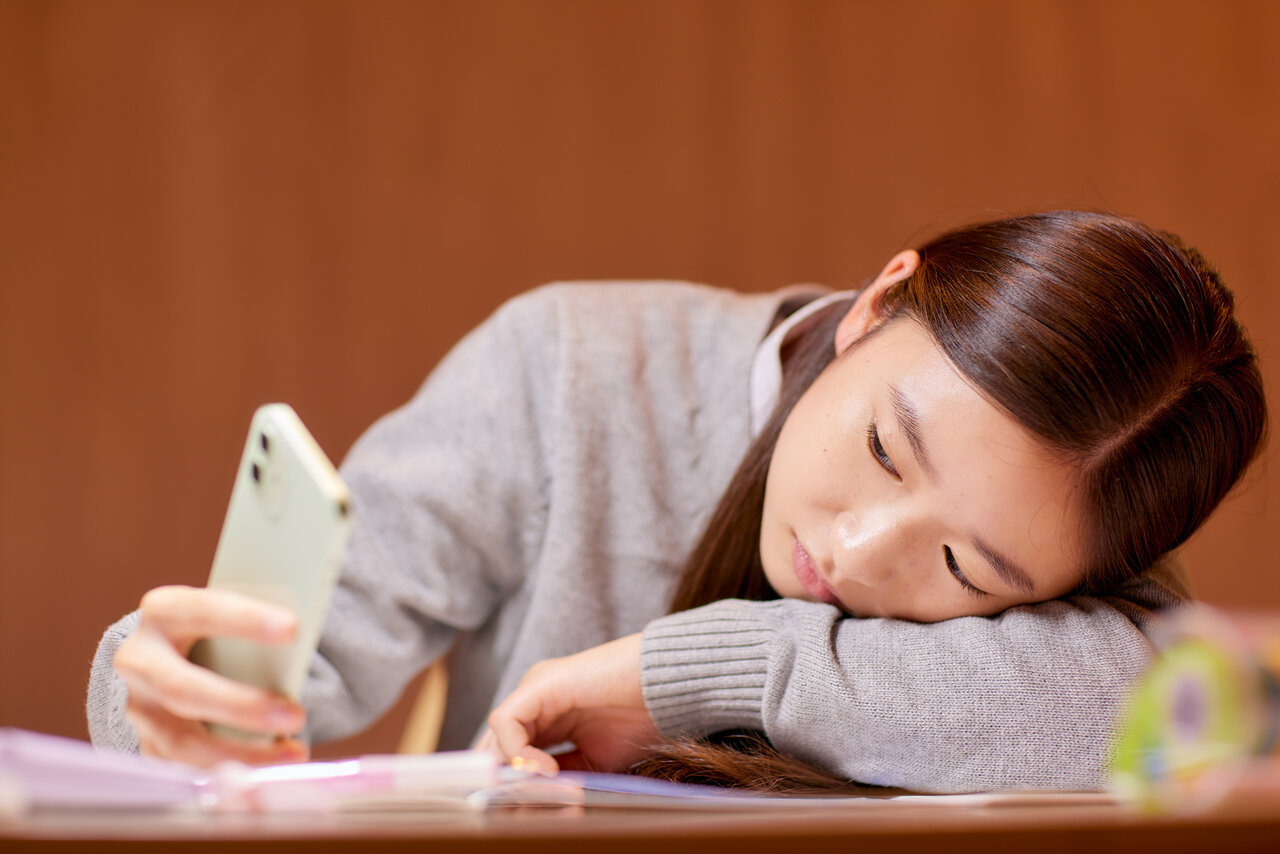






コクリコラボ
コクリコとAnyMaMa LIFESTYLE.Labが協働で、子育て課題解決×読書文化を目指すプロジェクト「コクリコラボ」。 ママの社会復帰を支援するサービス「AnyMaMa(エニママ)」で活躍するママたちのリアルな声を集めながら、新たなサービスや取り組み、ライフスタイルのアイデアを生み出していきます。 (Any MaMaについてはこちら:anymama.jp Twitter: @AnyMaMaJP )
コクリコとAnyMaMa LIFESTYLE.Labが協働で、子育て課題解決×読書文化を目指すプロジェクト「コクリコラボ」。 ママの社会復帰を支援するサービス「AnyMaMa(エニママ)」で活躍するママたちのリアルな声を集めながら、新たなサービスや取り組み、ライフスタイルのアイデアを生み出していきます。 (Any MaMaについてはこちら:anymama.jp Twitter: @AnyMaMaJP )