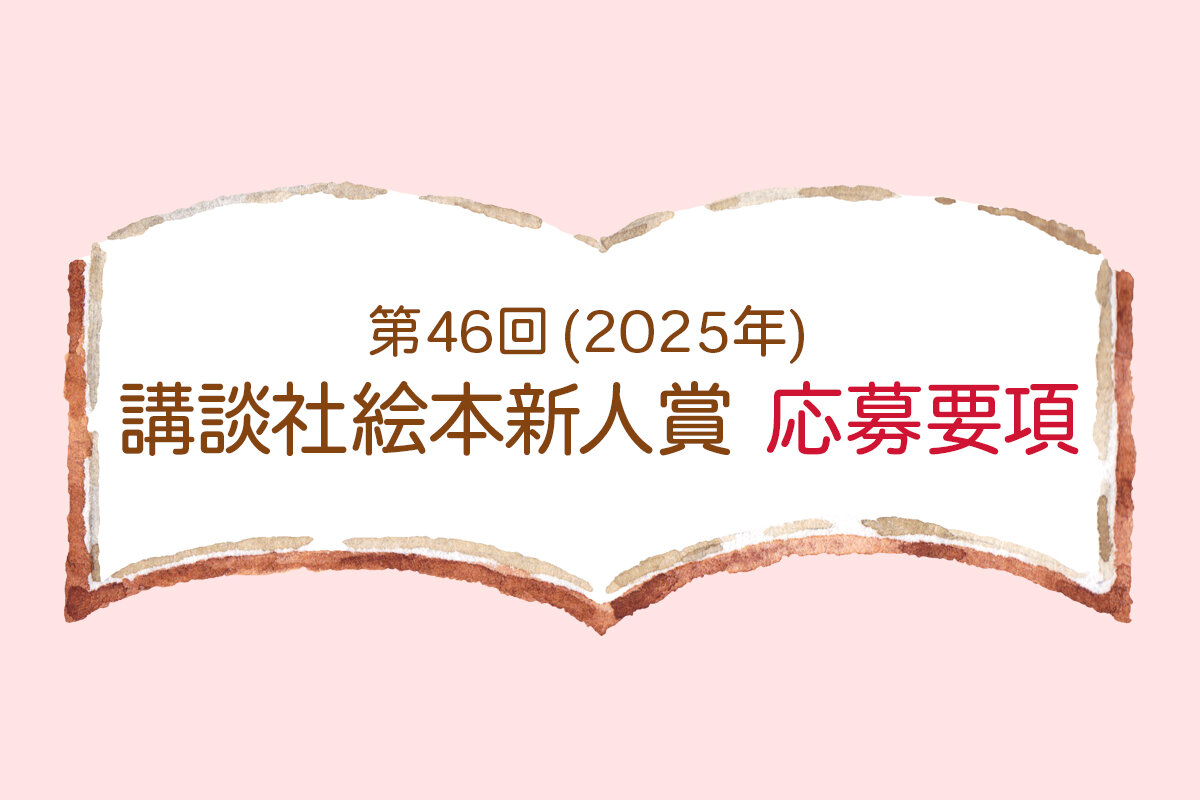第46回(2025年)講談社絵本新人賞 贈呈式のようす・受賞者の言葉・審査員の選評
2025.11.12

講談社絵本新人賞の贈呈式が行われました

会場には、選考委員の苅田澄子先生、たしろちさと先生、藤本ともひこ先生、三浦太郎先生。そして、受賞者の鹿毛トモタロウさん、かい のりひろさん、むぎはらさん、さとやまそらんさんが集まりました。


式の最後には、作品の原画を見ながら、選考委員の方々と受賞者のみなさんでご歓談。選考委員の方々から直接お話を聞くことのできる、貴重な時間になりました。




来年のご応募も、お待ちしております!
撮影/柏原力
受賞者の言葉
『オオカミさんのおうちになにがきた』 鹿毛トモタロウ(北海道)

『にんジャガ』 かい のりひろ(大阪府)

食べられずに忘れられたじゃがいも。それを見つけた少女が、そのじゃがいもをお母さんに見せます。お母さんはじゃがいもに忘れてしまったことを「ごめんなさい」と、きちんと謝ります。また、じゃがいもの頭から出た芽を見て、「かわいい」と言います。
話の展開の面白さだけでなく、こういうちょっとした一言も大切にしていきたいです。このたびは選出いただき、ありがとうございました。
『んはこんなふうにあそびます』 むぎはら(東京都)

このお話では、ぼくがひらがなの「ん」と出会います。んは「ん」としか喋りませんが、何を言いたいのかはちゃんとわかるようになっています。理解し合えない誰かと一緒に遊ぶことを、かろやかに描けていたらうれしいです。
昨年に続き2度目の佳作受賞です。ありがとうございました!
『おきないぞ』 さとやまそらん(福岡県)

このたびは素晴らしい評価をありがとうございました。
いつかこのお話がたくさんの人に届きますように。
審査員の先生方の選評(五十音順)
苅田澄子先生
佳作の『にんジャガ』は、ジャガイモの忍者が修行する姿がけなげでかわいくて、子どもはきっと応援したくなるはず。最後の忍術も鮮やか! 『んはこんなふうにあそびます』は「ん」という文字を主人公にした発想に驚きました。シンプルな絵にぴったりです。このお二人は前回も佳作を受賞されていて、安定感を感じました。『おきないぞ』はデフォルメがユニークで、おばけが本領発揮する前のあれこれを描くというアイディアも面白かったです。
選外にも惜しい……と思う作品がいくつもありました。自分の描きたいものが、子どもに楽しく伝わる表現になっているかどうかが大切なのかもしれません(自戒の念も込めて……)。
たしろちさと先生
『おきないぞ』は、くすっと笑って読みました。大きな場面移動のない内容ですが、読み進みながら視点の移動ができ、気持ちよくページを開いていくことができました。『にんジャガ』は、ジャガイモがなんとも味わい深いキャラクターで魅力的な作品でした。テンポよく楽しく読んで、でも最後はほのかに胸がキュンとなりました。『んはこんなふうにあそびます』は、発想の面白さにまず一票でした。ビビッドな色使いもこの作品に合っていて、気持ちのいい画面構成でした。
また、選外の作品の中にも心に残る作品がいくつもありました。『めぐちゃんのおしろ』は、きらりと光るセンスを感じる作品でした。『ニンナナンナ』は静かな夜の色が素敵でした。
藤本ともひこ先生
新人賞『オオカミさんのおうちになにがきた』は人物の感情を伝えるのに有効なコマ漫画の表現をうまく組み入れて、最後まで読ませ、気持ちいい着地。目で楽しい美しい絵。
「着想・着眼を絵本化する力」が賞との分かれ目。実はこの部分が容易ではない。ぼくも日々格闘している。『にんジャガ』構成もキャラも絵もよくできている。が。忍者色が弱い。淡々と見えた。理屈を越えていけるといい。『んはこんなふうにあそびます』さらりと気持ちいい画面処理は綺麗。が。「ん」のポテンシャルのアイデア発掘吟味不足は否めない。『おきないぞ』子どもの気持ちと、お化けの気持ちが物語の土台にあって素晴らしい。が。もっと奇想天外な起こし方があるかも。
そして決め手の「魔法の粉」が一振り必要だ。それが替えのきかない作家性だ。そこを読者は喜んでくれる。笑ってくれる。驚いてくれる。手を動かし続けて摑み取るしかない。
三浦太郎先生
『にんジャガ』は、昨年佳作を受賞された方の作品だとすぐにわかりました。前回よりもさらにスキルアップされ、もはやプロの作品と並ぶような安定感があります。なぜこの方がまだデビューされていないのか、不思議に思うほどです。
『んはこんなふうにあそびます』は、個人的にも好きな作品です。僕自身はこうした作品が作れないので、うらやましく思います。この方は、右から何かを入れると左から絵本になって出てくるような、不思議な才能をお持ちなのではなかろうか。
『おきないぞ』は、可愛らしい魅力にあふれた絵本だと感じました。このような作風は、作者の人柄や感覚からにじみ出るものだと思います。この感覚を大切にして、今後の制作に活かしてください。