

「ヒグラシ」の起源は日本最古の歌集「万葉集」! 涼しげで儚い鳴き声のヒグラシとはどんな昆虫?
【ちょっとマニアな生きもののふしぎ】昆虫研究家・伊藤弥寿彦先生が見つけた生きもののふしぎ (2/2) 1ページ目に戻る
2025.09.28
昆虫研究家:伊藤 弥寿彦
 2023年は、家の近くの公園で夜、ニイニイゼミとアブラゼミの羽化を観察し、静岡県でクマゼミの羽化を撮影して、それをMOVEのコラムで紹介しました。(こちら)
2023年は、家の近くの公園で夜、ニイニイゼミとアブラゼミの羽化を観察し、静岡県でクマゼミの羽化を撮影して、それをMOVEのコラムで紹介しました。(こちら)
2024年は、当時書いていた本の中でヒグラシの写真が必要になり、7月31日、撮影にチャレンジしてきました。どこに行けば良いのか、あては全然なかったのですが、とりあえず自分の勘を頼って、東京から海を渡って千葉県の袖ケ浦市を目指しました。気温35度近い炎天下の中ではヒグラシは見つからないと思い、家を出発したのは午後になってからでした。)

ヒグラシの声はこの森から響いていました。

ヒグラシは体長30~38mm。透明なはねに、緑で縁取られた茶色い胸、腹部は銀色っぽい毛に覆われてます。決して地味なセミとは思えないのですが、これが薄暗い森の中でヒノキの樹皮に止まっていると見事な「隠蔽色」になって、見つけるのは非常に難しいことが理解できました。

でもヒグラシにとってはここが絶好のすみかになっていたのでした。



【#ヒグラシ】薄暗い夜明けと夕暮れ時に鳴く

セミヤドリガは、幼虫がセミの体液を吸って成長するというまさかの肉食性のガです。セミヤドリガの成虫は、見た目は普通のガなのですが、(たぶん)オスがいません。単為生殖といって、メスが交尾することなく繁殖できるのです。

このガに寄生されたセミは死んでしまうのかというとそうではありません。セミはどうやら適当に体液を吸われているだけらしいのです。これは是非捕まえて、ガを成虫にしてみたい! と思いました。撮影後、そっとネットを近づけたのですが、あっという間にセミは飛び去ってしまいました。寄生されたセミは弱っていて簡単に捕まえられると思ったのですが、とんでもない。ピューッと飛んでいってしまったのでした。残念!
でもセミヤドリガについては、どうやってセミの体液を吸っているのか? どんなガの成虫になるのか? など疑問と知りたい欲求がフツフツと湧いてきたので、いつかまた改めて探してみたいと思っています。












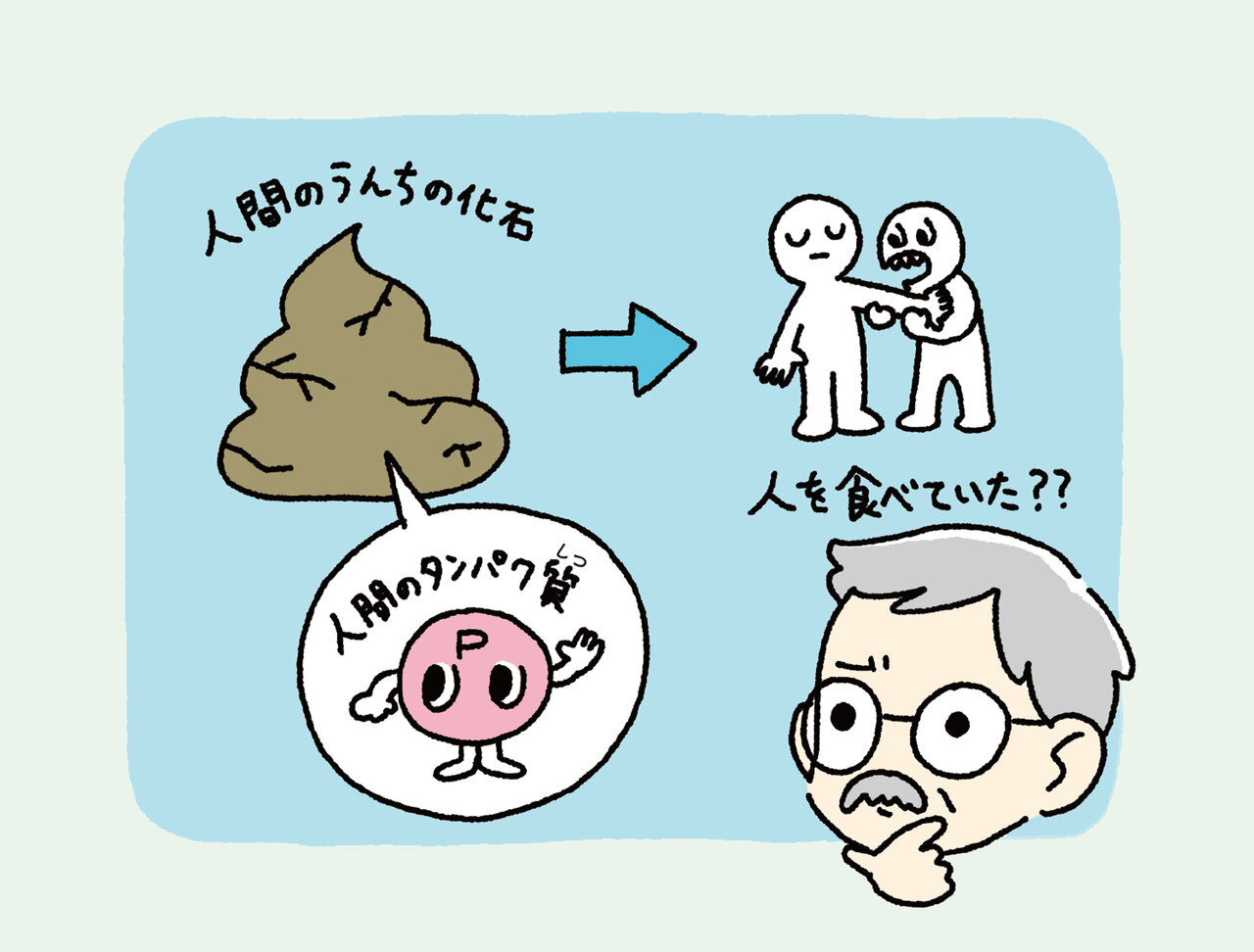










































































伊藤 弥寿彦
1963年東京都生まれ。学習院、ミネソタ州立大学(動物学)を経て、東海大学大学院で海洋生物を研究。20年以上にわたり自然番組ディレクター・昆虫研究家として世界中をめぐる。NHK「生きもの地球紀行」「ダーウィンが来た!」シリーズのほか、NHKスペシャル「明治神宮 不思議の森」「南極大紀行」MOVE「昆虫 新訂版」など作品多数。初代総理大臣・伊藤博文は曽祖父。
1963年東京都生まれ。学習院、ミネソタ州立大学(動物学)を経て、東海大学大学院で海洋生物を研究。20年以上にわたり自然番組ディレクター・昆虫研究家として世界中をめぐる。NHK「生きもの地球紀行」「ダーウィンが来た!」シリーズのほか、NHKスペシャル「明治神宮 不思議の森」「南極大紀行」MOVE「昆虫 新訂版」など作品多数。初代総理大臣・伊藤博文は曽祖父。