

発達障害の特性のある孫を育てる“祖父母”のストレスケア【後編 海外と国内の支援】〔言語聴覚士/社会福祉士〕が解説
#19 発達障害の特性のある子どもの「祖父母」への支援─後編~祖父母のストレスケア~ (2/2) 1ページ目に戻る
2025.11.21
言語聴覚士・社会福祉士:原 哲也
前回お話ししたように、発達障害の特性のある子の祖父母が子育てに大きな役割を担っているケースは実はたくさんあります。にもかかわらず、国内外問わず祖父母に焦点をあてた研究はとても少ないのです。
その中のひとつの研究では、自閉スペクトラム症の子どもの祖父母120名を対象に、祖父母がどんなことを求めているかを調査したところ、祖父母のニーズとしてもっとも多かったのが「情報がほしい」というものだったといいます。
〈参考: Needs of Grandparents of Preschool-Aged Children with ASD in Sweden. Rano Zakirova Engstrand, Lise Roll-Pettersson, Mara Westling Allodi, Tatja Hirvikoski Journal of autism and developmental disorders. 2020 Jun;50(6);1941-1957〉
孫を見る祖父母も疲労やストレスをかかえている
当該論文や他の見聞を考え合わせると、祖父母が求めている「情報」は、次のようなものだと考えられます。
①孫について感じる異常について、専門的な意見をききたい
②孫に接するとき、どうしたらいいのか?
③孫に自分は何をしてあげられるか?
④孫の親たちは全く気にしていないが、どうしたらいいのか?
⑤孫の将来はどうなるか?
これらの疑問に答えてくれる情報や情報先を知りたがっているということです。
アメリカの祖父母支援とは?
アメリカでは、祖父母対象のプログラムがかなり前から実践されています。いくつかをご紹介しましょう。
■テネシー大学児童発達センターのプログラム
障害のある孫を持つ祖父母らの心理的適応、祖父母の適切な対応による親のストレス軽減などを主な目的にして、障害幼児の祖父母が障害について学び、自身の感情を表出・共有できるような機会を週1回計22回行います。
このプログラムでは、ある祖父母のグループは、①まだ打ち解けない雰囲気の中で、リーダー役のソーシャルワーカーに各自の質問が向けられる段階から、②障害児が親に及ぼす影響や、親への協力の仕方について話し合う段階、そして、③本心の吐露と相互の励ましの段階、④絆が強まり会合が終結することへの不満が高じる一方、地域の活動への参加など各自が今後の展望を持つ段階へと変化したといいます。
このような参加者の変容を見ると、このプログラムを通じて祖父母は、障害のある子を育てる親へのサポートについて学ぶと同時に、祖父母という立場の心理をメンバー間でシェアすることで、同じ立場の絆を感じることができたのだろうと推察できます。これは祖父母にとって大きな支えになると思います。
■ワシントン大学児童発達・精神遅滞センターのプログラム
2ヵ月間隔で6回開催されるワークショップで、それぞれの気持ち(悲しみや失望感、心配など)や経験、知識を共有したり、抱える問題の解決法を話し合います。
このワークショップでは、子ども(孫)の障害や教育、福祉制度などをゲスト(医者、セラピスト、障害児の親など)から知ることで、祖父母は子どもやその家族のよりよき支援者になれるだろうという考えのもと開かれています。
ワークショップには、ファシリテーターがいて、参加者の考えを受け止め理解しつつ、参加者が自分の思いをより的確・明瞭に話せるように促し、グループの共通の思いや問題、関心事について参加者同士が主体的に考え合えるように促します。
■ニューヨーク貧困層の支援プログラム
ニューヨーク市でも貧困層を対象に祖父母への支援プログラムが行われました。対象は両親の離婚などの理由から親の代わりに障害児を育てている祖父母です。
祖父母は、各種の障害、サービスの入手法、孫の教育、接し方、問題行動、権利擁護、将来設計等について、2週ごとに6回学びます。そのプログラム実施日には祖父母の代わりに孫を世話するサービスを提供し、また、祖父母が会場まで往復するのに付き添いが手配されました。
このような配慮の中でプログラムに参加した祖父母は、抑鬱(よくうつ)傾向の緩和、家族に生じた問題への対応力の向上、孫育てへの自信の高まりが顕著に認められたということです。
発達障害の特性のある孫の子育てを祖父母が担っている場合、祖父母は疲労とストレスや孤独の中で孫育てをしていることが多いのです。そんな中でこれらの配慮は、祖父母の身体と心と現状に沿った優れたサービスだと言えます。
〈参考:『障害児の祖父母に対する支援についての展望』 今野和夫 秋田大学教育文化学部研究紀要教育科学部門66PP.45~54 2011 19)McCallion,P.&Kolomer,S.R.(2004)Controlled Evaluation of Support Groups for Grandparent Caregivers of Children With Developmental Disabilities and Delays.American Journal on Mental Retardation..Vol.109,No.5,352-361. 〉
日本における祖父母への専門的支援
一方日本では、孫の通院通所をサポートしたときに祖父母が、児童発達支援事業所や医療機関の専門家、行政の『ことばの相談』の窓口等にたずねるなどして情報収集するのがほとんどで、系統だった祖父母への専門的支援はまだあまりなされていないように思います。
しかし、私の取り組みを講演会や新聞記事などで知って、事業所に「子どもについて相談したい」と電話やメールをくださる方は、祖父母が断然多いのです。そのことを考えると、祖父母を対象とした施策や支援があってもいいのではないかと切に感じます。
例えば「祖父母」を対象とした冊子を作り、発達障害の特性のある孫の子育てについて、特性の基本的なことから、孫に祖父母ができること、孫を育てる親へのサポートなどを盛り込む。
さらにアメリカで行われているような、祖父母が感情を吐き出せるプログラムの実施、プログラムの実施にあたって祖父母が参加しやすいような配慮(上記の孫を世話するサービスや祖父母への付き添いなど)をするなど、援助すべきことはあると思います。
『昔からある遊び』のワークショップなどは祖父母ならではの経験と知恵が活きるものですし、祖父母だけが知っているという特別感は孫との絆を強くし、祖父母の心を軽くするかもしれません。
「祖父母が孫をみる」傾向は今後も続くでしょう。祖父母のために、そしてもちろん発達障害の特性のある子どものために、祖父母に対する支援サービスが必要だと思います。
最後に
今回は発達障害の特性のある子を孫に持つ祖父母への支援についてお伝えしました。次回(第20回)は、最終回です。
原哲也
一般社団法人WAKUWAKU PROJECT JAPAN代表理事・言語聴覚士・社会福祉士。
1966年生まれ、明治学院大学社会学部福祉学科卒業後、国立身体障害者リハビリテーションセンター学院・聴能言語専門職員養成課程修了。カナダ、東京、長野の障害児施設などで勤務。
2015年10月に、「発達障害のある子の家族を幸せにする」ことを志し、長野県諏訪市に、一般社団法人WAKUWAKU PROJECT JAPAN、児童発達支援事業所WAKUWAKUすたじおを設立。幼児期の療育、家族の相談に携わり、これまでに5000件以上の相談に対応。
著書に『発達障害の子の療育が全部わかる本』(講談社)、『発達障害のある子と家族が幸せになる方法~コミュニケーションが変わると子どもが育つ』(学苑社)などがある。

わが子が発達障害かもしれないと知ったとき、多くの方は「何をどうしたらいいのかわからない」と戸惑います。この本は、そうした保護者に向けて、18歳までの療育期を中心に、乳幼児期から生涯にわたって発達障害のある子に必要な情報を掲載しています。必要な支援を受けるためにも参考になる一冊です。




























































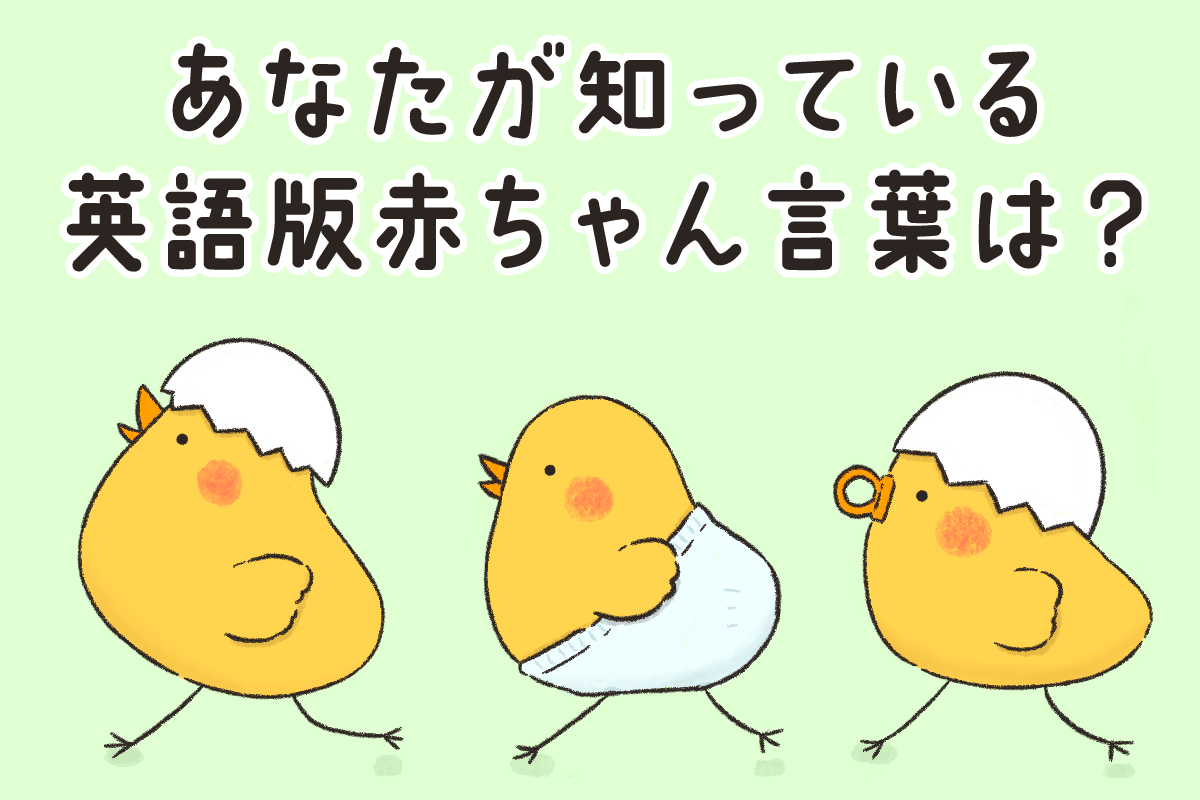


















































原 哲也
1966年生まれ、明治学院大学社会学部福祉学科卒業後、国立身体障害者リハビリテーションセンター学院・聴能言語専門職員養成課程修了。カナダ、東京、長野の障害児施設などで勤務。 2015年10月に、「発達障害のある子の家族を幸せにする」ことを志し、長野県諏訪市に、一般社団法人WAKUWAKU PROJECT JAPAN、児童発達支援事業所WAKUWAKUすたじおを設立。幼児期の療育、家族の相談に携わり、これまでに5000件以上の相談に対応。 著書に『発達障害の子の療育が全部わかる本』(講談社)、『発達障害のある子と家族が幸せになる方法~コミュニケーションが変わると子どもが育つ』(学苑社)などがある。 ●児童発達支援事業「WAKUWAKUすたじお」
1966年生まれ、明治学院大学社会学部福祉学科卒業後、国立身体障害者リハビリテーションセンター学院・聴能言語専門職員養成課程修了。カナダ、東京、長野の障害児施設などで勤務。 2015年10月に、「発達障害のある子の家族を幸せにする」ことを志し、長野県諏訪市に、一般社団法人WAKUWAKU PROJECT JAPAN、児童発達支援事業所WAKUWAKUすたじおを設立。幼児期の療育、家族の相談に携わり、これまでに5000件以上の相談に対応。 著書に『発達障害の子の療育が全部わかる本』(講談社)、『発達障害のある子と家族が幸せになる方法~コミュニケーションが変わると子どもが育つ』(学苑社)などがある。 ●児童発達支援事業「WAKUWAKUすたじお」