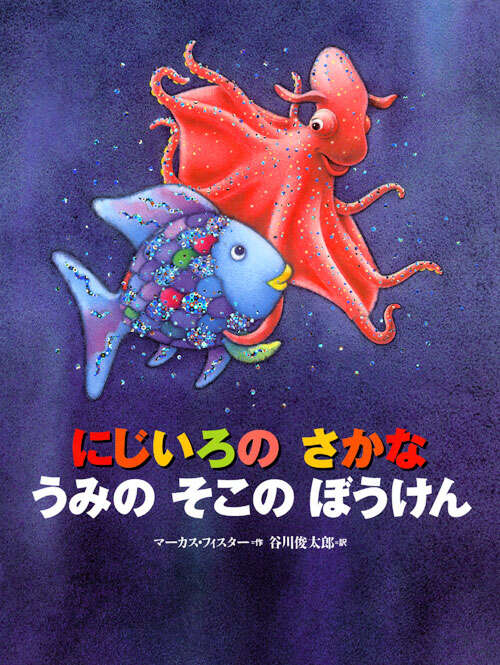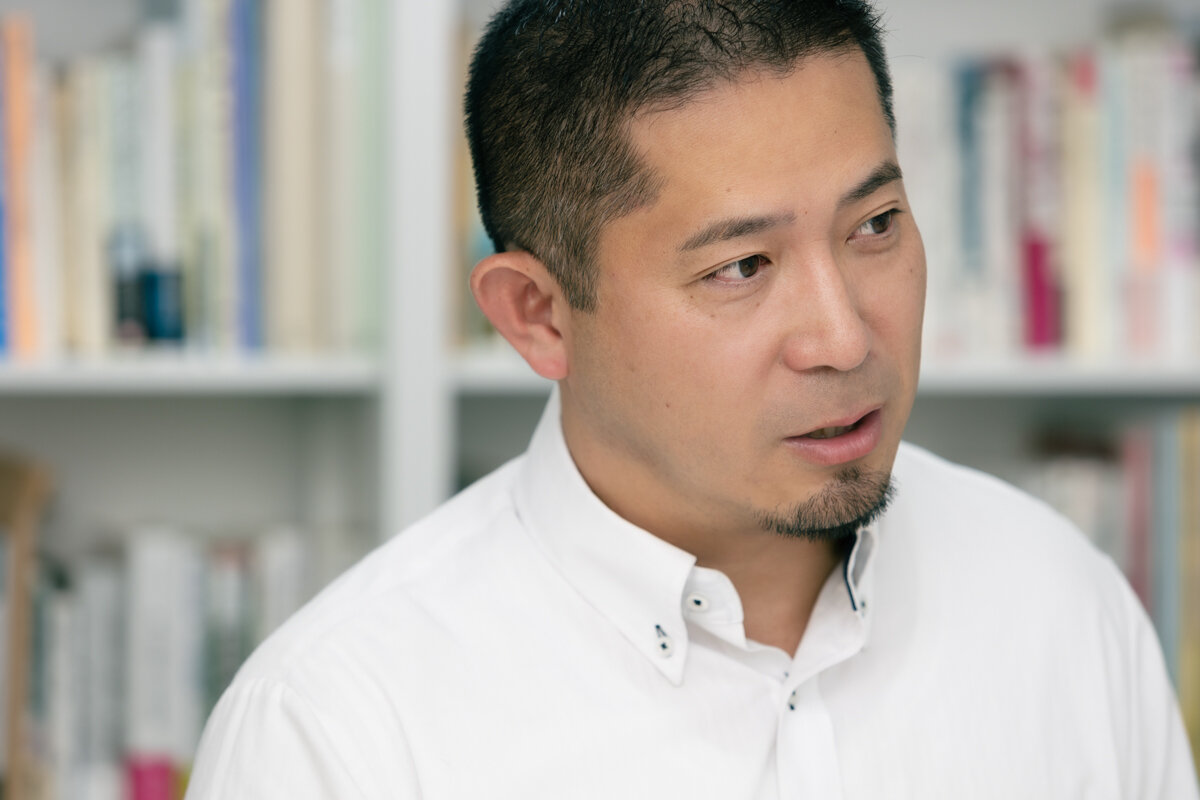「いじめ防止対策推進法」とは

いじめが報道されるたびに耳にする「いじめ防止対策推進法」。この法律があれば、学校に責任を問えるのでしょうか?
山下さんは「損害賠償のための法律ではなく、いじめへの調査や対応を学校に求めるための法律です」という点を強調します。
法律の目的は、子どもが「つらい」と感じた時点で学校が早めに調査し、必要な対応をとること。子どもの安全を守るためのルールです。
背景には、2011年の大津市のいじめ自殺事件があります。学校が事件直後早々に「いじめは関係ない」として調査をせず、大きな批判を受けました。この反省から、学校に早期対応を義務づける仕組みができたのです。
重大なケース(生命・心身・財産に重大な被害が生じた疑いがあるときや長期不登校など)では、学校が第三者委員会を設けて調査することも義務づけられています。
山下さん
「学校に求めるべき“最初の動き”は推進法に基づく早期調査と必要な対応です。調査の過程で明らかになった事実が、後に損害賠償などの判断につながることもありますが、この法律の目的は子どもを守るために学校を動かすことにあります」
「弁護士は、事実関係の整理や学校への働きかけを、子どもと保護者に助言の形で支援したり、深刻な事案では代理人として前面に出たりすることができます」
いじめの民事・刑事の法的手続きって、実際どうなの?
では、子どもがいじめの被害に遭ったら、どうすればよいのでしょうか。
【ネットでのいじめ被害の対応】
ネット上の書き込みの削除は、相手が特定できているなら、その相手に削除を直接求めたりSNS等の事業者の通報窓口に申し出て削除対応を求めます。
もちろん内容の性質によっては、すぐに対応すべきケースもあります。
性的画像・動画の拡散など悪質で緊急性が高い場合は、警察や法務局の窓口、業界団体(一般社団法人セーファーインターネット協会など)への通報を急ぎましょう。
ネットでのいじめの加害者に損害賠償などを求めるにあたり、投稿者が不明なときは、「発信者情報開示」という手続きがあります。
--------------------------------------
【発信者情報開示とは?】
ネット上で誹謗中傷などの被害を受けたとき、投稿者が誰か分からない場合に使える法的な手続きです。
●何をするの?
サイト運営者やプロバイダ(インターネット接続業者)に対して、投稿者の情報(IPアドレス、氏名、住所など)を開示してもらうよう求める仕組み。
●法律はどう変わった?
2022年10月に法律が改正され、「発信者情報開示命令」という新しい裁判手続きができ、いままで2段階だった手続きが一本化されてスムーズになった。
●費用や期間は?
多くの場合、弁護士に依頼。費用は事案の内容や受任する弁護士によって異なる。期間は新しい裁判手続きでは3~6ヵ月ほどかかるのが一般的だが事案によってそれ以上かかる場合もある。
--------------------------------------
【民事・刑事の法的手続き】
いじめの加害者や学校を相手にした法的手続きというと、民事の「訴訟」(裁判)が真っ先に思い浮かびます。
しかし、訴訟は公開で行われ、書面でのやり取りや証言が必要。精神的なストレスも大きくなります。
実は、法的手続きの方法は訴訟だけではありません。他にも「調停」(裁判所での話し合い)や「弁護士会ADR」(裁判外の解決手続き)など、非公開で進められる柔らかい手段もあります。
山下さん
「調停は非公開で行われ、訴訟と比べると当事者のプライバシーも守られます。非公開の弁護士会ADRとは、裁判所の訴訟手続きによらずに民事上のトラブルを解決するための機関です」
「事案によっては訴訟以外のやり方で区切りをつけたほうが、負担が少ない場合もあります。他方で、調停は、事実関係に争いがある部分について裁判所が事実認定まではしない、話し合いがまとまらないときに判決のような裁判所の判断がないまま終了するなど、負担が少ない分、デメリットもあります」
「法的手続きをとるかとらないか、とるとしてどういう手続きをとるか、子ども本人がしっかり情報を得て考えることを、大人が尊重することが大事です」
また、実際、被害に遭った子ども自身が「訴えを起こしたい」と考え、法的手続きを進めていくうちに、転校して新しい生活を始めると、「これ以上加害者に関わって貴重な時間を失いたくない」と途中で区切りをつける場合もあるといいます。
山下さん
「心の整理をつけて未来に進めるようになるプロセス自体が、とても大切なことだと思います」
深刻ないじめでは、刑事事件として警察に被害届や告訴状を出して捜査してもらうことが必要な場合もあります。
もっとも、刑事責任が認められるハードルは民事事件よりも高いので、刑事手続きにするかどうかは慎重に検討すること、特に子ども本人にメリット・デメリットをきちんと説明して話し合うことが大切です。
なお、最近、法務省が発表した「侮辱罪の事例集」では、過去に侮辱罪の判決をうけた173の事例が閲覧できます。


















![バレンタインに贈りたい“チョコレートの絵本”3選[絵本の専門家が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/385/large/0902ef78-ec72-4a81-948f-950d8216c43c.jpg?1767757141)




![お年玉と一緒に贈りたい“お正月の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/022/large/68833581-f835-4688-a9fe-33fa7156917c.jpg?1764905096)