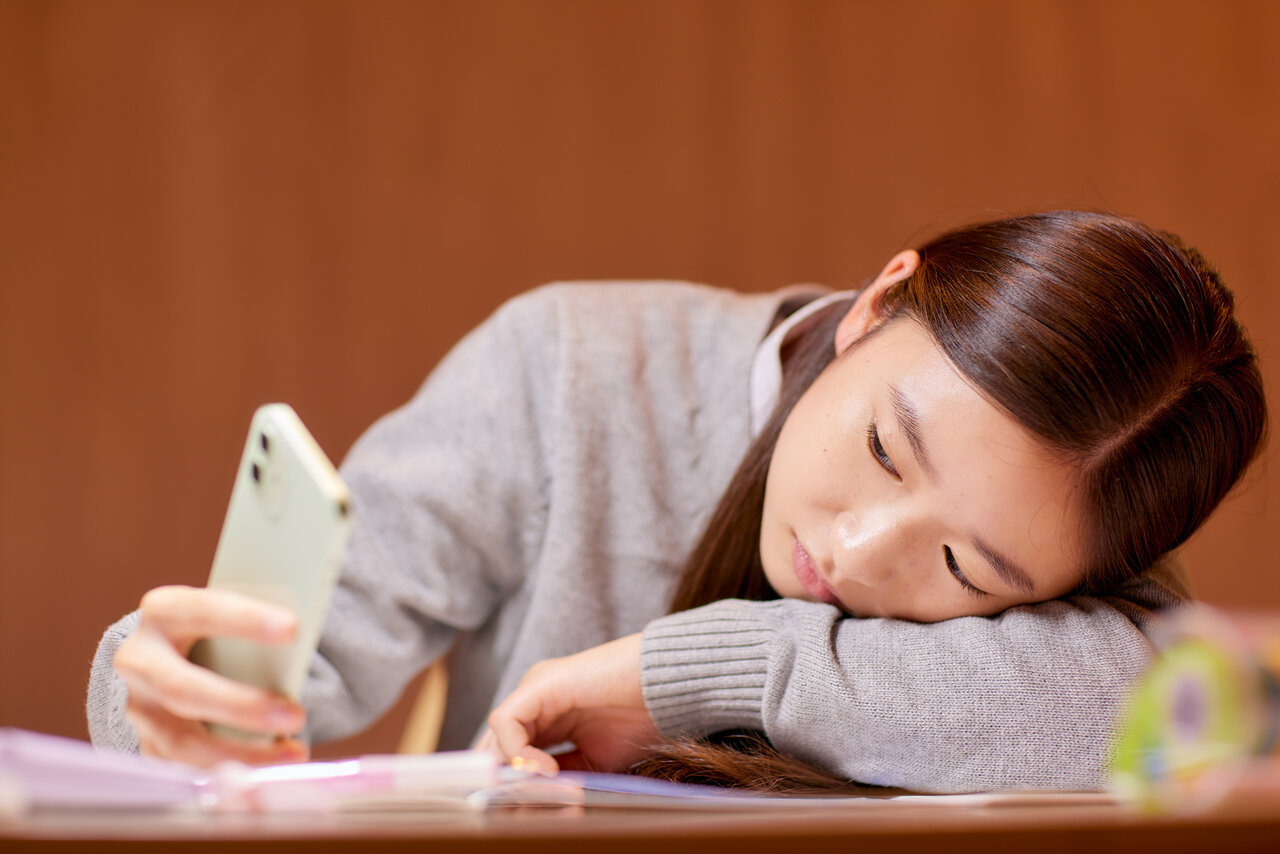どう乗り越えた? ママたちの中間反抗期の対策
ストレスを感じる中間反抗期。先輩ママたちはどのように乗り越えたのでしょうか。ここでは、ママたちから寄せられた中間反抗期の対策をご紹介します。
距離をおく
いったん距離をおくことで、子ども自身も冷静になれる時間をつくった。
これも成長の段階、と自分にいい聞かせていましたが、自分が疲れているときなどはカチンときて声を荒げていました。物理的な距離を取るのが一番だと思います。子どもが自分で社会に出ていくための準備期間だと思って。
多くのママが実践していたのが、「物理的に距離をおく」という方法でした。無理に向き合おうとせず、あえて少し離れて過ごすことで、言い合いを避けられたり、気持ちを整理できたりするようです。
家事を中断し、留守をパパに任せて近所のカフェへクールダウンしに行った。
ママも一人になれる時間があると、気持ちに余裕が生まれ、また笑顔で子どもと向き合えるようになりますね。パパのちょっとしたサポートが、大きな支えになります!
うるさくいわない
一度だけしかいわないからしっかり聞いてね、といってそれっきりいわないことを心がける。
つい口を出したくなるのが親心ですが、この時期は逆効果になることも。ときには「あえて何も言わない」勇気も必要です。
すべてひとつずつ、指摘していきたいですが、他人に迷惑をかけないことなら大目にみていることもありました。「ママもやったな~でも見つかった」や、イヤホンをいかに髪の毛にごまかしてかくして聞きながら登校したか、とか、学生のときドキドキしながら隠してやってたこと、そのときにしかドキドキしないこと、子ども本人に「大目にみるけど、他人に迷惑かけないこと。自分の命を脅かすことはしないでほしい」とだけ伝えています。
うるさくいわない、でも大切なことだけは伝える。親として大事にしたいスタンスですね。

話しあう
あなたはそう思うんだね。でもママはこう思うな。とアイメッセージを伝えるようにしました。
アイメッセージとは、「私」を主語にして、自分の気持ちを伝えるコミュニケーション方法です。「ママはこう感じたよ」と伝えることで、子どもは責められていると感じにくくなり、気持ちが届きやすくなるのかもしれません。
子どもが話を聞ける態勢が整うまでとにかく待ちます。顔を向き合って話せる姿勢ができたときにもう一度注意を投げかけたりしています。とてもストレスは感じていますが、間違いを伝えないことのほうがよりストレスが溜まってしまうので、伝えたいことはちゃんと伝えるように意識しています。
中間反抗期そのものよりも、いいたいことを我慢し続けるストレスのほうが辛い。これはきっと多くのママの本音なのではないでしょうか。
ママ以外の人から伝えてもらう
父親を挟んで、緩衝材をおくようにしている。
人を変えて話をしてもらった(もらっている)。たとえば、私のいうことをきかないときは、夫や祖父母に状況を説明して話してもらう。
毎日接しているママだと、「また怒られる」「口うるさいな」と、反発心が先に立ってしまうのもの。同じ内容でも、パパや祖父母、学校の先生など、いつもと違う相手だと、客観的に耳を傾けやすくなるのかもしれません。
毅然とした態度を取る
私自身が感情的になってしまうタイプで、子どもが反抗する態度が自分にそっくりで反省しました……。基本的には本人が落ち着くまで流しますが、いいかたがよくなかったり、ものにあたるときは感情を抑えて理性をもって注意するようにしています。感情的に𠮟るより、淡々と注意するほうが我が子には効くようです。
お友達や先生などにはしないこと。自分がされて嫌なことは相手が家族でもしてはいけないと伝え続けています。反抗されてもダメなものはダメ、ルールはルールと毅然とした態度で対応するように心がけています。
感情的にぶつかるのではなく、「ダメなことはダメ」と一貫した態度を示すこと。社会のルールや人との境界線を教えることは、子どもの成長のために親が果たすべき大切な役割です。
「現在進行形で悩んでいます」というママの声も多数
今回のアンケートでは、中間反抗期のときのうまい接しかたや声かけについて聞きましたが、「逆に教えてほしい!」というママの声もたくさん寄せられました。













![尊い!「初産の出産祝い」に贈りたい絵本 おすすめ3冊[子どもの本専門書店・店長]が選んだワケ](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/034/010/large/e9628861-8b69-458d-b5c8-90bee1bc0022.jpg?1755431245)