

【親子の脳の新事実】顔だけじゃなく脳も似ている! 脳科学で解明する 父・母・子どもの脳の「かたち」
脳科学から迫る親子の脳の「かたち」 #1 (3/3) 1ページ目に戻る
2025.11.06
東北大学学際科学フロンティア研究所助教、スマート・エイジング学際重点研究センター助教:松平 泉
脳の4種類の部分から親子の脳「かたち」を算出
──今回の研究では脳の「かたち」に注目されたとのことですが、脳の「かたち」とは具体的にはどのようなものなのでしょうか?
松平先生:脳の「かたち」をとらえる方法はいろいろありますが、今回の研究では、次の4種類の「かたち」の情報に注目しました。

親子の脳の類似性に関する研究で注目した、4種類の「かたち」の特徴
① 脳のシワを示す「脳回指数」
② 大脳皮質の広がりを表す「表面積」
③ 大脳皮質のぶ厚さを表す「皮質厚」
④ 脳の奥あたりに位置し、海馬などを含む「皮質下構造」の体積
4つとも脳の働きに関わる重要な特徴を持っている。ただし、これらの特徴の値が「大きい」=「頭がいい」というわけではなく、大きさが持つ意味は個人によって異なる。
4種類を採用した理由はいくつかありますが、①脳回指数と②表面積は、生まれる前などかなり早い段階で作られて変化が起こりにくい特徴があります。
一方、③皮質厚と④皮質下体積は、生まれてからの経験や環境の影響によって変化しやすい特徴を持っています。
変化が起こりにくいという特徴と、変化が起こりやすいという特徴を分析対象にすることで、脳をより多面的に理解することができるのです。

親子の脳を「シャッフル分析」 女の子のほうが両親に似ている場所が多い!
──父親、母親、子どもの3人1組の親子トリオ内でそれらを比較して、親子の脳が似ている・似ていないことがわかったのでしょうか。
松平先生:それだけで、わかったわけではないですね。たとえば、海馬の体積でお話しすると、お父さんの海馬の体積とお子さんの海馬の体積の2者の相関関係(ふたつのデータの間の関係の強さ)を見るだけでは、本当に「お父さんとお子さんだから似ている」のかどうか判断できません。
親子の脳が似ている・似ていないことを判断するには、少し複雑な分析が必要です。まず、実の親子(Aとaなど)のペアがたくさんいる状態で、「実の親子の相関係数」を算出します。相関係数とは、ふたつのデータ同士の関係の強さを表す数値のことです。
次に、親のデータをランダムにシャッフルして、他人の父親(Z)と子ども(a)といった他人同士のペアをたくさん作ります。そうして「他人同士の相関係数」を算出します。
「実の親子の相関係数」と「他人同士の相関係数」を比べて、前者が後者よりも充分に大きければ、「実のお父さんの海馬の体積が大きいと、その子どもの海馬の体積も大きい」という関係性、つまり「似ている」という解釈が得られるのです。

──親子といっても、性別は無視できないような……。異性親子と同性親子の組み合わせは何か関係したのでしょうか。
松平先生:はい、関係しました。父親×息子、父親×娘、母親×息子、母親×娘という4パターンそれぞれを分析すると、また別の傾向が見えてきました。
分析すると、子どもの性別で似ている・似ていないに男女差があったり、女の子のほうが両親に似ている場所が多いということもわかったんです。
─・─・─・─・─・─・─・─・─
異性親子と同性親子で脳の類似性に差が出たことがわかったのは、今までやっていそうでやっていなかった父・母・子の「親子トリオ」を研究対象にしたからにほかなりません。データを収集・分析するのは大変だったと松平先生はいいますが、苦労した分だけ得られたことは大きかったといえるでしょう。
次回は、親子の脳の類似性をさらに深掘り。なぜ男女で脳が似ている・似ていないに差が出るのか、脳が似ているということは行動や思考、性格が親と似ていることにつながるのか、などについて迫ります。
取材・文/梶原知恵
─◆─◆─◆─◆─◆─◆─

◆松平 泉(まつだいら いずみ)
東北大学学際科学フロンティア研究所助教、スマート・エイジング学際重点研究センター助教
専門は発達認知神経科学。『家族の脳科学』のプロジェクトにおいて、父・母・子の3人1組=親子トリオの脳や遺伝子からその関係性を分析し、人間の個性の成り立ちを解き明かす研究をしている。親子の脳の「かたち」が似ていることに関する成果は、世界初の研究として注目されている。
【脳科学から迫る親子の脳の「かたち」】の連載は、全2回。
続きを読む
※11月7日よりリンク有効
【関連書籍】
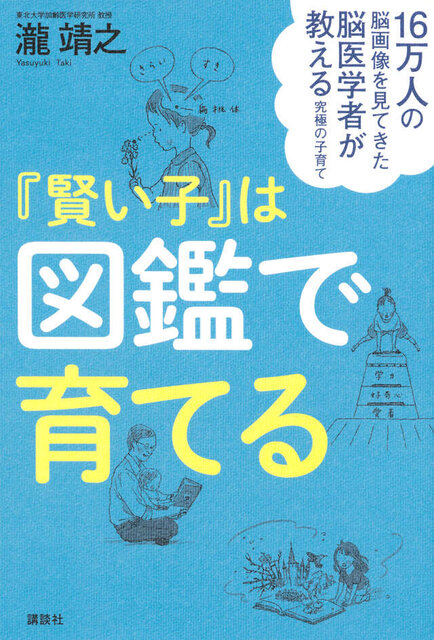
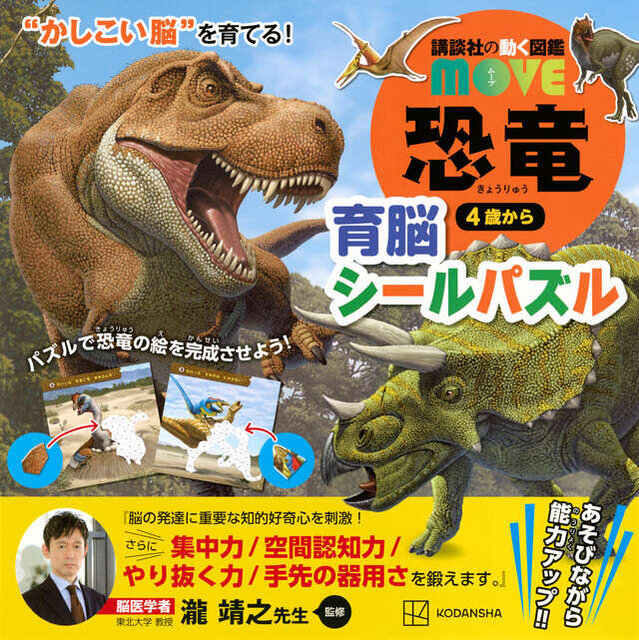

梶原 知恵
大学で児童文学を学ぶ。出版・広告・WEB制作の総合編集プロダクション、金融経済メディア、外資系IT企業のパートナー会社勤務を経て現在に。そのなかで書籍、雑誌、企業誌、フリーペーパー、Webコンテンツといった、さまざまな媒体を経験する。 現在は育児・教育からエンタメ、医療、料理、冠婚葬祭、金融、ITシステム情報まで、各媒体の企画・編集・執筆をワンストップで手がけている。趣味は観劇。特技は長唄。着付け師でもある。
大学で児童文学を学ぶ。出版・広告・WEB制作の総合編集プロダクション、金融経済メディア、外資系IT企業のパートナー会社勤務を経て現在に。そのなかで書籍、雑誌、企業誌、フリーペーパー、Webコンテンツといった、さまざまな媒体を経験する。 現在は育児・教育からエンタメ、医療、料理、冠婚葬祭、金融、ITシステム情報まで、各媒体の企画・編集・執筆をワンストップで手がけている。趣味は観劇。特技は長唄。着付け師でもある。




















![お年玉と一緒に贈りたい“お正月の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/022/large/68833581-f835-4688-a9fe-33fa7156917c.jpg?1764905096)

































































































松平 泉
東北大学学際科学フロンティア研究所助教、スマート・エイジング学際重点研究センター助教 専門は発達認知神経科学。『家族の脳科学』のプロジェクトにおいて、父・母・子の3人1組=親子トリオの脳や遺伝子からその関係性を分析し、人間の個性の成り立ちを解き明かす研究をしている。親子の脳の「かたち」が似ていることに関する成果は、世界初の研究として注目されている。 家族の脳科学
東北大学学際科学フロンティア研究所助教、スマート・エイジング学際重点研究センター助教 専門は発達認知神経科学。『家族の脳科学』のプロジェクトにおいて、父・母・子の3人1組=親子トリオの脳や遺伝子からその関係性を分析し、人間の個性の成り立ちを解き明かす研究をしている。親子の脳の「かたち」が似ていることに関する成果は、世界初の研究として注目されている。 家族の脳科学