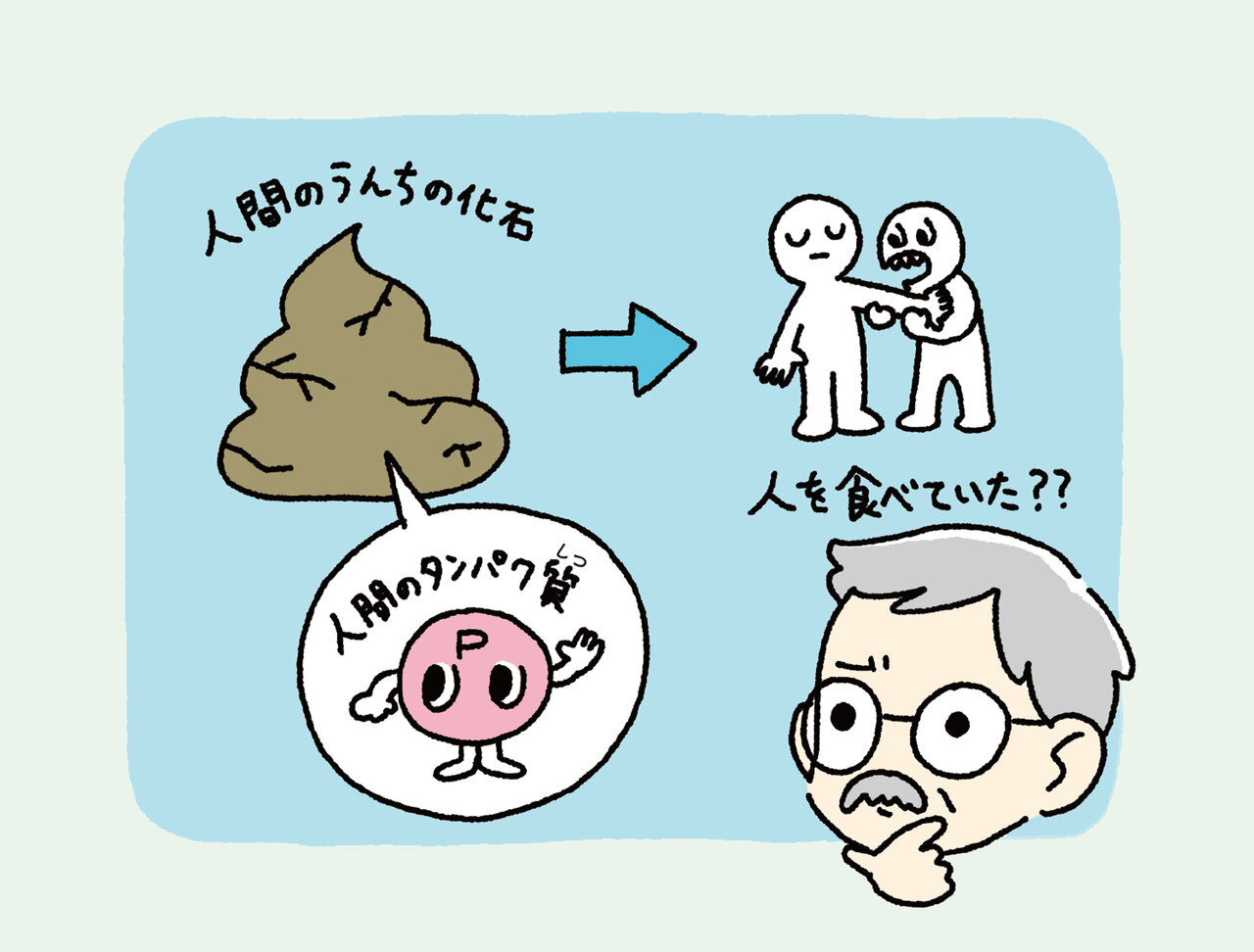

虫からキノコがはえるって、ほんとう?
生きものの謎に迫る!「生きものコラム」
2014.08.03
死んだ昆虫の体からキノコ!?

©️Takehiko Sato
それを『冬虫夏草(とうちゅうかそう)』といいます。
菌が生きた昆虫に寄生(きせい)して、殺し、その体を養分にしてキノコを生やします。
昆虫以外にも、クモやダニ、地下生のキノコであるツチダンゴに寄生するものもいます。
元々、冬虫夏草という名前は、中国で漢方薬として利用されてきた「シネンシストウチュウカソウ」を指すものでした。しかし、伝来した日本ではいつの間にか「昆虫から生えるキノコ」の総称として使われるようになったとされます。
世界からはおよそ500種が知らており、冬虫夏草の宝庫と言われる日本では、そのうちの約400種が見つかっています。冬虫夏草は、小さなものが多いですが、よくその姿を見てみると、奇妙で美しく自然の不思議を感じずにはいられません。
そんな冬虫夏草を見るには、どうしたらよいのでしょうか? 原生林に分け入らなければ見られないものもありますが、意外にも身近な場所で見られる種類もあります。
「クモタケ」や「オサムシタケ」は都市部の公園でも見られますし、身近な里山では、さまざまな冬虫夏草を見ることができます。
はじめは、なかなか見つけることが難しい冬虫夏草ですが、いくつか探すときのコツがあります。
まずは、発生時期に気をつけることです。冬虫夏草の発生は夏場、とくに梅雨の時期に多く、そのころがねらい目です。
次に、発生場所ですが、湿度の高い場所を好むので、森の中の沢沿いを探すとよいでしょう。
そして、冬虫夏草は、小さなものが多いですから、しゃがみこんだり、のぞきこんだりしながら、朽ち木や地面、葉の裏などを丁寧に見ていくことが大切です。
ぜひ皆さんも、冬虫夏草探しに挑戦してみてください。
参考文献:
日本冬虫夏草の会編著(2014)「冬虫夏草生態図鑑」誠文堂新光社
盛口満・安田守(2009)「冬虫夏草ハンドブック」文一総合出版
■関連:「植物」20ページ、191ページ






















































































