

とっても小さなカブトムシ、そのサイズの驚くべき理由とは?
【ちょっとマニアな季節の生きもの】サイエンスライター・柴田佳秀先生が見つけた生きもののふしぎ
2023.06.16
サイエンスライター:柴田 佳秀
小さなカブトムシ、そのサイズは遺伝ではない!
「昆虫酒場」とも呼ばれる木の幹からしみ出した樹液は、夜になるとカブトムシやクワガタはもちろん、ガやゴキブリなど、いろんな虫が集まってきてにぎわいます。反対にこわいスズメバチは、夜の樹液にはあまり来ないので安心です。昼間だとスズメバチがいるので近くで観察できないですからね。

普通のカブトムシは50mmくらいはありますから本当に小さい。いったいどうしてこんなに小さくなってしまったのでしょうか?

小さなカブトムシ君は昆虫酒場ではちょっと弱い存在です。エサを巡る戦いでも大きなカブトムシに負けてしまいますし、メスの奪い合いでも劣勢です。でも、観察を続けてみると、大きなカブトムシの隙を突いて、すばやく動きメスを獲得して交尾をしていました。フットワークを活かして懸命に生きているんですね。
「がんばれ!」とつい応援してしまいます。カブトムシがいたら、すぐに捕って虫かごに入れたくなりますが、ちょっとがまんして、虫たちのドラマを観察して見てはいかがでしょうか。とっても面白いのでおすすめです。












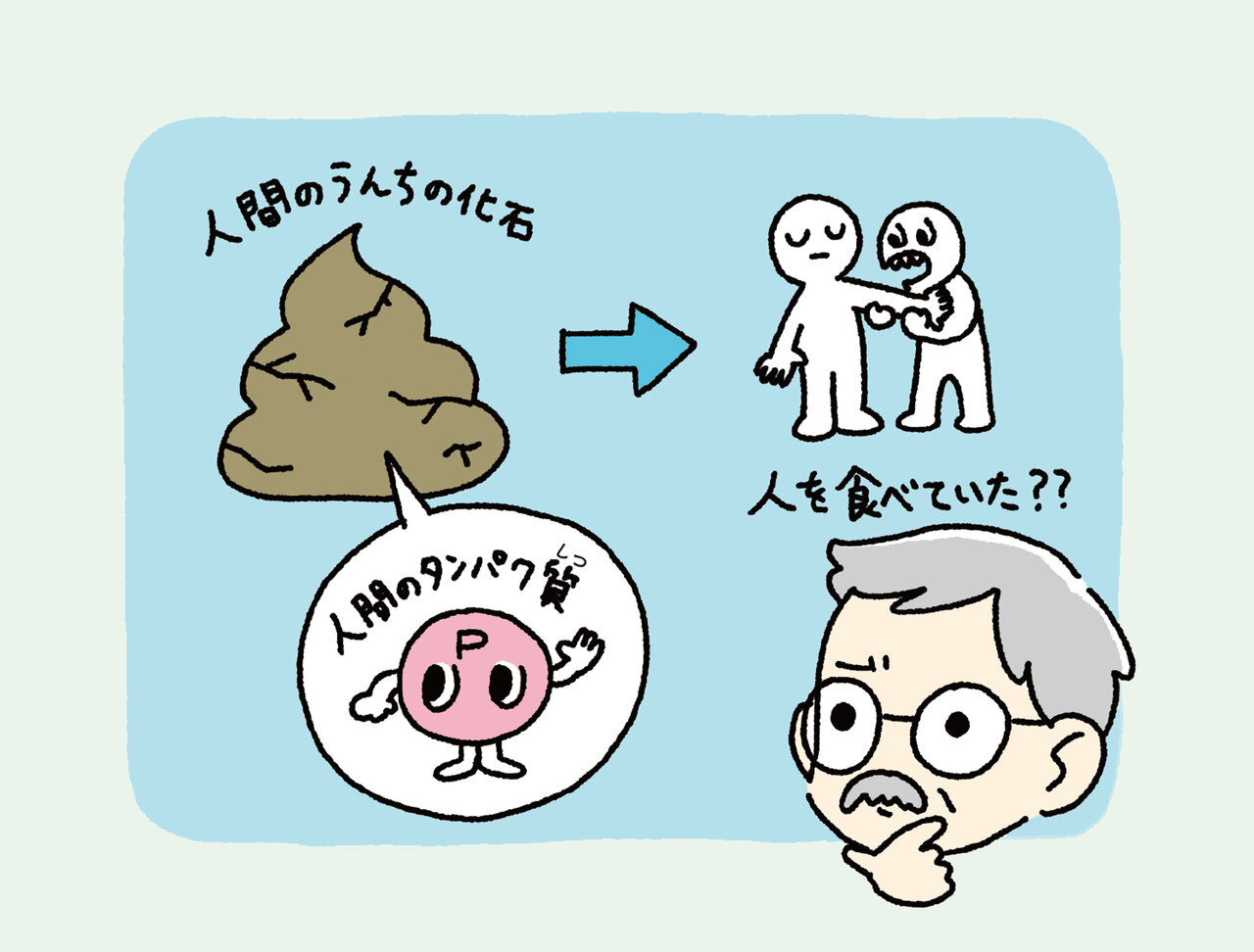
















































































柴田 佳秀
元ディレクターでNHK生きもの地球紀行などを制作。科学体験教室を幼稚園で実施中。著作にカラスの常識、講談社の図鑑MOVEシリーズの執筆など。BIRDER編集委員。都市鳥研究会幹事。科学技術ジャーナリスト会議会員。暦生活で連載中。MOVE「鳥」「危険生物 新訂版」「生きもののふしぎ 新訂版」等の執筆者。
元ディレクターでNHK生きもの地球紀行などを制作。科学体験教室を幼稚園で実施中。著作にカラスの常識、講談社の図鑑MOVEシリーズの執筆など。BIRDER編集委員。都市鳥研究会幹事。科学技術ジャーナリスト会議会員。暦生活で連載中。MOVE「鳥」「危険生物 新訂版」「生きもののふしぎ 新訂版」等の執筆者。