

「どう思う?」では子どもの“本当の言葉”は聞けない “国語力”が身につく問いを注目の教育者2名が伝授
国語教師・甲斐利恵子✕教育者・鳥羽和久対談#1「“言葉の力”の育て方」
2025.02.16

言葉の力は考え続けた末に身につく
鳥羽 最近は「言ってはいけないこと」に対する監視及び自己検閲が非常に強まりました。本来、言葉にいいも悪いもない。それは、手触りの現実のなかで、一人ひとりがつかみ取っていかなくてはならないものです。だからこそ、若いうちに「本当の言葉」を使ってみることはとても大切です。
甲斐 未知の言葉と出会ったときに、辞書を引いて、その意味をノートに書き写すだけでは、言葉の力はつかないですね。「言葉を学ぶ」というのは、先ほど鳥羽さんが言われたように、実際に使われる場面や、どんな属性の人たちが使う言葉なのかといった周辺情報も込みで知っていくことだから。実践の場で言葉を使って学ばないと、いつまでも言葉の力は身につきません。
鳥羽 いま、甲斐さんがおっしゃった「言葉が身につく」というのは、世間でいう「語彙力(ごいりょく)をつける」とは次元の違う話ですよね。これは『おやときどきこども』という本にも書いたことなんですが、言葉が血肉化しないというのは、例えば現代の子育ての難しさともつながっていると感じています。
*『おやときどきこども』鳥羽和久著。ナナロク社より2020年に刊行。
「なぜ子どもは親の話を聞かないのか」というのは、子育てにおける筆頭の悩みとしてたびたび語られることですが、それはいま、大人が語る言葉には身体性がともなっていないからでしょう。
なぜ、甲斐さんの言葉が子どもたちに届くのかと言えば、甲斐さんご自身が、単元の準備をすることを通して、勉強し続けている大人だからですよね。勉強し続けている身体が、その人の核になっていると子どもたちに伝わるからですよね。
勉強し続けるというのは、別の言い方をすると、変わり続けるということ。変わることを恐れない。でも、これができる人は限られているんですよ。普通は大人になったら、安定して生活したいのが当たり前です。
でも、子どもとかかわる大人は、どうしても変わり続けることが必要だと思うのです。一緒に勉強をするということは、一緒に変わっていくことなんじゃないでしょうか。
甲斐 昨年度(2023年)、沖縄戦を題材に授業をしました。沖縄戦の写真を見て感想を語り合ったり本や資料を読んだりして、短歌をつくり、最終的に随筆を書くという学習でした。
子どもたちも最初は尻込みするんです。「集団自決で、親が子どもを殺す気持ちなんてわかんないよ!」って。それでも、その状況に思いを寄せて考えていくことで、不自由な言葉が少しずつほどけていく。
自分の言葉とは心が動いたときに生まれるものだと思いますが、簡単には整った形で現れてくれないものです。ここで「言葉にできないほど悲しい出来事です」のように済ませてしまうと、言葉を生み出していく力から遠ざかってしまうように思います。
たどたどしくても、言葉にしてみる。これじゃない、これでもない、と考え続けているときに言葉の力は育つのではないでしょうか。こういう授業のときの子どもたちは、自分の心に生まれてくる情景や感情と真剣に向き合って言葉を探し、話しかけてきます。一緒に言葉を探す時間は、本当に大切な時間だと思っています。
●鳥羽和久(とば・かずひさ)PROFILE
教育者・作家。1976年福岡県生まれ。専門は日本文学・精神分析。大学院在学中の2002年に学習塾を開業。現在は、株式会社寺子屋ネット福岡代表取締役、学習塾「唐人町寺子屋」塾長、単位制高校「航空高校唐人町」校長、「オルタナティブスクールTERA」代表。著書多数。朝日新聞EduA教育相談員。
●甲斐利恵子(かい・りえこ)PROFILE
国語教師。福岡県生まれ。軽井沢風越学園スタッフ。東京都港区立赤坂中学など公立中学で38年間国語科の教員を経て、2021年に軽井沢風越学園に参画。光村図書中学校『国語』教科書編集委員などを歴任。著書に『国語授業づくりの基礎・基本 学びに向かう力を育む学習環境づくり』(共著・東洋館出版社)など。


甲斐 利恵子
福岡県生まれ。軽井沢風越学園スタッフ(7~9年生国語・9年生卒業探究担当)。学生時代から国語教師で国語教育研究家の、大村はま国語教室に学び続ける。東京都港区立赤坂中学など公立中学で38年間国語科の教員を経て、2021年に軽井沢風越学園に参画。 光村図書中学校『国語』教科書編集委員などを歴任。著書に『聞き手 話し手を育てる』『国語授業づくりの基礎・基本 学びに向かう力を育む学習環境づくり』(ともに共著・東洋館出版社)『子どもの情景』(光村教育図書)など。 ●軽井沢風越学園・甲斐利恵子先生紹介
福岡県生まれ。軽井沢風越学園スタッフ(7~9年生国語・9年生卒業探究担当)。学生時代から国語教師で国語教育研究家の、大村はま国語教室に学び続ける。東京都港区立赤坂中学など公立中学で38年間国語科の教員を経て、2021年に軽井沢風越学園に参画。 光村図書中学校『国語』教科書編集委員などを歴任。著書に『聞き手 話し手を育てる』『国語授業づくりの基礎・基本 学びに向かう力を育む学習環境づくり』(ともに共著・東洋館出版社)『子どもの情景』(光村教育図書)など。 ●軽井沢風越学園・甲斐利恵子先生紹介



















![【働くママの労働問題】「休憩時間はいらないから1時間早く退社したい!」これってできる?[社労士が回答]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/033/863/large/ce2347fc-d40d-4f17-a9be-b10df83ca08f.jpg?1754022044)

















































































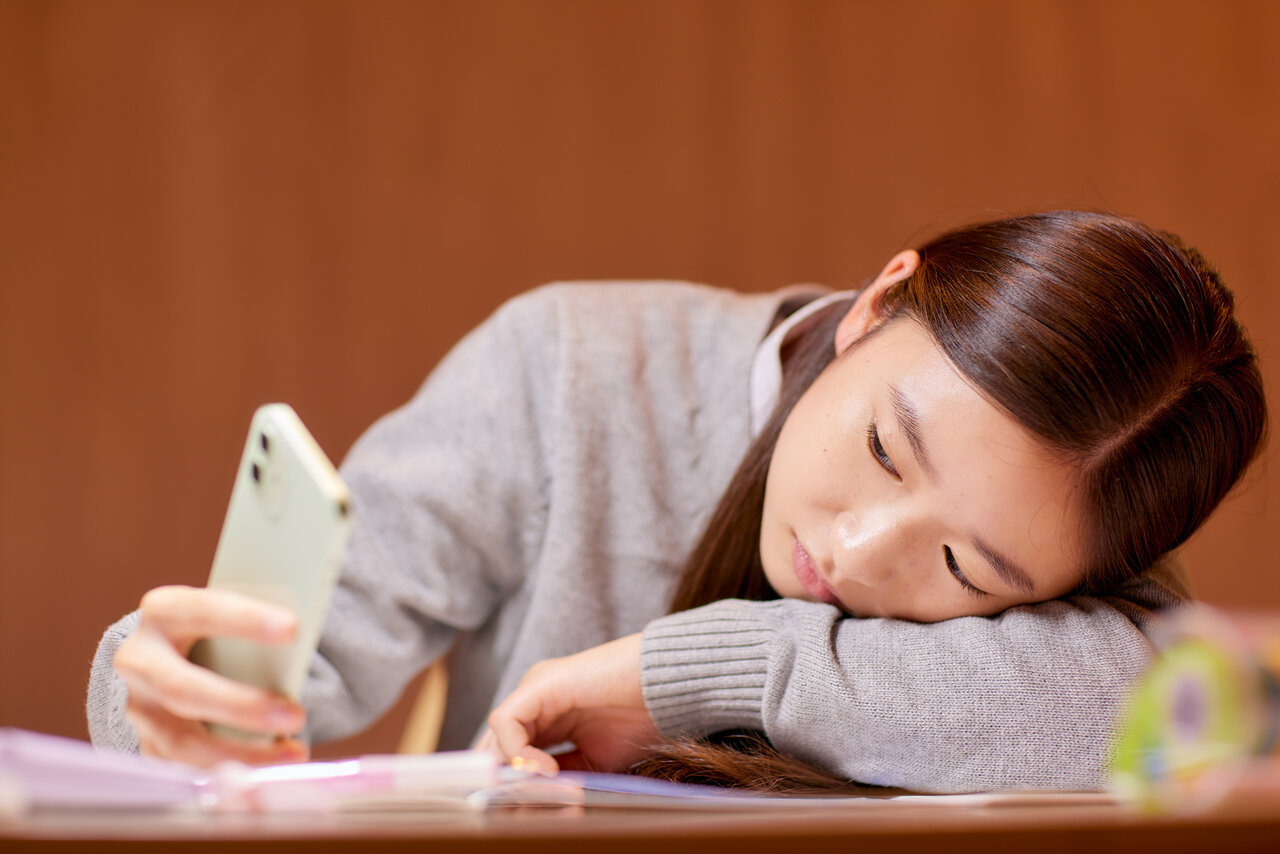





鳥羽 和久
教育者・作家。1976年福岡県生まれ。専門は日本文学・精神分析。2002年、大学院在学中に学習塾を開業。現在は、株式会社寺子屋ネット福岡代表取締役、学習塾「唐人町寺子屋」塾長、単位制高校「航空高校唐人町」校長、「オルタナティブスクールTERA」代表を務める。 小中高生150名超の学習指導に携わり、無時間割り授業、中学生向けの国語塾、高校生の哲学対話など、特色ある授業を開講。 著書に『君は君の人生の主役になれ』(筑摩書房)、『親子の手帖 増補版』(鳥影社)、『おやときどきこども』(ナナロク社)、『「推し」の文化論』(晶文社)、『「学び」がわからなくなったときに読む本』(編著、あさま社)など。 連載に大和書房「僕らはこうして大人になった」、西日本新聞「こども歳時記」、筑摩書房「十代を生き延びる 安心な僕らのレジスタンス」、晶文社「旅をしても僕はそのまま」など。朝日新聞EduA教育相談員。教育や現代カルチャーに関する講座、講演も多数(NHKカルチャー「推しの文化論」など)。 ●「唐人町寺子屋」HP
教育者・作家。1976年福岡県生まれ。専門は日本文学・精神分析。2002年、大学院在学中に学習塾を開業。現在は、株式会社寺子屋ネット福岡代表取締役、学習塾「唐人町寺子屋」塾長、単位制高校「航空高校唐人町」校長、「オルタナティブスクールTERA」代表を務める。 小中高生150名超の学習指導に携わり、無時間割り授業、中学生向けの国語塾、高校生の哲学対話など、特色ある授業を開講。 著書に『君は君の人生の主役になれ』(筑摩書房)、『親子の手帖 増補版』(鳥影社)、『おやときどきこども』(ナナロク社)、『「推し」の文化論』(晶文社)、『「学び」がわからなくなったときに読む本』(編著、あさま社)など。 連載に大和書房「僕らはこうして大人になった」、西日本新聞「こども歳時記」、筑摩書房「十代を生き延びる 安心な僕らのレジスタンス」、晶文社「旅をしても僕はそのまま」など。朝日新聞EduA教育相談員。教育や現代カルチャーに関する講座、講演も多数(NHKカルチャー「推しの文化論」など)。 ●「唐人町寺子屋」HP