

【国際バカロレア】伝統校が認定小学校に! 教科の枠にとらわれない学習方法で子どもの自己肯定感が高まる理由を取材!
〔国際バカロレア連載〕 #4 PYP認定校『聖ヨゼフ学園小学校』 (5/5) 1ページ目に戻る
2025.05.28
教科の枠にとらわれない生きる学び
──探究活動で取り上げるテーマは、特定の教科に当てはまらないけれど、社会で生きていく上で大切なことが多い印象です。
清水勝幸校長先生(以下、清水先生):世界ではこういった学びがスタンダードです。日本の学校は、受験をゴールにしているので、どうしても教科ごとの学習にフォーカスしがちですが、実社会には正解のないグローバルな課題がたくさんありますし、スマホで調べればあらゆる情報が得られます。知識だけでなく、今は「知識をもって何をするのか」が問われる時代だと思っています。

河野先生:IBが重視している「概念型探究学習」では、自分たちで課題を設定し、調べたり話し合ったりして最適解を探します。そして、やってみてうまくいかなければ、次にどうするべきか考えるというプロセスを繰り返す。これはまさに、私たち大人が仕事で踏んでいるプロセスと同じですよね。
グループワークを通じて、どうしたら良いチームが作れるか、自分の果たすべき役割はなにかを学ぶことも実社会で役に立つと思います。
6年生は1年間かけて探究活動を行う
河野先生:6年生は、今までの探究学習の集大成として、エキシビションという発表会に向けて1年間探究活動を行います。
自分自身の“パッション”からテーマを決めて、興味関心をどう社会に生かすことができるのかを考え、リサーチし、アクションを起こし検証します。エキシビションは自分で学びのサイクルを回すことができると証明する場でもあるのです。

清水先生:昨年のエキシビションでは、歴史について調べるチームがアウシュビッツを入り口に、集団心理について学び、クラスで意見を言いにくい子の気持ちを考える発表を行っていました。
歴史を生きた学びとして自分たちの課題に結び付けることができていて、見学に来ていた中高の先生方も驚いていました。
得意な能力を発揮する場があることで自己肯定感が高まる
──IBを導入して、一番良かったと思われるのはどんなことですか?
清水先生:探究活動では、調べるのが得意、コミュニケーションが得意、ユニークなアイデアを出せる、統率力があるなど、それぞれの生徒がもつ能力を発揮し活躍できる場が必ずあります。
それは、「自分が受け入れられている」「ありのままの自分でいていい」という、生徒たちの自己肯定感にもつながっていると思いますね。
───◆─────◆───
PYPでは探究学習を通じて、課題を設定しリサーチし、行動に起こして検証するという学びのサイクルを自ら回す経験を重ねていることがわかりました。
学習の土台をつくる小学生のうちに主体的な学び方を身につけることは、中学生以降に発展的な学習を進める上でも大きな力となるのではないでしょうか。
国際バカロレア認定校の取り組みを、これからも注目していきたいと思います。
撮影/日下部真紀
取材・文/北京子
聖ヨゼフ学園小学校
住所:神奈川県横浜市鶴見区東寺尾北台11-1
電話:045-581-8808
https://www.st-joseph.ac.jp/primary/














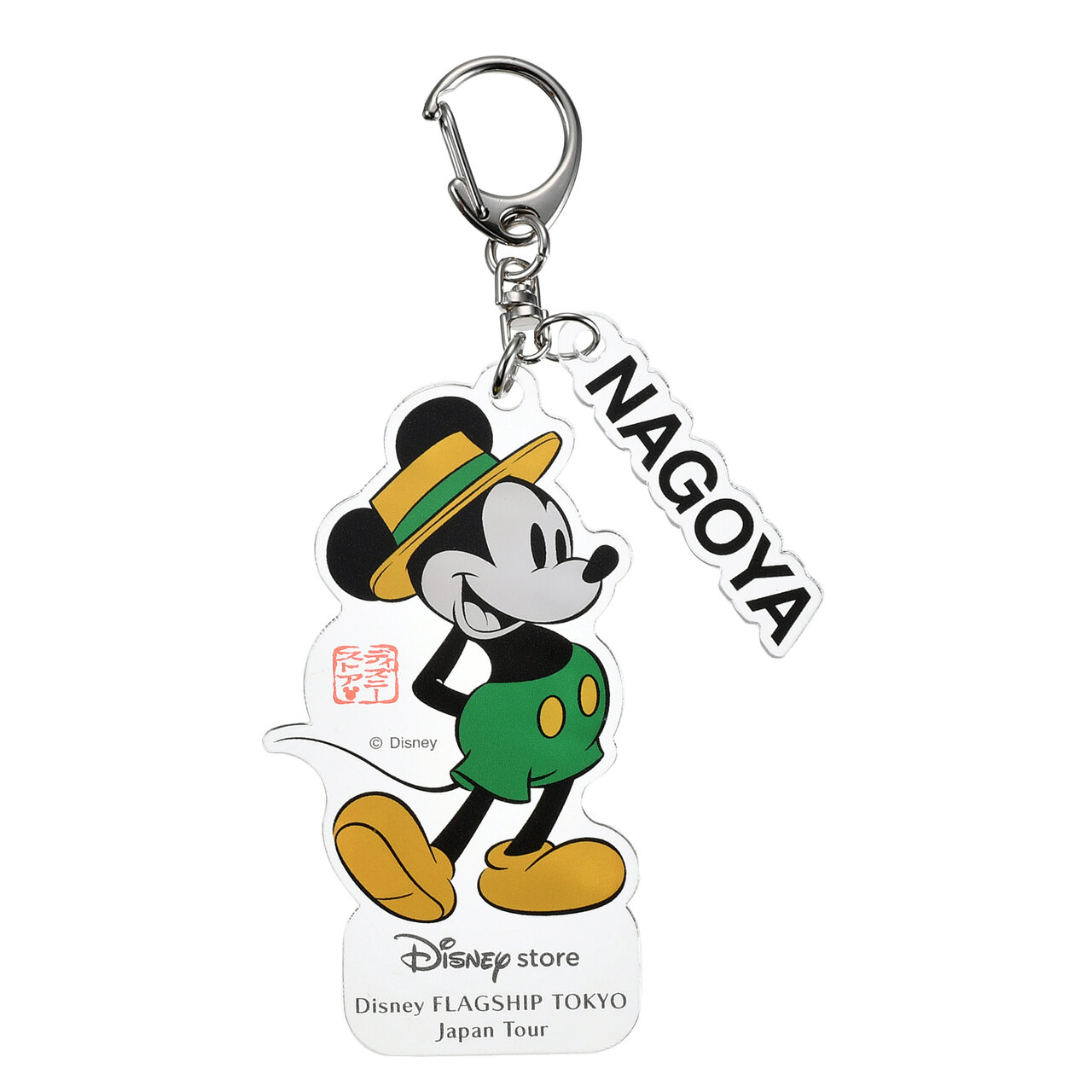




























































































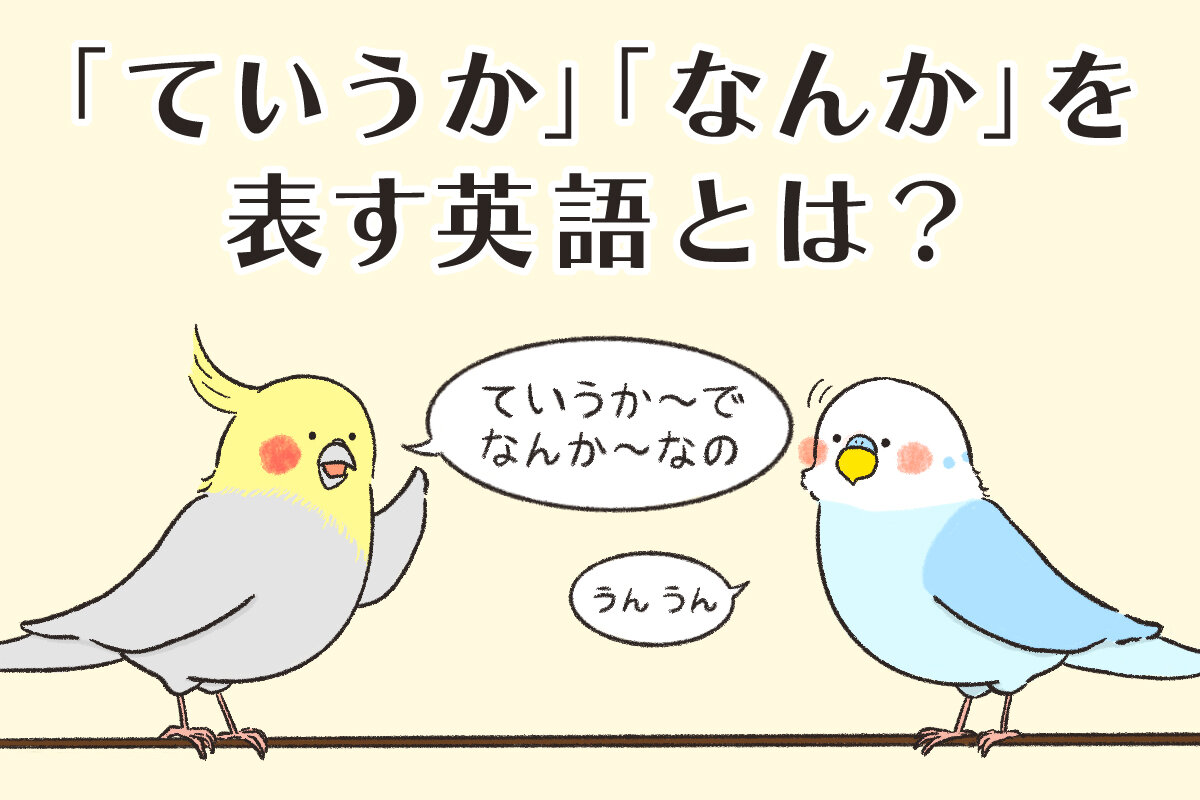










北 京子
フリーライター。 藤沢市在住。食の月刊誌の編集者を経て独立。食を中心に、SDGs、防災、農業などに関する取材・執筆を行う。 3児の母。自然の中で遊ぶこと、体を動かすこと、愛犬とたわむれることが好き。
フリーライター。 藤沢市在住。食の月刊誌の編集者を経て独立。食を中心に、SDGs、防災、農業などに関する取材・執筆を行う。 3児の母。自然の中で遊ぶこと、体を動かすこと、愛犬とたわむれることが好き。