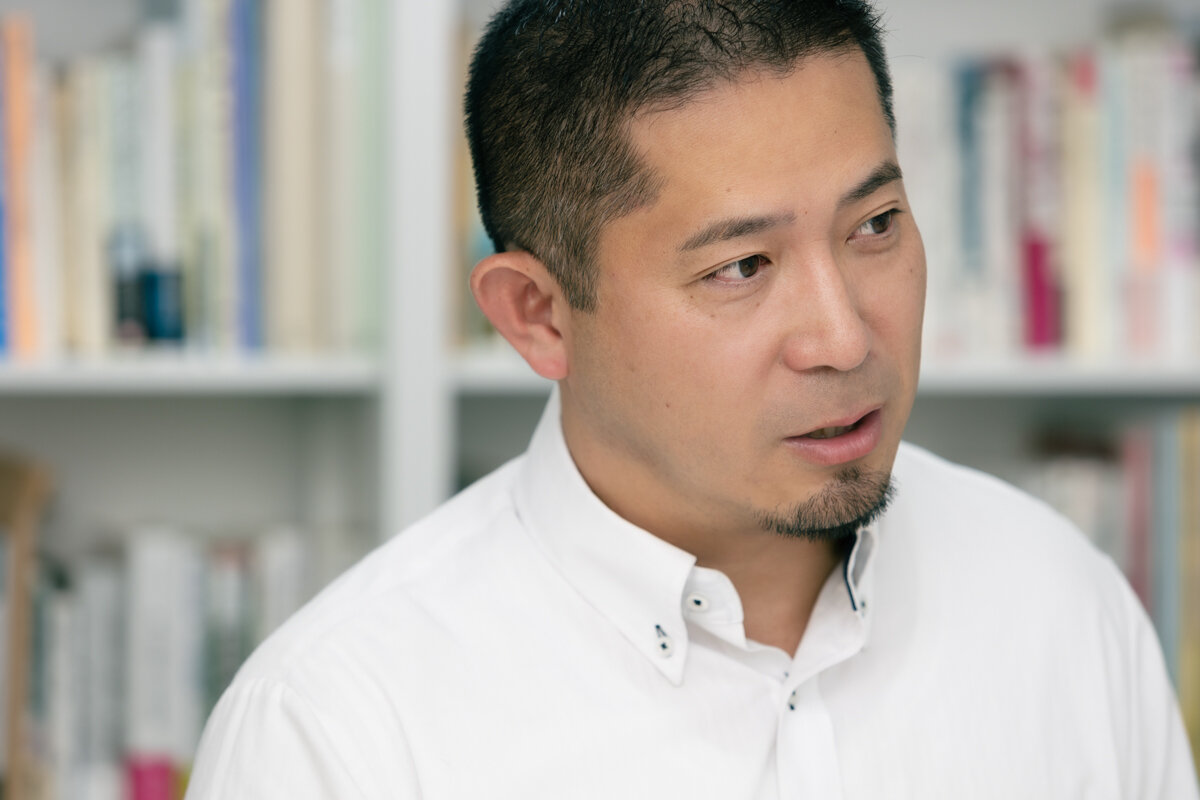【親の残念な口癖】が子どもの成長に悪影響 幸せな親子になれる「言い換え」と「テクニック」を〔教育評論家・親野智可等先生〕が徹底解説
子どもをダメにする親の口癖 #3 (2/3) 1ページ目に戻る
2025.05.23
教育評論家:親野 智可等
「国語、頑張ってすごいね! 次は算数も頑張ろう」で、子どもが感じることとは?
子どもがテストで前回よりもいい点数を持ち帰ってきたとき、「もっと頑張れば、もっといい点がとれるよ」、「国語がこれだけできたんだから、次は算数も頑張ろう」といってしまう親御さんは多いものです。
反射的に親の口からこぼれる言葉に、子どもは一体どんなことを感じているのでしょうか。
「親は褒めたあとに子どもの意欲をさらに引き出そうとしますが、そんな言い方をされても子どもは全然うれしくありませんし、次への意欲にもつながりません。
我が子は頑張ろうと思うどころか、『まだまだ頑張りが足りないんだ』と、自分が不十分であることを感じてしまいます。
ですから、褒めるときは余分なことはいわないこと。親の欲は不要です。純粋に我が子が努力したことを褒めてあげたほうが、実は意欲を引き出せます」(親野先生)
親が心がけたい言い換えフレーズ
「もっと頑張れば、もっといい点がとれるよ」
「国語がこれだけできたんだから、算数も頑張ろう」
→「国語、頑張ったんだね。パパママもうれしいよ」
いい点数がとれたことを子どもが喜んでいるなら、パパママも一緒に喜んであげることはもちろん大事です。しかし、点数にこだわりすぎないことも大切。それでないと、結果が悪いときに子どもは見せにくくなってしまいます。点数よりも、「一生懸命にやったもんね」と努力を褒めてあげましょう。
また、悪い点数をとった場合は、それを責めるのもNG。子どもの悔しい気持ちに共感して、一緒に悔しがってあげてください。そうすれば、悪い点数をとったときもちゃんと見せてくれるはずです。
親が表現を間違えると、きょうだい仲は悪くなる!?
「親御さんが反射的に使っている言葉では、きょうだいやお友だち間のことで、『仲良くしなきゃダメだよ』というフレーズがあります。
このようにいわれた子どもたちは、「自分たちは仲が良くないんだ」と思ってしまう可能性があります。否定的な言語化によって、子どもの中に否定的な自己イメージができてしまうからです。
したがって、子どもには肯定的な言い方を意識しましょう。肯定的な言語化は肯定的な自己イメージになり、それが設計図になってきょうだいもお友だち間も仲が良くなります」(親野先生)
親が心がけたい言い換えフレーズ
「仲良くしなきゃダメだよ」
→「ふたりの仲が良くて、パパママはうれしいな」
たとえば、きょうだいでテレビを見ているだけなのに、親から「仲が良い」といわれたら、「自分たちは仲が良いきょうだいなんだ」という、いいイメージを子どもは膨らませます。これによって、実際に仲良くなっていく可能性が高まります。