

子どもが「色覚異常」だったら? 20人に1人の男性が発症 眼科の名医が目の「異常」と日常に潜む「危険」を語る
「色覚異常」を長年研究する市川一夫先生に聞く (3/3) 1ページ目に戻る
2025.04.22
ライター:山口 真央
おそれすぎはNG! 色覚異常の子どもを持つ親の心構え
Q.色覚異常の子どもを持つ親は、どのような対応が必要ですか。

市川:お子さんが色覚異常だからといって、必要以上におそれることはありません。
私は色覚異常を、身体の特徴の1つだと考えています。
例えば背が低かったり、高かったりすることで、生活していて不便に感じることがありますよね。色覚異常も、それと同じです。
白人の男性は8%が色覚異常で、小学校に上がる前に必ず色覚検査を受けるそうです。私も色覚異常の白人と話したことがありますが、わからない色は友達に気軽に聞き、周りの人も慣れている様子でした。
まずは本人が色覚異常があることを自覚するのが、もっとも大切です。そして身近な人が、色覚異常を抱える人がどのような見え方をしているのか理解し、的確に対処するようにしましょう。
世の中はどんどん便利になっています。私たち眼科医も、色覚異常を抱える人向けに、AIで色を検知し、変換するアプリを開発中です。
この記事で紹介した症状は、強度の色覚異常に該当します。思い悩まず、まずは近くの眼科医に相談しながら、みんなでお子さんが安全に生活できる方法を考えていきましょう。
Q.色覚異常のことをもっと知るために、おすすめの書籍はありますか。
市川:手前味噌ですが拙著の『知られざる色覚異常の真実 改訂版』(幻冬舎)では、色覚異常の種類や見え方の違いを細かく説明しています。
また、お子さんといっしょに理解を深めるなら児童文学『ぼくの色、見つけた!』(志津栄子 作/末山りん 絵/講談社)もおすすめです。
主人公の信太朗が、色覚異常だと自覚し、友達や先生との関わりから、自分なりの「見え方」を模索していくお話です。
心配しすぎて信太朗くんに重圧をかけてしまうお母さんの姿も、いい反面教師になるかもしれません。
身近に色覚異常の人がいなくても、色の見え方が違う人が世の中にいることを知ってもらうために、多くの人に読んでもらいたい物語です。

色覚異常の少年が主人公の児童文学『ぼくの色、見つけた!』

第24回ちゅうでん児童文学賞で大賞をとった志津栄子の最新作は、「色覚異常」に向き合う子どもと家族を描いた物語。
トマトを区別できない、肉が焼けたタイミングがわからないことから、色覚異常が発覚し苦しむ信太朗は、母親から悪気なく「かわいそう」と言われ、試すような行為にガッカリ。さらに症状を知らないクラスメイトから似顔絵のくちびるを茶色に塗ったことを馬鹿にされ、すっかり自信を失ってしまいます。
学年が上がり、クラス担任が変わり自分自身に向き合ってくれたことで、自分の目へのとらえ方がすこしずつ変化する信太朗。そして信太朗が見つけた、彼しか見ることのできない「色」とは──。
「色覚異常」の理解が深まる、オンリーワンの物語をお楽しみください。



















![冬のギフトにぴったりな“雪の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/629/large/0368f492-6e08-49f4-8c18-b0d3c52fe98c.jpg?1770179405)
![【働くママの労働問題】「子持ち様」が気をつけるべき職場の人間関係のポイント[社労士が回答]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/623/large/5af9810f-c081-42b4-a484-d448e0f9e922.jpg?1770162654)





















































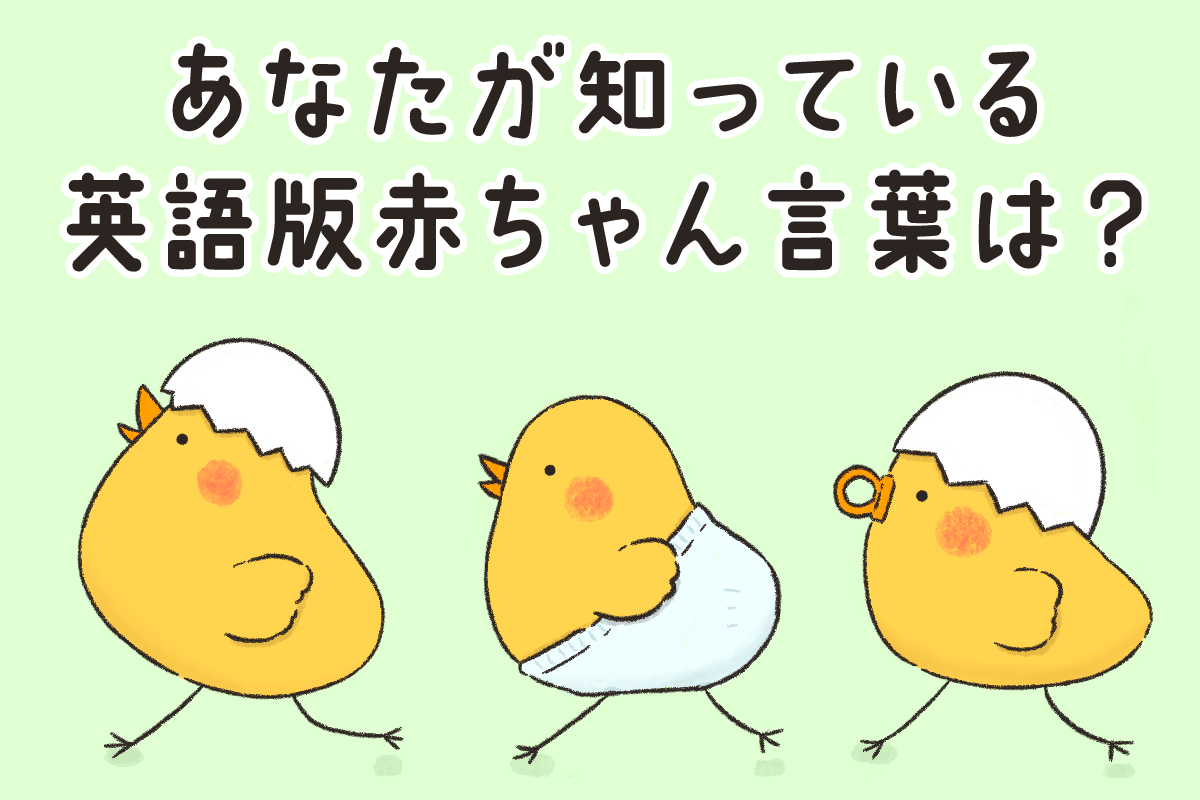








































山口 真央
幼児雑誌「げんき」「NHKのおかあさんといっしょ」「おともだち」「たのしい幼稚園」「テレビマガジン」の編集者兼ライター。2018年生まれの男子を育てる母。趣味はドラマとお笑いを観ること。
幼児雑誌「げんき」「NHKのおかあさんといっしょ」「おともだち」「たのしい幼稚園」「テレビマガジン」の編集者兼ライター。2018年生まれの男子を育てる母。趣味はドラマとお笑いを観ること。