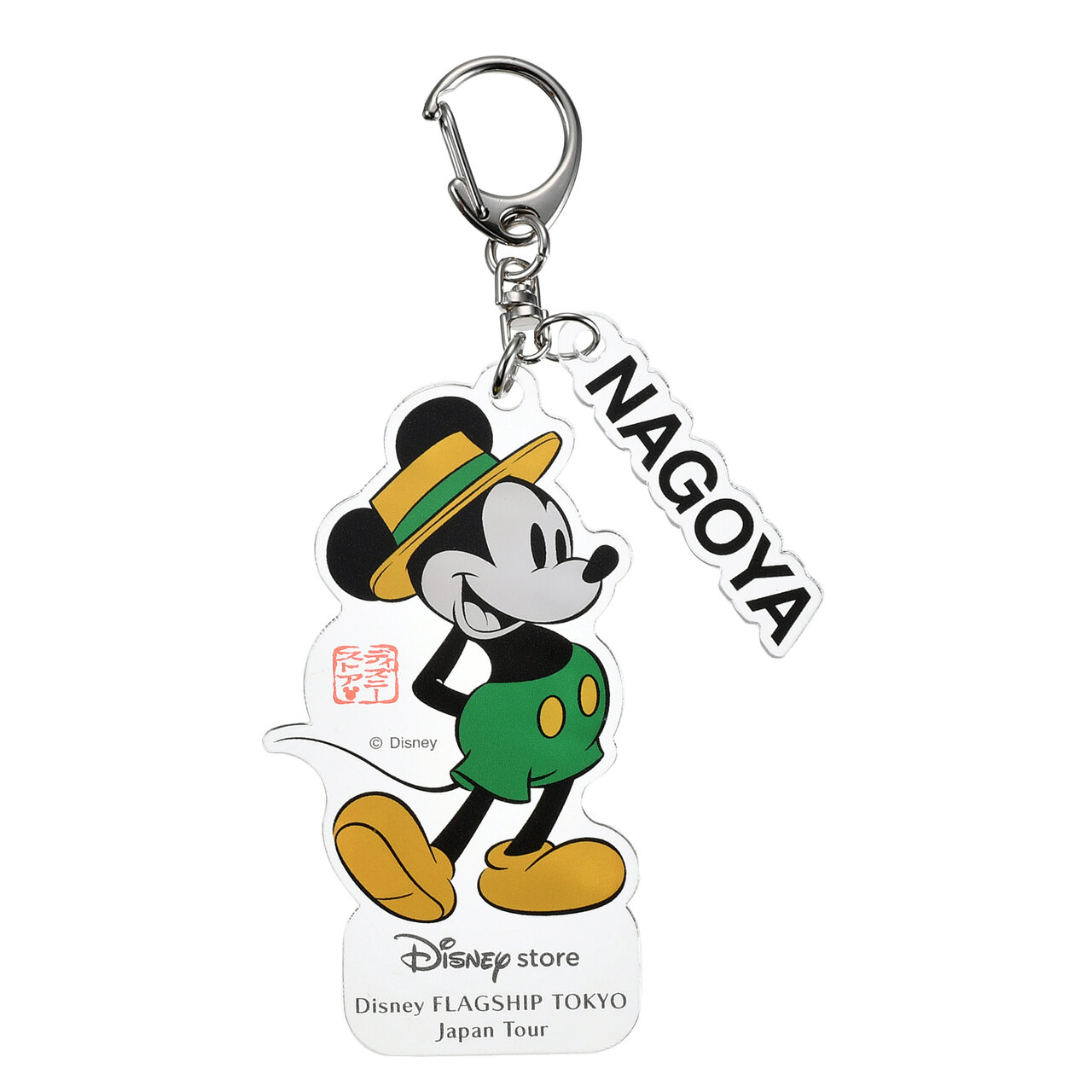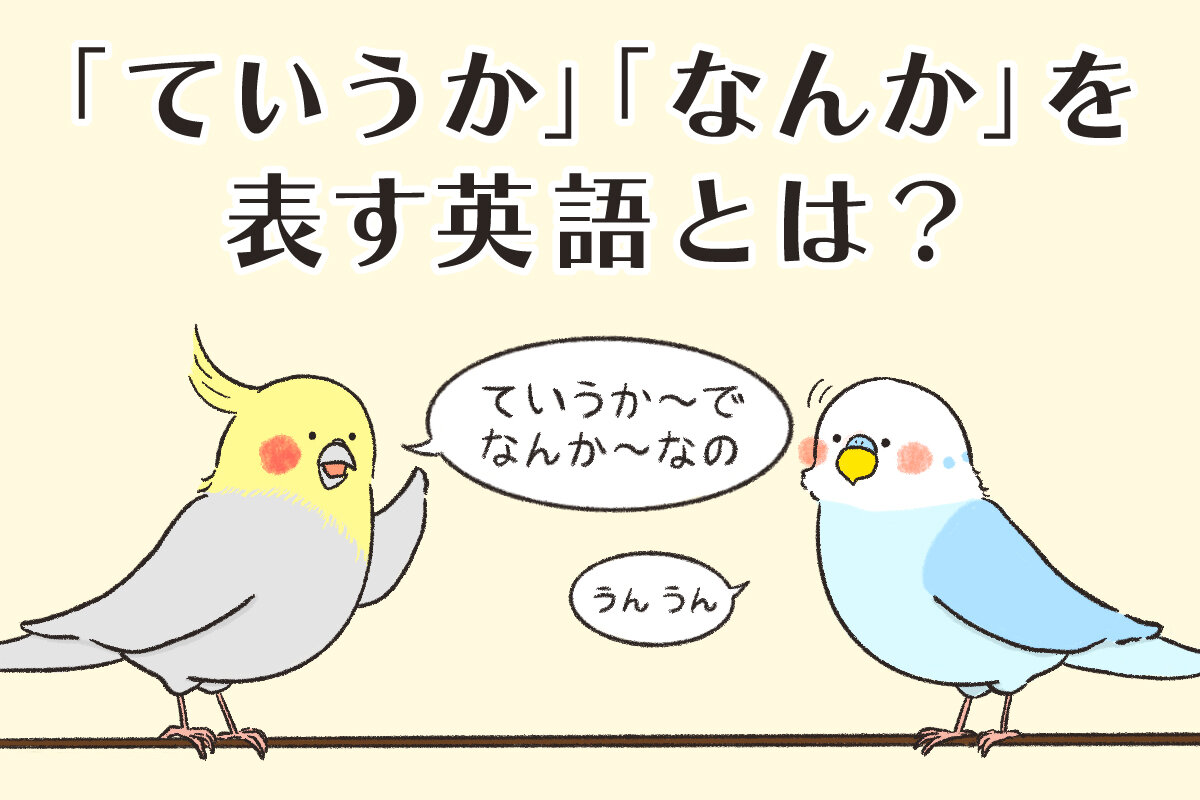【国際バカロレア】伝統校が認定小学校に! 教科の枠にとらわれない学習方法で子どもの自己肯定感が高まる理由を取材!
〔国際バカロレア連載〕 #4 PYP認定校『聖ヨゼフ学園小学校』 (3/5) 1ページ目に戻る
2025.05.28
探求学習では「正解」ではなく「自分なりの答え」を出す
──実際に導入されてみて、いかがでしたか?
河野先生:IBは非常によくできたフレームワークであって、これまでの日本の教育と相通ずるところも多く、決して特殊なものではないことがわかりました。学習内容をどうするか、どんな教材を使い、どんな場所に行き、どんな活動をするのかは学校に任されているので、カリキュラムも独自に組み立てることができますから。

河野先生:IB型の探究学習の時間では、教科の枠を超えた6つのテーマ(※2回目で紹介)について学んでいきます。学習内容と生活とのかかわりを考え、正解を探すのではなく、自分なりの答えをつくっていきます。
河野先生:従来型の一斉授業しか受けてこなかった子どもたちの多くは、最初は戸惑っていましたね。「正解がない」ということを不安に感じる子もいました。しかし、探究の面白さがわかってくると、どんどんはまっていき、今ではみんな探究の時間が大好きです。
教科学習と探究学習の往復でどちらの勉強も楽しく
──小学校は読み書きや計算など、基礎的な力を身につける時期でもあります。各教科の学習はどのように取り組んでいるのでしょうか?
河野先生:教科の学習内容で探求のユニットと関連付けられるものは、探求の授業の中で取り扱っています。
探求の時間は週7〜8時間設けていますので、具体的な活動と結び付けながら意欲的に学ぶことができています。もちろん履修漏れがあってはいけないので、従来どおりの教科の授業も併せて行っています。
ただ、各科の授業でも各先生の問いかけ方などには、探究的な要素を感じています。
探究活動によって、各教科で学んでいることが暮らしや社会とどうつながっているかを発見したり、逆に探究の時間に取り上げた内容をきっかけに各教科の単元に興味を持ったりするなど、良い循環が生まれていると思います。