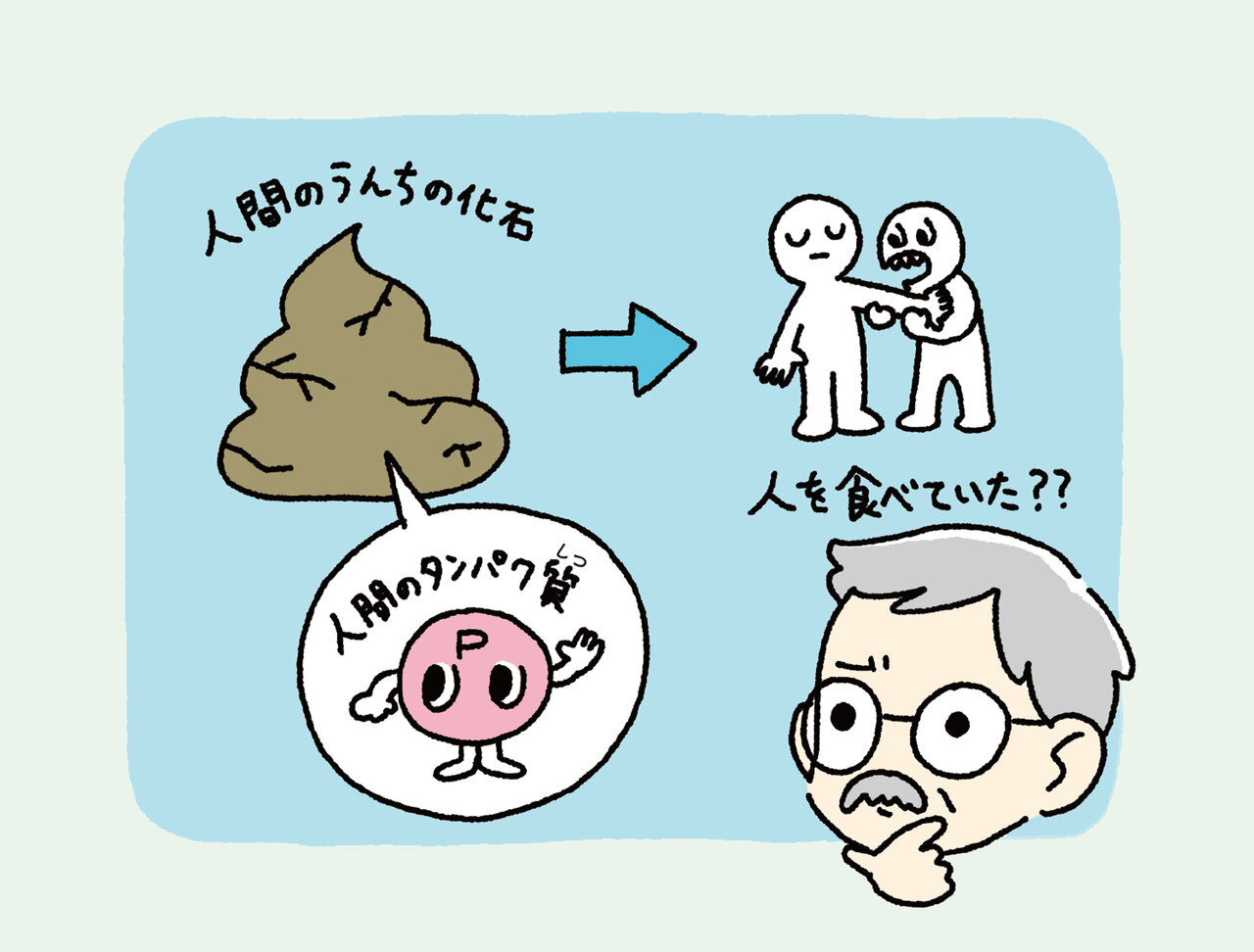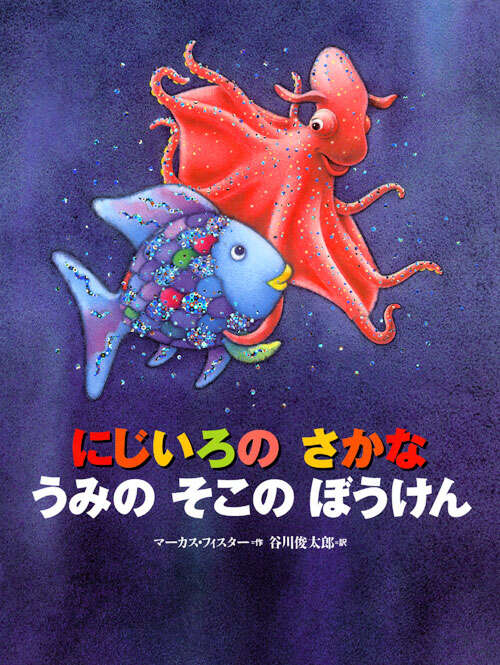中学生研究員 深刻な【海洋プラスチックごみ】問題を東京海洋大学から徹底レポート!
MOVEラボ研究員助手のはるきが 第4回「海の生物とプラギョミ」をレポート! (2/4) 1ページ目に戻る
2024.12.06

今回の探究先生は東京海洋大学の内田圭一教授です。内田教授は、海洋漂流ごみ問題の専門家で、練習船を利用してマイクロプラスチックの浮遊や漂流ごみ等に関する調査に取り組んでいらっしゃいます。
今回のカリキュラムも講義やワークショップ、施設の見学等、盛りだくさん!でした。
海洋プラスチックがなぜ注目されているのか?
ポイ捨てなどで捨てられてしまったプラスチックごみが、川から海へ流出し、海洋プラスチックごみとして、海岸や海底にたまったり、水中を浮遊したりします。マイクロプラスチックと呼ばれるのは、このうち5ミリ未満の微細なプラスチックになります。
プラスチックを含む海洋ごみは、生態系に影響を及ぼし、海洋環境の悪化、船舶航行の障害、漁業や観光への影響等、国内外でさまざまな問題を引き起こしています。

それが今、すでに世界の海に存在しているといわれるプラスチックごみは、合計で1億5000万トン。そこへ年間約800万トンも増えていると推定されていて、世界中で深刻な問題となっています。
マイクロプラスチックを見てみよう


こんなにも小さなマイクロプラスチックが数えられないほどの量になり、生態系に影響を及ぼしていると考えると、恐ろしさを感じます。
これからまた技術が進化し、さまざまなものが開発され、そして便利なものが生まれてくると、プラスチックの使用量が増えます。そして、それが環境中に放出されてしまうと、海洋漂流ごみやマイクロプラスチックがさらに増えてしまうと思います。
だから人間が作ったごみは、責任を持って“適切な処理をする”という考えを定着させることが大事だと思います。