

87年もの時を超えて今ふたたび友達に、1枚のポストカードから語られたもう一つの物語
『おとうさんのポストカード』監修者・中村真人 (3/3) 1ページ目に戻る
2025.11.11
ライター:中村 真人
幸運が重なったアメリカへの移住の裏で
母は歯科医、父は弁護士という専門職だったことで、おそらく旅費の資金はあったのだろうとヴェルナーさんは推測する。それだけでも幸運だったが、あのひっ迫した状況の中、映画界の大物の支援を得て家族3人でアメリカに渡れたのは奇跡的なことだった。
しかし、アメリカへの船上で母は結核にかかり、自由の国に渡った10ヵ月後に亡くなってしまう。ヴェルナーさんの7歳の誕生日の翌日のことだった。「母もホロコーストの犠牲者だと私はずっと思っていました」とヴェルナーさんは言う。
そんな悲しい出来事の後、ヴェルナーさんはニュージャージー州プリンストンにある父の従姉妹の家に預けられることになった。その家には子どもが3人いたが、ヴェルナーさんを含めた難民の子ども5人を受け入れてくれたという。ヴェルナー少年が2~3年を過ごすことになるその場所で、おどろくべき出会いが待っていた。
移住先で出会った、“驚きの人物”
「私たちの6軒先に、物理学者のアルベルト・アインシュタイン(1879~1955)が住んでいました。
私の祖母(亡くなった母の母親)は、アインシュタインの秘書だったヘレン・デュカスという女性と同郷で、生まれたときからよく知っていたのです。ですから、祖母がプリンストンの私を訪ねてきたとき、最初にしたのは近所のデュカス夫人を訪ねることでした。そこには、アインシュタインがいました。
彼は子どもが大好きで、私の手を取ると、庭を案内してくれました。それから書斎に連れていき、壁にかかるヴァイオリンを取って、私のために弾いてくれたのです。どんな曲を弾いたのかですって? まだ7~8歳の子どもにはさすがにわかりません。
でも、私は彼のことを“Onkel Albert”(アルベルトおじさん)とよく呼び、アインシュタインはいつも私にやさしく接してくれました」
ヴェルナーさんの話を聞きながら、その人間関係に出てくる地名を確認していくと、私はある共通点に気づいた。母方の出身地フライブルク、カール・レムリ(前述のドイツのラウプハイム出身のユダヤ人。アメリカへ移住し、映画プロデューサーとしてユニバーサル映画を創設。ウェルナーさん一家のアメリカ移住を支援してくれた人。)の故郷ラウプハイム、そしてアインシュタインが生まれたウルム。いずれも南ドイツの街だ。
特にラウプハイムとウルムは20キロしか離れておらず、レムリとアインシュタインがじつは親戚関係にもあることを私は後日知った。これらは決して偶然ではないのだろう。
差別と追放が常に隣り合わせで生きてきたユダヤ人は、近しい同郷同士を助け合うネットワークを大切にしていた。ドイツ系ユダヤ人に絡むいくつもの幸運に恵まれて、ヴェルナーさん一家はアメリカに脱出することができたのである。ヴェルナーさんとの尽きることのない会話は1時間半におよんだ。彼の人生でもゆうに1冊の物語が書けそうだが、ひとまずここで締めくくる。
「ヴェルナーにもう会えないのかなあ……」
『おとうさんのポストカード』で那須田淳さんが、ヘンリー少年の立場に立って書いたこの思いは、うれしいことに外れた。ヘンリーさんとヴェルナーさんは、自分の本を送り合うなど、87年ぶりの交流をあたためているという。
当時のお互いのことを覚えていないのは重要ではない。2人の子どもがあの時代を生き延び、長く充実した人生を歩んできたこと。1枚のポストカードをきっかけに、今ふたたび友だちになったことが何よりも尊いのだ。
「生きている限り、希望はある」
『おとうさんのポストカード』の制作の最後に、2人から大切なメッセージが届けられたという思いでいる。
\前編はこちらから/
戦争が始まる直前、主人公のヘンリーさんへポストカードを送ってくれた唯一の友達・ヴェルナーさん。戦後の行方はわかっていませんでしたが、87年の時を超えて運命の再会を果たします!
『おとうさんのポストカード』

第二次世界大戦直前、ドイツでのユダヤ人への迫害が過激化し、状況が緊迫するなか、多くのユダヤ人が子どもだけでも国外へ脱出させたいと願いました。多くの国が門戸を閉ざすなか、イギリスが子どもに限り入国を許可し、後に1万人ものユダヤ人の子どもを救ったのが「いのちの列車」でした。
戦後80年となった2025年、この「いのちの列車」によってホロコーストを生き延びた少年・ヘンリーとその父・マックスの実話に基づいた物語『おとうさんのポストカード』が刊行されました。迫害から逃れるため、「いのちの列車」に乗り一人イギリスへ渡ったヘンリー。幼い彼の心の支えになったのは、お父さんからのポストカードでした。
本書では、戦争当時のヘンリーと家族を取り巻く緊迫した状況とともに、実際に送られたポストカードの写真とそこに記された数多くのメッセージから、父から子への深い愛情と平和の尊さを伝えています。
戦後80年の今、触れてほしい一冊となっています。
ぜひ、お手にとってご覧ください。

\関連記事はこちら!/












![冬のギフトにぴったりな“雪の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/629/large/0368f492-6e08-49f4-8c18-b0d3c52fe98c.jpg?1770179405)





![【働くママの労働問題】「子持ち様」が気をつけるべき職場の人間関係のポイント[社労士が回答]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/623/large/5af9810f-c081-42b4-a484-d448e0f9e922.jpg?1770162654)





































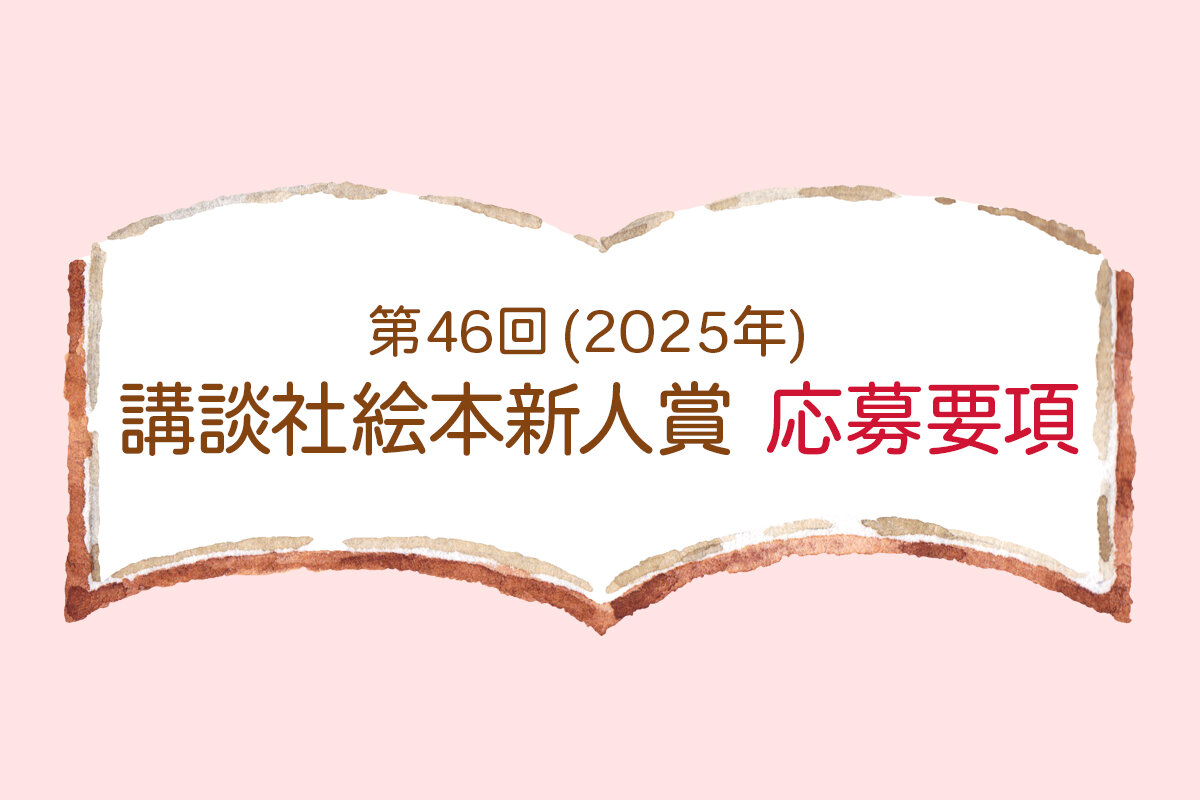




















































中村 真人
1975年横須賀市生まれ。10代のころからベルリン・フィルに憧れ、早稲田大学在学中は交響楽団に所属。2000年にベルリンに移住し、現在はフリーライターとしてクラシック音楽や歴史、戦争と記憶の継承などについて執筆している。著作に『明子のピアノ 被爆をこえて奏で継ぐ』(岩波ブックレット)、『ベルリンガイドブック』(地球の歩き方)など。これまで雑誌「世界」(岩波書店)にキンダートランスポート、アウシュヴィッツの焼却炉などのテーマで寄稿。(写真:Shinji Minegishi)
1975年横須賀市生まれ。10代のころからベルリン・フィルに憧れ、早稲田大学在学中は交響楽団に所属。2000年にベルリンに移住し、現在はフリーライターとしてクラシック音楽や歴史、戦争と記憶の継承などについて執筆している。著作に『明子のピアノ 被爆をこえて奏で継ぐ』(岩波ブックレット)、『ベルリンガイドブック』(地球の歩き方)など。これまで雑誌「世界」(岩波書店)にキンダートランスポート、アウシュヴィッツの焼却炉などのテーマで寄稿。(写真:Shinji Minegishi)