

発達障害の特性のある子どもの“きょうだい児”4つのタイプとストレス〔言語聴覚士/社会福祉士〕が解説
#16 発達障害の特性のある子どもの「きょうだい児」の支援─前編~きょうだい児のリアル~ (3/3) 1ページ目に戻る
2025.07.31
言語聴覚士・社会福祉士:原 哲也
きょうだい児の4つのタイプ
私の印象では、相談や臨床現場に同席するきょうだい児は、素直で、前向きで、やさしい子が多いです。実際、国内外の報告でも、「年長のきょうだい児は、早熟化の傾向」があるといわれています。
発達障害の特性のある兄弟姉妹がいるという環境の中で、きょうだい児はさまざまな気質や行動の特徴を示すようになります。
ここではきょうだい児の代表的な4つのタイプをご紹介します。
1.『親代わりをする子』
発達障害の特性のある兄弟姉妹に対して親の役割を担い、兄弟姉妹の面倒を見る、援助する度合いが高いです。たとえ正当な怒りであっても自分の怒りを表に出さず、自己中心的な子ども時代を経ることなく人に尽くすという、子どもらしくない思考や行動を積み重ねて早熟化していきます。とても良い子に見えますが、とても辛い思いをしています。
2.『優等生になる子』
このタイプも基本はいい子です。不安や葛藤のはけ口を家庭に求めるのではなく、勉強とかスポーツなどの家庭外の活動に見出しています。
障害を持っている兄弟姉妹のできないことを自分が肩代わりしてあげなくてはいけない、といつも心のどこかで思っています。しかし、ずっと背伸びをして生きているので、とても危うい状態にあることが多いです。そして、親はそれに気がつかないことがあります。
3.『退却する子』
家族と気持ちの上で距離を置き、障害を持っている兄弟姉妹のことはできるだけ気にしないようにしています。家族内でのストレスを感じたくないので、できる限り家族との活動にはかかわりたくないという気持ちが強く、家族での外出等は嫌います。
親はきょうだい児がそうする理由がわかるので、それを黙認する傾向があります。
4.『行動化する子』
自分の怒りなどを行動で表す子どもです。兄弟姉妹のために自分がストレスを抱えたり、甘えられないでいることを親に気づかせるために、いわゆる「悪いこと」をして親の注意を自分に向けようとします。そして敵意や憤りの感情を行動で表します。親が「悪いこと」をする理由を理解できないと、ずっと「悪いこと」をし続けるか、行動がエスカレートしてしまうこともあります。
参考
「障害児のきょうだい達の心の健康~きょうだい達をどう健やかに育てるか~」西村辨作
https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/other/aichi_col/z01/z01014/z0101401.html#hannou
最後に
きょうだい児の4つのタイプのうち、1、2はいい子のように見え、3、4は「親にとって」悩ましく困った子のように見えるかもしれません。しかし、どのタイプの子も、ストレスや不安を感じています。きょうだい児は、周囲の気づきや理解や配慮を必要とする子どもなのです。
私たち大人は、そのことを理解する必要があります。
特に1、2の子は自分中心であることが自然な子ども時代を、本当の自分を出せずに通り過ぎ、結果、本当の自分を生きることができないまま、大人になることもあります。
いい子に見える、そこには、いつかガタガタっと崩れ落ちる危うさがあることに十分に注意をしたいのです。
次回は、このような状況にあるきょうだい児への支援について考えていきます。
────────
今回は「発達障害の特性のある子どもを育てる家族への支援」の中から、発達障害の特性のある子をきょうだいに持つ子ども、「きょうだい児」の生の声とタイプについて原哲也先生に解説していただきました。
次回(第17回)では、「きょうだい児」の支援について、具体的に教えていただきます。
原哲也
一般社団法人WAKUWAKU PROJECT JAPAN代表理事・言語聴覚士・社会福祉士。
1966年生まれ、明治学院大学社会学部福祉学科卒業後、国立身体障害者リハビリテーションセンター学院・聴能言語専門職員養成課程修了。カナダ、東京、長野の障害児施設などで勤務。
2015年10月に、「発達障害のある子の家族を幸せにする」ことを志し、長野県諏訪市に、一般社団法人WAKUWAKU PROJECT JAPAN、児童発達支援事業所WAKUWAKUすたじおを設立。幼児期の療育、家族の相談に携わり、これまでに5000件以上の相談に対応。
著書に『発達障害の子の療育が全部わかる本』(講談社)、『発達障害のある子と家族が幸せになる方法~コミュニケーションが変わると子どもが育つ』(学苑社)などがある。
原哲也先生へのご相談を募集
コクリコでは、原先生の連載で取りあげるご相談を募集しています。お子さんの発達障害、発達特性、療育、家族の関わりについてなど、お悩みをお寄せください。
くわしくはこちら https://cocreco.kodansha.co.jp/general/present_event/sPFh8
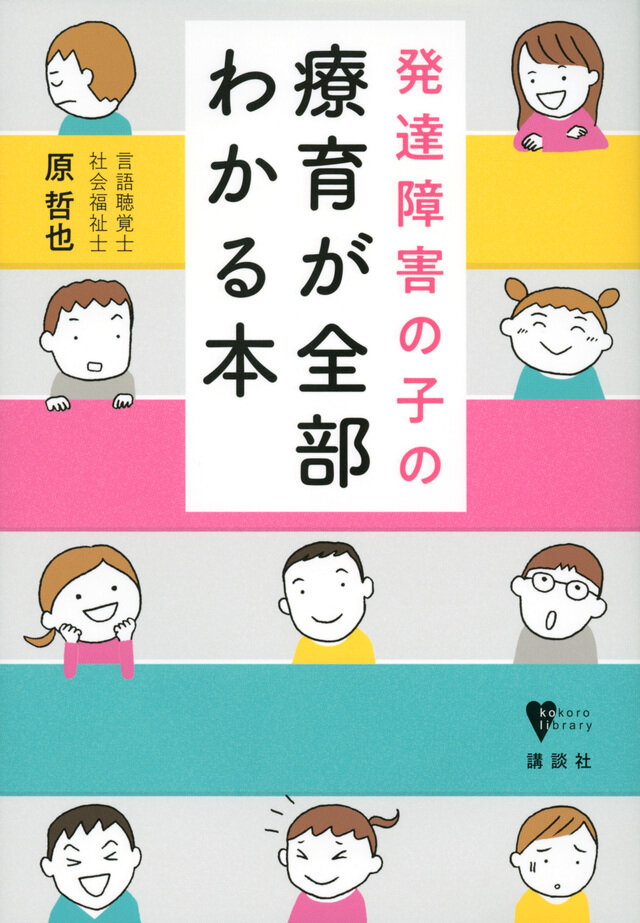
わが子が発達障害かもしれないと知ったとき、多くの方は「何をどうしたらいいのかわからない」と戸惑います。この本は、そうした保護者に向けて、18歳までの療育期を中心に、乳幼児期から生涯にわたって発達障害のある子に必要な情報を掲載しています。必要な支援を受けるためにも参考になる一冊です。



















































































































原 哲也
1966年生まれ、明治学院大学社会学部福祉学科卒業後、国立身体障害者リハビリテーションセンター学院・聴能言語専門職員養成課程修了。カナダ、東京、長野の障害児施設などで勤務。 2015年10月に、「発達障害のある子の家族を幸せにする」ことを志し、長野県諏訪市に、一般社団法人WAKUWAKU PROJECT JAPAN、児童発達支援事業所WAKUWAKUすたじおを設立。幼児期の療育、家族の相談に携わり、これまでに5000件以上の相談に対応。 著書に『発達障害の子の療育が全部わかる本』(講談社)、『発達障害のある子と家族が幸せになる方法~コミュニケーションが変わると子どもが育つ』(学苑社)などがある。 ●児童発達支援事業「WAKUWAKUすたじお」
1966年生まれ、明治学院大学社会学部福祉学科卒業後、国立身体障害者リハビリテーションセンター学院・聴能言語専門職員養成課程修了。カナダ、東京、長野の障害児施設などで勤務。 2015年10月に、「発達障害のある子の家族を幸せにする」ことを志し、長野県諏訪市に、一般社団法人WAKUWAKU PROJECT JAPAN、児童発達支援事業所WAKUWAKUすたじおを設立。幼児期の療育、家族の相談に携わり、これまでに5000件以上の相談に対応。 著書に『発達障害の子の療育が全部わかる本』(講談社)、『発達障害のある子と家族が幸せになる方法~コミュニケーションが変わると子どもが育つ』(学苑社)などがある。 ●児童発達支援事業「WAKUWAKUすたじお」