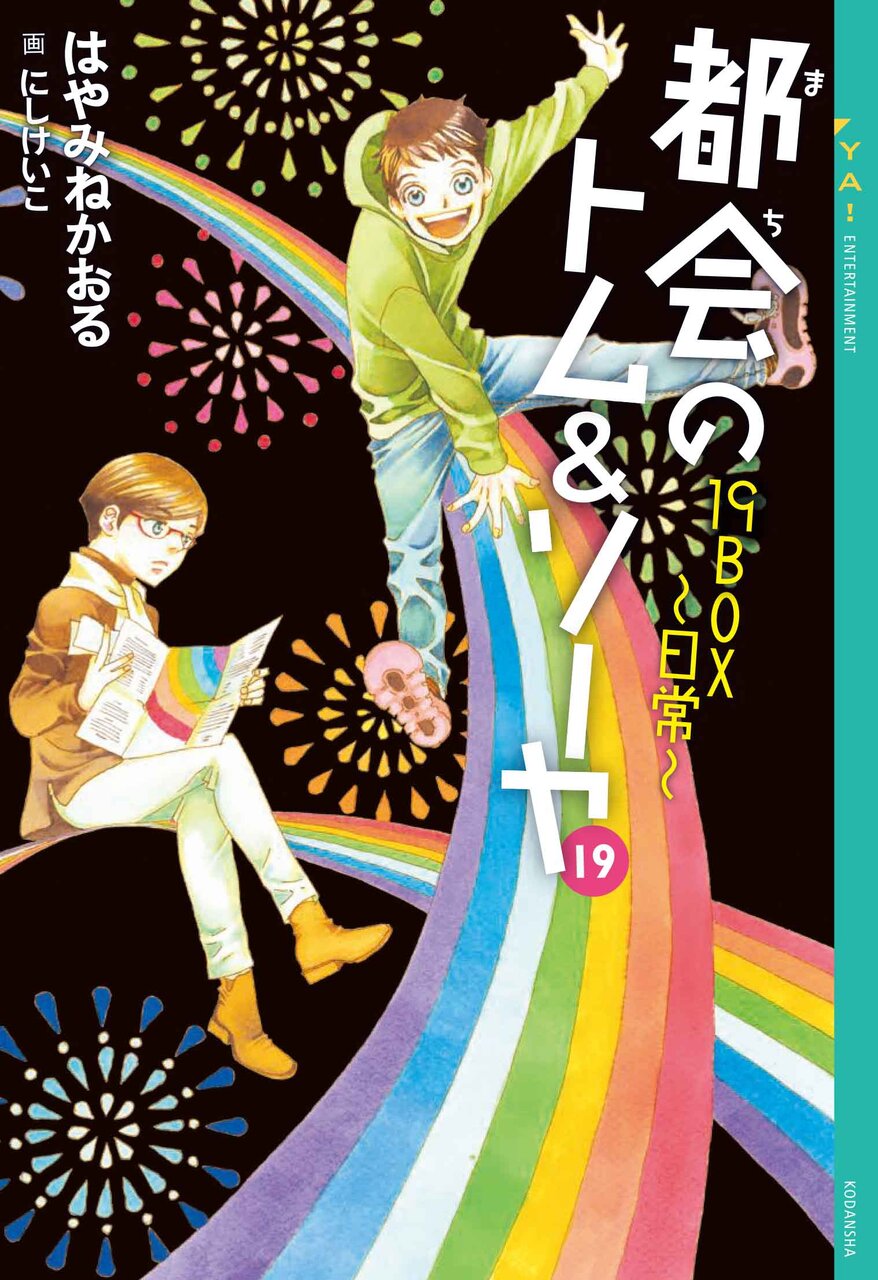思わず親子で夢中に! 楽しすぎるミュージアムデビューを叶える体験プログラムとは?
好奇心を刺激する仕組みが満載の「Museum Start あいうえの」を紹介! (2/3) 1ページ目に戻る
2025.08.13
東京・上野には、子どもの“初ミュージアム”にぴったりの環境が!
「ミュージアムは、子どもの学びにとって非常に優れた場所です。世界中から集まった“ホンモノ”に触れ、多様な価値観に出会い、考え、学ぶことができます」と小牟田さん。
そんなミュージアムが、上野恩賜公園にはなんと9つも集結。徒歩圏内にこの規模で文化施設が密集しているのは、世界的に見ても珍しいのだそうです。

「9つの文化施設が連携し、東京都美術館の学芸員と東京藝術大学の教員が推進役となって取り組んでいるのが『Museum Start あいうえの』です。“すべての子どもに、ミュージアムでの特別な体験を届けたい”という思いのもと、子どもたちのはじめてのミュージアム体験を応援する、さまざまな活動を行っています」
子どもも大人も行きたくなる! 「あいうえの」の4つの魅力
「Museum Start あいうえの」では、1回の体験で終わらせるのではなく、その後も親子でミュージアム体験ができるよう、「アートの楽しみ方」が身につく4つの工夫が凝らされています。
①ホンモノから学ぶ|展示室でじっくり見る・考える
「あいうえの」では、“探求型”のプログラムを大切にされています。実際の展示室でホンモノの作品や展示物をじっくり観察し、「見る→感じる→考える」経験を積んでいきます。また、9つのミュージアムが連携しているからこそできる体験もあるそう。
「たとえば、『色』に注目して、東京都美術館では建物の素材の色に着目し、国立科学博物館では、さまざまな種類の標本や資料の色を見比べながら観察します。
同じ種類のものでも色の違いをじっくり観察してみつけたことを共有します。異なる施設をまたいで体験することで、子どもの学びはさらに深まります。
本物の資料や作品に触れて、よく見て、感じたことや考えたことは誰かに言いたくなる。物を介したコミュニケーションこそ、ミュージアムならではの体験だと思うんですよね」
②多様なコミュニケーション|子どもに寄り添う「とびラー」
「プログラムには、“アート・コミュニケータ”である『とびラー』も参加します。とびラーは親や先生でもなく、また専門家やスタッフとも異なる立場。だからこそ、子どもたちの気づきをナチュラルに引き出してくれます」と小牟田さん。

まず注目すべきは、子どもだけでなく“保護者向け”のプログラムも用意されている点です。
たとえば「ファミリー&ティーンズプログラム」の「アートみるンダー」では、子どもたちが美術館のなかで建築や彫刻を鑑賞している一方、付き添いの保護者は別行動で親子でアートを楽しむためのコツを聞いたり、とびラーと保護者数名で一緒に作品をみる体験をします。
親子それぞれがアートに触れ、アートとの向き合い方を学ぶことで、その後のミュージアム訪問がもっと楽しくなる仕組みです。

③使いたくなるアイテム|「ミュージアム・スタート・パック」
プログラム参加者全員にプレゼントされるのが、「ミュージアム・スタート・パック」。上野公園内の9つの文化施設を、自分の力で楽しむための便利なセットです。

使い方はプログラム内でしっかりレクチャーされるので、持っていくだけで“冒険の気分”に。
「9つのミュージアムをまわり、ひみつの呪文を唱えるとオリジナルバッジがもらえるんです。これがモチベーションになって、もっとミュージアムをめぐりたくなるしかけになっています」と小牟田さん。
スタンプラリー感覚で、ミュージアムめぐりが楽しめますね!
④終わった後もつながる|「みんなの冒険ノート」
「みんなの冒険ノート」は、子どもたちが自分の鑑賞体験を写真や文章で記録し、投稿できるWebサービス。
「Webサイトにアップされた冒険ノートには、世界中の人がアクセスできるようになります。とびラーやスタッフが、届いた画像に“こんなふうに見つけてくれたんだね、ありがとう”などとコメントを返していて、双方向の発信ができるのが特徴です」

“伝える・共有する”という体験を通して、子どもたちの学びの意欲がさらに高まるしかけに、思わず「なるほど!」とうなずいてしまいます。
自分の記録が公式サイトにも掲載されることで、「また行きたい!」「もっと知りたい!」という気持ちが自然と育っていきますね。