

よく消える消しゴムは日本人が生み出した! たまたま見つかった消しゴム誕生ストーリー
ざんねん? びっくり! な文房具のひみつ事典(3:消しゴム) 文房具ライター・ヨシムラマリ
2024.06.15
文房具ライター:ヨシムラ マリ

私たちがふだんつかっている、鉛筆や消しゴムなどの文房具。いろいろな文房具の誕生したときには、「どうしてこうなった!?」と思ってしまう“ざんねん”なものや、いま見ても「すごいなあ!」と“びっくり”しちゃうものまでさまざま。そんなおもしろくてためになる、文房具の世界をのぞいてみましょう。
天然ゴムの消しゴムは夏はベトベト、冬はカチコチ!?
昔の消しゴムは、天然ゴムから作られていました。
天然ゴムが西洋の人びとに発見されたのは、コロンブスがアメリカ大陸へ航海した1493年ごろといわれています。
航海先で現地の人がはずむボールを作っているのを見て、「おもしろい物質だね」とヨーロッパでもちかえったものの、長いあいだとくに使いみちはありませんでした。

だれが最初に気づいたのかはわかりませんが、1770年代には
「天然ゴムでこすると、鉛筆で書いた線がキレイに消せる!」
と知られるようになっていました。
これは、黒鉛が筆記用具としてつかわれるようになってから、じつに200年もあとのことです。
それまで、人類は消しゴムなしでがんばっていたのですね。
天然ゴムは便利でよく消えます。
でも、なにぶん野生のゴムの木からとれる樹液が材料なので、品質が一定ではないのがなやみでした。
また、温度の影響をうけやすく、夏はベトベト、冬はカチコチになってしまうという、ざんねんな点もありました。

プラスチック製の消しゴムはじつは日本生まれ!
天然ゴムは生産できる国が限られています。
「もっとよく消えて、日本でも作れる消しゴムの素材はないだろうか?」
と考え出されたのが、塩化ビニルというプラスチックをつかう方法。
塩化ビニルの消しゴムは、1952年に堀口乾蔵(ほりぐち・かんぞう)が作り方の特許をとり、1956年にはいくつかの日本のメーカーが発売しました。
今となっては、天然ゴムではなく、プラスチックを材料にした消しゴムのほうがあたりまえになっています。

































































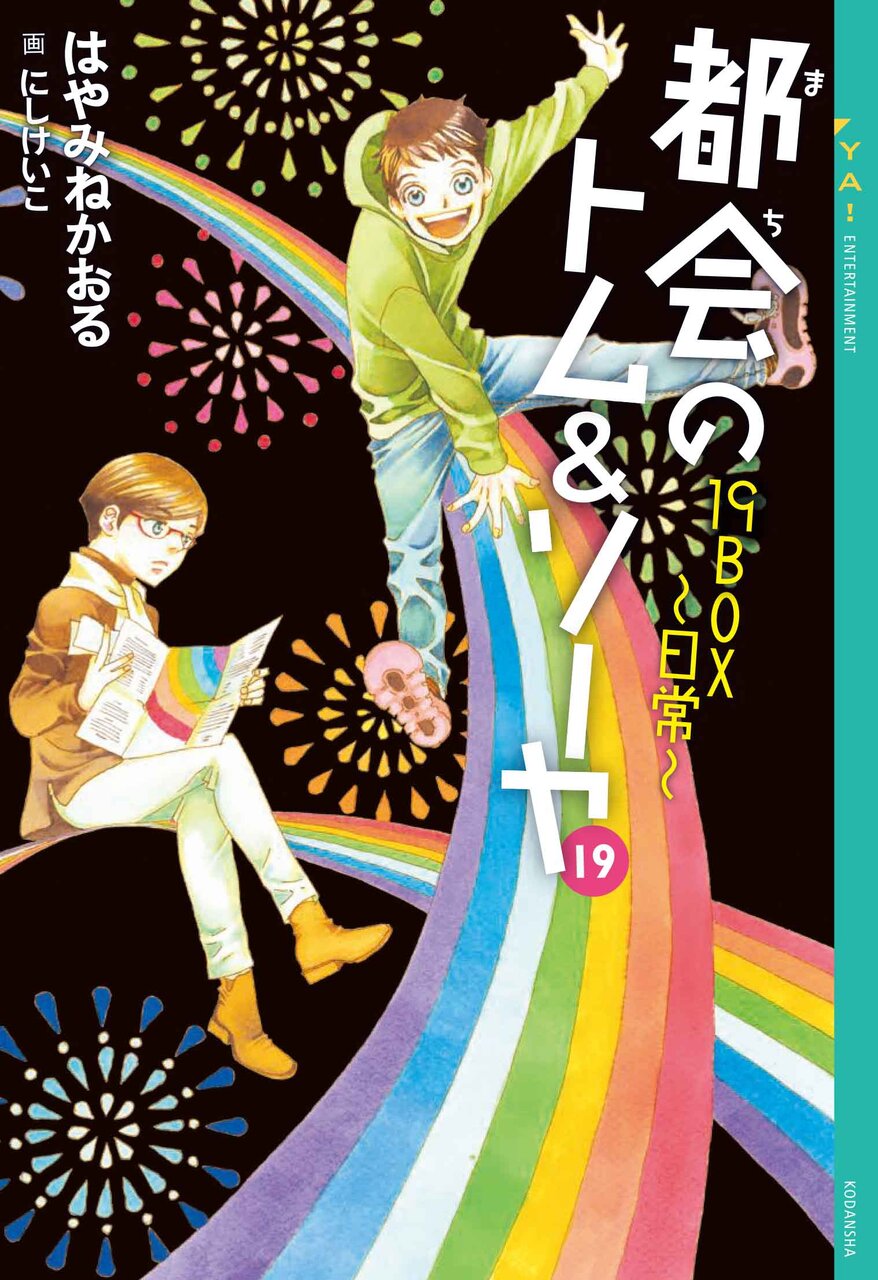






































ヨシムラ マリ
ライター/イラストレーター。1983年生まれ。神奈川県横浜市出身。子どもの頃から絵を描くのが好きで、身近な画材である紙やペンをきっかけに文房具にハマる。主な守備範囲はノートとペンと事務用品。 文具・オフィス用品メーカー大手の元社員で、現在は脱サラしてフリーランスとして活動中。著書に『ざんねん? びっくり! 文房具のひみつ事典』(講談社)、『文房具の解剖図鑑』(エクスナレッジ)がある。
ライター/イラストレーター。1983年生まれ。神奈川県横浜市出身。子どもの頃から絵を描くのが好きで、身近な画材である紙やペンをきっかけに文房具にハマる。主な守備範囲はノートとペンと事務用品。 文具・オフィス用品メーカー大手の元社員で、現在は脱サラしてフリーランスとして活動中。著書に『ざんねん? びっくり! 文房具のひみつ事典』(講談社)、『文房具の解剖図鑑』(エクスナレッジ)がある。