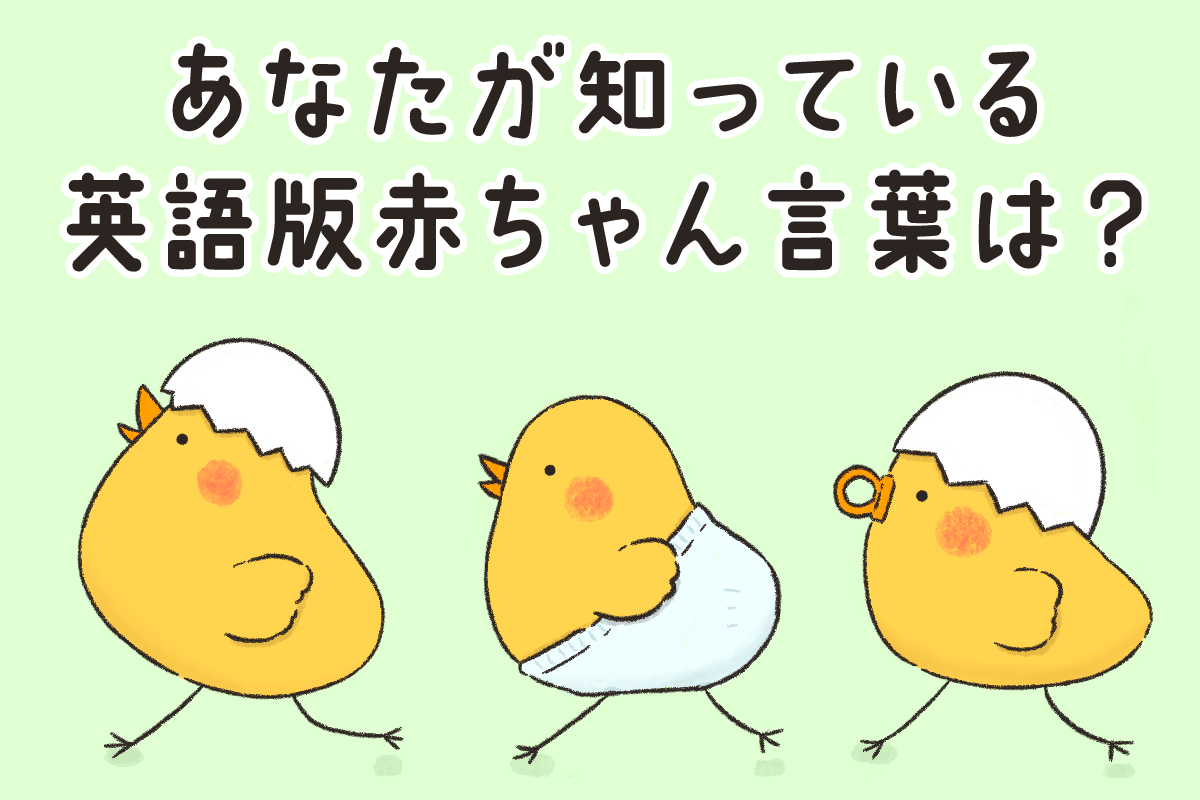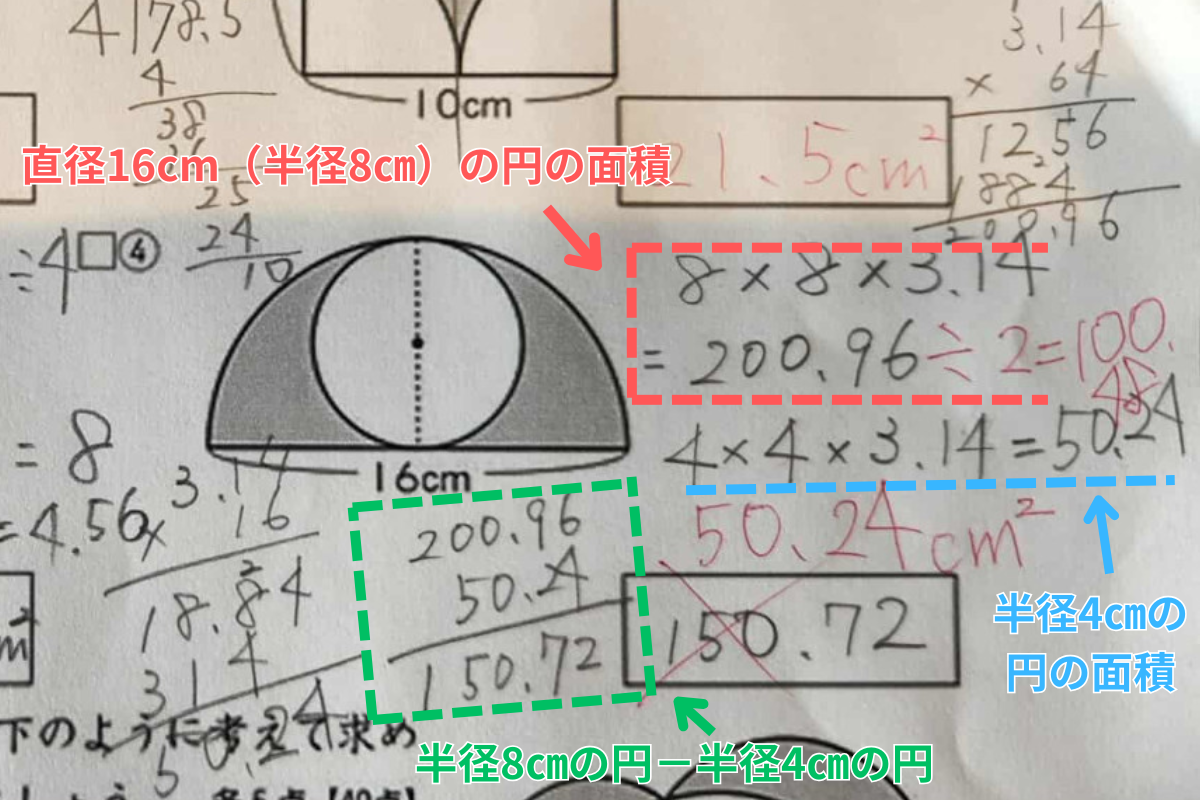「中学校で開花」「家庭と学校は両輪」主体性を信じた教員と保護者が語るリアルな声〔ある公立小学校教員の驚きの実践〕
現役教員に聞く 子どもが主体的になるヒント#4 保護者座談会編 (2/4) 1ページ目に戻る
2024.12.11
小野寺:うちの娘は天真爛漫だけど、学校に対しては少し斜に構えていました。それが大窪先生が担任になってから「学校大好き」に変わり、夏休みも学校に行きたくて「早く休みが終わらないかな」と言うくらいになりました。

──かなり大きな変化ですね。
小野寺:あんまり楽しそうだったから、「先生はどんな授業をしているの?」と聞いてみたら、「おおくぼっちは別になにもしてないよ」って言うんです(笑)。今、考えると、自由進度学習など子どもたちが進める授業のことだったんでしょうね。
夜に友だちとオンライン勉強会をしていることもありました。「三権分立」がテーマで、自分たちで調べる社会の授業でしたが、学校では時間が足りなかったから続きをやりたいと子どもたちが自主的に集まっていたとか……。
大窪先生(以下大窪):そうそう、ある子が提案して始まったんです。
門脇さん(以下門脇):大窪先生のクラスだけじゃなく、当時は学年全体で「決まった宿題」は出さない方針でしたよね。自分が勉強したいことを自主学習として取り組むのが宿題で、担任の先生に「自主学習をすごく頑張っていますよ」と言われたのを思い出しました。
内山さん(以下内山):私は、子どもが4年生のときに大窪先生に担任してもらったのですが、個人面談で相談した際、子どもをしっかり見てくれている安心感がありました。
小野寺:子どもたちが4年生のときに大窪先生が学年の担当になって、その後5、6年と持ち上がり、学年全体がすごく安定したと思います。5年生でコロナ禍になってイベントは次々中止、林間学校にも行けなくなりました。「代わりに何かやろう」となったときに、先生方は子どもにすべて委ねてくれました。
大窪:子どもたちが話し合って、全部決めたんです。学校でキャンプファイヤーをして、レトルトのご飯とカレーを温めて食べて、歌を歌って……。


小野寺:自分たちで考えて創ったものだから、すごく特別で忘れられない時間になっていました。「子どもの主体性を信じる」ってこういうことなんだなと、私も教えてもらいましたね。
中学校でさらに開花した主体性
──当時のお子さんたちは現在、全員が公立中学校の3年生です。小学校高学年で経験した「任せてもらえる」経験は、具体的にはどんな部分で花開いていると感じますか?
門脇:おかしいと思ったことには声をあげる。その上で、解決のために行動するようになり、校則などいろいろなことを変えていっています。
小野寺:体育祭など毎年同じ流れだった行事も、子どもたちが先生に提案して話し合って変更したんです。自ら行動する力が炸裂しています。
門脇:部活動でも小さな「いざこざ」を自分たちで解決する姿勢が常にあって、顧問の先生とも対等に話をしています。働きかければ自分たちの考えや意見を反映できる。そう信じて行動できるのは、小学校時代の経験があるからだと思います。
大窪:すごくうれしいですね。だけど、家庭での基盤も大きいです。子どもは家で言いたいことを言えるから、学校でも口に出せる。内山さんのお子さんは、環境学習のとき大手お菓子メーカーに「過剰包装を変えてほしい」と自ら電話していましたよね。あのときの行動力はすごかった! 家庭での見守りが、自信を持った行動につながるんだと思います。
内山:すごく張り切っていました。その後、包装が紙に変わって、「僕のおかげだ!」とうれしそうでした。
小野寺:子どもの主体性を考える上で、家庭と学校は両輪ですね。






















![クリスマスプレゼントにおすすめの“小学生向け絵本”3選[子どもの本専門店・店長が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/044/835/large/add5217c-b623-4fe3-aae5-53a1f5e2ba64.jpg?1763085159)