
日本語版の翻訳を終えたばかりの野坂悦子さんにお話を伺いました。
作:イヴォンヌ・ヤハテンベルフ 訳:野坂悦子 装丁:田中久子 講談社
左は、原書のオランダ語版『Hup Herman!』(Yvonne Jagtenberg GOTTMER) です。ちなみに、英語版のタイトルは、『Go! Percy』 。ヘルマンという主人公の名前が”パーシー”になっているんです! 日本語版では、ヘルマンのままにしてあります。
オランダの人気作家、イヴォンヌ・ヤハテンベルフの新作絵本『だれが いちばん? がんばれ、ヘルマン!』は、すこし変わった豚のヘルマンのお話です。
この絵本を訳しながら、私はオランダ人の作者イヴォンヌ・ヤハテンベルフさんがなぜ、この豚をあえて主人公に選んだのか、どうしても知りたくなりました。こんな主人公には、めったにお目にかかれませんから。
ヘルマンは、オランダ語でhangbuikzwijn、直訳すると“お腹のたれた豚”(英語ではポットベリーピッグ、日本語ではミニブタとも言われます)と呼ばれる種類の豚です。
”オランダでは人気のある品種なのでしょうか?”
そう質問すると、作者のイヴォンヌさんから、すぐに返事が届きました。

”hangbuikzwijn”は、オランダでは一般的ではなく、本の主人公として登場したこともありません。
主人公はたいてい、ウサギや、ピンクの豚ですからね。私はその豚が大好きで、おもしろくて、すごくユニークだと思いますし、親近感を覚えています。自分もちょっとこの豚みたいなんです。
でも、主人公に選んだ最大の理由は、私たちが”違い”を愛することを学べるからです。
ヘルマンは黒くて、そう……たしかに変わっています。そして、素晴らしいことに、私のもくろみは成功しました。いまでは、みんながヘルマンを愛しているんですよ。
イヴォンヌ・ヤハテンベルフ)
イヴォンヌさんが2020年にこの本でその賞を受賞している事実が、「みんながヘルマンを愛している」ことの証拠と言えるでしょう。
「あるがままの自分を受け入れようとするヘルマンは禅的、仏教的かしら」
という言葉があり、さらに悩みを深めていると、ころころ太ったヘルマンの姿が、ふと”だるま”のように見えたのです。
だるまの人形は、中国の仏教僧「達磨」が座禅する姿に似せて作られたものだと言われています。
こうして「だるまさん みたいな くろいぶた」という訳が生まれてきました。このたとえによって、ヘルマンの位置がぴたりと決まったように感じています。
でも、まわりのめんどりや、おんどりは「あたしがいちばん、おれってさいこう」といつも言い争ってばかりで、ヘルマンはもう、うんざり。
底抜けの楽観性と手放しの自信を持つ、われらが主人公は、
<だって、いちばん さいこうなのは ヘルマンなんです。 みんなに みせてあげよう>
と思いつき、走ったことなどないのに走り出して、みんなとの競争が始まってしまいます。
オランダは、2020年に発表されたユニセフによる子どもの幸福度の調査(*2)によると、2013年に引き続き、総合で1位となった国です(ちなみに38の先進国の中で、日本の総合順位は20位でした)。
私は自己肯定感の強いヘルマンの心の動きに、そんなオランダの幸せな子どもたちの横顔を感じました。それで「みんなにみてもらおう」ではなく、「みんなにみせてあげよう」という訳語を選んだのです。
幸福度の高いオランダにもやはり競争はあって、十代の子どもたちは両親との関係は良好であっても、学校ではプレッシャーを感じているという別の調査結果もあるのだとか。
この絵本はもちろん競争を肯定しているわけではなく、ここは起承転結の大きな「転」に当たるところ。その転が、また転を生み、最後には見事に着地してヘルマンらしいハッピーエンドを迎えるお話なのです。
ヘルマンはありのままの自分が好きなのに、うっかり自分に合わない競争に加わってしまい、でも最終的には自分を取りもどします。
生きていく中で、私たちは競争に巻きこまれることもあるけれど、自分自身を見失わず、自分の個性や力を大切にしてほしい。この本は、子どもたちにそう伝えてくれるかもしれません。

さあ、ヘルマンはこのあと、どうするでしょうか。
(『だれが いちばん? がんばれ、ヘルマン!』より)
注:
*1)「金の絵筆賞」 年に一度、CPNBという団体が、国内で出版されたオランダ人作家の絵本の中で最高の作品に贈る賞
*2)「子どもの幸福度の調査」 ユニセフ・インノチェンティ研究所が2020年9月3日に発表した報告書『レポートカード16-子どもたちに影響する世界:先進国の子どもの幸福度を形作るものは何か』より
イヴォンヌ・ヤハテンベルフの本
イラストレーター、作家、脚本家。オランダのティルブルフ市生まれ。アーネムの美術アカデミーを卒業後、1994年に初めて子どもの本に絵を描き、『とくべつな いちにち』(2001)で絵本作家デビュー。翌年、シャーロット・ケーラー奨学金を受ける。世界各地で読まれている「アルノ」「バロチェ」が主人公の絵本シリーズほか、『ちいさな かいじゅう モッタ』(福音館書店)など多くの絵本を手がけている。前年度に出版された児童書の中で最も優れたイラストレーション作品に贈られるオランダ「金の絵筆賞」を、2019年『ぼくのおじさん』(未邦訳)、2020年『だれが いちばん? がんばれ、ヘルマン!』で連続受賞。多岐にわたる才能は映画の脚本制作、本の挿絵や装丁、子ども用家具のデザインにも発揮されている。

作:イヴォンヌ・ヤハテンベルフ 訳:野坂悦子 講談社
「知らない学校に初めて行く日の不安は、日本もオランダも同じかもしれません」(野坂)
『ちいさな かいじゅう モッタ』
文・絵:イヴォンヌ・ヤハテンベルフ 訳:野坂悦子 福音館書店
「ぼくもすごいかいじゅうなんだと、認めてもらいたい、かわいい末っ子モッタのお話です」(野坂)
子どもと読みたい! オランダの絵本

作:シャルロット・デマトーン 訳:野坂悦子 ブロンズ新社
「想像力豊かな男の子には、おつかいだって大冒険。絵の中に何が隠されているかな?」(野坂)
『とんがりぼうしのオシップ 赤い糸のぼうけん』
作:アンネマリー・ファン・ハーリンゲン 訳:野坂悦子 BL出版
「オシップと一緒に赤い糸をたどって、ふしぎな世界へ出かけましょう!」(野坂)
野坂悦子さんが訳したオランダの実在の美術館のお話

野坂悦子さんが書いたオランダの実在のホテルのお話
















































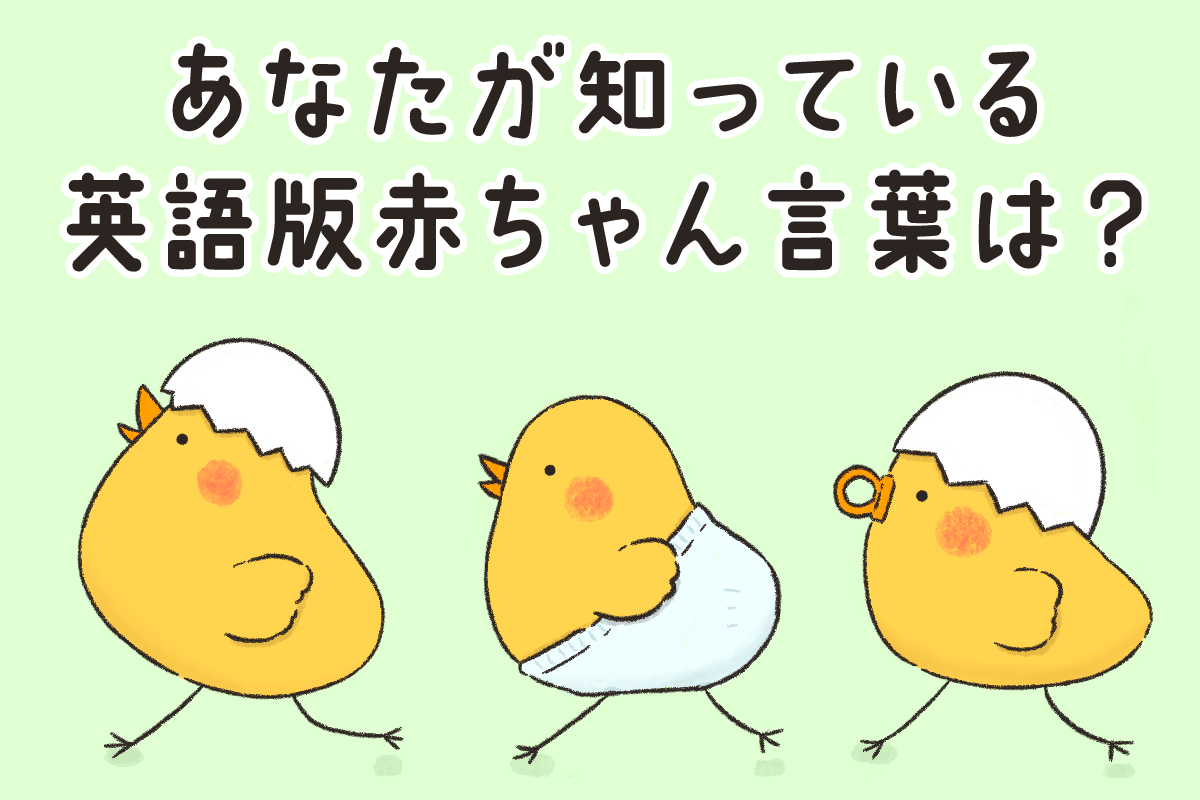















































野坂 悦子
東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒後後、オランダ、フランスの滞在を経て、1989年にオランダの絵本『レナレナ』(2019年朔北社より復刊)の翻訳でデビュー。『おじいちゃんわすれないよ』(金の星社)で第50回産経児童出版文化賞大賞を受賞。『ねえさんの青いヒジャブ』(BL出版)、『ぼくといっしょに』(ブロンズ新社)、『おいで、アラスカ!』(フレーベル館)をはじめ訳書は100点以上ある。創作絵本に『ようこそロイドホテルヘ』(牡丹靖佳絵、玉川大学出版部)など。 日本国際児童図書評議会(JBBY)会員。紙芝居文化の会海外統括委員も務める。
東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒後後、オランダ、フランスの滞在を経て、1989年にオランダの絵本『レナレナ』(2019年朔北社より復刊)の翻訳でデビュー。『おじいちゃんわすれないよ』(金の星社)で第50回産経児童出版文化賞大賞を受賞。『ねえさんの青いヒジャブ』(BL出版)、『ぼくといっしょに』(ブロンズ新社)、『おいで、アラスカ!』(フレーベル館)をはじめ訳書は100点以上ある。創作絵本に『ようこそロイドホテルヘ』(牡丹靖佳絵、玉川大学出版部)など。 日本国際児童図書評議会(JBBY)会員。紙芝居文化の会海外統括委員も務める。