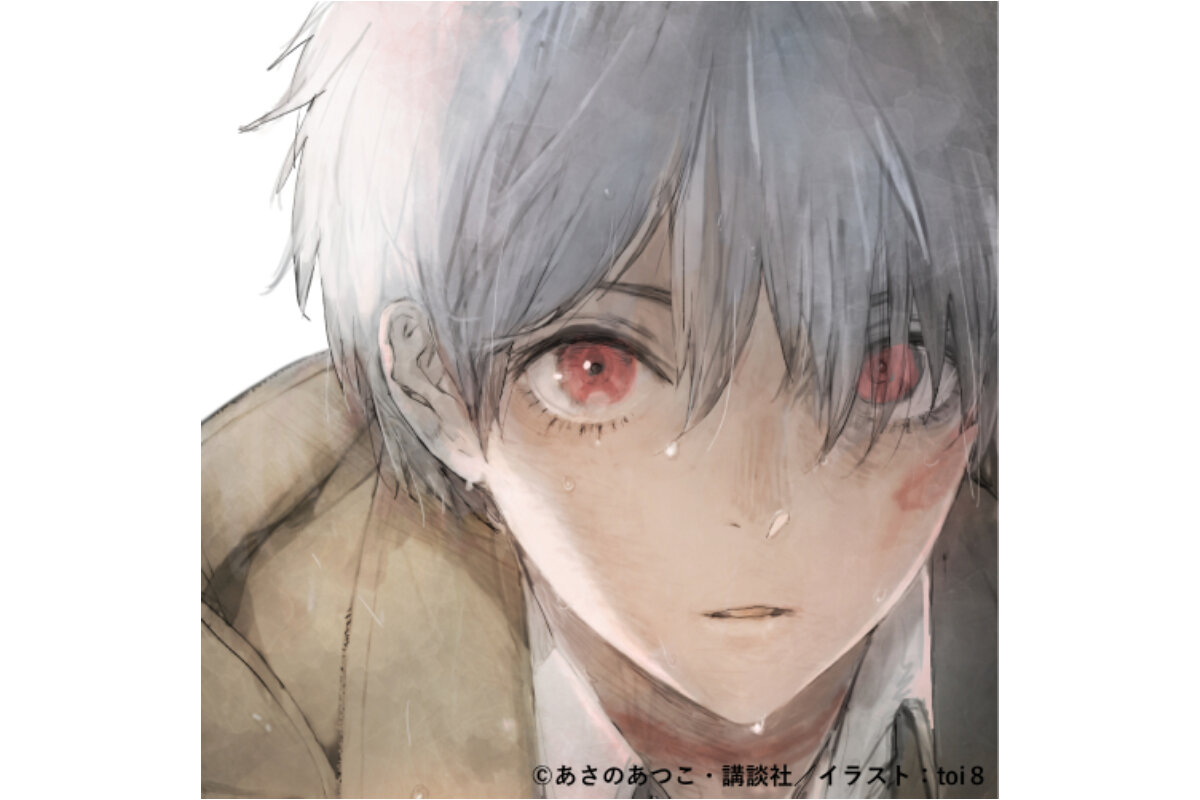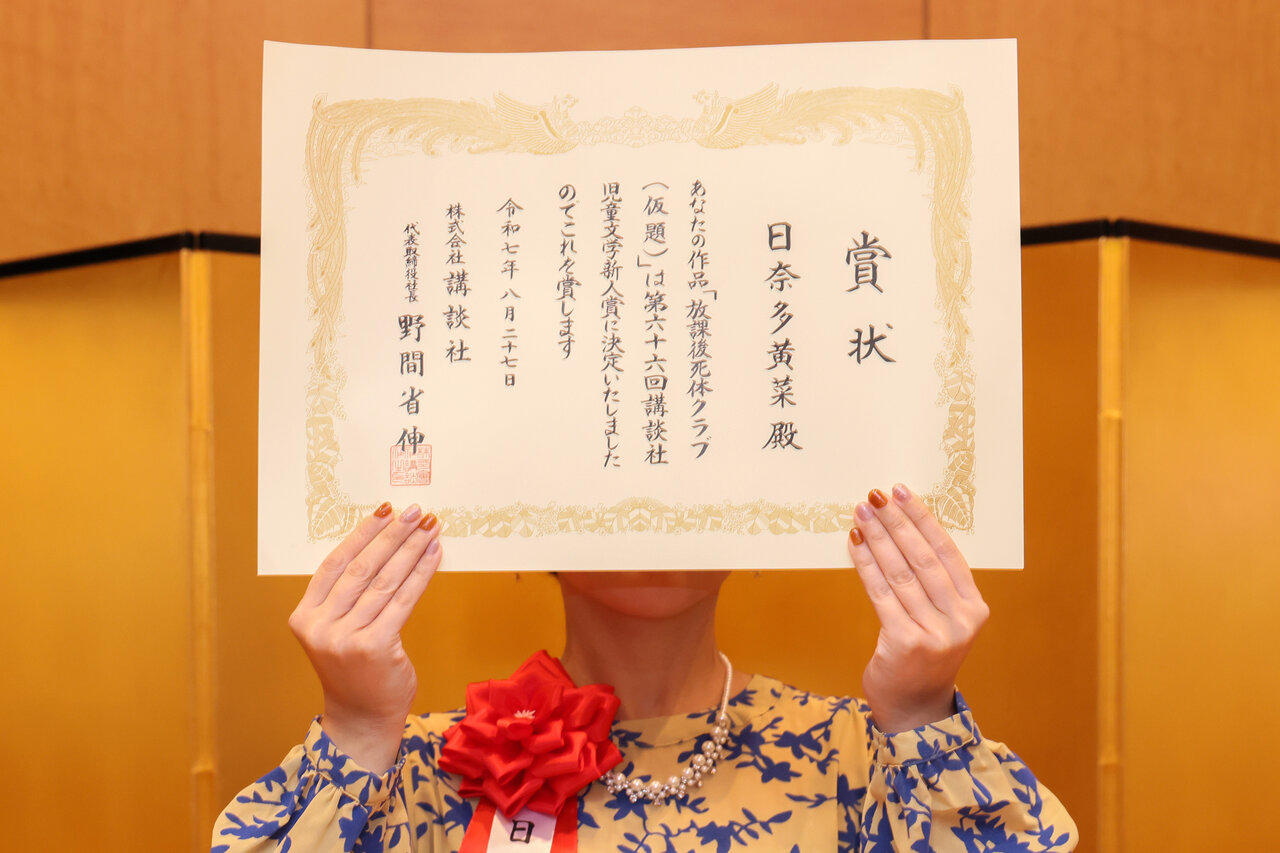子どもが「色覚異常」と診断されたら… 「色覚異常は“進化型“だ」作家・川端裕人が説く「色覚と進化のひみつ」に超ナットク
『いろ・いろ 色覚と進化のひみつ』著者 川端裕人さんインタビュー
2025.08.09

もし、お子さんが「色覚異常」と診断されたとき、親御さんはどう感じるのでしょう。「この先、困ることばかりではないか」と、不安を抱える方も多いかもしれません。
しかし、色の見え方の違いは、本当に「異常」と呼べるのでしょうか。
『いろ・いろ 色覚と進化のひみつ』などの著作があり、「色覚異常」について詳しい、作家の川端裕人さんは、「色覚異常は『進化型』である」と語ります。
「色覚異常」と診断された子どもたちに過度な重圧をかけないために、大人はどんな視点を持てばよいのでしょうか。川端さんのお話を伺いました。

哺乳類の進化にあわせて見え方は変わってきた
──「色覚異常」のある人が「進化型」と考えられている理由を教えてください。
川端:まず「色覚異常」は眼科の診断名から来ている表現で、生物学的には、「異常」ではありません。進化の中で培われた、ヒトの多様性の一部だと考えられています。
では、どんな進化なのか、思い切りざっくりと言いますと──、恐竜がまだ生きていたころの哺乳類は、恐竜の寝ている夜に生活することが多かったため、色を区別するよりも、暗いところでも見えやすい感度優先の目を持っていました。
恐竜が絶滅したあと、昼間の世界に出た哺乳類の中から、果物の成熟の度合いや、葉の緑の中にある果物の場所を、色で見分けられるサルの仲間がでてきました。食べられるものを遠くから見つけられて便利なために、それが広がったと言われています。現代の多くの人が赤と緑を見分けるのは、この見え方を受けついでいます。
ところが、これで終わりではありませんでした。やがてヒトが森を出て草原で狩りをするようになると、草むらにひそむ獲物や肉食動物を見分けるのに有利な色覚が登場しました。その色覚の持ち主は、赤と緑の区別をする代わりに、物の形や明るさの違いを見分けることに優れているのです。
そういった人たちの色覚を、私は「進化型」と呼んでいます。学術的には「派生型」と呼ぶことが多いのですが、一般向けには「進化型」と説明する研究者もいるので、そう呼ぶことにしました。

川端:太陽の出ている時間が短い北ヨーロッパなどには、色の違いよりも物の形や輪郭を見分けるのが得意な「進化型」の色覚の人が多いそうです。また漁業が盛んなイタリアの海沿いでは、「進化型」色覚の漁師は、水中の魚影を見分けるのに有利だと考えられているそうです。
生き物が持っているそれぞれの「見え方」の仕組みは、進化と深く結びついています。例えば、ミツバチも、カラスも、ネコも、カエルも、金魚も、みんな自分たち独自の色を見ています。
ヒトの場合は、進化の道筋の中で、たまたま同じ集団の中で別の見え方が混ざっているだけで、どの見え方かが「正常」で、どの見え方が「異常」だとすること自体がナンセンスなんです。ヒトにとって、集団の中に、こんなふうにいろんな見え方をする個人がいること自体が「正常」な状態なのだと、まず伝えたいです。