

【昆虫採集の聖地】高尾山で本気の虫とり! 珍しいヘビそっくりの幼虫を発見!
[ちょっとマニアな季節の生きもの]昆虫研究家・伊藤弥寿彦先生が見つけた生きもののふしぎ
2024.08.30
昆虫研究家:伊藤 弥寿彦
高尾山(昼の部)で見つけた昆虫を紹介します!

今回、ようやくみんなで自由に動けるようになり、満を持してのフィールド採集会となったわけです。8月に入り、東京の日中の気温は時に35度を越えるような危険な暑さだったので、どのようなメニューにしようか悩みましたが、結局「昼の虫」と「夜の虫」の両方を楽しんでもらおうと、2部制にすることにしました。
第1部は「昼の虫」探しです。夜の活動もあることを考えて、ちょっと遅めの午後2時に京王線「高尾山口駅」で待ち合わせとしました。ひであき君(17)、れいいちろう君(11)、ゆうま君(9)、はると君(9)、ゆのさん(7)がそれぞれお父さまやお母さまと一緒に参加、そしてMOVE 編集長の佐藤華さんが来てくれました。




でもこれはよくあること。そう簡単には採らせてくれません(笑)。
前日の雨のせいでしょう。未舗装の道には所々に水たまりができていました。目をこらすと湿った土の上で黒いアゲハがとまっています。オスのカラスアゲハが吸水していたのです。
気配を消してそ~っと近づく、れいいちろう、はると、ゆうとの3人。





木下沢林道には川沿いにクワの木が多く所々ヌルデもあります。クワの木を見上げていくと、確かにイッシキキモンがいる証拠がありました。葉に細い線のような穴が空いていて、これがイッシキキモンの成虫が食べた痕。「食痕」といいます。







人間は絶対に生で食べられません。それをこのビロードスズメの幼虫はムシャムシャと美味しそうに食べてしまうのには驚きました。













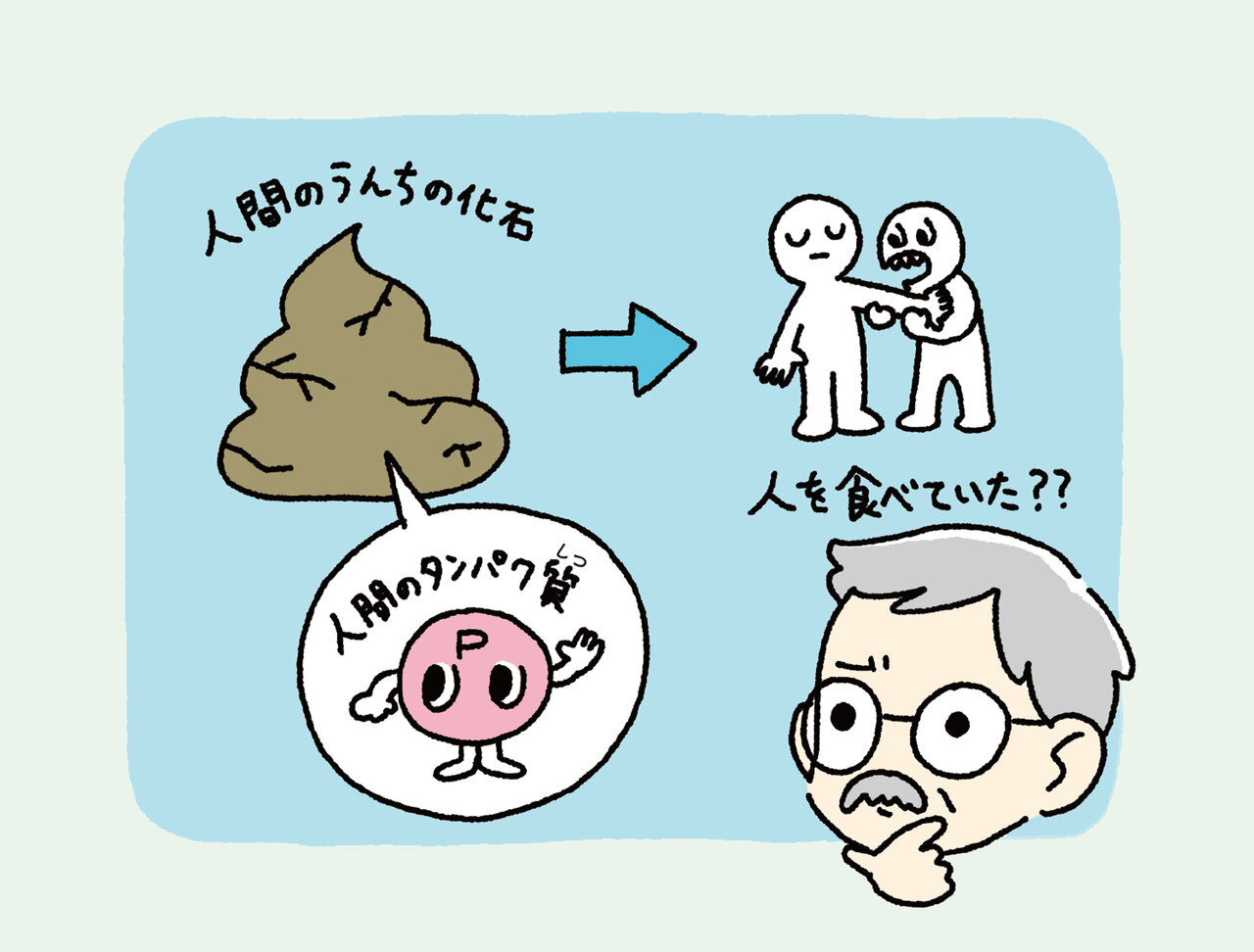














































































伊藤 弥寿彦
1963年東京都生まれ。学習院、ミネソタ州立大学(動物学)を経て、東海大学大学院で海洋生物を研究。20年以上にわたり自然番組ディレクター・昆虫研究家として世界中をめぐる。NHK「生きもの地球紀行」「ダーウィンが来た!」シリーズのほか、NHKスペシャル「明治神宮 不思議の森」「南極大紀行」MOVE「昆虫 新訂版」など作品多数。初代総理大臣・伊藤博文は曽祖父。
1963年東京都生まれ。学習院、ミネソタ州立大学(動物学)を経て、東海大学大学院で海洋生物を研究。20年以上にわたり自然番組ディレクター・昆虫研究家として世界中をめぐる。NHK「生きもの地球紀行」「ダーウィンが来た!」シリーズのほか、NHKスペシャル「明治神宮 不思議の森」「南極大紀行」MOVE「昆虫 新訂版」など作品多数。初代総理大臣・伊藤博文は曽祖父。