
働く日を1日、まるっと減らす
日本では、佐川急便やユニクロが1日の労働時間を10時間とし、週休3日を実現しています。
ファミリーマートやリクルートなども、週休3日制を導入し柔軟な働き方を取り入れていることが知られています。
また、たとえば私が住んでいるフランスでは数年前から、民間企業での週休3日制が試されています。

2023年に週休3日で働いたフランスのサラリーマンは約1万人。
調査によると、それらの職場の8割は、日本と同じ「1日の勤務時間を長くして、休日を1日増やす」スタイルでしたが、一部では「1日の勤務時間やお給料はそのまま、休日を1日増やす」形を取っているのが分かりました。
つまり、働く時間をまるっと1日分、短くしたのです。
週休3日の実現、30年前からの取り組み
1日の勤務時間はそのままで、週休3日にする……一見「無理でしょ?」とも思える方法が、フランスで行われているのには理由があります。
さかのぼること約30年前の1990年代、労働時間を短くするいくつかの政策によって、週休3日制が部分的に実現されたのです。
具体的には、「正社員の定時の勤務時間を週4日・合計32時間にできる」というものでした。
当時のフランスは、今の日本とほぼ同じ「週39時間」が標準の労働時間。そして高い失業率が問題になっていました。

そこでフランス政府は、この「正社員の働く時間を週4日・合計32時間にできる」政策によって、「従業員1人の働く時間を短くして、より多くの人を雇ってほしい」と、企業へ働きかけたのです。
さらに、「労働時間を短くして正社員の雇用を一定以上増やした企業には、社会保障の負担金を減額する」という見返りをつけて、企業にアピールしました。
その後フランスではさらに労働法が変わり、標準の定時が「週35時間」と短くなったので、この見返りはなくなりました。
それでも「より短い時間で働く正社員」にはニーズがあったのでしょう。「部分勤務の正社員」の形で、今も残っています(時間を短縮した分、お給料は減らされます)。
週休3日で子育てしながらキャリアを続ける
私の知り合いにも、この「部分勤務の正社員」で働く親たちがいます。会社に行くのは週4日、残りの3日間は自宅で子どもと過ごしています。
子どもが小さいうちはそうして仕事を続け、小学校高学年になったら、週5日勤務の完全フルタイムに戻るつもりだそうです。
実際フランスでは、3歳未満の子がいる母親の7割ほどが、サラリーマンの仕事を続けています。そのうちの3人に1人が「部分勤務の正社員」です。
出勤する日数は少なくなるけれど、会社に行ける日はしっかりと定時で働く。
それができるなら、正社員としてキャリアを続けられる人は増えるだろうな……と、私自身も働く親の1人として感じます。
6人に1人が時短勤務のフランス
そしてこの働き方を必要とする人・望む人は、母親だけではありません。
2023年のフランスで「部分勤務」で働くサラリーマンは、女性が4人に1人・男性は10人に1人。その数は全体の約17%にあたる約420万人、ほぼ「6人に1人」です。
働く日を1日ではなく、半日だけ減らす人もいます。それでも職場や社会はさほど問題なく回っているので、週休3日を試す職場が出てきているのでしょう。
ですがフランス政府としては、この「働く時間を1日分減らす」方法を一般的にするのは、まだ早すぎると見ているようす。
今、国家公務員の週休3日制が試験的に導入されていますが、そこで取られたのは日本と同じ「1日の勤務時間を長くして、休日を1日増やす」やり方です。
働く時間を短くしたら、どう変わる?
実はヨーロッパにはフランスだけではなく、アイスランドやベルギーなど、週休3日をテストしている国や企業が他にもいくつもあります。
それらヨーロッパの国々に共通しているのは、1990年代から続いている「労働時間を今より短くして、より多くの人に働いてもらい、国の生産性を上げよう」という取り組みです。
そもそもなぜ、そのような取り組みをしているのでしょう?
長時間労働の問題を研究する、京都大学の柴田悠(しばた・はるか)教授はこう説明します。
「ヨーロッパの国々がそうしている理由は、長時間労働はできないけれど働く意欲のある、多様な人が働けるようにしたかったから。より少ない勤務時間・日数でも生産できるよう、デジタル化を進めて、効率的に働けるようにしたのです」
いっぽう日本では今も、多くの職場で長時間労働が根強く残っています。正社員には「週5日・残業あり」の働き方が求められていて、そうできない人は正社員になれない・正社員でいられない状況が続いています。
「日本では、これからますます人口が減っていく『人口オーナス期(※)』が続きます。さまざまな事情がある人も、その人に可能な形で働けるようにしなければなりません」(柴田先生)
(※注:少子高齢化など人口の構成変化で経済にマイナス影響がある状態。オーナスとは負担、重荷という意味)
今の日本では人手不足が言われていますが、実は、働き手はいます。ないのは、その人たちが働ける条件の、仕事のほうではないでしょうか。
この4月から「希望する人の週休3日制」が始まった東京都では、まさにこの点を導入の理由としています。
子育てや介護など、さまざまな事情を抱える職員が増える中、選択肢を増やすことで、より多くの職員が働きやすい環境を整えていこう──週休3日制は、その環境整備の一つとして発表されました。
日本で土・日を休業とする「完全週休2日制」が導入されたころにも、「休日を増やして大丈夫なのか」という声はありました。ですが今では、広く日本社会に定着しています。
まず制度を整えたら、それを使っていくうちに社会が変わっていく。
週休3日制も、そんな変化の一つになるかもしれません。ぜひ、なってほしいです。
【参考・出典】
「週休3日制」試行に係るアンケート結果報告〔群馬県前橋市(2023年)〕
『週休3日』で働く-世界各国に広がる週4日勤務制・トライアル事例-(リクルートワークス研究所)
※フランスに関するデータやファクトは主に公的機関の情報を出典としています
https://dares.travail-emploi.gouv.fr
働き方・休み方を考えるときに読みたい本

日本と同じようにかつては「休めない国」だったフランス。今では仕事も経済も回しながらガッツリ休むようになったフランスのやり方をヒントに「休むための働き方」を考える。
第1章 休みベタな国から、休むために働く国へ
第2章 実録! 年5週間休む人々の働き方 ~ サラリーマン編
第3章 経営者&管理職が語る、休暇マネジメントの思想と実践
第4章 年休5週間が社会に与える影響は? データで見るバカンスの効能
第5章 今からできる! 法制度と実例から考える日本のバカンス

奏は最近、チアダンスに夢中だ。友達の愛里と叶翔と一緒に、毎日練習をがんばっている。
そんなある日、愛里のお父さんが倒れてしまう。原因は「働きすぎによる過労」だという。「たのまれたらつい、引き受けてしまう」人がそうなってしまいやすいと聞いて、奏はドキッとする。奏も、頼みを引き受けてしまうタイプだったから……。自分らしく働くって、なんだろう。いろいろな「働き方」を調べる奏のもとに、車いすダンサーといっしょに踊る機会が舞い込んできて……?




















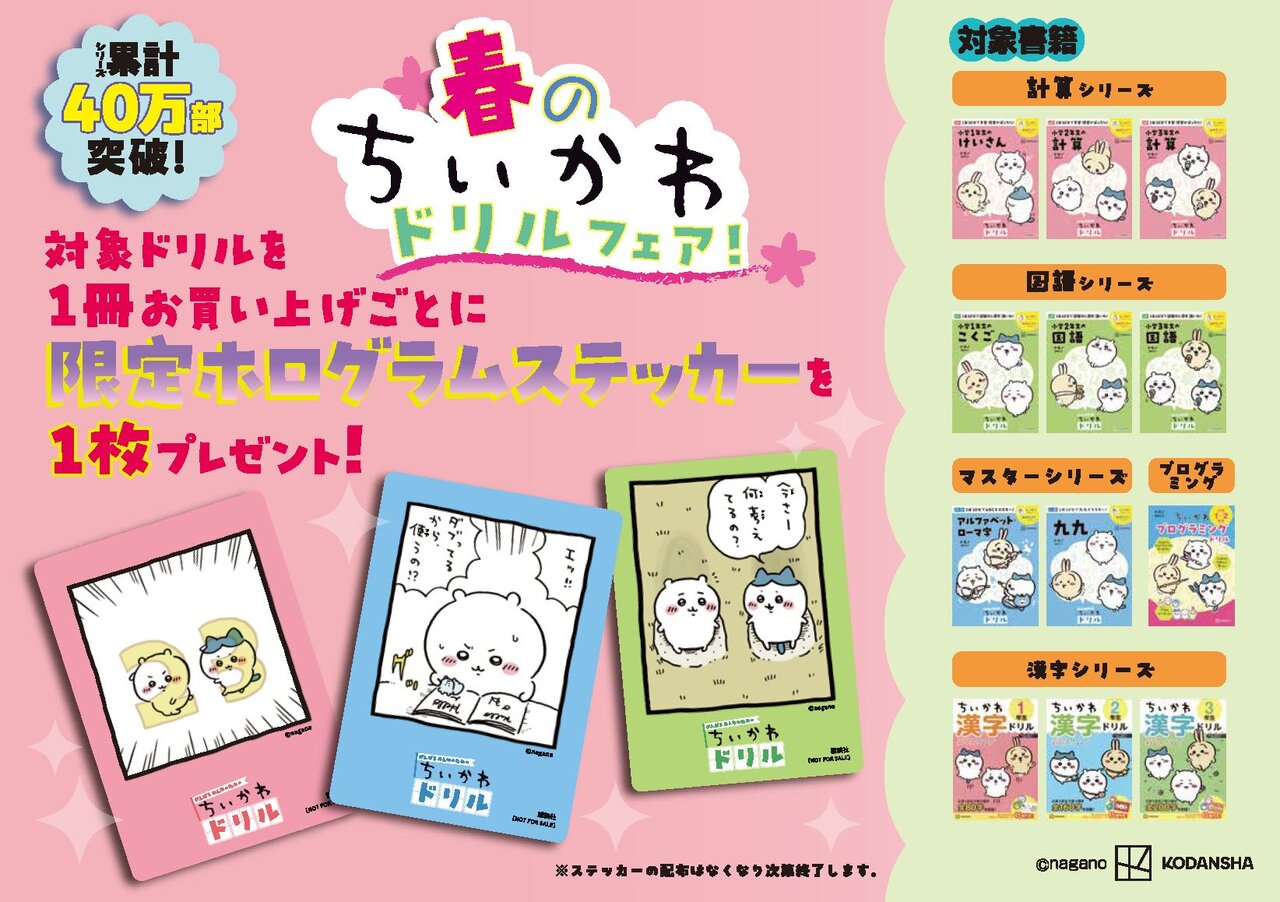
















































































髙崎 順子
1974年東京生まれ。東京大学文学部卒業後、都内の出版社勤務を経て渡仏。書籍や新聞雑誌、ウェブなど幅広い日本語メディアで、フランスの文化・社会を題材に寄稿している。著書に『フランスはどう少子化を克服したか』(新潮新書)、『パリのごちそう』(主婦と生活社)、『休暇のマネジメント 28連休を実現するための仕組みと働き方』(KADOKAWA)などがある。得意分野は子育て環境。
1974年東京生まれ。東京大学文学部卒業後、都内の出版社勤務を経て渡仏。書籍や新聞雑誌、ウェブなど幅広い日本語メディアで、フランスの文化・社会を題材に寄稿している。著書に『フランスはどう少子化を克服したか』(新潮新書)、『パリのごちそう』(主婦と生活社)、『休暇のマネジメント 28連休を実現するための仕組みと働き方』(KADOKAWA)などがある。得意分野は子育て環境。