

【読書嫌いも夢中に!】子育て世代必見! 子どもの知的好奇心を伸ばす〔3つのヒント〕
「読書週間」にもおすすめの本を紹介
2025.10.31

「読書の秋」と言われても、子どもがなかなか本を読んでくれない、どんな本を選べばいいか迷ってしまう。そんなお悩みを持つ親御さんは多いのではないでしょうか?
毎年10月27日から11月9日の「読書週間」は、子どもが本と出会う最高のきっかけです!
読書週間を充実させるための「具体的な方法とおすすめ本」をまとめました。
この記事で見つかる3つのヒント
・中学受験のテーマにもなった、子どもに多様な視点を育む一冊が見つかる!
・「はたらく細胞」など人気の知育本で、子どもが自発的に学習を始める秘密がわかる!
・漫画ノベライズを活用した、「読書嫌いを克服」させる魔法のテクニックが手に入る!
この秋、親子の会話が増え、子どもの学習意欲が伸びる。そんな最高の読書体験を、一緒にスタートさせましょう!
1【思考力UP】中学受験にも出題! 「多様性」を子どもに教える一冊
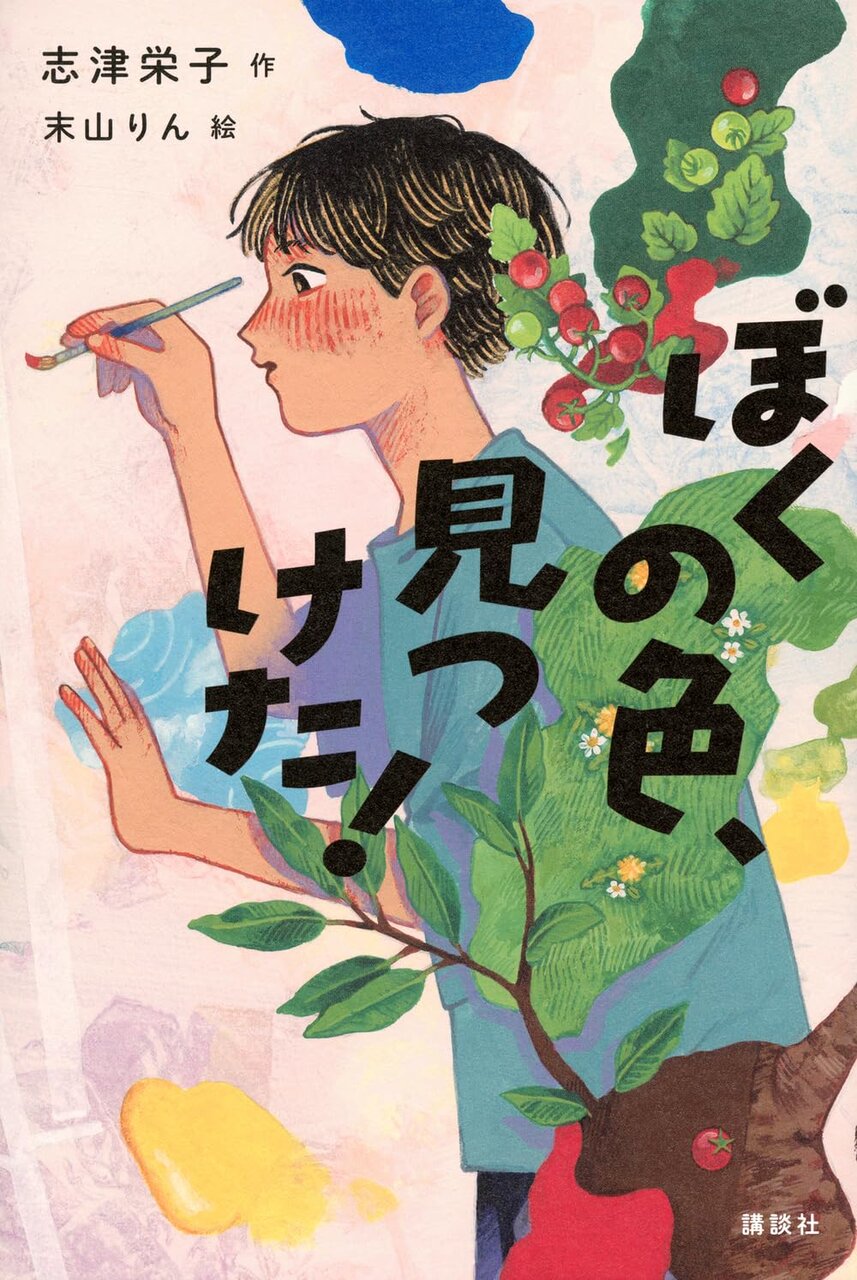
作:志津 栄子 絵:末山 りん
読書は、知識を増やすだけでなく、自分とは違う誰かの気持ちを想像したり、社会の様々なあり方を知ったりする機会を与えてくれます。これは、これからの時代を生きる子どもたちにとって、とても大切な「考える力」や「共感力」を育むことにつながります。
実は、近年の中学受験では、こうした社会の多様性に関するテーマが、課題図書や入試問題として取り上げられることが増えています 。
そこでおすすめしたいのが、元教師の作者が自身の実体験をもとに書いた児童文学、『ぼくの色、見つけた!』です。
この物語は、「色の感じ方の個性(色覚多様性)」をテーマにしています。主人公の男の子が、自分と他の人との「見え方」の違いに気づき、悩みながらも、ありのままの自分を受け入れていく姿が描かれています。
この本を通じて、子どもは「みんな違って、みんないい」という多様性の本質を、自然に学ぶことができます。そして保護者にとっても、子どもの小さな悩みや、他の子との違いにどう寄り添えばよいのか、大きなヒントをもらえる一冊です。
まずは難しいことを考えずに、物語として親子で楽しむことから始めてみてください。読んだ後、「主人公の男の子、どんな気持ちだったかな?」と話してみるだけで、子どもの心には、人を思いやる豊かな土壌が育っていくはずです。
〔知的好奇心を伸ばす 1つ目のヒント〕
紹介されている本: 『ぼくの色、見つけた!』
得られる知見: 中学入試の課題図書にも選ばれた、現代社会で考えるべき「多様性」や「ありのままを受け入れる心」を、子どもの目線で理解させる方法がわかります。
親子の学び: 作品を通して、子どもの小さな悩みや他者との違いをどう受け止め、どう寄り添うべきか、親として向き合うヒントが得られます。
▼【続きはこちら】課題図書から考える!多様性を育む児童文学▼
2【知的好奇心爆発】人気の知育本 「本を読んだら賢くなる」体験!
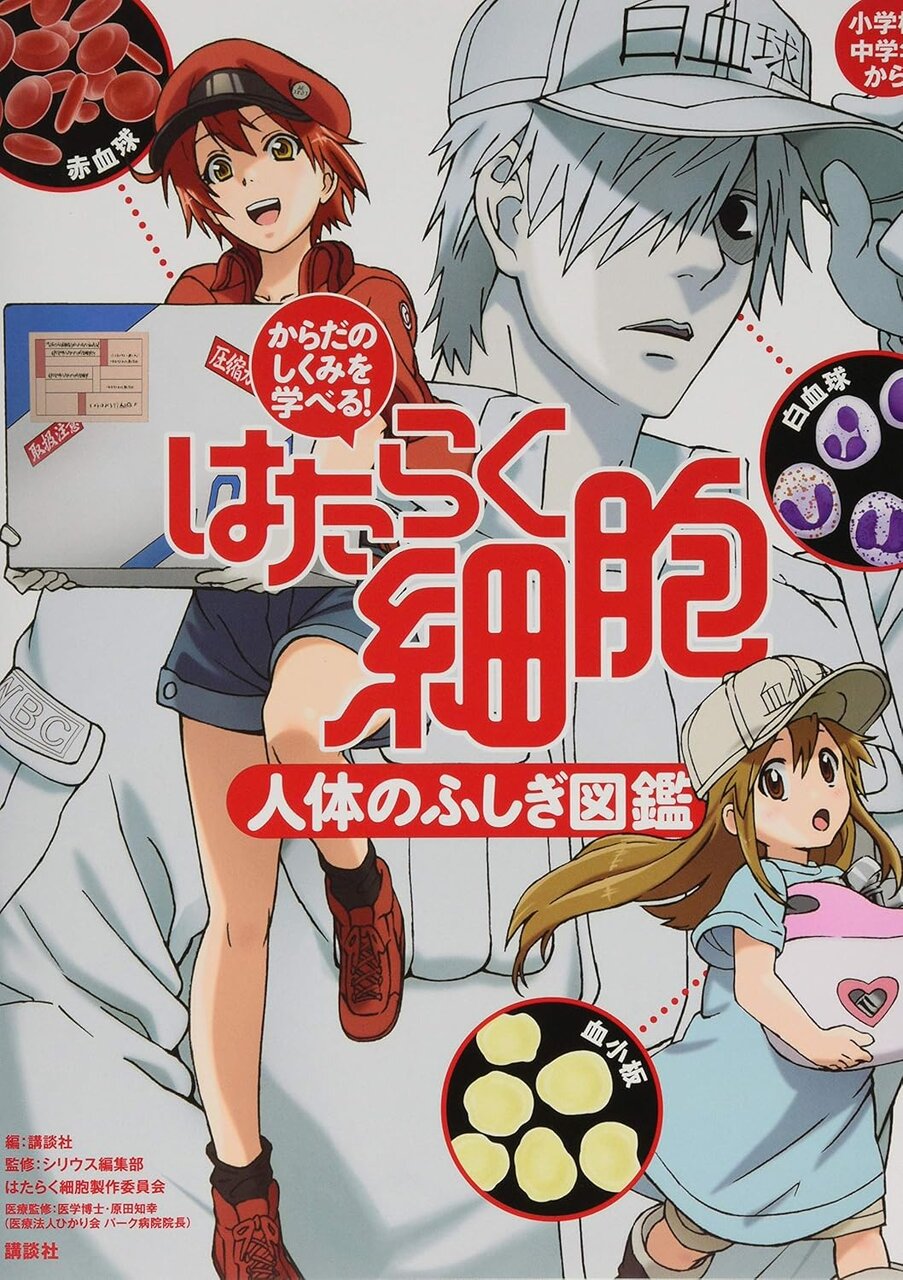
子どもたちの「これ、なあに?」「どうして?」という疑問のシャワーは、知的好奇心が豊かに育っている証拠です。その純粋な興味を「わかった!」という達成感に変えてくれるのが、知育本の持つ大きな力です。
特に、大人気シリーズ『はたらく細胞』の絵本や図鑑は、子どもの探究心に火をつけるのにぴったりのアイテム 。
私たちの体の中では、たくさんの細胞たちが一生懸命働いている――。そんな壮大な物語が、親しみやすいキャラクターたちによって、面白く解説されています。
このシリーズのすごいところは、子どもの興味に合わせてステップアップできる点です。
まずは漫画やアニメでキャラクターに親しみ、次に絵本でストーリーを楽しみ、さらに深く知りたくなったら図鑑を開く。この流れを親子で一緒に体験することで、子どもは遊びの延長線上で、自然に体の仕組みや免疫、感染症について学び始めます。
気づけば、「今日の給食の栄養は、どの細胞に届くのかな?」なんて、ハイレベルな「細胞トーク」が日常の会話に登場するかもしれません。
「勉強」と構えるのではなく、子どもの「なぜ?」に寄り添い、一緒にページをめくる時間そのものが、最高の知育体験になります。
〔知的好奇心を伸ばす 2つ目のヒント〕
紹介されている本: 『はたらく細胞 人体のふしぎ図鑑』『感染症を正しく学べる! ウイルス&細菌図鑑』など
得られる知見: 細胞やウイルスの知識が身につき、免疫や病気の仕組みを理解できるようになるため、ニュースで聞くワクチンや感染症の話題にも興味を持つようになります。
読書のコツ: 漫画やアニメから入って、次に絵本、そして図鑑へ、と子どもの興味を段階的に深め、学習の習慣化につなげる親子で実践できるステップがわかります。
▼【続きはこちら】 知育に最適!子どもが自発的に「細胞トーク」を始める方法▼
3【読書嫌い克服】漫画ノベライズで小説へ「最初の一歩」を!

もえぎ 桃 (著) リカチ (原著)
「漫画は大好きだけど、字だけの本はちょっと……」
そんなお子さんは、決して少なくありません。物語の世界を楽しむ力は十分にあるのに、活字の壁が、読書の楽しさから遠ざけてしまっているのかもしれません。
そんなときに、ぜひ試してほしいのが「漫画ノベライズ」という選択肢です。これは、人気の漫画を小説の形で書き起こしたもので、読書への「最初の一歩」を踏み出すための、魔法の架け橋になってくれます。
例えば、人気少女漫画『星降る王国のニナ』のノベライズ版は、多くの「活字が苦手」な子どもたちを小説の世界へと誘ってきました 。
なぜ漫画ノベライズが効果的なのでしょうか? それは、子どもたちがすでに大好きなキャラクターや、知っているストーリーだからこそ、安心して活字の世界に飛び込めるからです。頭の中で絵を思い浮かべながら読めるので、活字への抵抗感がぐっと下がります。
保護者としては、つい「ちゃんとした文学作品を読んでほしい」と思ってしまうかもしれません。でも、大切なのは、子ども自身が「読みたい!」と思う本を尊重してあげること 。「本は最高の娯楽なんだ」という視点を持つことで、子どもの読書習慣は、無理なく、長く続いていきます。
まずは「この漫画の小説版もあるみたいだよ」と、選択肢の一つとして見せてあげることから始めてみてはいかがでしょうか。
〔知的好奇心を伸ばす 3つ目のヒント〕
・紹介されている本: 『小説 星降る王国のニナ』
・得られる知見: 知っているキャラクターやストーリーだからこそ、活字への抵抗感が劇的に下がるという「漫画ノベライズ」の心理的なメリットがわかります。
・親の心構え: 子どもが本当に読みたい本を尊重し、「本は娯楽」として捉えることで、長続きする読書習慣を定着させる親の姿勢や声かけのヒントが得られます。
▼【続きはこちら】読書嫌いの子を救う!『星降る王国のニナ』で実践 ノベライズの活用術▼
今回ご紹介した3つのヒントは、あくまでたくさんの選択肢の中のほんの一部です。
大切なのは、お子さん一人ひとりの興味やペースに合わせること。そして何より、親子で本を囲む時間を「楽しいもの」にすることです。
焦らず、比べず、お子さんにぴったりの一冊との出会いを、ゆっくりと探してみてください。その一冊が、子どもの世界を豊かに広げる、大きなきっかけになるはずです。













![冬のギフトにぴったりな“雪の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/629/large/0368f492-6e08-49f4-8c18-b0d3c52fe98c.jpg?1770179405)
![【働くママの労働問題】「子持ち様」が気をつけるべき職場の人間関係のポイント[社労士が回答]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/623/large/5af9810f-c081-42b4-a484-d448e0f9e922.jpg?1770162654)






























































































