

「母だから・女だから」と言われて…坂東眞理子さんが「後輩ママ」に伝える「ジェンダーバイアス」との60年
2025.07.03
やってみなければわからない 挑戦のススメ
「“希少価値”が武器になって、やっと“自分らしさ”で勝負できるようになったんです」
そう坂東さんは振り返ります。

「現在でも、多くの女性が『管理職にはなりたくない』と口にします。“自分には能力がない”“向いていない”と思い込んでいる人が多いように思います」
「確かに昔は“俺についてこい”型のリーダーが主流でしたが、今は違います。チームで動き、支え合うスタイルに変わってきているんですよ。能力がないかどうか、向いていないどうかは、やってみなければわかりません」
それでも、「断ったほうが賢明だ」と考える女性が多いのが現実です。
「経験してみれば、“リーダーになることで視野が広がる”という実感があるはずです。でも、最初から遠慮していたら、そのチャンスに出会えません」
坂東さんは強調します。
「私は特別に優秀だったわけではありません。ただ、やってみたら意外とできた。ですから、普通の人こそ、自分を信じて挑戦してほしいと願っています」
「仕事か、家庭か」のプレッシャー
坂東さんが働きながら子育てをしていた昭和50年代は、仕事を持つ母親はまだ珍しく、支援制度も乏しい時代。保育園に入るのですら簡単ではありませんでした。
「家庭の中では『俺を取るか仕事を取るか』と迫ってくる男性が普通にいた時代です。職場でも『仕事の代わりをしてくれる人はいくらでもいるけど、子どもの母親は君だけだよ』と、“優しさ”を装ったプレッシャーをかけられることがありました」
「男性が同じようなことを言われることは、まずありません。『君の子どもの父親は君だけだよ、父親なんだから早く帰りなさい』なんて言われた男性はいないでしょう?」
当時、坂東さんに限らず、働きながら育児をする女性は、社会からも家族からも、そして、ときとして、自分自身からも「母親はこうあるべき」という基準からはずれていました。
「今でもそうかもしれませんが、子どもに対して『ごめんね』と思いながら働いているお母さんは少なくないと思います。自分で自分にプレッシャーをかけているんですね。私自身もそうでしたが、まず、そこから解放されなきゃいけない」
完璧じゃなくてもいい
私は完全な母親ではない、育児が十分でない、時間が足りない、能力が足りない……。坂東さんは、こんなふうに思っていたといいますが、あるとき、「じゃあ、どこに100%完全なお母さんがいるの?」と、発想を転換。
「完全な母親なんていない。どの子も、100%完璧な環境にいるわけじゃない。そんなふうに考えたら、気持ちが少し楽になりました。ですから、私は、みなさんにも、自分を追い詰めすぎないで、と伝えたいです」
世の中は少しずつ変わってきています。例えば、坂東さんが総長を務める昭和女子大学附属のこども園では、いまや朝の送りの多くを父親が担当しているという現実を見ても、それは明らか。
「本当に驚きます。時代は確実に変わってきているんですね。もちろん地域によってまだまだ課題もありますが、女性だけが頑張る必要はない。“夫婦で育てる”という意識が少しずつ根づき始めていると感じます」
そしてもう一つ。昭和・平成・令和の時代を「母親なんだから」「女なんだから」の声と闘い続けてきた坂東さんからのアドバイス。
働く女性「数の多さ」がパワーに

「かつては、私のように働きながら子育てをする女性は少数派。“私は仕事も育児も中途半端”などと自分を責めたり、挙げ句、泣く泣く仕事を辞めたり……。マイノリティは押し潰されていたわけです。でも、そのマイノリティが増えると受け入れられていくように思います。出産しても働く女性が増えていますから」
「数が多いと世の中に与える影響力も大きくなります。人によって事情や立場はさまざまですが、『働きたい』と考える女性は、どんどん外に出て働いてほしいと思います」
こう言ったあと、「私を見て」と笑う坂東さん。
「私なんか、でこぼこで、できないこともいっぱいあります(笑)。だけど、どうにかここまでやってきました。今はまだジェンダーバイアスが溢れている時代で、みなさん悩むことも多いでしょう。それでも生きていれば、細かいところでは悩まなくなるもの。生きるのが容易になりますよ」
坂東さんは「悩んでも何も生まれないんです」と、おおらかに生きることの大切さを明るく語ります。「逆風」の中でも歩みを止めることなく、前に進んできた坂東さんだからこその、説得力のある言葉。
その柔らかな物腰と笑顔が、令和の時代を生きる私たちの背中をぽん! と押してくれるようです。
─────────────────────
坂東眞理子さんへ「子育てとジェンダーバイアス」をテーマに伺う連載は前後編。
親の「ジェンダーバイアス」について、子どもの個性との向き合い方をお聞きした前編に続き、今回の後編では、ジェンダーバイアスを乗り越えてきた坂東さんの半生と子育てについてお聞きしました。
【参考】
厚生労働省 令和3年版働く女性の実情
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/21.html
男女雇用機会均等法成立35年を迎えて
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/21-03.pdf
撮影/市谷明美



佐藤 美由紀
広島県福山市出身。ノンフィクション作家、ライター。著書に、ベストセラーになった『世界でもっとも貧しい大統領 ホセ・ムヒカの言葉』のほか、『ゲバラのHIROSHIMA』、『信念の女 ルシア・トポランスキー』など。また、佐藤真澄(さとう ますみ)名義で児童向けのノンフィクション作品も手がける。主な児童書作品に『ヒロシマをのこす 平和記念資料館をつくった人・長岡省吾』(令和2年度「児童福祉文化賞」受賞)、『ボニンアイランドの夏:ふたつの国の間でゆれた小笠原』(第46回緑陰図書)、『小惑星探査機「はやぶさ」宇宙の旅』(第44回緑陰図書)、『立てないキリンの赤ちゃんをすくえ 安佐動物公園の挑戦』、『たとえ悪者になっても ある犬の訓練士のはなし』などがある。近著は『生まれかわるヒロシマの折り鶴』。
広島県福山市出身。ノンフィクション作家、ライター。著書に、ベストセラーになった『世界でもっとも貧しい大統領 ホセ・ムヒカの言葉』のほか、『ゲバラのHIROSHIMA』、『信念の女 ルシア・トポランスキー』など。また、佐藤真澄(さとう ますみ)名義で児童向けのノンフィクション作品も手がける。主な児童書作品に『ヒロシマをのこす 平和記念資料館をつくった人・長岡省吾』(令和2年度「児童福祉文化賞」受賞)、『ボニンアイランドの夏:ふたつの国の間でゆれた小笠原』(第46回緑陰図書)、『小惑星探査機「はやぶさ」宇宙の旅』(第44回緑陰図書)、『立てないキリンの赤ちゃんをすくえ 安佐動物公園の挑戦』、『たとえ悪者になっても ある犬の訓練士のはなし』などがある。近著は『生まれかわるヒロシマの折り鶴』。




















![【働くママの労働問題】「休憩時間はいらないから1時間早く退社したい!」これってできる?[社労士が回答]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/033/863/large/ce2347fc-d40d-4f17-a9be-b10df83ca08f.jpg?1754022044)















































































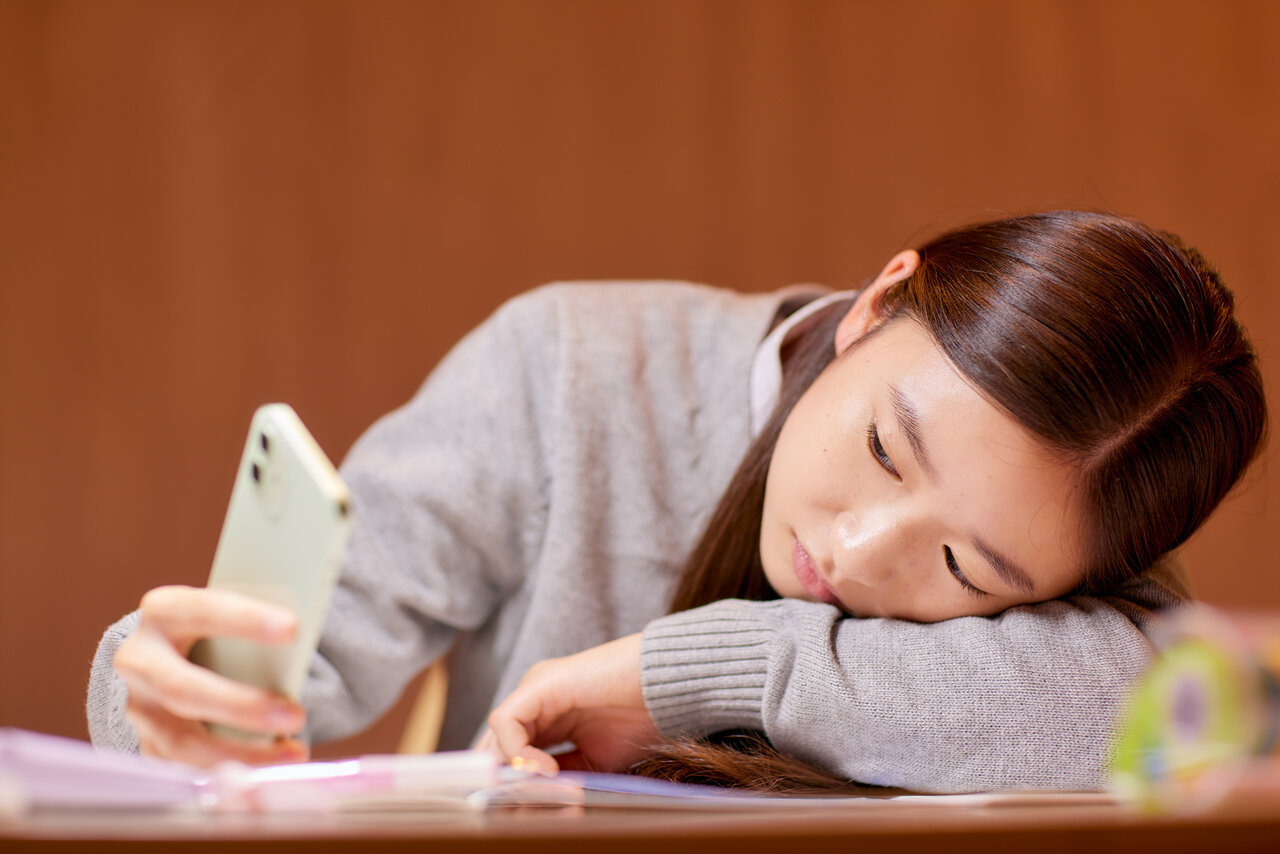









坂東 眞理子
1946年、富山県生まれ。東京大学卒業。1969年総理府入省。内閣広報室参事官、男女共同参画室長、埼玉県副知事等を経て、1998年女性初の総領事(オーストラリア・ブリスベン)。2001年内閣府初代男女共同参画局長。2004年昭和女子大学教授となり、同大学女性文化研究所長、2007年同大学学長、2014年同大学理事長、2016年から同大学総長。 ベストセラー『女性の品格』『親の品格』(以上、PHP新書)のほか『錆びない生き方』(講談社)『美しい日本語のすすめ』(小学館101新書)『幸せの作法』(アスキー新書)『大人になる前に身につけてほしいこと』(PHP研究所)『祖父母の品格 孫を持つすべての人へ』(朝日新聞出版)など著書多数。
1946年、富山県生まれ。東京大学卒業。1969年総理府入省。内閣広報室参事官、男女共同参画室長、埼玉県副知事等を経て、1998年女性初の総領事(オーストラリア・ブリスベン)。2001年内閣府初代男女共同参画局長。2004年昭和女子大学教授となり、同大学女性文化研究所長、2007年同大学学長、2014年同大学理事長、2016年から同大学総長。 ベストセラー『女性の品格』『親の品格』(以上、PHP新書)のほか『錆びない生き方』(講談社)『美しい日本語のすすめ』(小学館101新書)『幸せの作法』(アスキー新書)『大人になる前に身につけてほしいこと』(PHP研究所)『祖父母の品格 孫を持つすべての人へ』(朝日新聞出版)など著書多数。