

舌切りすずめが食べていた「のり」の正体とは!? 昔はのりとして何を使っていた?
ざんねん? びっくり! な文房具のひみつ事典(4:のり) 文房具ライター・ヨシムラマリ
2024.06.22
文房具ライター:ヨシムラ マリ

私たちがふだんつかっている、鉛筆や消しゴムなどの文房具。いろいろな文房具の誕生したときには、「どうしてこうなった!?」と思ってしまう“ざんねん”なものや、いま見ても「すごいなあ!」と“びっくり”しちゃうものまでさまざま。そんなおもしろくてためになる、文房具の世界をのぞいてみましょう。
昔はニカワというものをよく使っていた
今みたいなのりができる前、5000年以上も昔からつかわれていたのりのひとつに、ニカワがあります。
おもな成分は、動物の皮や骨ずいからとれるゼラチンです。
ゼラチンはゼリーの材料ととしてもおなじみですね。

ニカワは、そのままだとカチカチにかわいてしまいます。
のりとしてつかうためには、丸一日水のつけてふやかしてから、お湯であたためてとかさなくてはいけません。
このとき、あたためすぎてもダメなので、なかなかめんどうです。
それに動物の皮や骨からできているので、ツーンとしたくさいにおいもします。
日本でよく「のり」として使われていたモノ
フエキ糊やヤマト糊のようなでんぷんのりは、日本では平安時代のころからありました。
昔はお米を煮て作ったものだったので、ほぼおかゆですね。
おとぎ話の「舌切りすずめ」では、おばあさんが作ったのりをスズメが食べてしまって、怒ったおばあさんに舌を切られます。
そんなざんねんなことになったのも、のりがお米で作られていたから。
本物のスズメも、じつはお米が大好物なので、そんなお話ができたのかも?







































































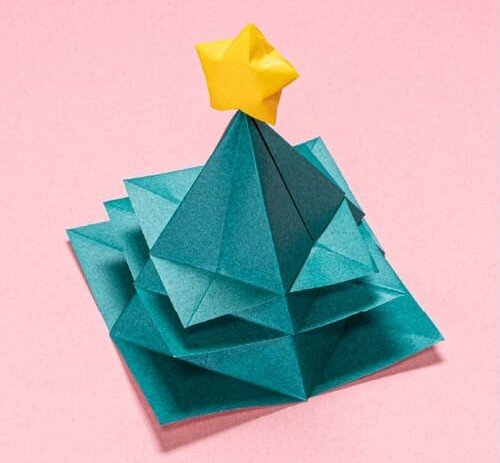










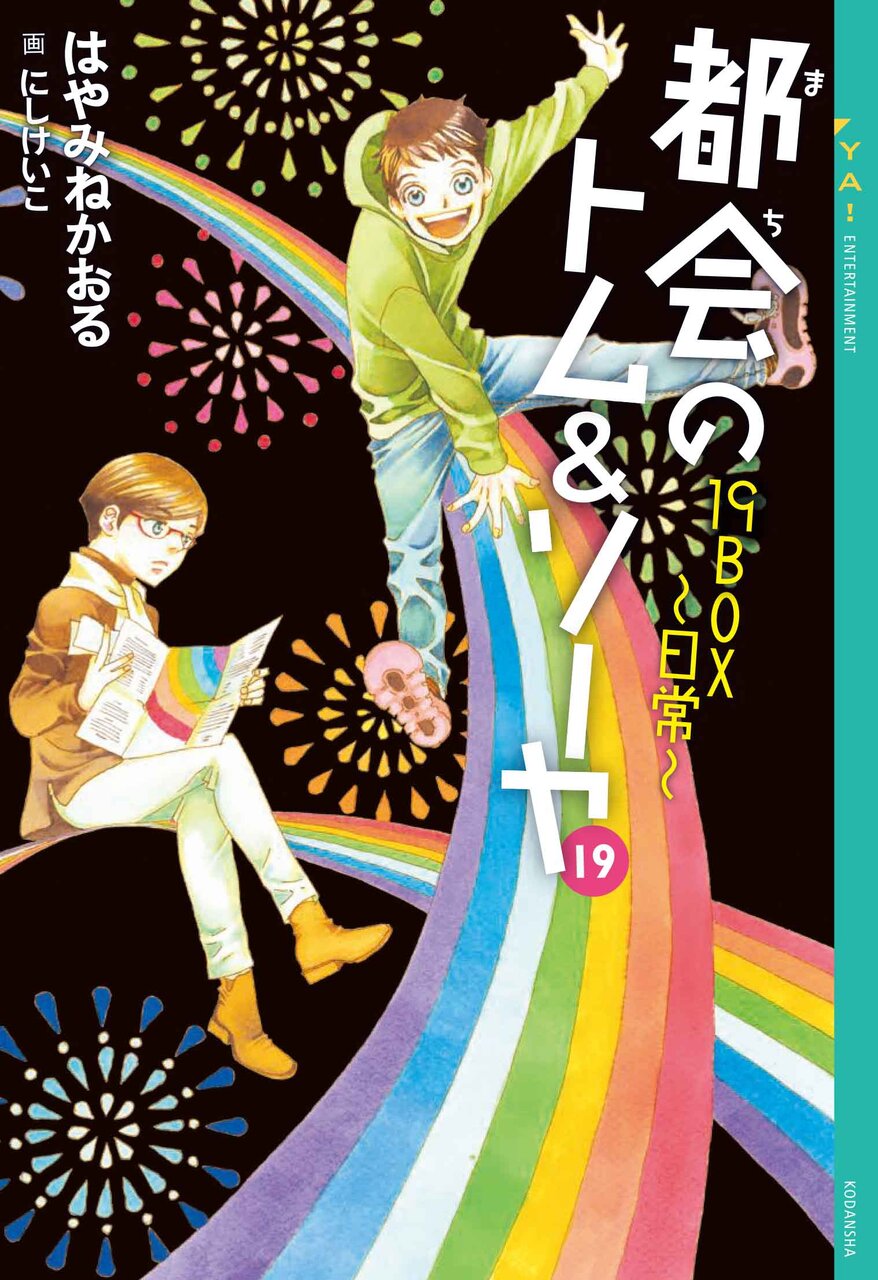





























ヨシムラ マリ
ライター/イラストレーター。1983年生まれ。神奈川県横浜市出身。子どもの頃から絵を描くのが好きで、身近な画材である紙やペンをきっかけに文房具にハマる。主な守備範囲はノートとペンと事務用品。 文具・オフィス用品メーカー大手の元社員で、現在は脱サラしてフリーランスとして活動中。著書に『ざんねん? びっくり! 文房具のひみつ事典』(講談社)、『文房具の解剖図鑑』(エクスナレッジ)がある。
ライター/イラストレーター。1983年生まれ。神奈川県横浜市出身。子どもの頃から絵を描くのが好きで、身近な画材である紙やペンをきっかけに文房具にハマる。主な守備範囲はノートとペンと事務用品。 文具・オフィス用品メーカー大手の元社員で、現在は脱サラしてフリーランスとして活動中。著書に『ざんねん? びっくり! 文房具のひみつ事典』(講談社)、『文房具の解剖図鑑』(エクスナレッジ)がある。