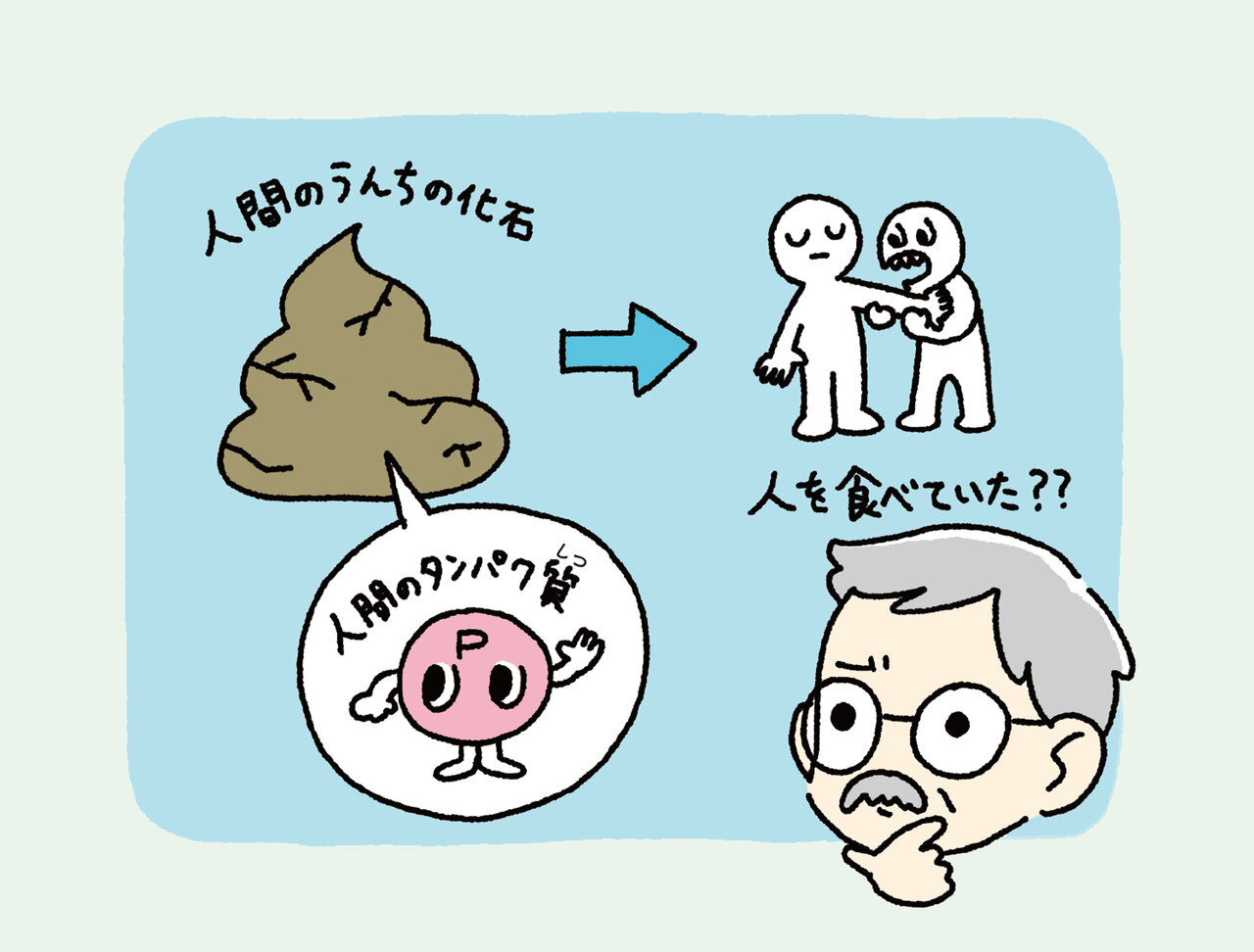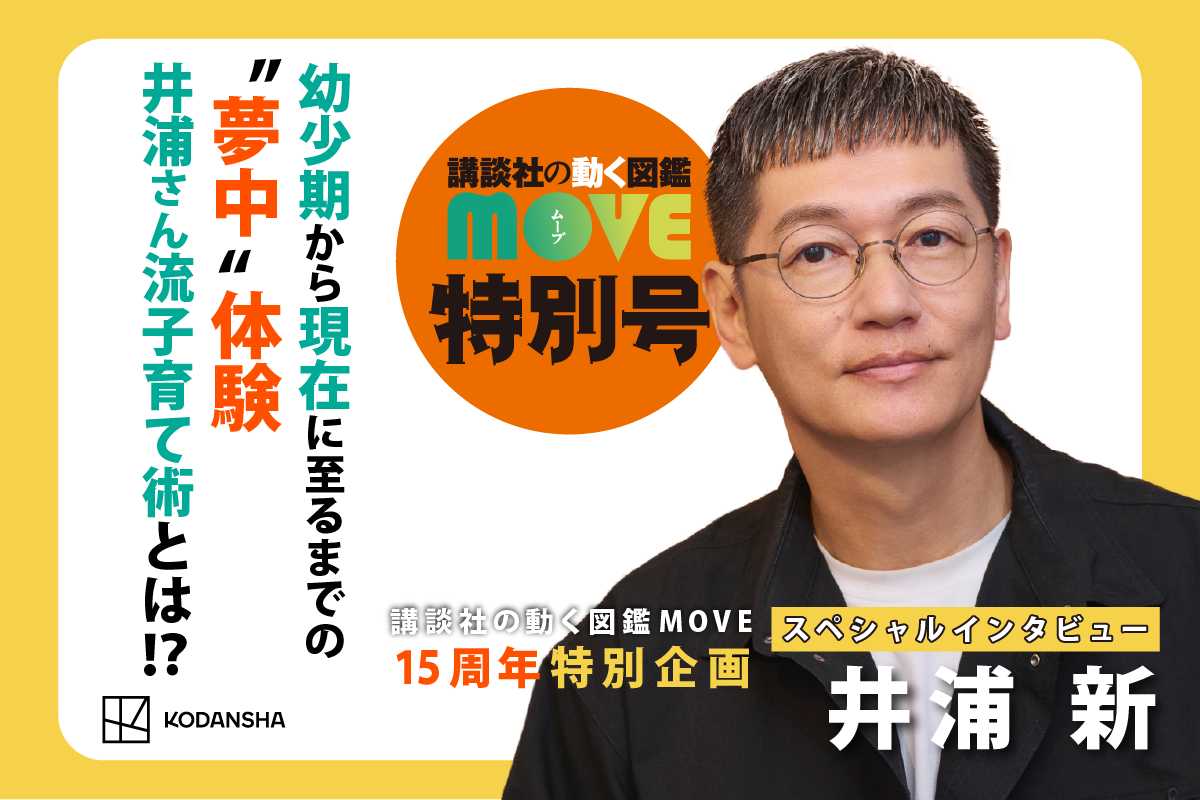虫たちが冬眠から目覚める啓蟄の季節! 昆虫の観察・撮影のコツをプロが伝授!
「はじめてのずかん こんちゅう」は昆虫の生体写真が満載!
2022.03.07
ことしの昆虫観察は写真撮影にこだわってみよう
それはどうやら標本ではなく、生きた昆虫の写真を使っているから。昆虫の本当の姿が見られ、昆虫の顔の表情まで見られるような動きのある写真が並んでいます。その写真のほとんどは「伊丹市昆虫館」の館長・奥山 清市さんが撮影したもの。生体写真の撮影のコツや、昆虫観察の方法について、お話を聞いてみました。
1970年山形県生まれ。1995年より伊丹市昆虫館に勤務。現在は同館館長を務める傍ら、昆虫たちをパートナーに「学び」「驚き」「笑い」「癒し」を多くの方に届ける手段として、写真撮影にも取り組む。著書に「くらべてわかる昆虫」(山と渓谷社)「超拡大で虫と植物と鉱物を撮る—超拡大撮影の魅力と深度合成のテクニック」(文一総合出版)など。
 <うかがった質問はこちら>
<うかがった質問はこちら>
① 白バック(白の背景)で、生体写真を撮影する時のこだわりのポイント、苦労した点
② 生体写真と標本写真のそれぞれのいいところ
③ 未就学児親子が昆虫を観察するときのポイント)
「まずは、昆虫たちのできるだけ“生き生き”とした姿を撮影したいと思っているのですが、昆虫たちはじっとしてくれるはずもなく、逃げる、跳ねる、飛ぶ、噛む、刺すなどしてくるので、それをなんとか落ち着いてもらうのが、本当に大変。
それをどうやって落ち着かせているのか、というと、最近は『ひたすら待つ』の一択です(笑)虫たちが良いポーズをとってくれるまで、徹底的につきあう覚悟で挑んでいます」

こうして撮影していると、標本や生態写真では感じることができなかった“かっこよさ”を感じることがあるので、やめられませんね。まったく興味のなかった昆虫(失礼)を、ふと白バックで撮影してみて、パソコンの画面でみたとき、『もしかしてけっこう良い虫かも』と気づいてしまうことが多々あり、その結果、これまでノーマークだった虫が、いつのまにか大好きな虫に変わるきっかけになることも少なくありません。
ちなみに、理想の白バック写真というか究極は、ど根性ガエルのぴょん吉です(笑)つまり、生きたまま平面に封じ込めたと錯覚するような写真ですね」
「生体写真は、やはりリアルなポーズ、実際に実物と出会った時と同じ姿、同じポーズを記録できることですね。これは、昆虫の生き生きとした姿を記録するだけでなく、野外で出会ったときに、見分けるためにとても実用的でもあります。昆虫の姿、形をキャッチーにわかりやすく観察するのにむいています。
ただし、白バックでは、ポーズによってはどうしても、隠れて見えない部位がでてくるのです。標本写真では、そういう部分が少ないし、じっくり細部を確認することがきることがよいところですね。昆虫の特徴をまるごとじっくり観察するのにむいています」

子どもと昆虫観察をするとき親がやるべきことは?

「実は、虫をみつける力は、大人や小学生よりも未就学児のほうが格段に優れていると思います。へんな先入観がないのと、やはり視点が低いというのが大きいかと思います。なので、親子でさがす場合は、未就学児に見つけてもらうのがよいでしょう。
見つけたときに褒めてあげれば、モチベーションもあがりますし、逆に親も虫探しのテクニックを教えてもらうことができます。そして、親も童心にかえって、いっしょに虫探しをするのがよいと思います。
ただ、未就学児はあまりつかまえるのは上手じゃないので、つかまえるアシストを親がしっかりやってあげる必要があります。ここで大切なので、かわりにとってあげるのではなく、あくまでもアシストに専念することです。
自分でつかまえた虫というのと、とってももらった虫というのでは、未就学児のモチベーション持続がぜんぜん違います。ただ、逃がすと、パパがあのとき、へんに動いたからだとか、声を出したからだとかブチブチと文句を言われてしまいますが(笑)それも試練です。
つかまえた虫は、100均などで売っている、透明なケースにいれて、名前調べと観察(ここではじめて図鑑の出番ですね)をおこなってから、逃してあげるのがよいかと思います。もちろん、家につれてかえって飼いたいというのであれば、その意志を尊重して手伝ってあげてください」