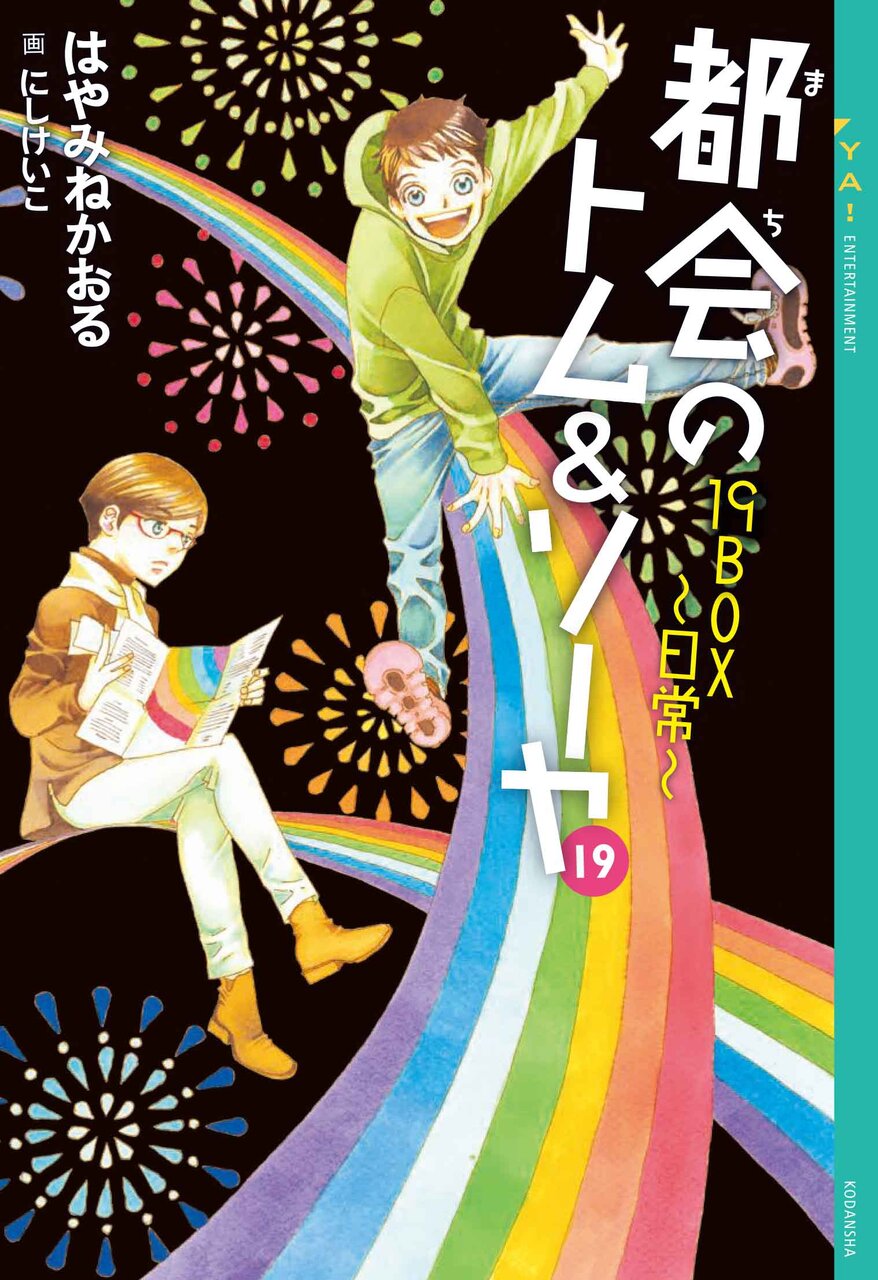今、読みたい! 瀬戸内・小豆島が舞台の名作「二十四の瞳」
昭和の小豆島を舞台にした、涙と笑顔の感動ストーリー
2025.07.05
青い鳥文庫で日本の名作「二十四の瞳」を読もう!
壺井栄は、1899年香川県の小豆島(しょうどしま)で生まれ、大正時代に上京。のちに詩人の壺井繁治(つぼい しげじ)と結婚し、小説、随筆を1500篇あまり発表しました。
その代表作が、「二十四の瞳(にじゅうしのひとみ)」。新米先生と12人の子どもたちの心のふれあいを描いたこの作品は、映画化もされて大ヒット!
小豆島は、瀬戸内では淡路島につぐ大きさの島で昔から花こう岩とそうめん・オリーブが有名。ですが、「二十四の瞳」で、それにもまして広く日本中に知られるようになりました。
島の港には、「二十四の瞳」の像がたてられ、今も観光客を出迎えています。
『二十四の瞳』

 「おはよう!」
「おはよう!」
1928年(昭和3年)春、小豆島のみさきの村に、新しい女の先生がやってきました。いつものように新米の先生をいじめようと待ちぶせていた子どもたちは、びっくり。その先生は、洋服を着て、自転車にのって軽快な姿であらわれたのでした。
そんな大石先生と、12人の1年生の子どもたち。笑いあり、涙ありの心温まる毎日が丁寧にえがかれます。
そして生活に少しずつ、でも確実に影を落とす戦争の存在。子どもたちはぐんぐん成長していきますが、貧しさや徴兵の影響を受けて困難におちいっていきます。
生まれたときから戦争があり、教育を受けて自分もいつかは国のためと信じて疑わない子。夫を戦争に送り出し複雑な気持ちの大石先生。女に生まれたことを残念と思い、レールを敷かれた運命を受け入れる子。「しもた!」と言いながら徴兵されていった子。
さまざまな人々の思いと運命をえがいた、戦争の悲惨さを伝えながらも、日常の尊さを温かくえがく、不朽の名作。
このほかにも、青い鳥文庫には日本の名作がいっぱい。あなたのお気に入りを見つけてみてね!