

子どもたちに大人気の「日曜日」シリーズが完結! 最終巻『地下室の日曜日 ゆめのこうきゅうマンションだ!』にこめた想いを、村上しいこさんと田中六大さんに聞きました!
シリーズ完結記念! 村上しいこ×田中六大インタビュー2
2025.07.03
編集者・文筆業:高木 香織

写真:森清
2010年に刊行されてから15年間にわたり、全30巻続いた「日曜日」シリーズが、『地下室の日曜日 ゆめのこうきゅうマンションだ!』で完結しました。子どもたちがいない学校の日曜日に、教室にある道具や備品がのびのびと活躍するお話は、子どもたちに大切に読み継がれてきました。なぜ日曜日シリーズはこんなにおもしろいの? 子どもたちに伝えたい想いは? そんなことを知りたくて、作者の村上しいこさんといきいきとした絵を描いてきた田中六大さんにお話を伺いました。15年間を振り返り、最初の刊行のいきさつから150近くものキャラクターの裏話まで、ワクワクの秘密がいっぱいですよ!

「地下室」の住人たちが18階建てのマンションに引っ越し?
──このたび完結編として『地下室の日曜日 ゆめのこうきゅうマンションだ!』が刊行されました。ところで小学校には、地下室があるのですか?
村上しいこさん(以下、しいこさん):音楽室や理科室、図書室などの学校の10の教室を20巻で2回ずつ取り上げてしまい、「続きをどうしよう?」となったときに、まだ取り上げていないパソコン室や放送室がまず思い浮かんだんです。でも、実際に小学校に取材に行って見せてもらったら、パソコン室はパソコンしかない。放送室はマイクとミキサーしかなくて、これではキャラクターが作れないな……と困ってしまって。それで、小学校に通っているお子さんを持つおかあさんたちにお話を聞いてみたのです。すると、最近は防災室やあそび室、用具室などがあるというのです。
──防災意識の高まりや、子どもたちの学校生活の変化を受けてそういう教室も増えているんですね。
しいこさん:そうなんです。それと、架空の地下室を舞台にするというアイディアも浮かんで、担当編集者に相談すると「もう日曜日シリーズという世界観ができているから、実際にない部屋でもいいですよ」と言ってくださったんです。
それで、防災室、用具室、資料室、あそび室に地下室を取り上げることになり、この5部屋を2巡して、10巻作ることになったのです。

村上しいこさん
田中六大さん(以下、六大さん):『地下室の日曜日 ゆめのこうきゅうマンションだ!』では、いつも日が当たらない地下室にいるキャラクターたちが、18階もある高いマンションに行こうとするのがおもしろかったですね。
──本の表紙裏の「せんねん町の地図」の真ん中に、大きいマンションが描かれました。今は日本中に細いマンションがにょきにょきできていますから、まさにタイムリーなお話ですよね。
作画も手描きからフルデジタルへ変化
六大さん:道具や物じゃない、人間や妖怪のようなキャラクターが増えましたよね。
しいこさん:ろくろ首にしゅくだいこぞう。しゅくだいこぞうって、なんやって話(笑)。地下子さんと雪女がかわいいね。原稿を六大さんに渡すと、「どんな絵が上がってくるのかな」と楽しみでした。
六大さん:30巻も書いている間に、絵のタッチも変わりました。最初はフェルトペンのような筆ペンで描いていたのですが、今は毛筆の筆ペンを使っています。着色は、28巻まではコピック(マーカーの一種)で塗っていました。29巻ではコピックとパソコンソフトのフォトショップを試させてもらいました。アナログとデジタルのミックスですね。
30巻の着色は、フルデジタルです。本のカバーの雪女の青い着物と、しゅくだいこぞうの緑のシャツの色がすごくきれいに出ました。この青は、コピックではなかなか出ないんですよ。

上が初期のころに使っていたフェルトの筆ペン。下は毛筆の筆ペン。
「ろくろ首が橋の下からびゅーんと首を出す」イメージを絵でわかりやすく
──絵を描くとき、どこを工夫されていますか。
六大さん:楽しく読めるように意識しています。それから、小さな子が文字だけでは想像できないことを、絵で補助してあげるつもりで描いています。キャラクターがどこにいるか、位置関係はどうなっているか。子どもたちがうまくイメージできるように描いています。
『地下室の日曜日 ゆめのこうきゅうマンションだ!』には、川のそばで話しているシーンがあります。でも、どんな位置で話しているかが文章だけではわかりにくいかもしれません。
例えば、「ろくろ首は、橋の下から、びゅーんと、首をのばしていきました。」という文があります。この「びゅーんと橋の下から首を出す」というイメージを絵で表しました。こんな構図も面白いかなと思って。
しいこさん:面白かったですね。日曜日シリーズは、子どもたちは絵をとても楽しむのよね。

ろくろ首は、橋の下から、びゅーんと、首をのばしていきました。
六大さん:バンクシー、ならぬドンクシーが登場したのはびっくりしました。しかも、そのドンクシーが描いた絵は、しいこさんから「牛みたいな動物を、子どもが、せおっています」と指定されていて、その発想にまたまたびっくりしました。「ドンクシーの絵」は、なぜ、子どもが牛を背負っているんですか?
しいこさん:牛が子どもを背負っていたら、あたりまえじゃない(笑)。
実は以前、六大さんの個展を観に行ったら、写実的な絵が展示されていたんです。その絵が素晴らしくて、いつか鉛筆だけで描いたデッサンのような「ザ・絵描き」という絵を描いてもらいたい、と思っていたのです。ちょうどバンクシーが世間を騒がせていたので、入れてみました。

バンクシー、ならぬドンクシー
子どもたちで相談して、考える力をつけてほしい
──かっぱおんせんのおばちゃんやおまわりさんなど、街の大人たちも魅力的な人が多いですよね。登場人物にモデルはいるんですか?
しいこさん:どうですかね……。でも、日曜日シリーズに登場する大人って、後ろめたさがあったり、怪しかったり、失敗ばかりしていたり、子どもより子どもっぽかったりするんですよ。本を読んだ子どもたちが「こんな大人もおるよねー」と思うようなキャラクターにするようにはしています。親や学校の先生のように、正しいことをきちんと言う大人は極力描かないようにしています。その逆を書きたいのです。
大人だって、むかしはみんな子どもだったわけですよね。今の子どもたちって、学校でも家庭でもむかしより窮屈な気がするんです。お話に登場する大人たちは、とっても自由にふるまっています。そんな姿を見て、子どもたちに「あんたらもっと自由でええんやで」というメッセージを伝えられたらと思います。
六大さん:友だちとの付き合い方などは、「日曜日」シリーズの重要なテーマのように思えるけど、最初からそれを書こうとは決めていない印象ですよね。
──「ここでけんかをさせて、ここで仲直りさせる」といった筋書きを、最初に考えるのではないのですね。
しいこさん:そうです。日曜日シリーズがここまで続いたのは、テーマありきではなかったからだと思います。
登場人物は多いけれど、大人は少ない。大人が諭すのではなくて、子どもたちに考える力をつけてほしい。日曜日シリーズには、これが色濃く出ていると思います。私も、私が書くのではなくて、登場人物たちの力を借りながら書いている、という感覚なんです。私が書くというよりも、登場人物たちが好きなように動いてくれたほうが、たぶんおもしろいんです。

田中六大さん
「かっぱおんせんの歌」が、15年たってサプライズ合唱
──日曜日シリーズを始めてから15年間で、子どもたちは変わりましたか。
六大さん:15年くらいだとよくわからないのですが、ぼくの子どものころを思い出すと、むかしの子どものほうが野蛮だったかな(笑)。やんちゃな感じ、今の子どものほうがやさしくて、人のことを気にしてくれますね。
しいこさん:人のことをとても気にするし、傷つきやすいですよね。生きづらさや居場所がないという声もリアルに聞きます。もっと自由な心でいていいし、自分の思ったことはどんどん発言していい。自分を抱え込みすぎずに、いろいろな体験をしてほしいと思います。
ダメダメと言われることもたくさんあり、大人の都合のいいようにおとなしい子に収まっているけれど、それだけではなくて、もっと自由に気持ちを表現していい。私は子どもの自由な気持ちを受け止められる大人でいたいし、自由な発想でいいよ、という作品をこれからも書いていきたいと思っています。
六大さん:ぼくの住んでいるマンションの1階にすっごく小さな土のあるスペースがあって、そこに小学校3~4年生くらいの子どもたちが集まって基地を作って遊んでいるのを、最近たまたま見たんです。「今でもやってるんだ!」とうれしくなりました。
しいこさん:私も子どものころに、基地を作りましたね。
──しいこさんは、最近ちょっとうれしいことがあったそうですね。
しいこさん:そうなんです。1巻の『音楽室の日曜日』の巻末に、「かっぱおんせんの歌」の楽譜が載っています。今年の2月に台湾の台北国際ブックフェアに参加したのですが、台湾の方たちが、この歌を合唱してくださって。私が台北に行くと知って、急きょ皆さんで練習してくださったそうなんです。
──しいこさんが作詞、ベートーベンとご友人の細井里枝子さんが作曲された歌ですね。ベートーベンは、ちょっと気の弱いピアニストとして本に登場しています。「かっぱおんせんの歌」は、ベートーベンの交響曲第9番のエッセンスが入った楽しい曲ですね。
しいこさん:その曲をサプライズで歌ってくださって。15年前に作った曲が、今になって再現されたんです。びっくりしましたけど、うれしかったです。

かっぱおんせんの歌

台北国際ブックフェアでのしいこさん。台湾でも「日曜日」シリーズは大人気!
日曜日シリーズを読んで、子どもたちに「しあわせ貯金」を貯めてもらいたい
――子どもの本に携わる方として、心がけていらっしゃることはなんですか。
しいこさん:一番大事なのは、うそは書かないことです。うそを書くと子どもたちは受け入れません。大人の都合のいいように、「こう書いたら面白いやろ?」というスタンスで描いたものは、絶対面白くなりません。
六大さん:ぼくが好きなのは、夢なのかなと思って読み進めていると、「あっ、夢じゃないんだ!」というお話。けっこう面白いです。5巻の『保健室の日曜日』では、キャラクターたちが病院に行くのですが、地下に教室があって看護師さんが授業をしているんです。
――「血がこわいほうたい」とか、「しんぞうの音をこもりうたがわりにねむっちゃう、ちょうしんき」といった「こんなものいらん」と言われた物たちが、「いらん科」に来て授業を受けているのですよね。
六大さん:病院の2階にも、変な科がいっぱいあるんです。
――けんかをしているおじさんがいる「けん科」、のんびりくつろいでいる「うらら科」、ちょんまげの人たちが踊りを踊っている「ええじゃない科」、プールでイルカが泳いでいる「イル科」などですね。六大さんが見開きのカラー絵に描いてくれているので、思わず細かいところまで見入ってしまいます。
しいこさん:夢オチはやらないようにしているんです。「いろいろあったけど、これは夢でした」という終わり方にしてしまうと、「なんや、夢やったんやん」と、読者ががっかりしてしまうから。よりリアルに、「もしかしたら、こういう世界がほんとうにあるんじゃないか」という世界観が大事。「ありそうでない。なさそうである」ところを描くようにしています。
六大さん:ぼくは、本を読んでいるときに子どもたちに楽しんでもらえれば、それが一番です。自分の想いをうまく言葉にできないので、絵の線なんかを見ながら、うすーい感じで伝わっていればいいかな、と思っています。
――絵を見ながら、いろいろ感じてもらえるといいですね。
しいこさん:六大さんの絵を見ていると、心が開放されるよう。気持ちが晴れますよね。
――学校の休み時間に日曜日シリーズを読んで、クスリと笑う。次の休み時間にも、またクスッと笑う。その小さな積み重ねが楽しい。子どもにとって、学校は大きな場所を占める世界です。そんな学校の生活の中で、楽しみを見つけられた子どもはしあわせだと思います。この日曜日シリーズが、そのお手伝いをできるといいですね。
しいこさん:日曜日シリーズを読んで、たくさんの子どもたちに「しあわせ貯金」を貯めてもらいたいですね。
……第1回〈小学生が夢中の「日曜日」シリーズ 15年間で30巻ついに完結! 人気の秘密を村上しいこさんと田中六大さんが教えてくれた!〉では、刊行のいきさつや、人気キャラクターのゆかいなお話がたっぷり!

●村上しいこ(むらかみ・しいこ)
三重県生まれ。『うたうとは小さないのちのひろいあげ』で第53回野間児童文芸賞受賞。おもな作品に「へんなともだち マンホーくん」シリーズ(たかいよしかず・絵)、「七転びダッシュ!」シリーズなど。「学校の日曜日」シリーズの最新刊『地下室の日曜日 ゆめのこうきゅうマンションだ!』が好評発売中。
●田中六大(たなか・ろくだい)
1980年、東京都生まれ。『うどん対ラーメン』などの絵本のほか、さし絵を担当した本に『アチチの小鬼』(岡田淳・作)、『おたすけじぞう』(はるくはるる・文)、『ぼくはなんでもできるもん』(いとうみく・作)など。
●聞き手/高木香織(たかぎ・かおり)
出版社勤務を経て編集・文筆業。2人の娘を持つ。子育て・児童書・健康・医療の本を多く手掛ける。編集・編集協力に『美智子さま マナーとお言葉の流儀』『子どもの「学習脳」を育てる法則』(ともにこう書房)、『部活やめてもいいですか。』『頭のよい子の家にある「もの」』『モンテッソーリで解決! 子育ての悩みに今すぐ役立つQ&A68』『かみさまのおはなし』『エトワール! バレエ事典』(すべて講談社)など多数。著書に『後期高齢者医療がよくわかる』(リヨン社)、『ママが守る! 家庭の新型インフルエンザ対策』(講談社)がある。













![冬のギフトにぴったりな“雪の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/629/large/0368f492-6e08-49f4-8c18-b0d3c52fe98c.jpg?1770179405)
![【働くママの労働問題】「子持ち様」が気をつけるべき職場の人間関係のポイント[社労士が回答]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/623/large/5af9810f-c081-42b4-a484-d448e0f9e922.jpg?1770162654)











































































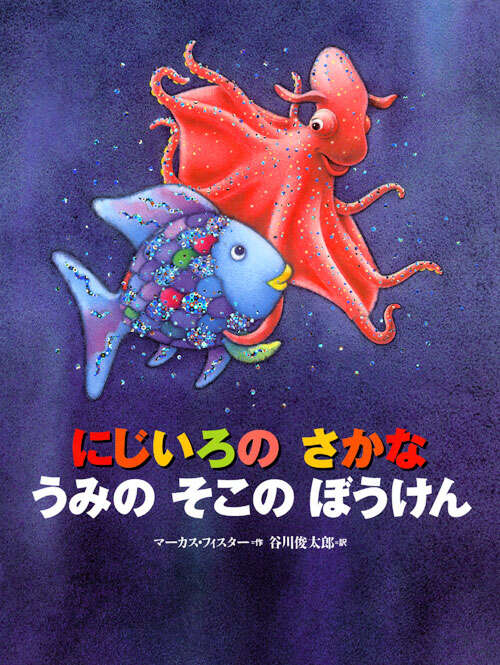













高木 香織
出版社勤務を経て編集・文筆業。2人の娘を持つ。子育て・児童書・健康・医療の本を多く手掛ける。編集・編集協力に『美智子さま マナーとお言葉の流儀』『子どもの「学習脳」を育てる法則』(ともにこう書房)、『部活やめてもいいですか。』『頭のよい子の家にある「もの」』『モンテッソーリで解決! 子育ての悩みに今すぐ役立つQ&A68』『かみさまのおはなし』『エトワール! バレエ事典』(すべて講談社)など多数。著書に『後期高齢者医療がよくわかる』(リヨン社)、『ママが守る! 家庭の新型インフルエンザ対策』(講談社)がある。
出版社勤務を経て編集・文筆業。2人の娘を持つ。子育て・児童書・健康・医療の本を多く手掛ける。編集・編集協力に『美智子さま マナーとお言葉の流儀』『子どもの「学習脳」を育てる法則』(ともにこう書房)、『部活やめてもいいですか。』『頭のよい子の家にある「もの」』『モンテッソーリで解決! 子育ての悩みに今すぐ役立つQ&A68』『かみさまのおはなし』『エトワール! バレエ事典』(すべて講談社)など多数。著書に『後期高齢者医療がよくわかる』(リヨン社)、『ママが守る! 家庭の新型インフルエンザ対策』(講談社)がある。