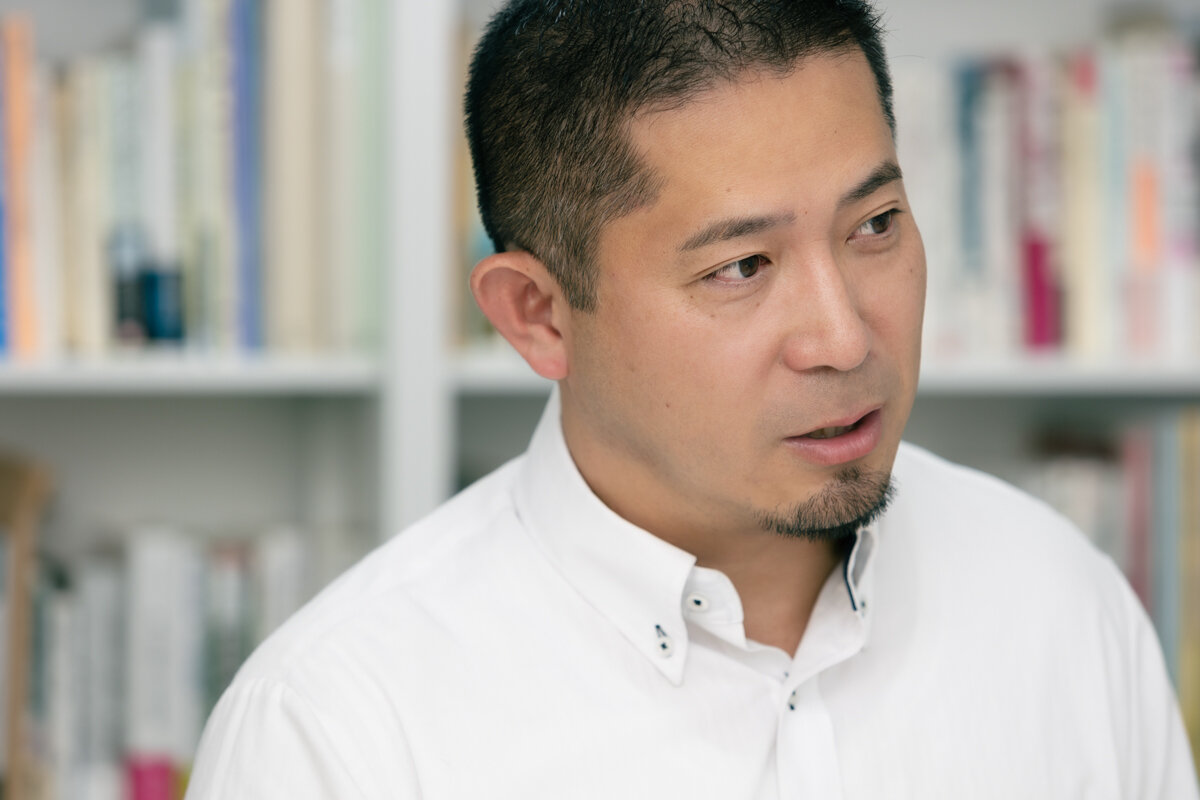【特別養子縁組】の母・久保田智子が娘に「生みの母がいる」と明かして 相談員の「今はやめておこう」に助けられた
養親当事者・久保田智子(兵庫県姫路市教育長、元TBSアナウンサー)インタビュー【2/3】~娘を迎え入れるまで~ (3/4) 1ページ目に戻る
2025.04.03
兵庫県姫路市教育長:久保田 智子
信頼できる相談員はかけがえのない存在
さらに、久保田さんは続けます。
「ふたつ目は、信頼できる相談員さんがいること。養子といっても、日常の子育てはおそらく産んで育てているご家庭と変わりはないと思います。ただ、養子の場合、違いとして、子どもに生い立ちについて話す『真実告知』があります。
今、真実告知は子どものために幼いうちにしたほうがよいといわれています。とはいえ、やはりどのように伝えるのが子どもにとってよいのかは迷ってしまいます。子どもによっても違いますしね。そんなときに、自分たちの状況を話してアドバイスをくださる相談員さんの存在はとてもありがたいものです。
我が家は、娘が2歳半のときから真実告知をしています。日常会話の中で、『ハナちゃんにはもう一人、生みの母がいるんだよ』と伝えています。ただ、子どもが成長するにつれて思いや受けとめかたは変化しますし、それを読み取るのは難しい。
あるとき、相談員さんに娘の反応の変化について相談したときに『娘さんは生みの母がいることはわかっているようですけれど、今その話を聞くのは少し嫌なのかもしれません。しばらく話をするのはやめておきましょうか』とアドバイスをいただいたことがありました。
そこで初めて子どもの気持ちの変化に気づくことができ、とてもありがたかったです」
そして、大切なのは相談員との相性だとも語ります。
「私がお世話になっている相談員さんは、単純な子育ての悩みについても伴走してくれたんです。加えて、特別養子縁組であるという境遇がもたらしかねない事柄に対する予防策や適応策もアドバイスしてくれました。
娘が小さかったころはひんぱんに会っていて、もう日常に溶け込んでいるような当たり前の存在として頼りにさせてもらっていました。今は会う回数は減っていますが、年1回は近況を報告できる会が開催されています。
相談員さんにとってはそれぞれの家庭に細かいアドバイスをするのは、正直難しい部分もあるのかなと。なので、養親と相談員の間合いが合うこともとても重要だと感じます」
あっせん団体との面談が夫婦の話し合いを深めた
養子縁組のあっせん団体についてたびたび耳にするのが養親になるための審査がかなり厳しいということ。なかには、面接時に厳しい忠告を受け、子どもを育てたい気持ちをそがれてしまうような養親希望者もいると聞きます。
「私は、最初の面接官が今もお世話になっている相談員さんだったんです。なので、その部分についてはラッキーだったと思います。
でも、将来病気になるかもしれないし、障害があるかもしれない、どんな子どもでも受け入れられますかなどと、起こりうる可能性をいろいろと聞かされて、驚きや不安感が増したのも事実です。今から思えば当たり前で、自分で産んだとしても起こりうることなのですが。
ただ、さまざまな想定を聞いたことで、私たちはそもそもどうして子どもを育てたいと思っているのかという本質的な部分を夫婦で話し合うきっかけになりました。気持ちを整理しながら話し合ったことが、最終的に登録する決断につながった部分もあります。
養親希望者は、もともと不安の中で一歩を踏み出した人だと思うんです。不安な気持ちで訪れた先で、いろんな可能性について聞かされると、自分たちには無理かもと感じてしまうのは自然なことですよね。
もちろん、団体側も子どもの命を預けるのだから、現実を包み隠さずに真剣にお話をされているのだということはわかります。よく相談員さんと話すのですが、特別養子縁組の制度には素晴らしいことがたくさんあるので、それについてもしっかり話したうえで、多角的に制度の理解を促すのが大切なんだろうなって思います。
不安をあおるのでもなく、安易に決断のでもなく、それぞれの家庭がしっかりと納得して選択できるのが理想だと感じています」