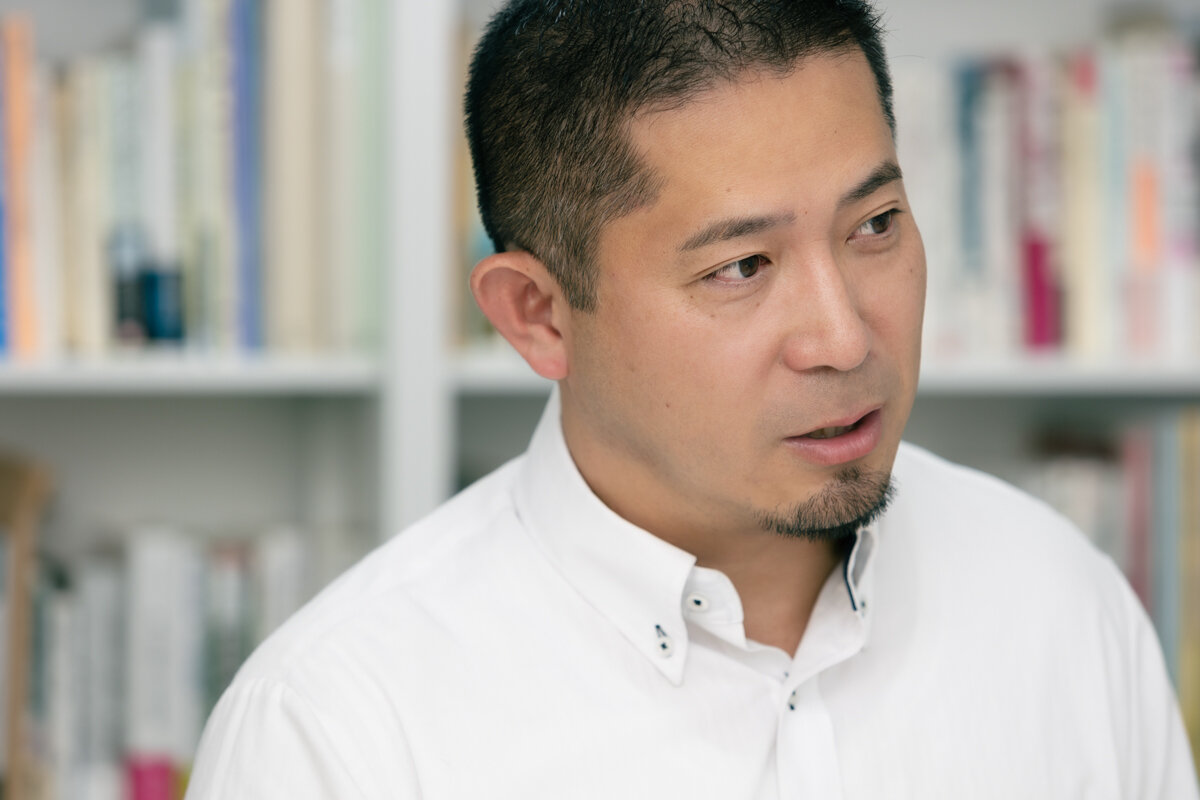【特別養子縁組】の母・久保田智子が娘に「生みの母がいる」と明かして 相談員の「今はやめておこう」に助けられた
養親当事者・久保田智子(兵庫県姫路市教育長、元TBSアナウンサー)インタビュー【2/3】~娘を迎え入れるまで~ (2/4) 1ページ目に戻る
2025.04.03
兵庫県姫路市教育長:久保田 智子

養子あっせん団体に望む2つのこと
20代前半で子どもを産むことは医学的な問題で難しいと知った久保田智子さん。2015年の結婚以降、夫婦で養子縁組について話し合いを重ね、2019年に生後4日目のハナちゃんを長女として迎え入れました。
久保田さんが利用したのは特別養子縁組制度で、子どもの親権や戸籍は生みの親から「養親」のもとに移り、法的にも実子と同じ扱いとなります。
「私たち夫婦はできれば新生児を迎えたいと希望していました。家族としての積み重ねが幼いころからたくさんできればいいなと考えていました」
特別養子縁組制度を利用するには、児童相談所に申し込む場合と、自治体の認可を受けたあっせん団体に依頼する場合の2つの方法があります。久保田さんたちが、養子縁組を申し込んだのは民間のあっせん団体でした。
「夫のアメリカでの赴任期間が終わり、帰国するタイミングで本格的に養子縁組について調べ始めました。まだアメリカ在住で児童相談所には行きづらいし、自然とホームページがある民間の団体ということになりました。自治体にも問い合わせたのですが、説明会が月に1日しかなくて予定が合わなかったりして都合をつけることができませんでした」
あっせん団体を決めるまでにどんなことに気を配っていたのでしょうか。
「当時は、右も左もわからない状態で調べていましたね。そして2つのあっせん団体(以下:団体)の説明会に参加して、相談員さんにとても安心感を持てた団体に依頼することにしました。
私は相談員さんが決め手になりましたが、これから団体を選ぶ方に伝えたいことは2つあります。
ひとつ目は、子どもが成長してからも継続・存在していそうな団体かどうか。なぜなら、子どもの出生に関する細かい情報は基本的には団体が管理しているからです。私たち養親は出生のすべてを知ることはできません。生みの母や父の詳細などはわからないことも多々あります。
子どもが成長して、生みの母や父について知りたいときや、万が一、病気など身体的な理由で助けてもらわないといけないときなどは、やはり団体を通すことになると思います。だから、この先も団体が存在してくれていないと困るということは、強く思います」