

最初の発見から10年! アンモナイト化石の新種の見つけ方、研究方法を古生物学者が解説!
【ちょっとマニアな古生物のふしぎ】古生物学者・相場大佑先生が見つけた古生物のふしぎ (2/2) 1ページ目に戻る
2025.10.08
古生物学者:相場 大佑
新種は何の仲間か
今回の新種を異常巻アンモナイトの中のどの属にするべきか、とても悩みました。それはこの新種が、複数の属にそれぞれ似ている部分を併せ持っていたためです。例えば、トゲがないということは、ユーボストリコセラス属というグループの特徴と同じですが、殻の先端(子どものときに作った部分)に注目すると、ハイファントセラス属にとてもよく似ています。また、それ以外にも似ているところがいくつかあります。しかし、ハイファントセラス属はトゲが4列あることがもっとも重要な特徴であり、それとは一致しません。

しかし、ハイファントセラス属から、進化の過程でトゲを失って生まれた可能性が捨てられないという、分類と進化の解釈に矛盾が残る形になりました。これはつまり、今回の新種が、現在の分類のルールには収まらない、例外的な変わり者であるということかもしれません。
学名
パープレクサムはラテン語で「混乱した」「悩ませる」というような意味の言葉です。どっちの特徴も持っているため、分類が難しいということに由来しています。
復元画
新種を含めた異常巻アンモナイトはあまり泳ぎが上手くなく、小さな生き物を吸うようにして食べる食性だったと考えられています。そのため、現在生きている頭足類のうち、似た生態をもつ深海に生きているタコのなかまの姿を参考にしています。

終わりに
僕が発表したアンモナイトの新種は今回で3種になりました。新種の発表はやっぱりいいものです。新種を発見したときは心が躍るようなトキメキを感じ、発表できたときはなんとも言えない安心感に包まれます。
実はまだ、発表待ちの新種を他にもいくつか抱えています。今度は10年もかけないで世に出してあげたいと思います。
https://bioone.org/journals/paleontological-research/volume-29/issue-1/prpsj.250015/A-
New-Species-of-Eubostrychoceras-Ammonoidea-Nostoceratidae-from-the-
Santonian/10.2517/prpsj.250015.full
写真・文/相場大佑












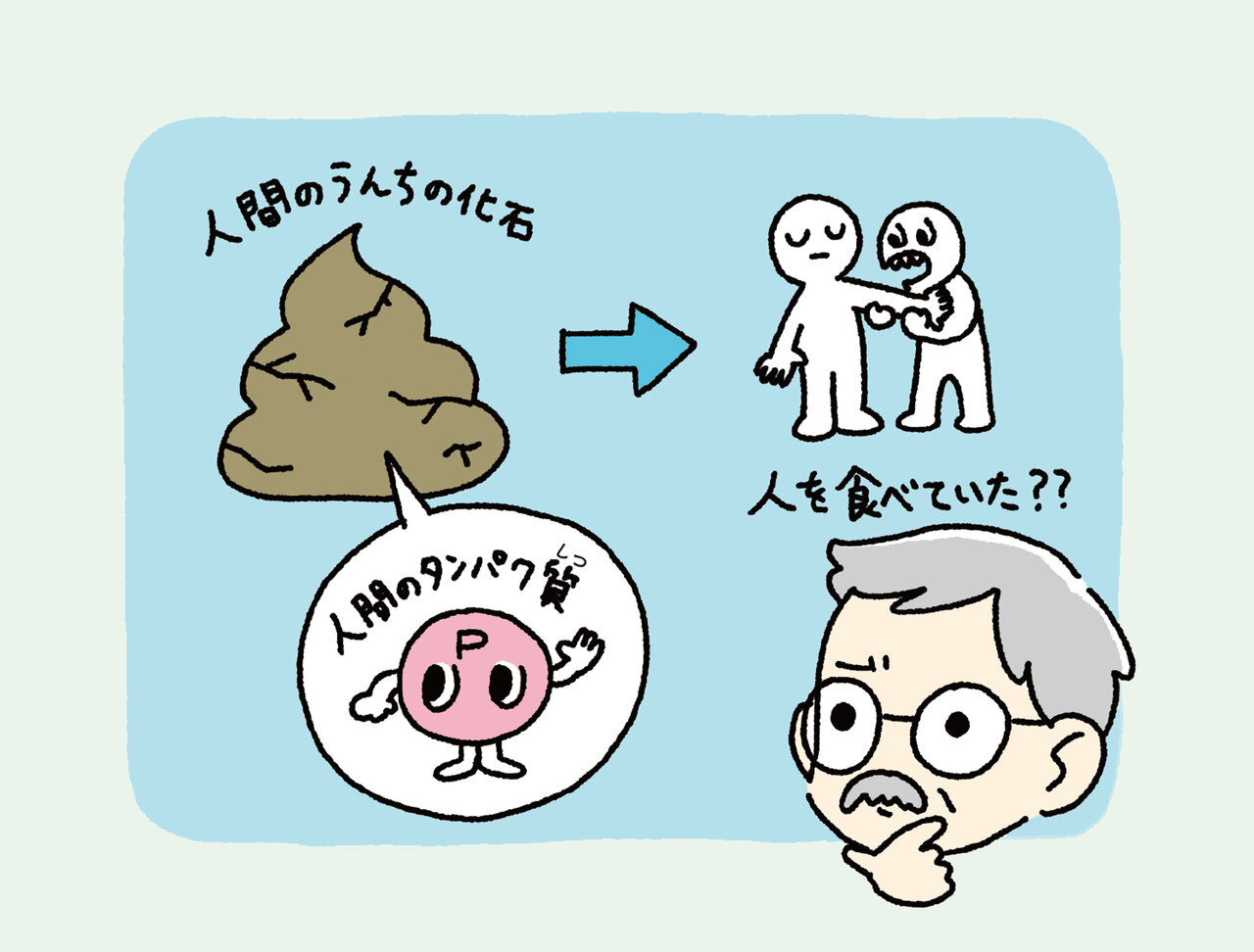










































































相場 大佑
深田地質研究所 主査研究員。1989年 東京都生まれ。2017年 横浜国立大学大学院博士課程修了、博士(学術)。三笠市立博物館 研究員を経て、2023年より現所属。専門は古生物学(特にアンモナイト)。北海道から見つかった白亜紀の異常巻きアンモナイトの新種を、これまでに3種発表したほか、アンモナイトの生物としての姿に迫るべく、性別や生活史などについても研究を進めている。 また、巡回展『ポケモン化石博物館』を企画し、総合監修を務める。
深田地質研究所 主査研究員。1989年 東京都生まれ。2017年 横浜国立大学大学院博士課程修了、博士(学術)。三笠市立博物館 研究員を経て、2023年より現所属。専門は古生物学(特にアンモナイト)。北海道から見つかった白亜紀の異常巻きアンモナイトの新種を、これまでに3種発表したほか、アンモナイトの生物としての姿に迫るべく、性別や生活史などについても研究を進めている。 また、巡回展『ポケモン化石博物館』を企画し、総合監修を務める。