

日本初!赤ちゃんが誕生した【マルミミゾウ】に会いに安佐動物公園へ!
〈新連載〉ドリトル柴田の「動物園に行ってみた!」vol.3 (2/2) 1ページ目に戻る
2025.09.12
科学ジャーナリスト:柴田 佳秀
アフリカスイギュウがいた!
今度はずいぶん広いエリア。アフリカの動物たちのゾーンです。そして、なんだかウシみたいな動物がいました。アフリカスイギュウです。

ビッグ・ファイブに出会えるのは安佐動物公園だけ
アフリカのサファリツアーでは、「アフリカスイギュウ」「アフリカゾウ」「ヒョウ」「サイ」「ライオン」の5種類を、危険で遭遇が難しい大型動物として“ビッグ・ファイブ”と呼び、この5種すべてに出会うことがツアーの大きな目標とされています。

野生では絶滅した動物がいた

この動物、実は野生では絶滅しているのです。
不幸中の幸いで、動物園にいた個体が生き残り、その子孫を増やしてきた結果、現在は野生復帰に向けた取り組みが進められています。しかも、日本で見られるのは、この安佐動物公園と熊本市動植物園のわずか2ヵ所だけ。そんな希少なシフゾウを、間近でじっくり観察できたのは本当に感動的でした。
ただ残念なのは、そんなに貴重な動物だと知らず、「ただのシカ」と思って素通りしてしまう人が多いことです。そして、両園のシフゾウはいずれも高齢のため、もしかすると近い将来、日本ではもう会えない日が来るかもしれません。

動物が近いから大きさがよくわかる!
ライオン舎の一部はガラス張りになっており、ご覧のとおり、まさに目の前でライオンを見ることができます。最近、多くの動物園で取り入れられている展示方法ですが、安佐動物公園では特に距離が近く、その迫力は圧巻。動物のリアルなサイズ感がよくわかる展示になっていると思います。


動物園の大きな魅力のひとつは、「え、こんなに大きいの!?」「思ったより小さい!」と、本物の大きさを体感できること。これは写真や映像では絶対に味わえない驚きです。安佐動物公園は、そんな“実物の迫力”をたっぷり楽しめる場所だと感じました。
マルミミゾウの赤ちゃんがすくすく育ち、公開されたら、ぜひまた訪れたいと思います。どうか元気に大きくなりますように。(取材:2025年6月4日)

写真・文/柴田 佳秀















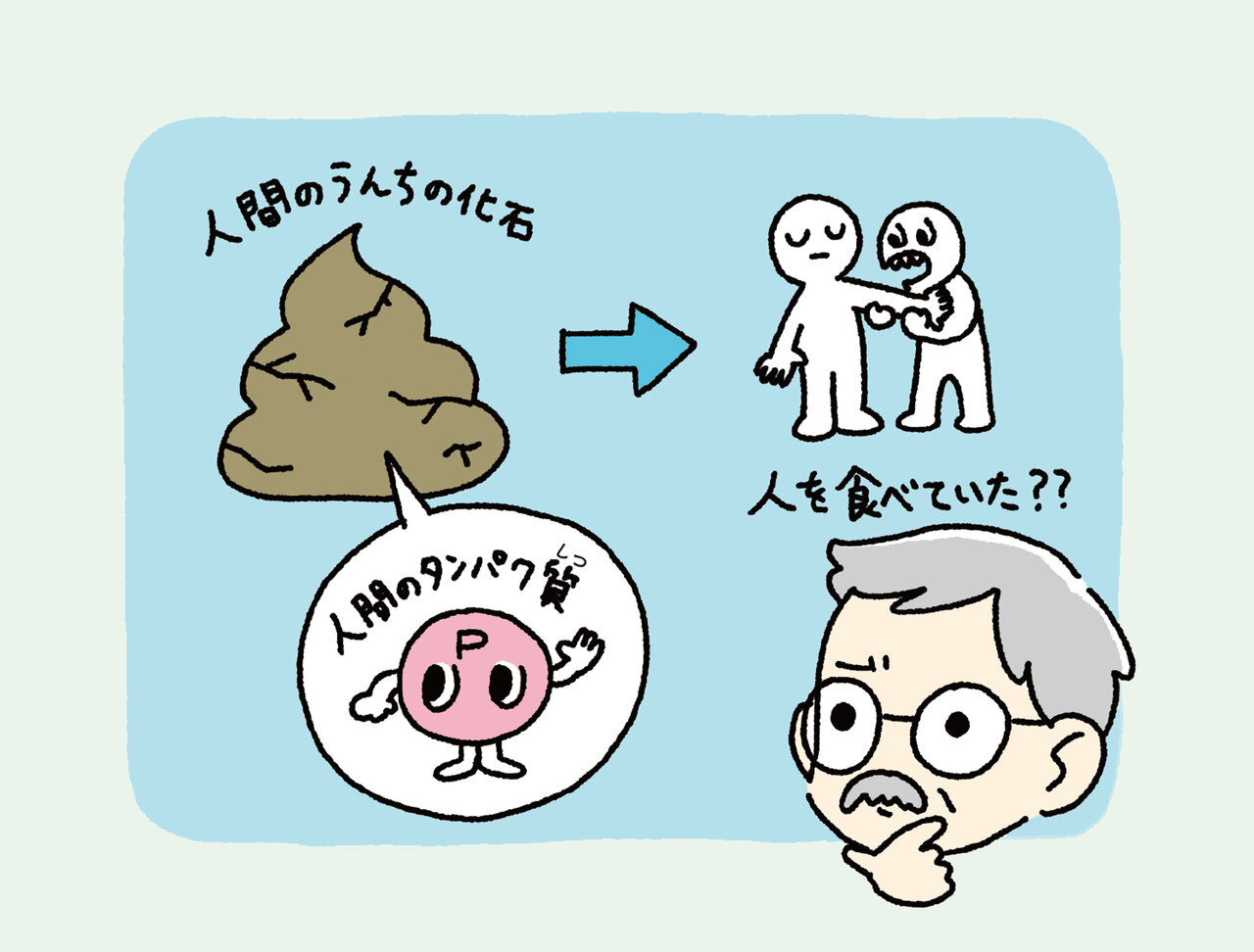














































































柴田 佳秀
元ディレクターでNHK生きもの地球紀行などを制作。科学体験教室を幼稚園で実施中。著作にカラスの常識、講談社の図鑑MOVEシリーズの執筆など。BIRDER編集委員。都市鳥研究会幹事。科学技術ジャーナリスト会議会員。暦生活で連載中。MOVE「鳥」「危険生物 新訂版」「生きもののふしぎ 新訂版」等の執筆者。
元ディレクターでNHK生きもの地球紀行などを制作。科学体験教室を幼稚園で実施中。著作にカラスの常識、講談社の図鑑MOVEシリーズの執筆など。BIRDER編集委員。都市鳥研究会幹事。科学技術ジャーナリスト会議会員。暦生活で連載中。MOVE「鳥」「危険生物 新訂版」「生きもののふしぎ 新訂版」等の執筆者。