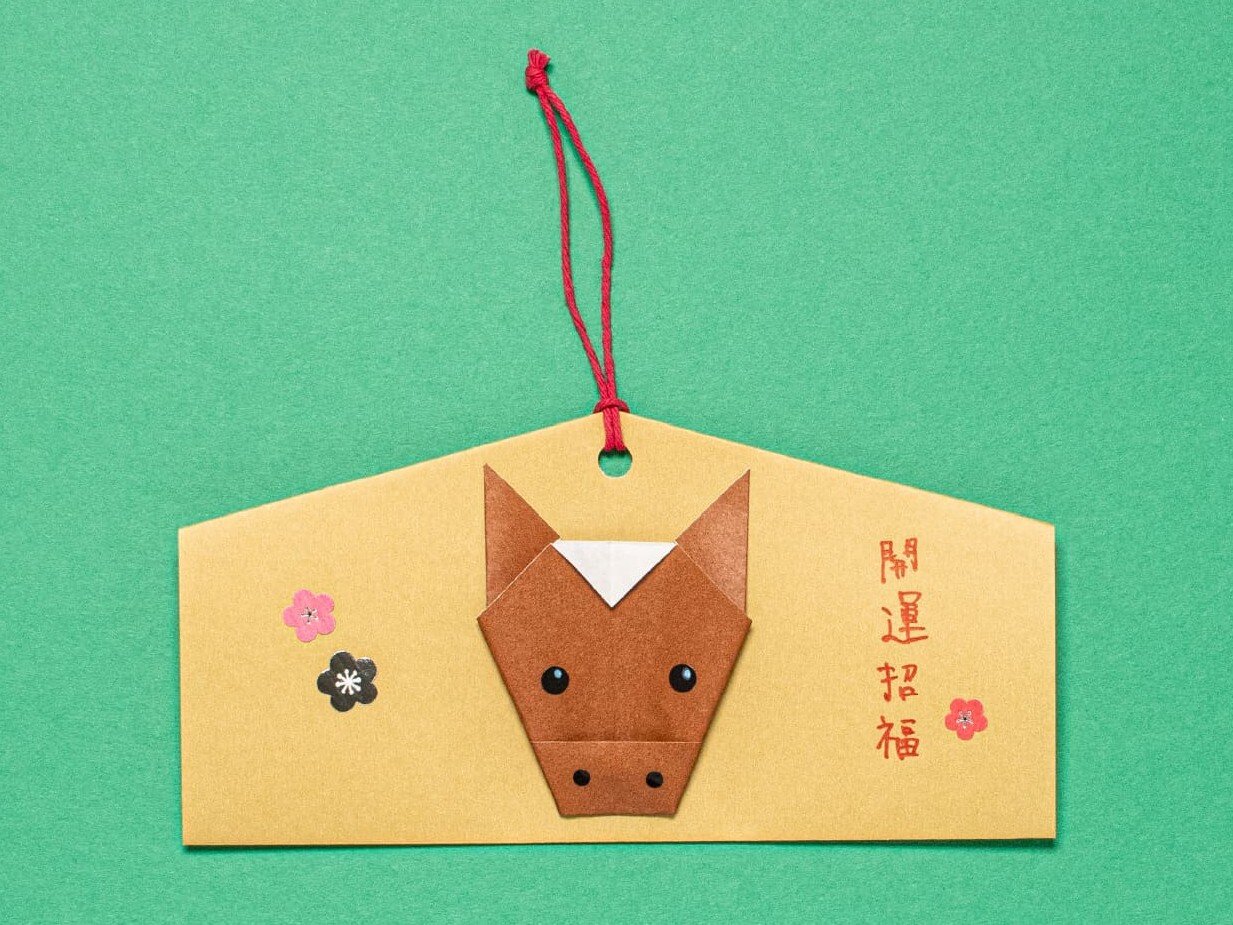発達障害の特性のある子どもを持つ親や家族への支援【精神的負担】編 〔言語聴覚士/社会福祉士〕が解説
#13 発達障害の特性のある子の母親の精神的負担への支援〔言語聴覚士/社会福祉士:原哲也先生の解説〕 (2/3) 1ページ目に戻る
2025.04.30
言語聴覚士・社会福祉士:原 哲也
発達障害の特性のある子どもを育てる親同士の支え合い
①「親の会」
地域の発達障害の特性のある子をもつ親による「親の会」には、「発達障害の特性の子を育てる先輩」がいて、今困っていることや将来への不安など共通の悩みについて話し合うことができます。
また、先輩参加者は、就園、就学、進学、就職などについてや療育の場所の情報など、居住地域の情報を多く持っています。療育や進学等の制度は自治体ごとにかなり異なるので、地域の情報は貴重です。
さらに、特別支援学級や特別支援学校の実情なども「先輩」はよく知っているものです。地域の保健センターや児童発達支援センター、医療機関、そして保育園・幼稚園、小学校など、教育、医療、福祉の機関はどうしても縦割りになり、機関同士の連携や情報共有が十分ではないことがありますが、「先輩」は横断的な情報を持っていたりします。
一般社団法人 日本自閉症協会には、全国の親の会の情報があります。一度のぞいてみられてもよいのではないでしょうか。
https://www.autism.or.jp/accession/
親同士が顔を合わせてつながることはとても大事なことです。私の事業所では、事業所主催のワークショップで保護者が交流したり、自然発生的に保護者がお茶会を開いて交流することがあります。そのときの保護者の表情を見ていると、どの方も、普段子どもと一緒にいるときは明らかに違う、穏やかな表情をされています。わかり合えること、支え合うことの大切さを感じます。
②ペアレント・メンター
『ペアレント・メンター』という制度があります。自らも発達障害の特性のある子の子育てを経験し、かつ相談支援のトレーニングを受けた『ペアレント・メンター』が、対面して話を聞いてくれた上で共感的なサポートを行い、同時に地域の情報を提供してくれます。
日本ペアレント・メンター研究会のHPには、「高い共感性に基づくメンターによる支援は、専門家による支援とは違った効果があることが指摘され、厚生労働省においても有効な家族支援システムとして推奨されています」(日本ペアレント・メンター研究会HP https://parentmentor.jp/parent-mentor)との記載があります。
専門職に相談するのがよいということはわかるが、緊張してしまってうまく相談できないかもしれないという方は、ペアレント・メンターのほうが話がしやすいかもしれません。
残念ながらメンターの数はまだ多くはなく、近くに必ずメンターがいるといえる状況にはないのですが、興味のある方は、日本ペアレント・メンター研究会のHPでぜひ、探してみてください。
https://parentmentor.jp/local-organization
③SNSや当事者の情報サイト
Xやインスタグラムなどでは、多くの発達障害の特性のある子を持つ親が発信をしています。そこで同じ状況の中で同じ悩みを持つ人同士が交流することで、気持ちを吐き出したり、支え合うことはあるのだと思います。ずっと年上のお子さんを持つ方の発信は、まだ小さいお子さんを持つ方にとって、将来を考える参考になることも多々あるでしょう。
ただ、匿名での情報発信では、情報が間違っていることもあります。また、それが必ずしも我が子にあてはまるわけではありません。なので、何かを取り入れる場合はぜひ、お子さんがリアルで療育を受けている専門職に相談してほしいと思います。また一般的なネットリテラシーが必要であることももちろんです。





















![お年玉と一緒に贈りたい“お正月の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/022/large/68833581-f835-4688-a9fe-33fa7156917c.jpg?1764905096)