

小学生が夢中の「日曜日」シリーズ 15年間で30巻ついに完結! 人気の秘密を村上しいこさんと田中六大さんが教えてくれた!
シリーズ完結記念! 村上しいこ×田中六大インタビュー1
2025.07.02
編集者・文筆業:高木 香織

写真:森清
2010年に刊行されてから15年間にわたり、全30巻続いた「日曜日」シリーズが、『地下室の日曜日 ゆめのこうきゅうマンションだ!』で完結しました。子どもたちがいない学校の日曜日に、教室にある道具や備品がのびのびと活躍するお話は、子どもたちに大切に読み継がれてきました。なぜ日曜日シリーズはこんなにおもしろいの? 子どもたちに伝えたい想いは? そんなことを知りたくて、作者の村上しいこさんといきいきとした絵を描いてきた田中六大さんにお話を伺いました。15年間を振り返り、最初の刊行のいきさつから150近くものキャラクターの裏話まで、ワクワクの秘密がいっぱいですよ!
〈「日曜日」シリーズのストーリー〉ここは、せんねん町の、まんねん小学校。学校がお休みの日曜日、教室はしーんと静まりかえってると思うでしょ。でも、ちがうんですよね、これが……。子どもたちがいない教室では、道具や備品が羽を伸ばして遊んでいます。「今日はなにをしようかな?」「街に行こう!」。すると、びっくりする事件に巻き込まれて……! 子どもたちが知らない学校のようすを描く、抱腹絶倒のものがたり!
「ふだん子どもたちが知らない学校のようす」を描く本を作ろう
──15年間にわたる全30巻の完結編が無事刊行されました。長い間、ほんとうにお疲れさまでした。「日曜日」シリーズは、どのようないきさつで始まったのですか。
村上しいこさん(以下、しいこさん):児童文学者の交流会で、講談社の編集者さんに声をかけられたのが最初です。「いくつか原稿を見せてほしい」と言われたので、それまでに書いたなかからパターンの違うお話を3本選んで送ったんです。すると、「Aのお話のここ、Bのお話のここ、というように、3本のお話のよい部分をチョイスして、一つのお話にまとめてください」とおっしゃるのです。
そのうちの1本のお話に「学校」が入っていたのです。日曜日に学校の道具や物が人間のように過ごしています。そんな、子どもたちが知らない学校のようすを描いたらおもしろいだろう。ふだん自分たちが知らない世界を知りたい、という子どもたちの興味を引くお話を書いてほしい、と依頼されたのが始まりです。

村上しいこさん
──どんな読者層を想定されていたのですか。
しいこさん:スタートしたときのねらいは、幼年童話ではあるけれど、ふだんから本を読んでいる小学1年生でも読めて、ふだんあまり本を読むことを得意としない高学年以上の子どもも楽しく読めるお話、ということでした。なかには幼稚園生でも読んでいるお子さんもいました。「学校のこと、わかるの?」と聞くと、きょうだいが小学校に通っていてときどき一緒に行くので、教室のイメージが湧くと言っていました。読者層は広いですね。
「日曜日」シリーズの絵を描いたことで、関西弁の仕事が殺到
──田中六大さんが絵を担当されたのは、どのようないきさつからですか。
しいこさん:六大さんが描かれた絵本を拝見して、ぜひお願いしたいと私が希望したのです。お引き受けくださってうれしかったです。
──登場人物は関西弁を話しますね。
しいこさん:初代の編集者さんが「関西弁でも共通語でもどちらでもいいですよ」と言ってくださったので、私の書きやすい関西弁で始めました。私は三重県生まれなので、関西弁といっても三重弁ですね。
──とてもマイルドで安心感があって、楽しい言葉ですよね。
しいこさん:もし共通語で書いていたら、六大さんのいきおいのあるおもしろい絵とバランスが取れなかったかもしれませんね。
田中六大さん(以下、六大さん):ぼく、日曜日シリーズを描いてから、関西弁の文に絵をつける仕事がめちゃくちゃ増えました。もう、半分くらいは関西弁の仕事です(笑)。
しいこさん:「関西弁の文には六大さんの絵がぴったりやー」と、出版社の編集さんたちが思われたのでしょうね。

田中六大さん
物語はキャラクターたちが教えてくれる
六大さん:キャラクターたちがかならず街に行きますが、それも最初から決まっていたのですか。
しいこさん:決まっていました。学校の中だけだと、世界観が狭くなってしまいますからね。学校の物が地域に出かけていって、それを街の人たちもふつうに受け入れています。「なんで鍋が歩いてるの?」なんて、街の人たちは思いません。
六大さん:書くとき、まず話の入り口はどうやって考えるのですか。
しいこさん:まずキャラクターを考えて、男女分けをします。この物は女の子っぽいとか、男の子っぽいとかで決めて、だいたい同じ数くらいにします。そして、キャラクター設定をして性格を決めたら、紙に書き出します。その紙をじーっと眺めて、「あなたはどこに行きたい? 何をしたい? どんなことがあったら楽しい?」と語りかけるんです。そして、あとはキャラクターが動き出すのを待つ。動き出したら、書き始めるんです。
「言葉が降ってくる」と言う作家がいますが、それは天才です。私は言葉が天から降ってこないから、キャラクターに話しかけたりしながら、あっちこっちに種をまいておくんです。種に水をあげたり、肥料をあげたりしながら、芽が出てくるのを待つんですね。
──キャラクターがお話を教えてくれるまで、じっと待つのですね。
しいこさん:自分で強引に創り上げたお話は、理屈っぽくなってしまうようです。とにかく待っていて、キャラクターが動き出したら、どこに行って何をするかを決めます。そうやって書き始めると、そのうちお話が動いていくんです。
でも、ゴールにたどり着けないこともあるんです。それは、お話の前半に無理があったから。「このセリフに無理があった」と思ったら、キャラクターに「集合集合、戻るよー」と言って、いったん振り出しに戻ります。そうして、キャラクターが再び動き出して、いい感じに進んだらよし。逆に、いい感じに進みすぎても、一度戻るようにしています。行きすぎて失敗することもあるんですよ。
どんなキャラクターも六大さんが「なんとかしてくれる」
──六大さんは、1巻目の『音楽室の日曜日』の原稿を受け取ったとき、どう思われましたか。
六大さん:おもしろいと思いました。でも、最初だったのでシステムがよくわからなくて、お話に登場しないハンドベルを勝手に入れちゃったんです。しかも、カバー絵に堂々と出ちゃって。
しいこさん:あったあった、隠れキャラですよね。「あれ? ハンドベル、セリフがない」って(笑)。
六大さん:すみません。これ、ぼくが勝手に描いちゃったんです。全巻通してセリフがないのはこれだけです。
──ハンドベルは、11巻目の『音楽室の日曜日 歌え!オルガンちゃん』では、しっかり本文に登場していますね。
しいこさん:11巻めを書くときに1巻めを読み返したら、「ハンドベル本文に出てないやん!」となって、11巻目には入れたんですよ。
音楽室にある楽器のトライアングルなんて、ほっそいからどうやって絵を描くんやろう、って思っていました。ほっそいところに顔を描いたら、目なんて見えへんでしょ。そうしたら、三角のなかにうまいこと顔を描いてくれて。

記念すべきシリーズ第1巻『音楽室の日曜日』。メトロノームの後ろにこっそりハンドベルが! トライアングルの顔は三角の空間の中に描かれている。
六大さん:ちょっとマンガっぽくしたかったのです。9巻の『家庭科室の日曜日』に登場する「たちばさみ」も、取っ手の輪のなかの空間に顔を描くしかない。すると、45度以上後ろに向くと、顔が見えなくなっちゃう(笑)。横向きも後ろ向きの絵も描けないのです。
しいこさん:「温度計」もね。1巻目の『音楽室の日曜日』のトライアングルを見て、「どんなキャラクターでも、六大さんがなんとかしてくれるんや」と思ったの。原稿を書いたら「あとはお願いします」と丸投げ(笑)。日曜日シリーズは、「六大さんの絵があってこそ」なんです。


たちばさみ(上)と温度計
苦し紛れに作った保健室の「たんこぶ」が愛おしい
──お好きなキャラクターは誰ですか。
しいこさん:「たんこぶ」ですね。道具ではないけれど、芯がしっかりしていて、健気というか、一生懸命さが伝わってきますよね。
──5巻の『保健室の日曜日』と15巻の『保健室の日曜日 なぞなぞピクニックへいきたいかぁ!』に登場していますね。
六大さん:ぼくも好きです。たんこぶをキャラクターにしようなんて、よく思いつきましたよね、すごいな。
しいこさん:保健室の備品が少なくて、苦しまぎれに作ったキャラクターなの(笑)。
──たんこぶは子どもたちに一番多いけがかもしれませんね。ちょっとすねてみたり、一人でどこかに行っちゃったり。
しいこさん:血肉が通っている感じでちょっとかわいい。
六大さん:好きというより謎なのが、10巻の『教室の日曜日』のスピーカーです。文の中に「スピーカーが8本の足を動かして、くもみたいにカサカサ、はいおりてきました。」とあるのです。それまで、あまりキャラクターの詳しい指定はされていなかったのに、なぜ足が8本あるのですか。
しいこさん:なんで足8本にこだわったんやろ?
六大さん:カサカサ壁を歩くとあったから、イメージとしてはカブトムシみたいな感じかなぁ、って。


お気に入りのたんこぶ(上)と、なぜか8本足のスピーカー
しいこさん:たぶんそんな感じやろ(笑)。
──2巻の『理科室の日曜日』に出てくる「人体もけい」は、ガイコツですよね……?
六大さん:あれは、ぼく間違えて描いちゃったんですね。
しいこさん:いやいや、最初は人体模型を描いてくれたのだけど、内臓などが気持ち悪いからと、ガイコツになったの(笑)
六大さん:あ、そうでしたね。笑顔がかわいい感じにしてみました。
──これらはみんな、絵を描くアイデアを絞り出したキャラクターですね。

取材中にガイコツを描く六大さん
男子に圧倒的な人気の「落としもののパンツ」
──子どもたちに人気のキャラクターは誰ですか?
しいこさん:圧倒的に「落としもののパンツ」やね。女子は好みのキャラクターがばらけるのですが、パンツは圧倒的に男子からの人気。たぶん「パンツ」というワードが好きなんですよ。堂々と「パンツ」と言えるから。
──8巻の『職員室の日曜日』と18巻の『職員室の日曜日 図書魔女ちゃんとバクちゃん』に登場しますね。どうしてパンツが人気とわかるのですか?
しいこさん:講演会のあとのサイン会や、小学校での読み聞かせのときなどに、子どもたちから直接聞くのです。日曜日シリーズは、どこの小学校の図書館や学級文庫においてあって、よく読まれているんです。
──男の子は、ちょっとヘンなもの、きたないものとか好きですからね。
六大さん:犬のウンチのキャラクターとかを出したら、もしかしたら人気が出たかもしれませんね(笑)。
しいこさん:女の子は、机の中からそーっと出してきて「私、これ好き」と、好きなキャラクターを教えてくれたりするんですよ。
六大さん:ぼくがビジュアルとして気に入っているのは、21巻の『防災室の日曜日 カラスてんぐととうめい人間』に登場する非常用のチョコレート。「チョコレート」という文字を顔にしているんです。
──「CHOCOLATE」の真ん中あたりの2つの「O」が両目で、その間の「C」が鼻になっていますよね。これはうまくぴったりはまりましたね!


男の子に大人気の落としもののパンツ(上)と、六大さんお気に入りのチョコレート
あなたに寄り添ってくれる「自分に似ているキャラクター」に出会えるように
──日曜日シリーズには、150近くものキャラクターが登場したそうですね。
しいこさん:ちょっぴり威張っているけどほんとうは気が弱かったり、思いっきりてきとうだったり、ほんとうにいろんなキャラクターが出てきました。でも、どのキャラクターも、問題をみんなで相談しながら解決していきます。自分が弱いところは友だちが助けてくれる、友だちができないところは自分が助けてあげる。そういった関係を、日曜日シリーズの中で、子どもたちが自分の気持ちとして感じることができるといいですね。そして、「こういう子、クラスにおるよね」「自分に少し似ているな」と、子どもたちに寄り添えるキャラクターに出会ってくれるといいなと思います。
……つづく〈子どもたちに大人気の「日曜日」シリーズが完結! 最終巻『地下室の日曜日 ゆめのこうきゅうマンションだ!』にこめた想いを、作家・村上しいこさんと画家・田中六大さんに聞きました!〉では、ふしぎなキャラクターや作画のヒミツが明らかに!


シリーズ最終刊『地下室の日曜日 ゆめのこうきゅうマンションだ!』は絶賛発売中!
●村上しいこ(むらかみ・しいこ)
三重県生まれ。『うたうとは小さないのちのひろいあげ』で第53回野間児童文芸賞受賞。おもな作品に「へんなともだち マンホーくん」シリーズ(たかいよしかず・絵)、「七転びダッシュ!」シリーズなど。「学校の日曜日」シリーズの最新刊『地下室の日曜日 ゆめのこうきゅうマンションだ!』が好評発売中。
●田中六大(たなか・ろくだい)
1980年、東京都生まれ。『うどん対ラーメン』などの絵本のほか、さし絵を担当した本に『アチチの小鬼』(岡田淳・作)、『おたすけじぞう』(はるくはるる・文)、『ぼくはなんでもできるもん』(いとうみく・作)など。
●聞き手/高木香織(たかぎ・かおり)
出版社勤務を経て編集・文筆業。2人の娘を持つ。子育て・児童書・健康・医療の本を多く手掛ける。編集・編集協力に『美智子さま マナーとお言葉の流儀』『子どもの「学習脳」を育てる法則』(ともにこう書房)、『部活やめてもいいですか。』『頭のよい子の家にある「もの」』『モンテッソーリで解決! 子育ての悩みに今すぐ役立つQ&A68』『かみさまのおはなし』『エトワール! バレエ事典』(すべて講談社)など多数。著書に『後期高齢者医療がよくわかる』(リヨン社)、『ママが守る! 家庭の新型インフルエンザ対策』(講談社)がある。












![冬のギフトにぴったりな“雪の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/629/large/0368f492-6e08-49f4-8c18-b0d3c52fe98c.jpg?1770179405)
![【働くママの労働問題】「子持ち様」が気をつけるべき職場の人間関係のポイント[社労士が回答]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/623/large/5af9810f-c081-42b4-a484-d448e0f9e922.jpg?1770162654)







































































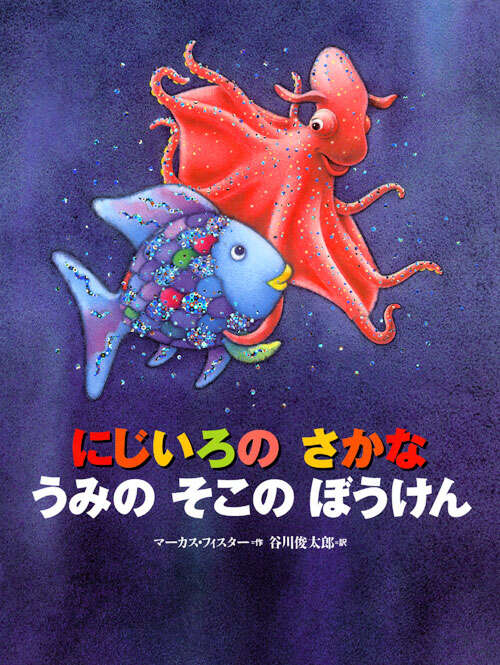















高木 香織
出版社勤務を経て編集・文筆業。2人の娘を持つ。子育て・児童書・健康・医療の本を多く手掛ける。編集・編集協力に『美智子さま マナーとお言葉の流儀』『子どもの「学習脳」を育てる法則』(ともにこう書房)、『部活やめてもいいですか。』『頭のよい子の家にある「もの」』『モンテッソーリで解決! 子育ての悩みに今すぐ役立つQ&A68』『かみさまのおはなし』『エトワール! バレエ事典』(すべて講談社)など多数。著書に『後期高齢者医療がよくわかる』(リヨン社)、『ママが守る! 家庭の新型インフルエンザ対策』(講談社)がある。
出版社勤務を経て編集・文筆業。2人の娘を持つ。子育て・児童書・健康・医療の本を多く手掛ける。編集・編集協力に『美智子さま マナーとお言葉の流儀』『子どもの「学習脳」を育てる法則』(ともにこう書房)、『部活やめてもいいですか。』『頭のよい子の家にある「もの」』『モンテッソーリで解決! 子育ての悩みに今すぐ役立つQ&A68』『かみさまのおはなし』『エトワール! バレエ事典』(すべて講談社)など多数。著書に『後期高齢者医療がよくわかる』(リヨン社)、『ママが守る! 家庭の新型インフルエンザ対策』(講談社)がある。