

「親ガチャ外れた」という言葉を聞くと、自分が責められているようで苦しい。流行しているから使っているだけで、深い意味はないかもしれないけれど、やっぱり傷ついてしまいますよね。そんなときに助けになるのが「哲学」です。
哲学は、心の内を思考や対話で解きほぐし、人に考えを伝える適切な「言葉」を見つける学問。教えてくれるのは、哲学研究者で書籍『こども哲学』の監修もつとめる佐藤邦政先生(茨城大学大学院講師)です。自分の感情を言葉にしながら深掘りしていくと、ちょっぴり心がスッキリします!

【ギモン】SNSなどで「親ガチャ外れた」という言葉を見ると、もしかしたら自分も子どもにそう思われているかもしれないと考えてしまい、悲しくなります。どうしたらよいでしょうか?
【ヒント①】「あなた自身を否定する言葉ではない」と考えましょう

佐藤先生:確かに「親ガチャ」という言葉はインパクトが強すぎて、全否定されたような気持ちになってしまいますよね。ウェブサイトやSNSなどで話題になる言葉は、日々新しいものが生まれては消えていきます。
哲学的なアプローチだと、発言者が「親ガチャ外れた」という言葉をどういう意味で使っているのか、というところから考えます。
その発言者が自分の子どもで顔を合わせて話ができる状態であれば、言葉を発したときの状況や態度などを観察していると、「あ、この子はそういう意味で『親ガチャが外れた』という言葉を使ったのか」と紐解くことができます。
でも、SNSで不特定多数の人に発している場合は、手掛かりが少なくて見極めるのが難しい。親からネグレクトされている子どもの切実の声かもしれませんし、友人と話しているときの軽い気持ちの発言かもしれません。さらに、同じ言葉であっても、世代によって解釈がズレているという場合もあります。
ですから、SNSで発信された言葉は、「あなた自身を否定する言葉ではない」と受け止めるのがよいと思います。
【ヒント②】「否定」ではなく「理解」を求めているかも?
佐藤先生:もし、SNSで「親ガチャ外れた」という投稿を目にしても、文字どおりの意味だと判断するのは気が早いかもしれません。
SNSに投稿できているということは、「親ガチャ外れた」という気持ちを吐露できる余裕はあるということですよね。投稿を親に見られたらリアルに仕返しされるなどの状況であれば、そのような発言はできないですし。本当に親のせいで不幸になっている深刻なケースもありますが、SNS上の文字だけで全てを判断することは難しいのが現実です。
たとえば、発言者は誰かを否定したいのではなく、自分が納得のいかない状況に不満があったり、親に対してモヤモヤしている気持ちがあったりして、「親ガチャ外れた」という言葉を使ったのかもしれない。そう推測することもできます。誰かを否定したいのではなく、「私は大変だ」ということを理解し、共感してもらいたかった場合もあるのかなと。
もし私の身近に、自分の子どもから「親ガチャ外れた」と言われて悩んでいる人がいたら、「こうやって、子どもが言ったことを受けて真剣に悩んでいるのだから、ハズレの親であるはずがありません。だからもっと話を聞いてみたり、子どもが自分から話してくれるまでそっとしておいたりするとよいです」と声をかけると思います。
【結論】単純に「言葉」だけで傷つく必要はない
言葉が持つ力はものすごく強いので、不特定多数に向けられた発言でも傷ついてしまうこともあります。その言葉を使った背景や話の流れなどがわからない場合は、気にしすぎないのが一番です。
もし実際に子どもに言われた場合は、お互いにどんな思いを抱えているのか、顔を突き合わせて話し合うことが必要かもしれません。話す態度や口調によって、言葉の真意も違ってきます。冗談ぽく言ったのか、それとも話の流れで傷つけるような言葉が出てしまったのか。目の前の子どもの様子を観察すると、「言葉」の背景にあるいろんな情報が得られると思います。
【今回の哲学のヒント】#アパテイア #ストア派

撮影/市谷明美
子育てがちょっとラクになる「こども哲学」連載
「心のモヤモヤ」を哲学で考える〔こども哲学・第1回〕
「やりたいこと」が見つからない?〔こども哲学・第2回〕
「登校しぶり」を支える親のケア〔こども哲学・第4回〕
「対応」へのモヤモヤどうする?〔こども哲学・第5回〕
「我慢しない」人付き合いのヒケツ〔こども哲学・第6回〕
こども哲学

\一生モノの教養が身につく!/
人に自慢し、明日から使いたくなる学問図鑑。これ1冊にこどもから大人まで、正解のない時代に役立つ哲学の知識が盛りだくさん。
有名な哲学者やテーマが短い文章とくすりと笑えるイラストで楽しく学べる。生き方は自由に選べる? 新しいものってどう作る? 世界のすべてがわかる? これからの時代に大事なのは自分で考える力だ!
〈小学上級・中学から・すべての漢字にふりがなつき〉

中村 美奈子
絵本サイトの運営に関わり、絵本作家への取材も多数。また漫画、アニメ、映画、ゲーム、アイドルなど幅広いエンターテインメントジャンルで記事を執筆。漫画家や声優、役者、監督、クリエイターなど、これまでに200名以上へのインタビューを経験している。
絵本サイトの運営に関わり、絵本作家への取材も多数。また漫画、アニメ、映画、ゲーム、アイドルなど幅広いエンターテインメントジャンルで記事を執筆。漫画家や声優、役者、監督、クリエイターなど、これまでに200名以上へのインタビューを経験している。
















![冬のギフトにぴったりな“雪の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/629/large/0368f492-6e08-49f4-8c18-b0d3c52fe98c.jpg?1770179405)
![【働くママの労働問題】「子持ち様」が気をつけるべき職場の人間関係のポイント[社労士が回答]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/623/large/5af9810f-c081-42b4-a484-d448e0f9e922.jpg?1770162654)












































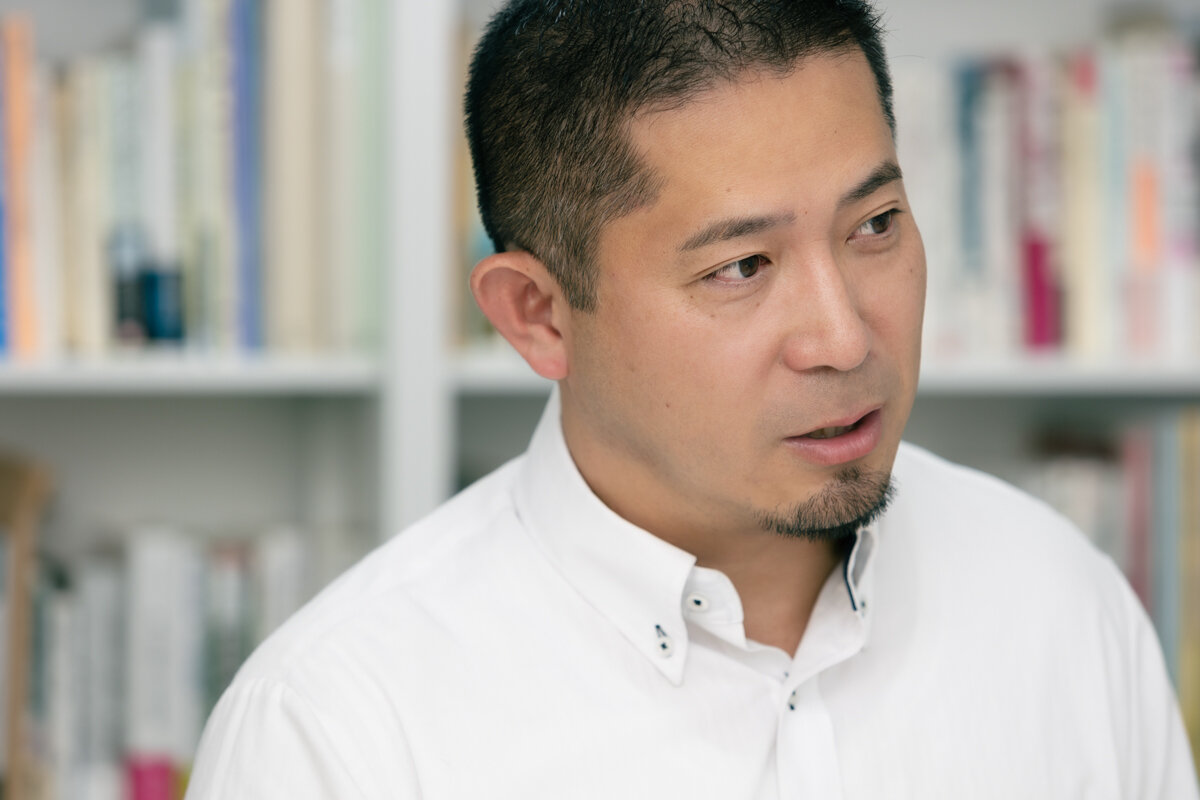



















































佐藤 邦政
茨城大学教育学部社会科教育(倫理学)講師。博士(文学)。研究内容は、不正義の複雑なありようと人間の多面的なあり方を一つひとつ紐解いていくこと。たとえば、私の父は社会的立場の弱い若手同僚や子どもにめっぽう優しく、会社で権力に抵抗を示す正義感がある人でしたが、家では母に厳しく接するときがありました。そんな矜持のあった父の姿が、人間を「こういう人だ」と単純化せず、じっくりと考えつづける今の私の研究関心を形作っています。家では4歳の娘と共働きの妻との3人暮らし。普段、娘に怒られてばかりいますが、そんな喜怒哀楽を表現してくれる娘を誇らしく思っています。
茨城大学教育学部社会科教育(倫理学)講師。博士(文学)。研究内容は、不正義の複雑なありようと人間の多面的なあり方を一つひとつ紐解いていくこと。たとえば、私の父は社会的立場の弱い若手同僚や子どもにめっぽう優しく、会社で権力に抵抗を示す正義感がある人でしたが、家では母に厳しく接するときがありました。そんな矜持のあった父の姿が、人間を「こういう人だ」と単純化せず、じっくりと考えつづける今の私の研究関心を形作っています。家では4歳の娘と共働きの妻との3人暮らし。普段、娘に怒られてばかりいますが、そんな喜怒哀楽を表現してくれる娘を誇らしく思っています。