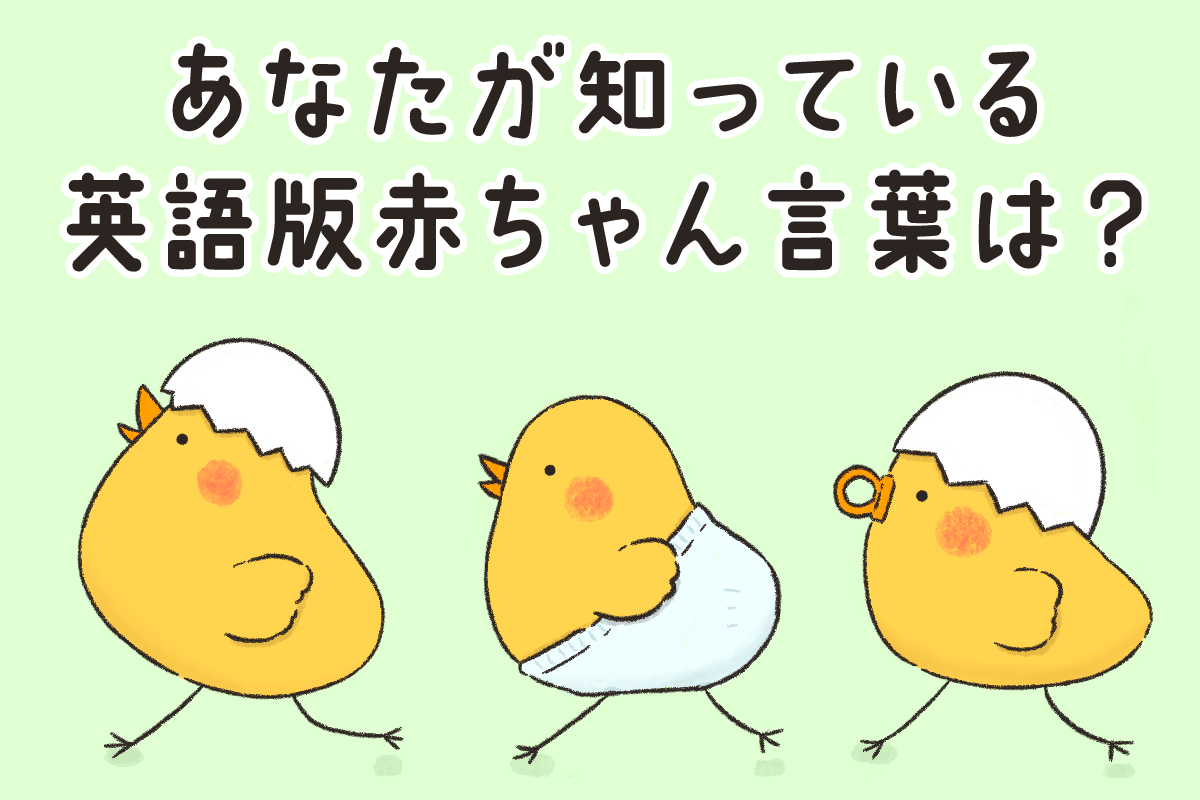中学受験の「親ミッション」 中受伴走を終えたママ教育ジャーナリストが小6年後半=本番直前期を明かす
リアル中学受験伴走レポ #3 ~ダメージを回避するために知っておきたい6年生後期編(夏休み~受験本番)~
2024.05.30
教育ジャーナリスト:佐野 倫子

まだまだ沈静化とはいかない令和の中学受験。今回は2024年2月に中学受験を伴走(親のサポート)を終えた教育ジャーナリストの佐野倫子さんが語る、「中学受験のリアルロードマップ」。
3回目は、受験の天王山である夏休みから、本番モードに入る6年生の後期(夏休みから受験期)における親のミッションと直前期のタスクを語っていただきました。
佐野倫子(さの・みちこ)
東京生まれ、早稲田大学卒。航空業界・出版社勤務を経て作家・教育ジャーナリストに。著書は『天現寺ウォーズ』、『中学受験ウォーズ 君と私が選んだ未来』(イカロス出版)。男子2人を育児中。
目次
受験生の夏休みの8割は塾
教育ジャーナリストの佐野倫子です。
3回目では、中学受験の天王寺と言えるぐらいに重要な夏休みから、本番までにしておきたいことをお伝えしていきたいと思います。
受験生の夏休み、子どもたちは7~8割の時間を塾に費やしています。もちろん塾によって日数は変わりますが、基本的に1日の多くの時間を夏期講習や志望校別特訓授業を受けることになります。勉強時間は1日10時間を超える子も。
夏以降、志望校別特訓が始まりますので、ますます教材の量は増えていきます。この時期からしっかり整理してあげましょう。ミスした問題をコピーしてノートにはったり、科目ごと、単元ごとに、すぐに教材が取り出せるようファイルしてあげたりすると効率があがります。
夏休みは時間を区切って息抜きを
そして夏休みは長丁場。息抜きをするのも忘れてはいけません。親は、塾の時間がちょっとした凪の時間。もしきょうだいがいる場合は、この時間にぜひ一緒に過ごす時間を取ってあげてください。たまにはお出かけをしたりして、リフレッシュタイムも。
「子どもが塾で頑張っているのに、いいのかな?」と少し良心が痛むかもしれません。でも、中学受験生の親は本当に忙しく、ストレスも相当なもの。うまく気分転換をして乗り切りましょう。
もちろん一番ストレスがかかっている受験生本人も、うまく息抜きをさせてあげたいですよね。実体験を振り返ると、丸一日遊びにいくのは難しいのが後期の生活です。ほぼ毎週のように模試やテストがありますし、小テストで細かくクラスや席次が変わるためです。
周囲を見ると、読書や公園、場合によってはメリハリがつけられるのであればゲーム類の時間を設定していらっしゃいました。模試の帰りに美味しいランチを食べるなどもおススメ。親子で話し合い、ダラダラせずに時間を区切って有効に使うことが大切です。
過去問は親がリードして
いよいよ、本番が来る……。私がそう実感したのは、6年生の9月。夏休みが終わったころでした。
9月になるといよいよ本格的に志望校の過去問にとりかかる時期になります。過去問は、1校1年分を解き、間違えた問題を解きなおすだけでも半日かかります。一方、この時期からは土日両方とも演習授業と志望校特訓ということも珍しくありません。
つまり絶対的に時間が足りないのが6年生後期。ということで、過去問を解けるのは第一志望から併願校を含めて、20年分くらいだと言われています。これを志望度合いで割る、というイメージです。第一志望は5年以上取り組んだほうが自信をもって挑めるでしょう。
さて、この過去問スケジュールですが、大手塾に通っているとなかなか個別にスケジュールを組んでもらうというわけにいきません。ここは親の出番。効果的な作戦を立てるために、日頃から子どもの習熟度や、得意不得意をある程度把握し、適切なタイミングを計る必要があります。
とはいえ、なかなか計画どおりにはいかないのが過去問進捗。我が家の場合も、本当は12月までに解き終えるように、と塾から指導がありましたが、実際は1月になっても併願校の過去問数年分を残していました。
我が家の過去問予定表のリアルな進捗は以下のとおり。
第一志望 8月1回 9月3回 10月4回 11月4回 12月2回
第二志望 10月2回 11月2回
第三志望 11月1回 12月1回
第四志望 1月1回
第五志望 11月1回
(以下略)
……セオリーから結構離れています(笑)。これは、第一志望校が独特の形式だったため、偏重して対策が必要だと判断したこと。また、志望度合いの低い学校は、第一志望の過去問を多く解いたぶん時間がなくなり、合格最低点、あるいは数点足りない点を取った時点で泣く泣くそれ以上やることをあきらめた結果です。
また、間違えた問題は印をつけて質問に行くように促していました。ただ、必要以上に解きなおしに時間をかけすぎないことも大切と先生からアドバイスがありました。
予定どおりにいかなくなったときは、焦らず、優先順位を明確にし、塾の先生に相談することをお勧めします。
















![お年玉と一緒に贈りたい“お正月の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/022/large/68833581-f835-4688-a9fe-33fa7156917c.jpg?1764905096)