

特に共働きの家で起こりがちなのが、「子どものために仕事を休むのはいつも母親」という不公平な状態。今回だけは夫に頼みたいと相談しても、まったく考えるそぶりもなく、
「俺は仕事、休めないよ」。
「私だってもう休めない!」と声を強めたり、そう言いたいのをグッとこらえたことのある人は、多いのではないでしょうか。
発熱など予想できないハプニングだけではなく、乳児検診や定期的な通院、保護者会など、前もって把握できる予定もあります。それなのに、どうして夫は仕事を調整できない・しないのでしょう?
「家で仕事の話はしたくない」という心理
「これはご家庭の状況や、それぞれの仕事や働き方によっても違うものですね。それでもやはり、ここにも社会の構造が影響しています」
布柴先生は再び、「男は外で仕事、女は家で家事育児」の時代を振り返ります。
この役割分担が主流だった時代、父親は家族に細かく仕事の話をしないものでした。
その名残で「家には仕事を持ち込まない」「仕事場に家庭の事情を挟まない」と考える人は、今もいます。「家でまで仕事の話はしたくない」という人も。
「共働きが増えて妻が働くようになっても、家ではお互いの仕事の話はしない傾向があります。加えて日本では、女性の非正規雇用や時短勤務が男性よりもかなり多く、夫と妻の働き方や仕事内容が違うケースが少なくありません」
夫婦で違う「休みにくさ」の意識
最新の調査では、子どものいる世帯の80%が「共働き」であることがわかっています(令和6年・厚生労働省)
子持ち共働き夫婦の約4割は「夫も妻も正規雇用」ですが、のこりの約6割の夫婦は、片方が正社員で片方はパートなど、「雇用の形が異なる」働き方をしています。
仕事先や雇用の形が違えば、夫婦で「休みにくさ」や「休めない時期」が違うのは当然のこと。
それを伝え合い、把握し合わないまま、なんとなく「子どもの体調不良や用事で休むのは、いつも妻」という形になっていないでしょうか?
そうなる要因はやはり、性別役割分業の思い込みにあると、布柴先生は説明します。
「この不公平感を減らすには、夫婦でお互いの仕事の内容や状況を共有することが欠かせません。休みにくさや繁忙期を把握しあった上で、片方に負担が偏りすぎないように、助け合っていくのが望ましいです」

第一歩は、お互いの仕事に関心を持ち合うこと。
その上で、定期的な用事だけではなく、急な発熱などの緊急事態に対するルールも前もって決めておくのが良いでしょう。一度分担を決めたら終わりではなく、その都度の状況をこまめに知らせるのも大切です。
「子どもの用事には母親が付き添う」という思い込みは、夫婦だけではなく、保育園や義理家族、病院など、日本社会のさまざまなところにもあります。
その思い込みに対処するため、子どもの書類に書く「第一の連絡先」を夫の電話番号にする、というやり方も。妻が対応するときでも、夫がその状況に関わる形を自然に作れます。
────◆────◆────
子育て世代にむけた「夫婦喧嘩のイライラ・モヤモヤ解決法」は全3回。第2回となる今回は「危機感の違い」などを取り上げました。
イライラ・モヤモヤが生まれるのは、個人だけではない、社会の構造が理由。それを理解できると、相手個人を責めずに話し合いができ、夫婦で対策を考えられます。
ですが厄介なことに、その「話し合い」の場を作ろうとして、さらにイライラ・モヤモヤが発生してしまうことも。
そんな難しい場面にも、状況を解きほぐして理解する方法と対策はあるでしょうか。第3回でも引き続き、布柴靖枝先生に伺います。
【第3回】8月8日(金)公開
取材・文/髙崎 順子
参考・出典
国民生活基本調査
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa24/index.html

髙崎 順子
1974年東京生まれ。東京大学文学部卒業後、都内の出版社勤務を経て渡仏。書籍や新聞雑誌、ウェブなど幅広い日本語メディアで、フランスの文化・社会を題材に寄稿している。著書に『フランスはどう少子化を克服したか』(新潮新書)、『パリのごちそう』(主婦と生活社)、『休暇のマネジメント 28連休を実現するための仕組みと働き方』(KADOKAWA)などがある。得意分野は子育て環境。
1974年東京生まれ。東京大学文学部卒業後、都内の出版社勤務を経て渡仏。書籍や新聞雑誌、ウェブなど幅広い日本語メディアで、フランスの文化・社会を題材に寄稿している。著書に『フランスはどう少子化を克服したか』(新潮新書)、『パリのごちそう』(主婦と生活社)、『休暇のマネジメント 28連休を実現するための仕組みと働き方』(KADOKAWA)などがある。得意分野は子育て環境。








































































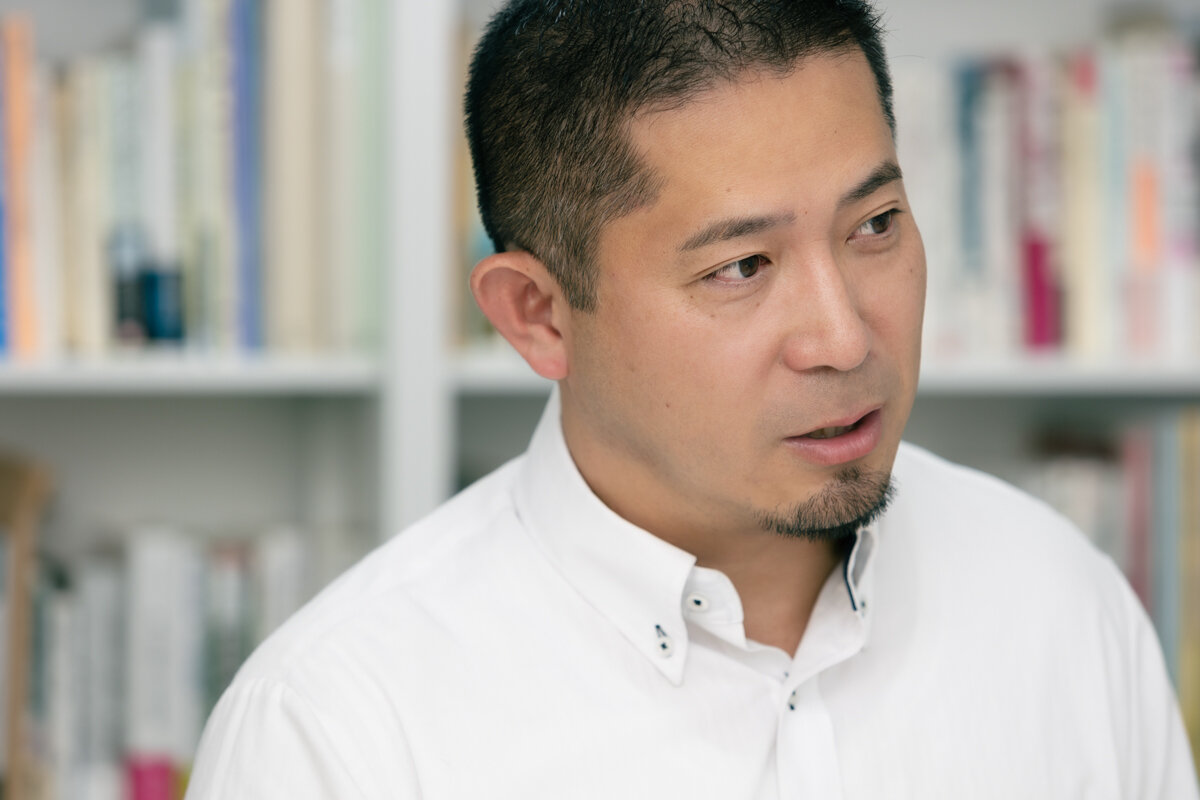







































布柴 靖枝
文教大学人間科学部臨床心理学科教授、文教大学大学院付属臨床相談研究所 所長。 京都大学大学院博士後期課程修了。博士(教育学)。 家族心理学、統合的家族療法が専門。長年にわたりカウンセリングに従事。女性問題やジェンダーを基に生じる暴力(DV、ハラスメントなど)への支援を、心理臨床のみならず、国連の活動に関わり、グローバルな活動を展開している。 日本家族心理学会理事,認定NPO法人日本BPW連合会理事長,国連NGO国内女性委員会副委員長,内閣府男女共同参画推進連携会議議員,埼玉県男女共同参画審議会会長,一般社団法人DICTネットワーキング研究会共同代表理事(2025年7月1日現在) 資格:公認心理師,臨床心理士,家族心理士,社会福祉士,上級教育カウンセラー
文教大学人間科学部臨床心理学科教授、文教大学大学院付属臨床相談研究所 所長。 京都大学大学院博士後期課程修了。博士(教育学)。 家族心理学、統合的家族療法が専門。長年にわたりカウンセリングに従事。女性問題やジェンダーを基に生じる暴力(DV、ハラスメントなど)への支援を、心理臨床のみならず、国連の活動に関わり、グローバルな活動を展開している。 日本家族心理学会理事,認定NPO法人日本BPW連合会理事長,国連NGO国内女性委員会副委員長,内閣府男女共同参画推進連携会議議員,埼玉県男女共同参画審議会会長,一般社団法人DICTネットワーキング研究会共同代表理事(2025年7月1日現在) 資格:公認心理師,臨床心理士,家族心理士,社会福祉士,上級教育カウンセラー