

【不登校児】がいる家庭 “当事者”になって初めてわかる「重み」「辛さ」「消耗」とは…気鋭の出版ジャーナリストが初めて明かした
不登校児がいる家庭へ 当事者だから語れること (2/3) 1ページ目に戻る
2025.08.23
出版ジャーナリスト:飯田 一史
「選択肢がある」ことと「やりたい」と思うかは別の話
教育ジャーナリスト・おおたとしまささんによる『不登校でも学べる』など、不登校の児童・生徒向けのフリースクールその他の選択肢を紹介した本が今ではいくつも出ている。
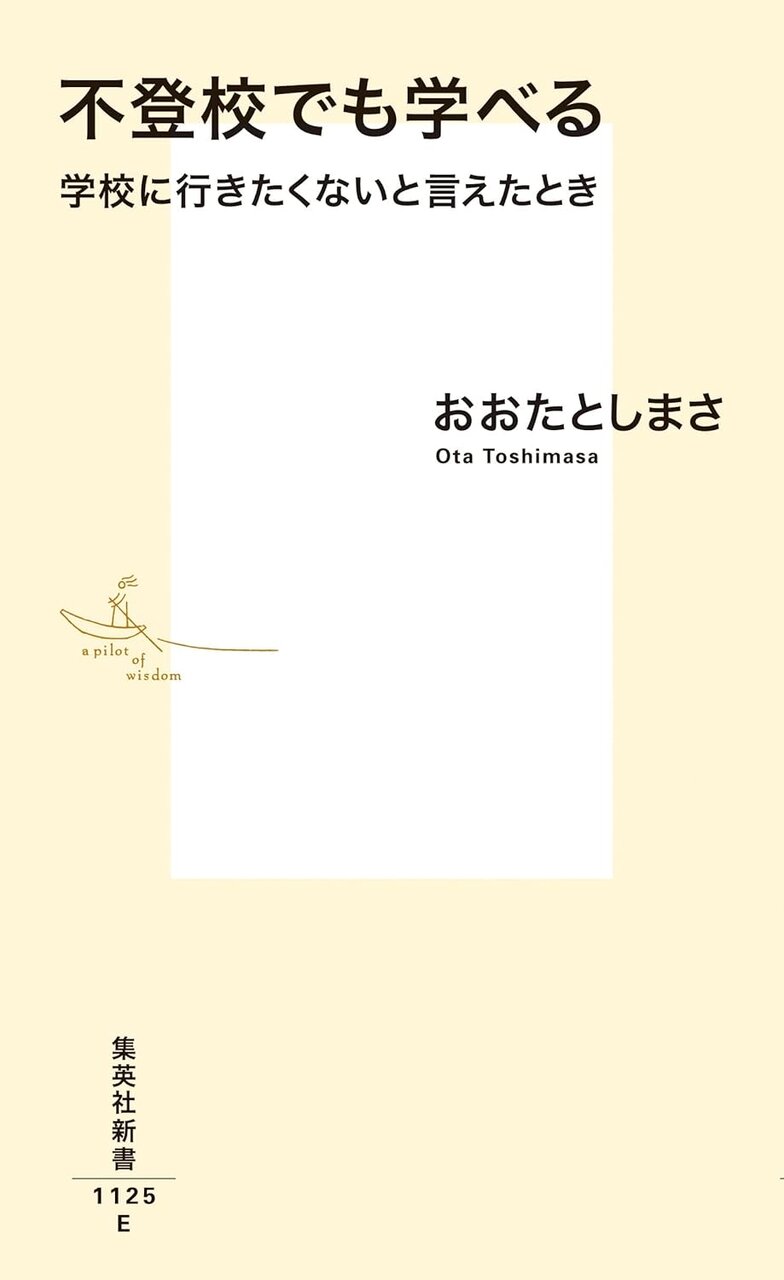
不登校になった場合にどんなオルタナティブな道があるのかを知るためのカタログとしてはとても有用だ。
ただ、そういう選択肢があるとわかっても問題がなくなるわけではない。「AやBやCがあります」ということがわかっても、具体的に我が子にとってどれならいいのかは、試してみるまでわからない。
それ以前に「そういう場所があるのはわかったが、うちからだと距離的に通えない」「金銭的に折り合わない」等々を、ひとつひとつ親側が判断して除外していく段階で、一手間も二手間もかかる。
そうして選んだところへお試し体験の予約などをして行くわけだが、先方との日程調整や、「そういう場所に行ってみよう」と本人を説得し、連れ出すまでにまた疲れるのだ。
そして、試してみたのにハマらなかった場合の徒労感、それがいくつも続いた場合のあの感じは、親子お互いにとって重くのしかかる。
最初の段階では、まずまずの反応だったので契約や手続きをしたのに、そのあとすぐやる気がなくなったり、やっぱりダメだった、となったりすることも全然ある。
お金やそこまでにかかった時間がムダになる。これも正直、心理的にダメージである。
「こっちは仕事休んで行ってんだぞ!」などと思ってしまうが、当然こちらがキレても何も解決しない。
「昔と違って学校に行かなくても、いろいろあるから大丈夫」というのは、理屈上そうなのだが、その子にとってどれが合っているのかは事前にはわからないものなのだ。
合っていたとしても、本人がそれで納得して続けていこうと思うかどうかは、また別の話である。たいていは一発でフィットする場所やサービスを引き当てられるわけではない。
それに、「まあ、これなら」というものが見つかるまで「いろいろ」やらされる子ども側からしても、相当めんどうくさいだろうし、大人への不信や不満が募る。
また、例えばオンライン学習サービスなどを契約したからといって、勉強するモチベーション自体をそういうサービスが作ってくれるわけでもない。勉強したらポイントがもらえるとかゲームができるといった外発的な動機付けはがんばってしてくれるけれど、内発性がゼロなら子どもは立ち上げることすらしない。
学習に対する内発性が育っていない、あるいは心が閉じてしまった不登校の子どもの場合、「やる気にさえなればいくらでも勉強できるよ」という環境を用意してもどうにもならない。






































































































