

東海初の【学びの多様化学校】岐阜市立草潤中学校〔徹底ルポ〕 「学校が生徒に合わせればいい」驚きの取り組みとは?
不登校の子の新たな学びの選択肢「学びの多様化学校」 #2 (5/5) 1ページ目に戻る
2025.09.14
「学校行事」も生徒の発案から
──子どもたち自身からやりたい、学びたい気持ちが出てくるのは、素晴らしいことですよね。
石榑先生:そうなんです。行事もあらかじめ決まっているものは最低限で、生徒の発案や企画で実現するものが多いんです。今年は音楽が好きな子が多く、地域の方たちを呼んでフェスをやりたいと意気込んでいます。
──参加したくないという子もいませんか?
石榑先生:もちろんいます。先日もソフトボール大会をしたのですが、守りだけ参加する子や攻撃だけ参加する子、応援に徹する子もいれば、教室から眺めているだけの子もいました。
オンラインで見学している子や、全くかかわらない子もいます。参加する・しないも生徒自身が決定します。

自己選択の積み重ねが自己肯定感を育む
──あらゆる面で生徒自身が選択し、決定できることを大切にされているんですね。
石榑先生:はい、自分らしくいられるための選択・決定できることが自己肯定感を育むことにもつながると考えています。
マイタイムや総合的な学習の時間に地域の方を講師としてお呼びしたり、生徒たちが地域の活動に参加したりする機会も多いのですが、いろんな方から「学校が元気になってきた」と声をいただきます。
自己決定を繰り返す中で、「自分がどうしたいか」「どうありたいか」に向き合い、それによって自信や主体性の育成につながっています。さらに、持っている力を誰かのために使っていきたいという思いも生まれてきているのを感じます。
4月の入学当初、「学校はつまらない、何もやる気がない」と話していた子がいたんですね。でも焼き菓子作りには興味があるというので、音楽、美術、技術・家庭の中で好きなことを学べる「セルフデザイン」や「マイタイム」などの時間にお菓子作りをしたらどうかと勧めてみたんです。
すると、みんなに「おいしい」と喜んでもらったのがきっかけで、地域の方たちにも食べてもらいたいと、すごく意欲的になってきています。私たちも、その願いをかなえるためにどんなサポートが必要か、一緒に考えているところです。
先生や職員はじめ、たくさんの大人に応援されているという実感が子どもたちの力になっているのかなとも思います。
──安心できる居場所に信頼できる大人がいて、自分で選択・決定できる環境があれば、子どもはちゃんと伸びていくんですね。
石榑先生:もちろん仕組みや制度の問題だけではないんですよね。こういう環境があっても通えない子はいます。50人いたら50人違うわけなので、できる限りオーダーメイドで、子どもたちのありのままを受け入れていけたらと思っています。
───◆─────◆───
草潤中学校では、自己選択・自己決定の機会を保障することで、子どもたちは自信や主体性を取り戻し、自ら成長している様子がうかがえました。3回目は、対話を通じて子どもたちに寄り添う、大分県の「くす若草小中学校」の様子をお伝えします。
取材・文/北京子
【学びの多様化学校の連載】
1回目を読む(神戸女子大学教授・伊藤美奈子先生インタビュー)。
3回目を読む(学びの多様化学校 大分県「くす若草小中学校」)。
※3回目は公開日までリンク無効

岐阜市立草潤中学校
住所:岐阜県岐阜市金宝町4‐1
電話:058‐263‐3801
https://gifu-city.schoolcms.net/soujun-j/
【関連書籍】





















![クリスマスプレゼントにおすすめの“小学生向け絵本”3選[子どもの本専門店・店長が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/044/835/large/add5217c-b623-4fe3-aae5-53a1f5e2ba64.jpg?1763085159)












































































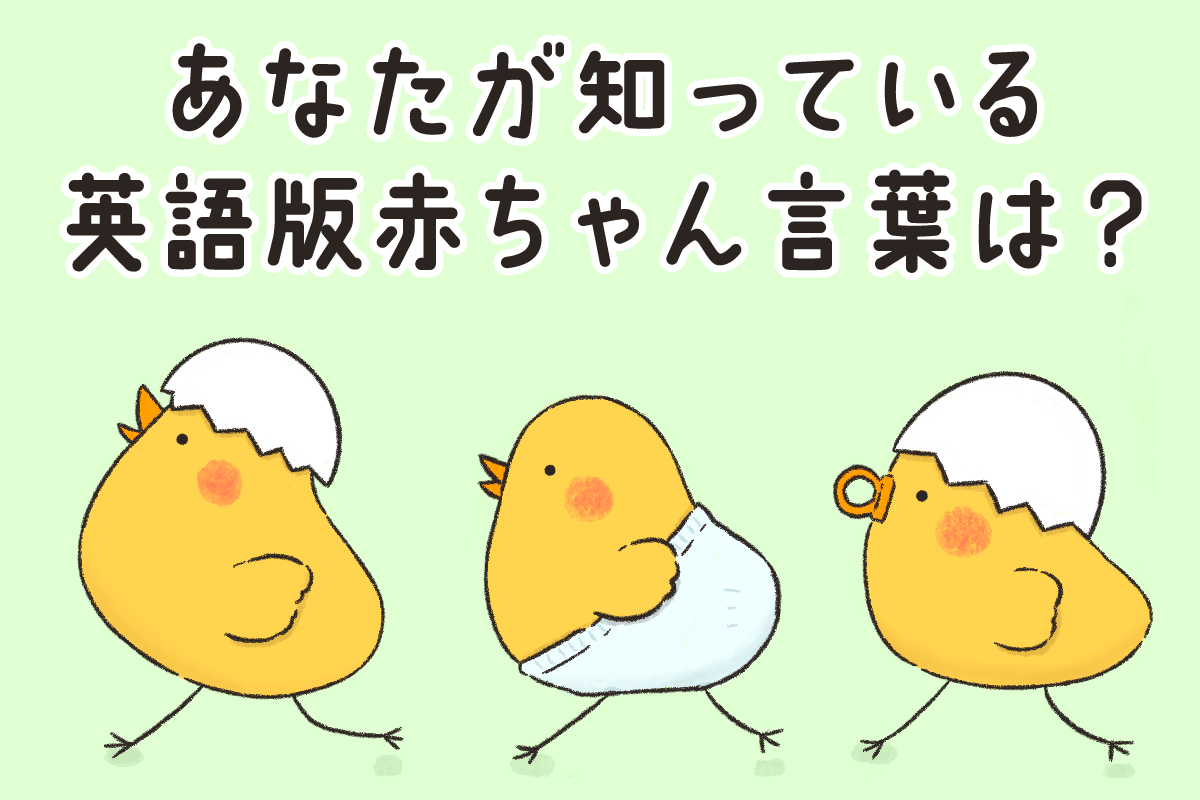

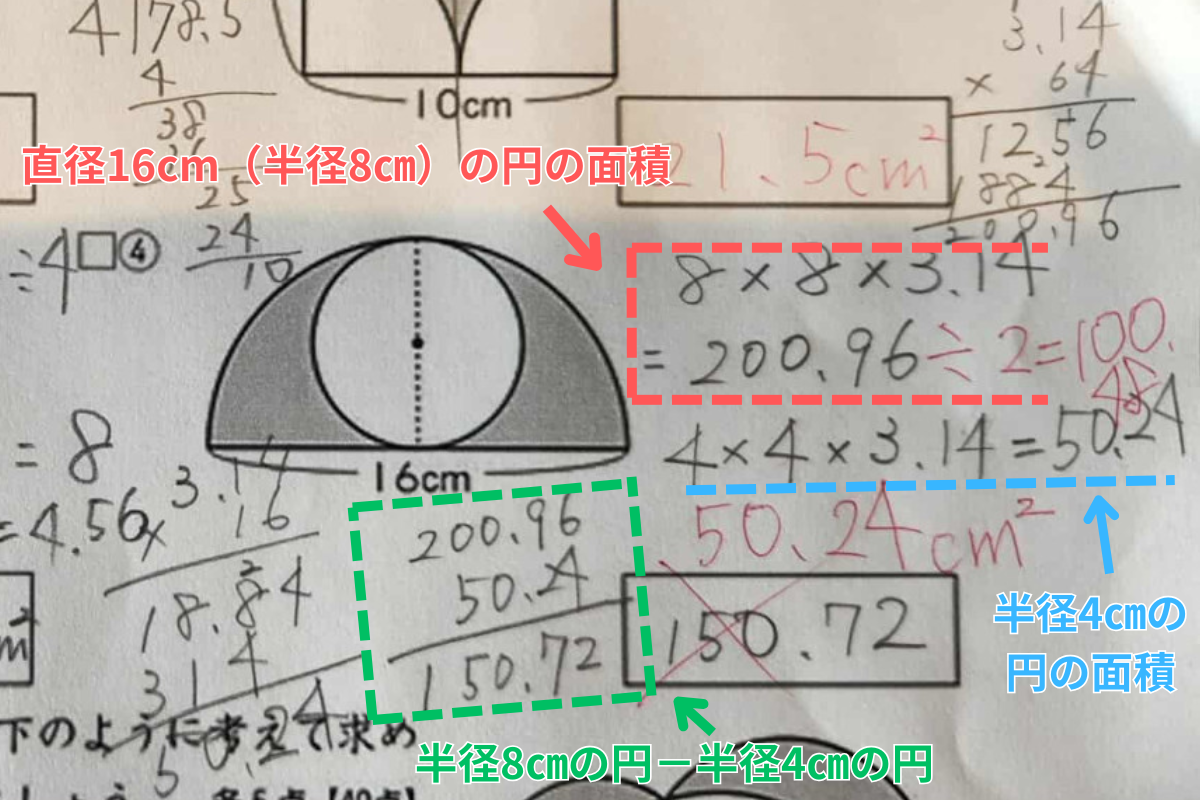






北 京子
フリーライター。 藤沢市在住。食の月刊誌の編集者を経て独立。食を中心に、SDGs、防災、農業などに関する取材・執筆を行う。 3児の母。自然の中で遊ぶこと、体を動かすこと、愛犬とたわむれることが好き。
フリーライター。 藤沢市在住。食の月刊誌の編集者を経て独立。食を中心に、SDGs、防災、農業などに関する取材・執筆を行う。 3児の母。自然の中で遊ぶこと、体を動かすこと、愛犬とたわむれることが好き。