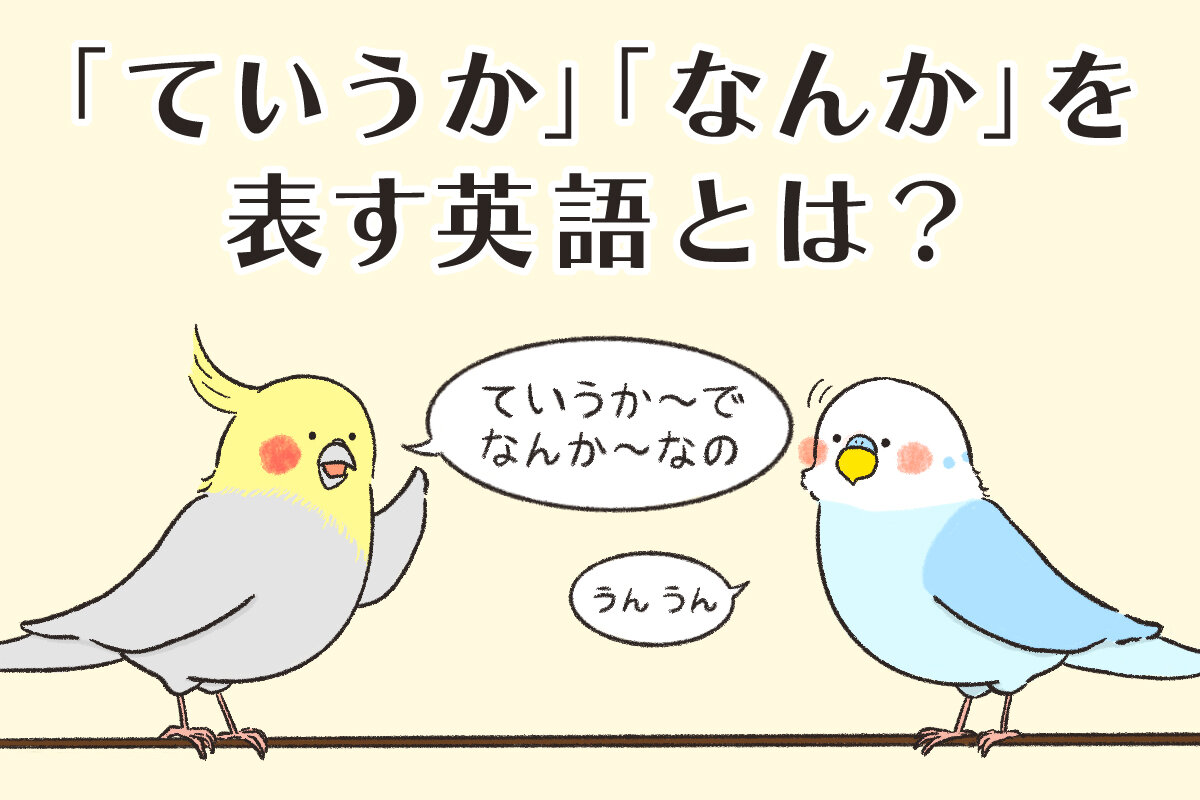

【子どものスマホ】利用時間を減らす秘策 「家庭内でルールを作り、親も守る」が想定外の効果〔脳科学者が解説〕
子育て中の家庭が知っておきたい「スマホ利用のリスクとメリット」 #2 ~東北大学助教・榊󠄀浩平先生に聞く、スマホ時間を減らすための方法編~ (4/4) 1ページ目に戻る
2024.12.13
東北大学応用認知神経科学センター助教:榊󠄀 浩平
ネットで調べた情報は忘れやすい
――最近は、勉強にもスマホを使う子が増えているようです。その影響についてはいかがですか?
榊󠄀先生:ネットで調べたことより、紙の辞書で調べたことのほうがしっかり記憶されるという実験結果があります。
もちろん、短時間で効率的に調べられるのはネットですが、その間、前頭前野はゲームをしているときと同じようにほぼ活動していない状態。一方、紙の辞書を引くときは、指先で薄い紙をめくる、五十音順に文字を探すなどプロセスが複雑な分、脳は活発な状態をキープします。
1回目でもお話ししたとおり、脳は負荷をかけなければ働きません。脳の活動が高まらなければ、どれだけ調べても記憶には残りにくいのです。
大切なのは、使う目的を見失わないこと
󠄀榊󠄀先生:ネットで調べた情報を忘れやすいという傾向は、“デジタル性健忘”や“Google効果”とも言われています。仕事などでスピードや効率を重視するなら、ネットで調べればいいと思います。
しかし子どもの学習の目的は、ただ情報を得ることではなく、知識を自分の中に蓄えて活用できるようにすること。目的に合わせて使い分ける必要があります。
──学校でもタブレット学習が広がっています。
榊󠄀先生:大切なのは、「その先に何を目指すのか」だと私は思います。子どもたちのどんな資質を伸ばしたいのか、何のためにデジタル機器を使うのか、ということを十分に議論することが重要です。それは家庭でも言えること。
実は、世界に先駆けてICT教育を推し進めてきたスウェーデンは、昨年、アナログ教育への回帰を決定しています。もちろん、満場一致ではなく、いろんな意見があるでしょう。
日本は今後どうするのか、十分な検証と議論を重ねたうえで、子どもたちの可能性を伸ばしていってほしいと思います。
───◆─────◆───
親子で一緒にルールを決めて守ることで、子どものスマホの利用時間を減らせることがわかりました。大人自身も、スマホとの付き合い方を見直す必要がありそうですね。次回からは、対してスマホを駆使した超効率的な勉強法を網羅し、成績を上げるノウハウを紹介する『東大式スマホ勉強術』の著者であり、YouTube「スマホ学園」を運営する現役東大生・西岡壱誠さんに、スマホ依存にならない正しいスマホ勉強法についてお聞きします。
取材・文/北 京子
スマホと学力に関する記事は全4回。
1回目を読む。
3回目を読む。
4回目を読む。
(※3回目、4回目は公開日までリンク無効)


北 京子
フリーライター。 藤沢市在住。食の月刊誌の編集者を経て独立。食を中心に、SDGs、防災、農業などに関する取材・執筆を行う。 3児の母。自然の中で遊ぶこと、体を動かすこと、愛犬とたわむれることが好き。
フリーライター。 藤沢市在住。食の月刊誌の編集者を経て独立。食を中心に、SDGs、防災、農業などに関する取材・執筆を行う。 3児の母。自然の中で遊ぶこと、体を動かすこと、愛犬とたわむれることが好き。












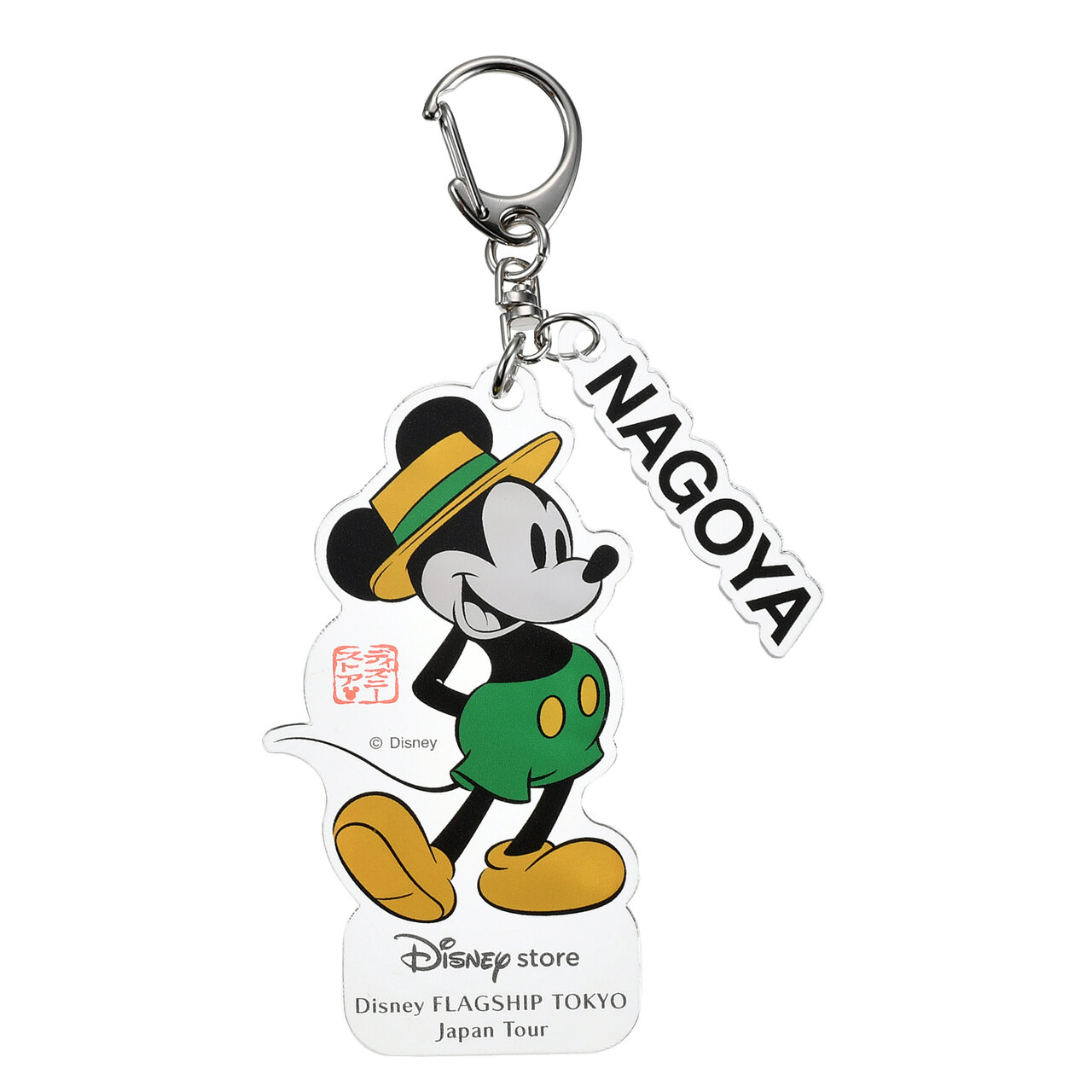

































































































榊󠄀 浩平
1989年千葉県生まれ。東北大学 加齢医学研究所 応用認知神経科学センター助教。医学博士。 認知機能、対人関係能力、精神衛生を向上させるなど、人間の「生きる力」を育てる脳科学的な教育法の研究、開発を行う。 主な著書に『スマホはどこまで脳を壊すか』(朝日新書)、共著に『最新脳科学でついに出た結論「本の読み方」で学力は決まる』(青春出版社)。
1989年千葉県生まれ。東北大学 加齢医学研究所 応用認知神経科学センター助教。医学博士。 認知機能、対人関係能力、精神衛生を向上させるなど、人間の「生きる力」を育てる脳科学的な教育法の研究、開発を行う。 主な著書に『スマホはどこまで脳を壊すか』(朝日新書)、共著に『最新脳科学でついに出た結論「本の読み方」で学力は決まる』(青春出版社)。