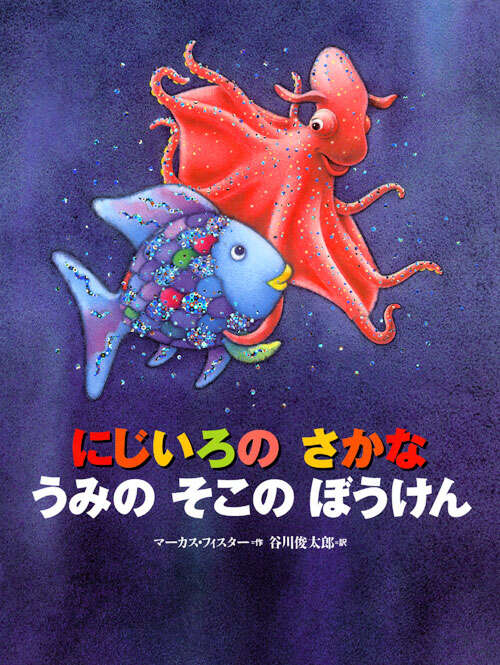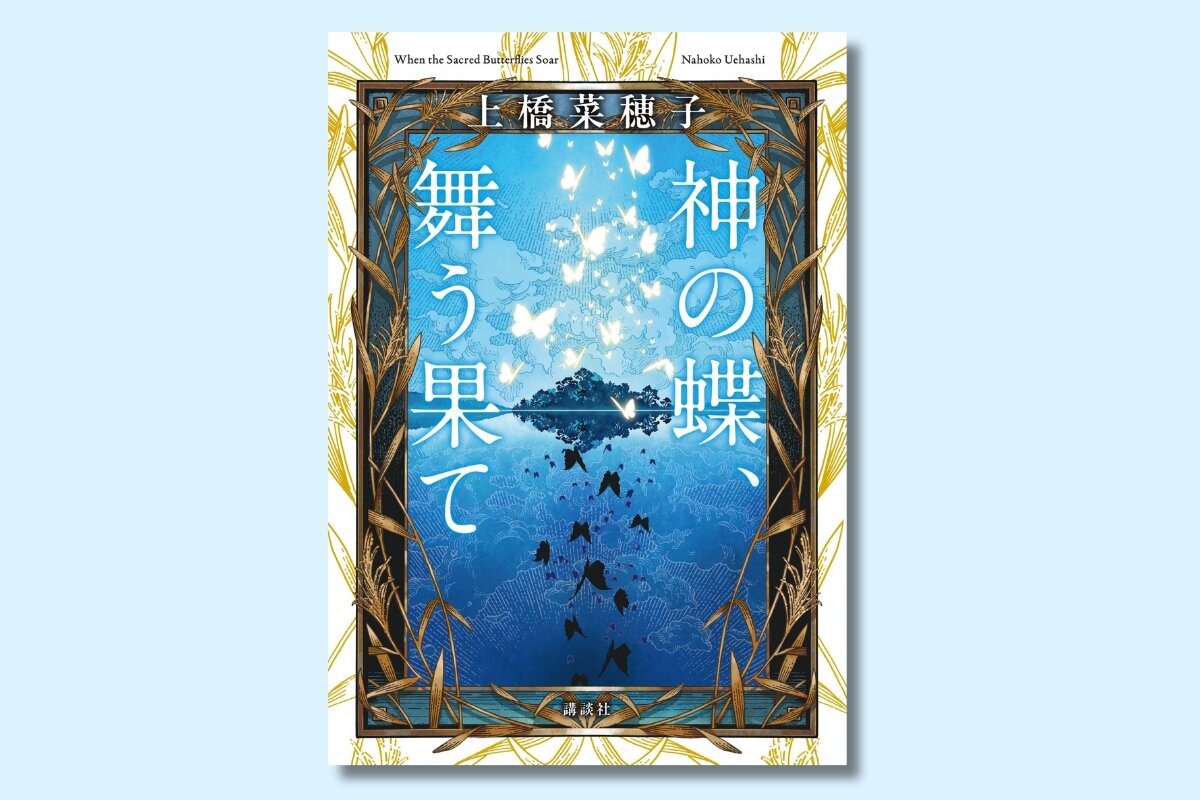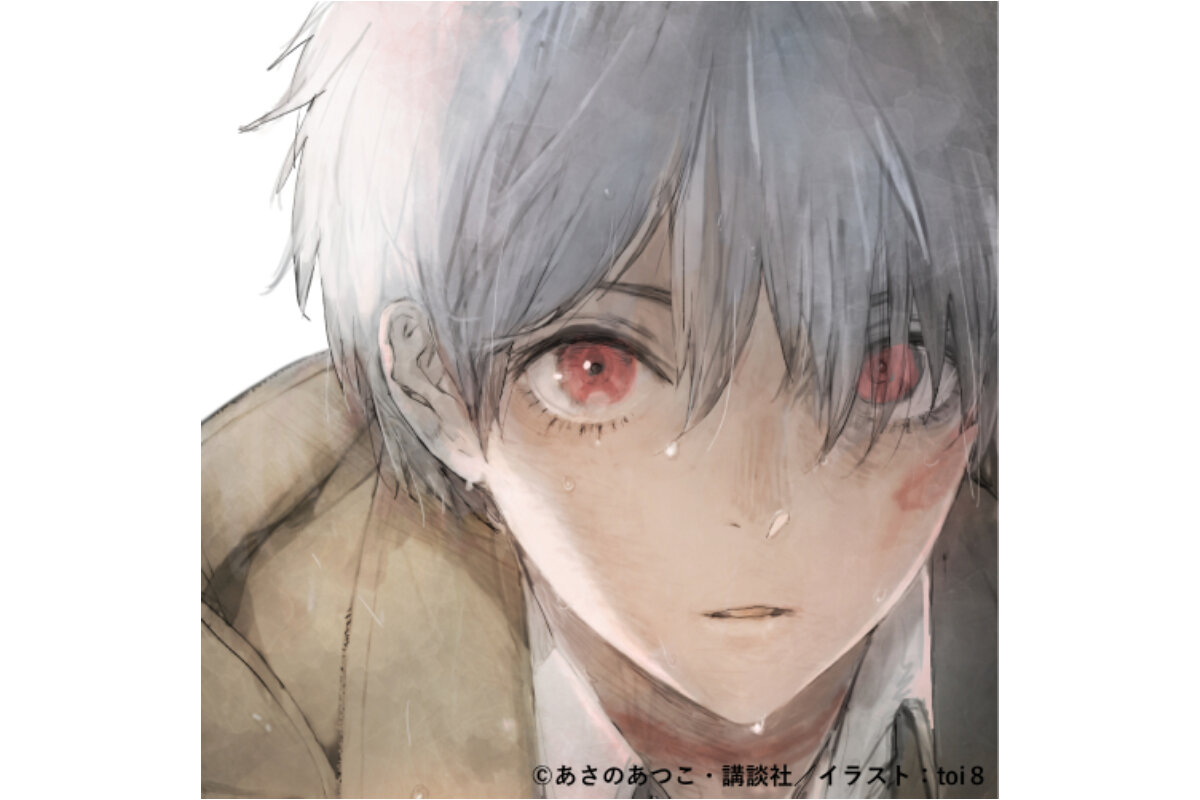「過激すぎる」は大人の誤解!? 子どもが『サバイバル』『デスゲーム』に熱中する本当の理由とは
出版ジャーナリスト・飯田一史のこの本おススメ! 第5回 「サバイバル・デスゲーム」 (3/5) 1ページ目に戻る
2025.09.27
ライター:飯田 一史
「デスゲーム」も大人が過度に遠ざける必要はない
サバイバルものから派生するようにして1990年代末に刊行された『バトル・ロワイアル』(著:高見広春/太田出版)をきっかけに、いわゆるデスゲームものが登場しました。2000年代には『王様ゲーム』(著:金沢伸明/双葉社)や、『リアル鬼ごっこ』『×ゲーム』(著:山田悠介/共に幻冬舎文庫)などが流行しています。
『バトル・ロワイアル』(著:高見広春/太田出版)
『王様ゲーム』(著:金沢伸明/双葉社)
デスゲームものは生死をかけたゲームの緊迫感、場合によっては子ども同士で脱落者を選ぶ、殺し合いをする、という設定の過激さが物議をかもしました。
大人が積極的に読ませたい本ではなかったものの、中高生からは熱い支持を得て、今でも一定の人気があるジャンルとして残っています。
誤解している大人が多いのですが、読者はデスゲームで人が脱落していく様子を、猟奇的に楽しんでいるわけではありません。殺人事件が起こるミステリーで、人が死ぬこと自体を楽しむ人がいないのと同じです。
・主人公たちが死や脱落を回避するために必死で知恵をしぼり、決死の行動をする様子
・日常生活ではきれいごとや表面的な部分にとどまっていた人間関係が、死を前にしてふだん見せていないお互いの本性や本音が垣間見えるところ
・家族や仲間、想い人に託して散っていく献身的な姿
このようなところに惹かれています。ですから大人が過度に心配したり、遠ざけたりする必要はないと思います。
2010年代にはデスゲーム、サバイバルものの表現をソフトにして、小学生でも安心して読めるシリーズが児童文庫で次々に始まり、人気を集めます。
選書①『人狼サバイバル』
『人狼サバイバル』(著:甘雪こおり/講談社)もそういう流れから出てきた人気作品ですが、ひと味もふた味も違います。

作:甘雪こおり/絵:himesuz(講談社)
Amazonで見る↓
人狼は「村人陣営」と「人狼陣営」に分かれて、会話や推理を使いながら自分の陣営の勝利を目指すコミュニケーションゲームで、『人狼サバイバル』はこの人狼探しのゲームをベースにしたサバイバルもの。
デスゲームものでは、最後まで生き残るか、主催者に勝った参加者の願いがかなうといった設定がよく見られます。『人狼サバイバル』もそうなのですが、参加する中学生たちの動機・背景や、叶えたい願いが時折、非常に考えさせられるものになっています。
詳しくはネタバレになるので避けますが、ネグレクト(保護者からの虐待)や人類に争いをやめさせるために人間のある部分を根本的に変えてしまう、といったものがあります。
しばしば「海外のティーン向けの小説と比べると、日本では社会問題について扱った人気作品が少ない」といった否定的な声があがりますが、『人狼サバイバル』はサバイバルもののドキドキ感や推理のおもしろさを提供しつつ、同時に読者にとって身近な問題から国際紛争・戦争まで、登場キャラクターに感情移入させながら問いを投げかける作品になっています。











![お年玉と一緒に贈りたい“お正月の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/022/large/68833581-f835-4688-a9fe-33fa7156917c.jpg?1764905096)





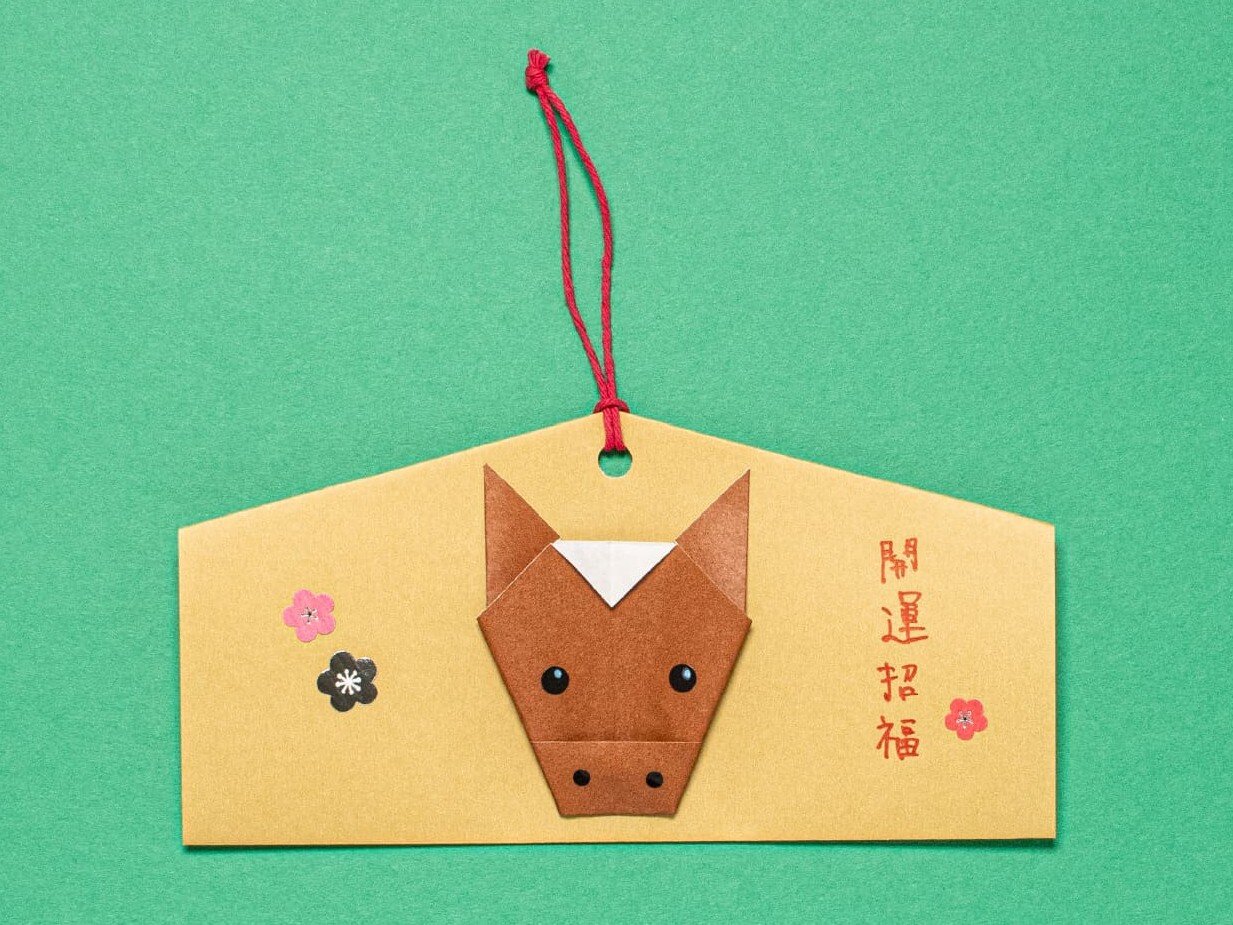



![クリスマスプレゼントにおすすめの“小学生向け絵本”3選[子どもの本専門店・店長が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/044/835/large/add5217c-b623-4fe3-aae5-53a1f5e2ba64.jpg?1763085159)