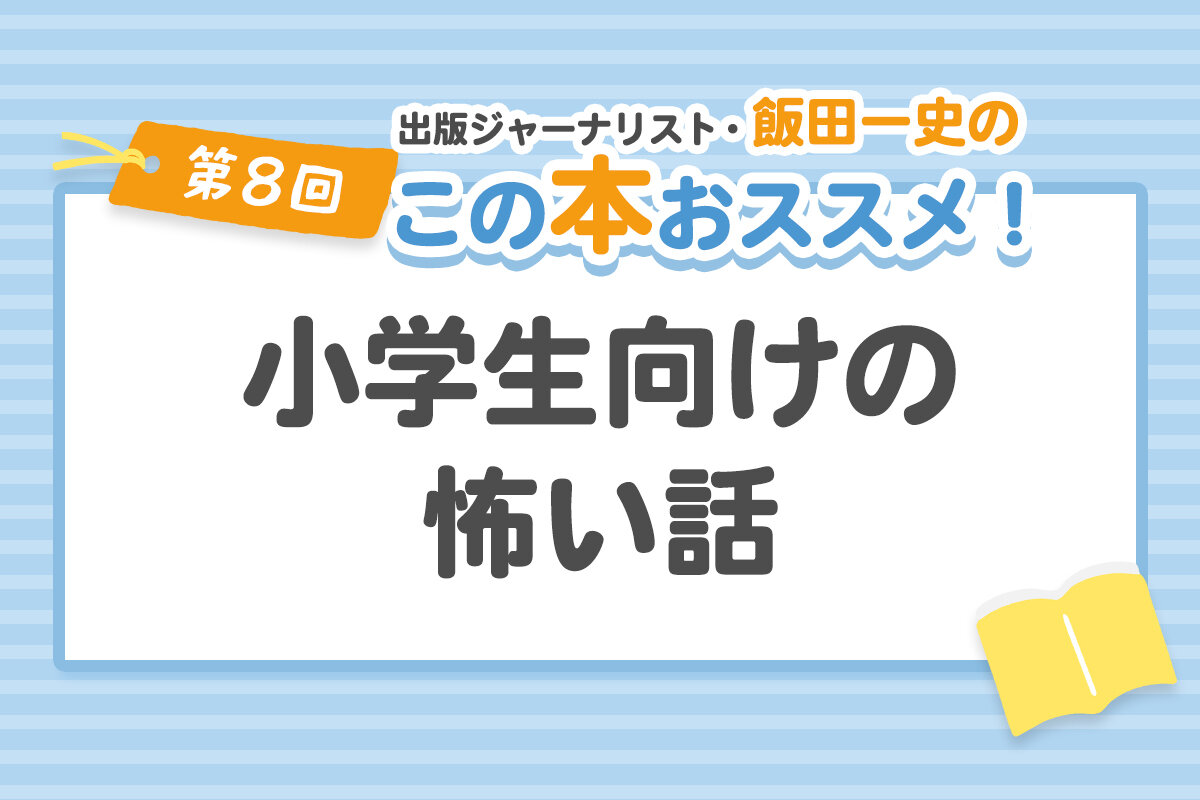知っているキャラクターやエピソードが読書のハードルを下げる
読書嫌いな子に「漫画ノベライズ」がおすすめの理由の1つ目は、「漫画の世界がそのまま小説になっていること」です。
知っているキャラクターやエピソードが出てくるので、お子さんも「ちょっと読んでみようかな」という気になりやすいでしょう。本を読まなかった子が本を開くようになったら、その子の読書人生においての大きな一歩に!
それでも、おもしろくなければ、子どもはページをめくる手を止めてしまいます。そんなときに助けになるのが、2つ目の理由「漫画の絵を見たことがあるから、小説になっても『ここはあのシーンだ!』と想像しやすいこと」です。読み始めた読者の気持ちを物語に引きこみ、「おもしろい!」と感じてもらえるように工夫して書かれているのです。
もえぎさんは、ストーリーやコマ運びは「原作そのまま」の流れを守り、さらに原作の持つ魅力が読者に伝わるように心がけているといいます。漫画の内容を文字で表現するときに、意識していることはなんでしょうか。
もえぎ 漫画ノベライズは、原作ファンにとっては「答え合わせ」ができる副読本のようなものかと思います。
例えば『小説 星降る王国のニナ』のP112〜113で、姫巫女アリシャの身代わりとして城に連れ去られた主人公・ニナが、よからぬ企みをする貴族にそそのかされて城外に出て、自分を探しに来たアズールが刺客に襲われるというシーンがあります。
勝手に城を抜け出したニナは、自分が昔住んでいた場所を見に行きました。しかしそこにはなにもなく、「ニナ」という名前の少女がいたという過去が消え、まるで死んだみたいだと感じます。自分を城に連れて行ったアズールを責めるニナ。ニナの心の痛みを理解したアズールは、「今なら逃げても追わない」と言いますが、ニナはある決意を持ってそれを拒み、「許してやる。死んでやるよ。」と答えます。
笑って言ったつもりが、泣き笑いになってしまったニナ。そのニナを見たアズールの反応を、漫画では3コマを使って表情の変化を表現しています。セリフもモノローグもありませんが、その表情からアズールがなにを感じたのか、言葉がなくとも読み手に伝わってくる、すばらしいシーンです。

そこを小説では、「そのさびしすぎる笑顔が、アズールに突き刺さる。空っぽの心に、今まで感じたことのない感情があふれ出した。それが愛しさであることは、アズール自身にもわかっていない」と文章化しました。
このときもっとも大切にしたのが、「原作とズレた解釈になっていないか」です。自分はもちろん、編集者にも、何度もチェックしてもらっています。
言葉になると「楽しさ」を実感しやすい
漫画ノベライズをおすすめする3つ目の理由は、物語がより深く楽しめることです。
漫画ノベライズでは、キャラクターの気持ちや細かい出来事が、ていねいに書かれていることが多いのです。漫画を読んでいたときには気づかなかった伏線や、別の角度から見ると話に深みがあることなどに気づくと、子どもは「読むことが楽しい」と実感しやすくなります。
その点も、もえぎさんは細部まで心配りをして執筆しています。
もえぎ 執筆にあたり、原作漫画を読んでいる人だけではなく、原作漫画をまだ読んでいない読者も意識しています。
原作漫画をまだ読んでいない読者にとっては、初めて出会う物語。なるべくわかりやすく、ストーリーを追っていけるようにと心がけています。
青い鳥文庫の読者は小学生が中心ですから、文章は読みやすく、平易な表現で、キャラクターの行動や心情をはっきりと書くこと。
例えば『小説 星降る王国のニナ』のP23で、無理矢理お城に連れてこられたニナが、アリシャの身代わりとしてお姫様の洋服に着替えさせられた姿を、アズールが目にするシーンがあります。
原作では、アズールが「これがあの小汚い小僧」、ニナが「おまえっあのときの灰金目(きんめ)!」と言い合う様子を、1コマで表現していますが、小説では、4行を使って、だれがなにを言ったのか、どんな状況だったのかをていねいに説明しました。
---------
「これがあの小汚い小僧」
まるで本物の姫君……と思ったと同時に、ニナが怒鳴った。
「おまえっあのときの灰金目!」
みごとな変身ぶりと思ったのは一瞬だけで、口を開くと小僧のままだった。
---------
もえぎ 原作漫画を読めばノリでわかるところも、小説ではていねいにわかりやすく。うるさくない程度にキャラクターの心情を入れて、読者に疑問が残らないようにと工夫しています。
しかし小説では、読む側がもっとも視点を合わせやすい人を「主人公」として書く必要が出てきます。その場合「主人公の視点」で物事を描写したり、主人公の心の動きをメインで書くことになりますが、もえぎさんが心情描写で気をつけていることはなんでしょうか。
もえぎ これは本当に悩ましいです! 漫画はだれのセリフでだれの行動か一目でわかりますが、小説は視点がころころ変わると違和感が出ます。基本は「三人称神視点」ですが、なるべくニナに視点を固定して書き、視点がアズールに移るときもできるだけ違和感が出ないようにと何度も推敲し、編集者にもチェックしてもらいました。
また児童書ということで、一番意識している存在があります。