

石川宏千花/著 脇田茜/画
【主な登場人物】
★ 淡島三津(あわしまみつ):この物語の主人公。
★ 江場小巻(えばこまき):三津の大伯母。72歳。御殿之郷を営んでいる。
★ 多岐(たき):船着き場で三津を出迎えた、年齢不詳の男。
【主な地名、名称】
★ 場家之島(ばけのしま):東京から遠く離れた島。
★ 御殿之郷(ごてんのさと):島唯一の旅館。豪華絢爛で、全貌が見えないくらいまで建て増しをしている。
【これまでのおはなし】
父の海外赴任に伴い、淡島三津は大伯母・小巻の元に身を寄せることになった。東京から遠く離れた場家之島へ着くと、黒いスーツの男・多岐が恭しく出迎える。傍らには黒塗りの人力車!? 小巻が営む島唯一の旅館「御殿之郷」の豪華さを前に立ちすくむ三津だが、小巻から掛けられたのは「……ずいぶんと、俗世の垢をつけてもどってきたものですね。鼻が曲がりそう」という言葉だった。
無自覚な初恋
1
世の中に、あんなに冷たく感じる水があるなんて……。
夏だというのにがたがたと震えながら、体に張りついた制服を急いで脱ぎ捨てた三津は、浴場の戸を横に引いた。と同時に、声にはならない声で悲鳴をあげる。
人がいた。しかも三人。大伯母のうしろに控えていた着物姿の女性たちだ。よく見れば、そろってまだ若い。顔も似ている。なぜか袖を白いタスキでしばってたくしあげている。
いきなり自分だけが裸、という状態になった三津は、よく見る悪夢を思い出していた。
あるときは、教室の自分の席。あるときは、校庭のすみ。あるときは、人通りの多い交差点のまん中。場所はさまざまだけど、状況は決まって同じ。自分だけが全裸なのだ。
わたしだけ服を着ていない! そう気がついた瞬間の、血の気が引くあの感じ。どうしよう、まわりの人たちはまだ気づいていない。なにか着るものを手に入れなくちゃ。それまでは気づかないで。わたしだけが裸でいることに、どうかだれも気がつかないで──。
「──ま、三津さま!」
わあっと叫びそうになったくらい、驚いた。気がつけば、女性のひとりがすぐそばにいた。
「お体を清めさせていただきます」
やさしく背中を押された。だだっ広い浴場は無人で、湯煙だけが優雅にたゆたっている。岩場を模したような浴場だった。洗い場はなく、湯煙の奥に湯が張られた場所がうっすらと見えている。岩場と湯船の境目まできたところで、三津はようやく、我に返った。
「あのっ! 自分で洗えます!」
このままでは三人がかりで体を洗われることになってしまう、と思ったら、自然と声が大きくなった。
「小巻さまに、俗世の垢をしっかりと落としてさしあげるようにと命じられております」
「しっかり洗います。一生懸命、ちゃんと洗います! 自分で洗わせてください!」
よほど必死な様子に見えたのか、三人は顔を見合わせると、湯煙の向こうへとさがっていった。足もとに、手桶と白い粉状のものが入った陶製の器が置かれているのに気づく。急いで手桶を手に取ると、頭から湯をかぶった。
いつもの何倍も時間をかけて全身を洗い終えた三津は、おそるおそる湯船に足先を入れた。ほんの少し先までが白くけむっている湯船の中を、そろそろと進んでいく。
どこまで進んでも終わりがない。どれだけ広いお風呂なんだろう、と思っていたら、急に霧が晴れたようになって、目の前が開けた。
そうして三津の目の前にあらわれたのは、はるか眼下の広大な海を見下ろす絶景だった。室内の浴場だとばかり思っていたそこは、岩山の山肌部分からせり出すように設けられた露天の浴場だったのだ。
ひゅおおぉ、と下から風が吹きあげてくる。潮のにおいがした。
「……すごい」
思わず漏らした感嘆の声に、「なにが?」と返事があった。え? と顔を横に向ける。すぐそばに、色白できめの細かい肌質の横顔があった。あご先くらいの長さの髪を、前髪ごとかきあげている。先客がいたらしい。
こんにちは、と頭をさげようとして、ん? となる。わずかではあるものの、違和感があった。こちらを向いた顔を乗せている首の太さや肩幅の広さに。

反射的に深く湯に沈みこんだ三津は、すかさず距離を取った。
「どうして逃げちゃうの?」
離れた分だけ近づいてくる。あまりにも堂々と近づいてくるものだから、自分が勘違いしただけ? と不安になった。
「……あの」
湯から顔を出し、話しかけてみた。
「お泊まりの方ですか?」
間近で見るその顔は、肌の白さといい、やさしげに垂れた目尻といい、あごの小ささといい、女性っぽさの特徴といってしまってもよさそうなものをたっぷりと取りそろえていた。声だって、ちょっと低めではあるけれど、野太かったりはしない。やっぱり勘違いだったんだ、と三津はほっと息をつく。
「泊まってはいないけど、ここの湯にはよく浸かりにきてるよ」
「そうなんですね」
「きみは?」
「あ、わたしはこの旅館の経営者の親戚に当たる者で──」
そこまで説明したところで、目の前にあった色白なその顔が、ふいっと横を向いた。
「……まずい。小巻に気づかれた」
小巻? おばさんのこと? 呼び捨て? と三津がいぶかしんでいると、急に脱衣所のほうが騒がしくなった。
「またね。見覚えがある気のするお嬢さん」
ざばあっと目の前の湯が騒ぐ。立ちあがろうとしているその人の、胸のあたりが目に入った。つるりとなめらかで、ゆるやかなふくらみしか持たない筋肉質な胸板……。
気がついたときには、自分でもびっくりするような悲鳴をあげていた。
2
複数の手で体を支えられたのは覚えている。そのあとの記憶がはっきりしていない。自分の足で歩いたのはたしかだと思うのだけれど。
はっと目が覚めたようになったときには、ソファに腰をおろしていた。広々とした和室の一角に置かれた、ビロード張りのソファだ。楚々とした畳や襖や障子の世界に、深い紅色のビロードが不思議と相性がいい。
顔を横に向ける。多岐がいた。
まっすぐ前を見て、ソファの横に直立している。
「たっ……きさん」
とっさに名前を呼んでしまった。はい、と返事がある。返事をされても、とっさに呼んでしまっただけなので、「あ、いえ……」というしかない。
とりあえず、記憶をたどった。
露天の浴場で悲鳴をあげて、それから何人かの人たちに支えられながら長い廊下を移動してきて、とこれまでのことを順に思い出すうちに、「ふっ」と声が出た。服! と叫びそうになったのを途中で我慢したのだ。胸もとに手をやると、厚めの生地に指先が触れる。裸ではなかった。よかった、裸じゃない、と安堵しかけたところで、ぎくりとなる。
だれが? 自分では、身につけた記憶がない。それでも着衣の状態になっているということは、だれかが着せてくれたということだ。
「ご安心を」
ひそめた声で、多岐が教えてくれた。
「わたくしではなく、あちらの者たちが」
あちらの者たち、といいながら多岐が視線を向けた場所には、浴場にいた三人の女性たちの姿があった。襖を背にして、横ならびに正座している。あの人たちが、と今度こそほっとしたのも束の間、すぐにまた、黒い雨雲のようなものが胸の中に立ちこめてきた。
「あの、お風呂にいた人って……」
男性でしたよね? とつづけようとしたところに、しゅばんっ、といきおいよく襖が開けられる音が聞こえてきた。畳の上をすべるように進んでくる足音が、そのあとにつづく。
「当主が三津をお呼びだ。執務室にくるようにとおっしゃっている」
聞きおぼえのない声に、そろりと視線をあげる。能面のような、というたとえがまっ先に思い浮かぶ顔が、そこにはあった。
つるりと白い肌といい、まぶたの肉が薄い目尻のあがった目といい、一文字に引きむすばれた色素の薄いくちびるといい、能面っぽさを感じない部分を見つけるほうがむずかしいくらいだ。視線がこちらに向けられそうな気配を感じた。あわてて顔を伏せる。
「三津」
名前を呼ばれた。伏せたばかりの顔をあげる。まともに目が合ってしまった。射抜くような視線に、びりびりと皮膚に電流が走る。
「江場哉重だ。きみにとってはいとこに当たる。七年前に一度会っているはずだけど、覚えていないかな」
カエ、という響きは、なんとなく耳にしたことがある気がする。ただし、顔にはさっぱり見覚えがない。
「惚けた顔をしているな。この島にいたときの記憶がないというのは本当らしい」
どうしてそれを? とぎくりとなった三津に、ふ、と哉重が表情をやわらげる。
「お父上に話しただろう? 《御殿之郷》の記憶がない、と」
たしかに話した。この島に身を寄せることが決まったとき、一応、と思って。
「ご心配されたのか、当主にご相談の連絡があったんだ」
それで自分も知っている、ということらしかった。
経緯がわかっても、父親にしか話していなかったことが、いつのまにか大伯母たちにも知られていた、という思いがけない事実へのショックは残る。胸の死角で、ふる、と水ようかんが揺れた。
不意に哉重が、三津の顔にかかっていた髪に触れてくる。
血管の浮いた手首が、白い長袖Tシャツの袖口からのぞいた。細身の黒いパンツを合わせたラフないでたちに、前髪だけを長く残した大人っぽい髪型がよく似合っている。二十歳くらいに見えるけれど、三津には男性の歳がよくわからない。もしかしたら、もっと若いのかもしれない。
「わたしはよく覚えているよ、三津。きみはとてもかわいらしかった」
髪が、やさしく顔からはらわれる。不思議なことに、哉重には触れられても平気だった。いとこだから? 理由は三津にもわからない。もちろん、とささやくようにいって、哉重がその能面のような顔を近づけてくる。
「いまも、とてもかわいらしい」
海を見て育った人だからだろうか。瞳の色が、ほんのわずかに青みがかって見えた。
3
三津には、胸の死角がふたつある。
ひとつには、黒く光った水ようかんが、ぴたりとはまりこんでいる。ふとした拍子にふるふると震えては、忘れられたらどんなに楽になるだろう、と思うあの場面を、決して忘れさせてはくれない。
もうひとつの死角には、なにもない。ぽかんと黒く口を開いているだけの場所だ。ただし、そこはただの入り口で、奥には果てのないブラックホール状のものが広がっている。
どうしてそこにそんなものができてしまったのか、いつできたのかは、三津にもわからない。ぼんやりとわかっているのは、本当はここにも、なにかがぴたりとはまりこんでいたんだろうな、ということだけ。それを自分は忘れている。
訪れたことは覚えているのに、《御殿之郷》の詳細は忘れてしまっていたのと同じだ。なにかがそこにあったことは覚えているのに、それがなにかは思い出せない。
思い出せたらなにかが変わるのだろうか。なんとなく気が晴れないまま日々を過ごしている自分とは、決別できる?
「はあ……」
深いため息が聞こえてきた。畳一枚分はありそうな飴色の執務机をはさんで向かい合っている、大伯母の江場小巻がついたため息だ。
「俗世の垢にまみれたせいもあるのでしょうが、あなたは本当に……」
あなたは本当に? そのつづきを、小巻は口にしなかった。それでも、なにかよくないことをいおうとしたのだということはわかったので、三津はますます萎縮してしまう。小巻の威圧感は、これまで三津が接したことのあるどんな大人のものよりも、ストレートで迫力があった。わかりやすくいえば、とってもこわい。
大伯母の執務室は、長い廊下のつき当たりにあった。襖が開くと、さらにその奥に、飴色の重厚な扉がある。扉は観音開きに開く。すると、そこには大正ロマン風の空間が広がっているのだった。
執務机から少し離れた場所に、向かい合わせに置かれた背もたれの高い椅子。三津はそこに、ただ体を小さくして座っている。歓迎されていないことはわかった。本当にもうよくわかったから、と思いながら、時間が過ぎるのをじっと待っている。
いつのまにか着せられていた服は、ロング丈の紺色のワンピースだった。首が詰まっていて、湯上がりの体には少しだけ苦しい。
「まずは、あなたにこれを」
卓上に、なにかが置かれた。シルバーのネックレスのようだ。複数の星が重ねられたデザインの、小ぶりなヘッドがついている。
「天狗除けです。つけておきなさい」
「てん……」
……ぐ?
教室ほども広さのあるこの執務室にやってきてから、はじめてちゃんと顔をあげた三津に、小巻がするどく視線を投げてくる。
「先ほど浴場であなたにちょっかいをかけてきたでしょう。ああいった輩を寄せつけないための〈呪〉がかけてあります」
取りにきなさい、と目で命じられた。しゅ、ってなんだろう、と考えながら、執務机の前へと急ぐ。
華奢なチェーンといい、ヘッドのデザインといい、ぱっと見は、本命の彼女へのプレゼントのようにしか見えない。天狗除け、という耳慣れない言葉とは、どうにも結びつかなかった。もしかすると、なにかの比喩なのかもしれない。たとえば、刺されると厄介な虫をそう呼ぶとか。悪い虫、のいいかえとしての天狗。それなら意味も通じる。
「特別な材質で作らせてありますから、そのまま入浴してもかまいません。常に身につけておきなさい」
「つけ……あ、はい」
いまつけろ、ということらしい。手に取ったネックレスの金具をはずし、首のうしろに手を回す。見られているせいか、金具がうまくかみ合わない。見かねた小巻が、「手伝っておあげなさい」と扉を背にして控えていた多岐に命じた。
「あっ、いえ! だいじょうぶです」
当然のように三津はそれを辞退した。ネックレスをつける手伝いなんて、店頭の販売員をのぞけば、それなりに親密な相手にしてもらうことだ。多岐さん──というよりは、男の人──に、してもらいたくはなかった。
「もうちょっとで……あ、できました」
多岐が足を踏み出す前に、なんとか装着することができた。そんな三津の様子を見ていた小巻が、またもや遠慮のないため息をつく。
「重症のようね……」
重症というのが、いまの自分の言動の中のなにかをさしていったのだということはわかったけれど、どこがどう病気っぽかったのかは、三津にはわからなかった。
唐突に、問いかけられる。
「本当に、島での記憶がないのですね?」
はい、と答える途中で、もうけっこう、というように小巻が片手をあげる。
「わかりました。簡潔に説明します。一度しかいいませんから、しっかりと頭にお入れなさい。七年前、あなたはこの場家之島を訪れた際に、無自覚な《寄託》をしています。いまのあなたに深刻な問題が生じているのは、その影響です」
深刻な問題──それは、ついさっきいわれた、重症、と関係があるのだろうか。自分はなにか、病気のようなものにかかってしまっているということ?
「滞在時の記憶がないということですから、これも覚えていないのでしょうが、あなたはこの島で初恋を経験しているはずなのです。一刻も早くその相手を思い出し、しかるべき対処をしなければなりません」
……はつこい? おばさんはいま、初恋といった?
困惑する三津にはおかまいなしに、小巻は一方的に話を打ち切ってしまう。
「明日、《咫尺》のご機会をいただいてあります。初恋の相手をさがすお手伝いをしていただけるようお願いしました。失礼のないようにお会いしてきなさい」
しせき、がなにか、これまたよくわからなかったけれど、だれか目上の人に会いにいくのだな、ということだけは理解できた。
4
三津に与えられた住まいは、《御殿之郷》からは少し離れた場所にあるのだという。多岐の案内で、向かうことになった。
岩肌に張りついている、赤く塗られた空中階段を前後してのぼっていく。気になっていたことをたずねてみた。
「天狗、と大伯母はいってましたけど、あれって害虫かなにかの比喩ですよね?」
初恋も気になってはいたものの、まずはこれだ。多岐は即座に、「いえ」と否定した。
「天狗は天狗です。おそらく、三津さまもご存知の、くちびるの代わりにくちばしを持ち、肩甲骨の代わりに巨大な翼を持つ、あの天狗でまちがいございません」
「……浴場でわたしが顔を合わせた方のことを、おばさんは天狗といったようですけど」
「ええ、あれもまた、天狗です。ただし、ただの天狗ではございません。大天狗です」
ただの天狗と、大天狗とのちがいがわからない。なにより、ごく当たり前のように天狗が実在するものとして話が進んでいることに、三津の頭はまだ追いついていなかった。
「くちばし……は、ついていなかったように思うのですが」
「人の姿に化けていたのでしょう」
「化けられるのですか?」
「大天狗ですから」
多岐は、きけばなんでも教えてくれる。それなのに、一向にわかった気にならないのはどうしてなのだろう。
「あちらが三津さまのお住まいになります」
階段をのぼりきったところで多岐がさし示したのは、まるで灯台のような、洋風の白い建物だった。灯台のような、と三津が思ったのは、建物の形が円筒状だったことと、建っている場所が、海にせり出しながら拓けた場所だったからだ。眼下の海をいき交う船を見守っているように見えた。だから、灯台。
「一階にリビングダイニング、浴室、手洗い所がございます。寝室を兼ねたプライベートスペースは、お二階に」
建物の内部の説明をしながら、外壁と同じく白く塗られた扉を多岐が開く。
外観から想像したよりも、ずっと広々とした空間がそこにはあった。床と天井は板張りで、白いペンキで塗られている。二方向にある窓の木枠も白一色だ。海側に面した窓は、開ければそのまま外に出られる大きなもので、夕暮れどきだというのに室内がまだ明るい。
そちらの窓際には、ソファセット、テレビ、背の低い棚といった、どの家のリビングにもありそうなものが配置され、シンプルなキッチンは、つき当たりの窓の下に設えられている。右手の壁には扉がふたつ、その奥に、高い天井に向かって伸びる螺旋階段があった。
「扉はそれぞれ浴室と手洗い所のものになります。お二階へは、そちらの螺旋階段をお使いください」
きょろきょろと室内を見回していた三津は、ふと気になってたずねた。
「ここには、わたしひとりで?」
「そのようにご用意させていただきました」
こんな広い家に、たったひとり。しかも、大伯母をはじめ、たくさんの人がいる《御殿之郷》からは離れた場所に、ぽつんと一軒だけの家──。
日が沈んだあとの、大きな窓が真っ黒に塗りつぶされた様子を想像して、三津はひそかに背筋を震わせた。
(第3回へ続きます。4月1日ごろ更新です)
第1話はこちら
石川宏千花さんの新連載記念『YA作家になりたい人のための文章講座~十四歳のための小説を書いているわたしがお話しできる5つのこと~』はこちら!
(毎月1日、15日更新します)












![「卒園おめでとう」を伝える絵本3選! 門出を祝うプレゼントにぴったりな名作[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/879/large/fe3c9db7-2339-4abc-a2cd-c276cc46fa59.jpg?1772501924)






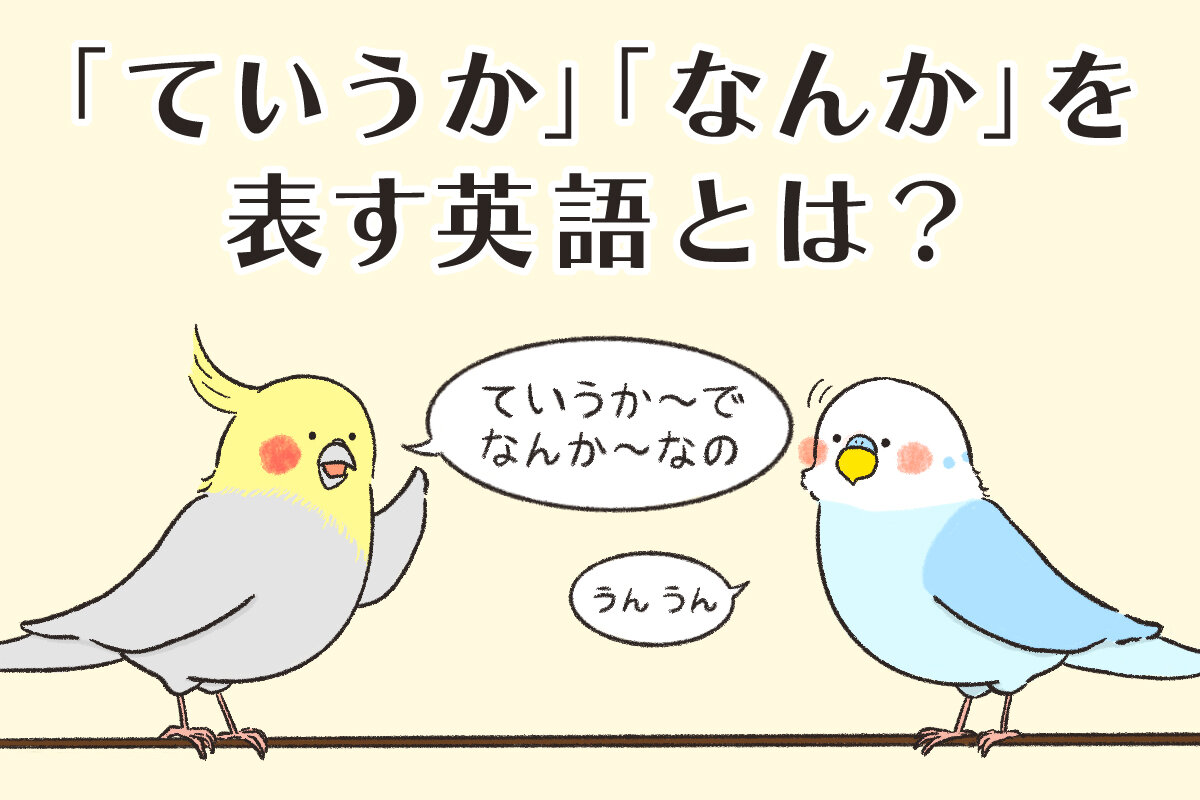



























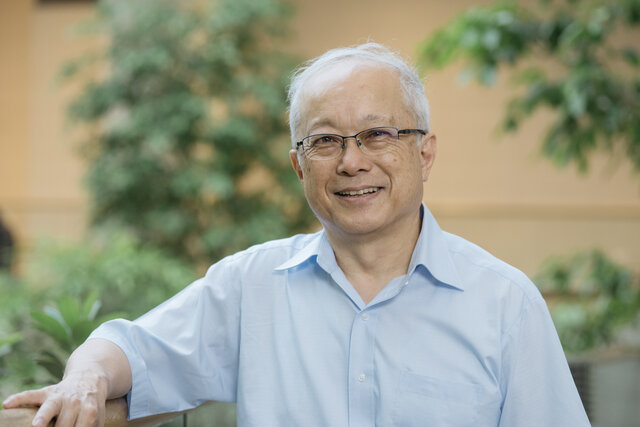


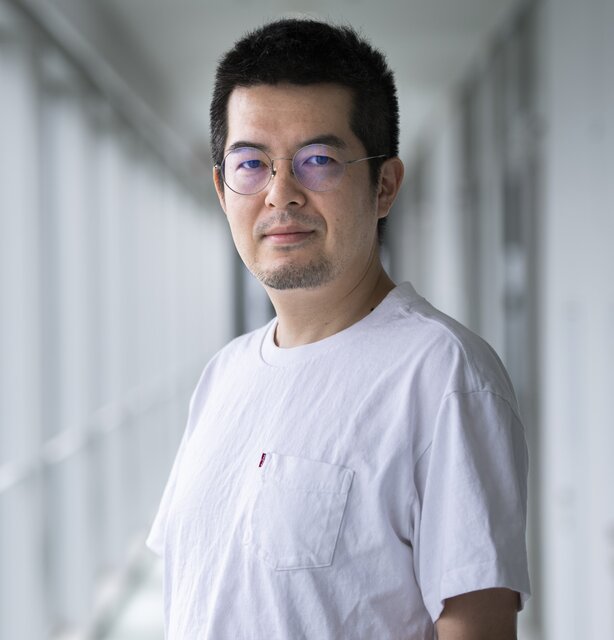






























































石川 宏千花
『ユリエルとグレン』で、第48回講談社児童文学新人賞佳作、日本児童文学者協会新人賞受賞。主な作品に『お面屋たまよし1~5』『死神うどんカフェ1号店』『メイド イン 十四歳』(以上、講談社)、『墓守りのレオ』(小学館)などがある。『少年Nの長い長い旅』(YA! ENTERTAINMENT)と『少年Nのいない世界』(講談社タイガ)を同時刊行して話題となった。『拝啓パンクスノットデッドさま』(くもん出版)で、日本児童文学者協会賞を受賞。
『ユリエルとグレン』で、第48回講談社児童文学新人賞佳作、日本児童文学者協会新人賞受賞。主な作品に『お面屋たまよし1~5』『死神うどんカフェ1号店』『メイド イン 十四歳』(以上、講談社)、『墓守りのレオ』(小学館)などがある。『少年Nの長い長い旅』(YA! ENTERTAINMENT)と『少年Nのいない世界』(講談社タイガ)を同時刊行して話題となった。『拝啓パンクスノットデッドさま』(くもん出版)で、日本児童文学者協会賞を受賞。