![「卒園おめでとう」を伝える絵本3選! 門出を祝うプレゼントにぴったりな名作[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/879/large/fe3c9db7-2339-4abc-a2cd-c276cc46fa59.jpg?1772501924)

【新連載】『化け之島初恋さがし三つ巴』石川宏千花
第1話
2022.03.01

石川宏千花/著 脇田茜/画
【主な登場人物】
★ 淡島三津(あわしまみつ):この物語の主人公
★ 江場小巻(えばこまき)
★ 多岐(たき)
【主な地名、名称】
★ 場家之島(ばけのしま)
★ 御殿之郷(ごてんのさと)
ふたりが見つめているのは、眼下の海だ。
欠けはじめの月が、真っ黒な海面に映っている。たゆたうように揺れている。風は吹かず、樹々も騒がず、静かな夜がただ更けていく。
突き出た崖の先端に、ふたりはならんで立っている。ひとりは、長い黒髪を背中でひとつに束ねた少女で、淡い藤色の着物に浅葱の帯をきゅっとしめている。もうひとりは、墨一色の着流し姿の青年だ。少女よりも、頭ふたつ分は背が高い。
長い沈黙を経て、少女が口を開いた。
「わたしの前にあるのは、台だけ水に浸かった天秤だ。一方を選べば、一方は水に沈む。この島の人々を、沈めるわけにはいかない」
「オレは……沈んでもいいと?」
「おまえは飛べるじゃないか。どこにだって飛んでいける。わたしはちがう。この島の人々もちがう。飛んでどこかに逃げ出すことはできない」
「おまえのためなら、翼など捨てても──」
いいかけていたその先を、少女の手のひらがやさしくおおってさえぎった。
「いうな。いわないでくれ」
青年の口もとをおおった自分の手の甲に、少女はそっとくちびるを寄せた。
「さあ、いけ」
すばやく体を離すと、少女はふたたび、眼下の海に向き直った。
ばさっ、と翼が開く音がする。月光に照らされていた少女の横顔が、暗くかげった。真っ黒な翼をひるがえして、青年が空の彼方に消えていく。
月だけが、ふたりの別れを見ていた。
胸の死角で震えているもの
1
──いわなければよかった。
後悔は、黒く光った水ようかんのようだ。胸の死角にぴたりとはまりこんでふるふると震えながら、いつまでたっても消えてなくならない。
『お父さん、あのね』
だめ! そんなこと教えちゃだめ。
『お母さんね、本当はあのとき……』
ほら、お父さんの顔色が変わった。
頭の中では、だめ、いっちゃだめ、とくり返し叫んでいるのに、なぜだかくちびるは勝手に動いてしまう。
『──……──』
がくん、と体が大きく揺れた。
見開いた淡島三津の目に、まっ青な海が飛びこんでくる。海だ……と、声には出さずに胸の中だけでつぶやいて、三津は上半身を車窓に向けた。新品の夏の日差しを浴びて、海全体がぎらぎらと輝いている。
東京生まれ東京育ちの三津には、いまだに海は、異界が領有するものにしか思えない。畏怖と憧れ。その両方に胸が震えてしまう。
覚悟はしていたものの、長い道のりだった。メトロ、京浜急行、飛行機、タクシー、一車両だけのローカル線、と乗りついできたうえに、この列車をおりたあとにもまだ、乗らなければならないものがある。船だ。一日に二便だけ出ているという連絡船で海をわたって、ようやく目的地にたどりつくことができる。
なにを着ていこうかと迷った末に、制服を選んだのは失敗だった。長時間、複数の座席と三津の体とのあいだでプレスされつづけたプリーツのひだが、アイロンしたての状態を保っているはずがない。みっともなく広がってしまっているにちがいなかった。
もう着ることのない制服だから、と名残惜しく思って選んだわけではない。そもそも、ブレザータイプのありふれた紺の制服で、愛着の持ちようもなかった。ただ、あらたまった服装といえば制服だという思いこみが、三津にあっただけだ。
予定どおりの時刻に、車両はホームにすべりこんだ。
着々と三津は運ばれていく。これまでとはまるでちがった環境が待つ日々へと。

2
「十五時四十五分発、場家之島ゆき、乗船予定の方はお急ぎくださーい」
白い小型フェリーを背にした作業服のおじさんが、くり返し乗船を呼びかけていた。
コンクリートのしっかりとした地面であっても、海面がすぐそこだと歩くのがちょっとだけこわい。風も少し強かった。
東京を離れる前に、ふと思い立って三津は髪を切っている。胸まで届く長さだった髪をあご先くらいの長さにし、同じだけ長かった前髪も眉の位置で切りそろえ、ショートボブと呼ばれる髪型にした。風に吹かれた前髪がおでこをくすぐるのに、まだ慣れていない。
「すみません、乗ります」
三津がそう声をかけると、作業服のおじさんは、にっこり笑って答えた。
「やあ、これはどうも。東京からおいでんさった淡島さんですな」
日焼けのしすぎなのか、ぎょっとするほど赤黒い顔をしている。
はい、そうです、と答えながら、あれ? と三津は思った。事前に乗船の予約はしていない。どうして顔を見ただけで、〈東京からきた淡島さん〉だとわかったのだろう。
顔に出ていたのかもしれない。おじさんのほうから説明してくれた。
「小巻さまからご連絡をいただいとります」
「小巻おばさんから……そうですか」
三津を船に乗せると、作業服のおじさんは小さく頭をさげて離れていった。軽くほほ笑んでから、頭をさげ返す。あ、と思った。きょう、はじめて笑ったかもしれない、と。
自宅を離れるのがいやだったわけではない。入学して間もない都内の女子校から転校するのがつらかったわけでもない。三津はもう長いあいだ、なんとなく気が晴れない、という状態のまま日々を過ごしている。ひとりでいるときには、笑う必要がない。だから、笑っていなかった。それだけのことだった。
「十五時四十五分発の場家之島ゆき、もうじき出航いたしまーす。お急ぎくださーい」
呼びこみをつづけながら、作業服のおじさんが船尾のほうに回りこんでいく。出航の準備をはじめるようだ。
当座の生活必需品と着替えだけをつめこんだ布製の旅行バッグを足もとに置いて、簡素なオレンジ色の座席に腰をおろす。
自然と顔が横を向いた。海原だけが、視界のすべてになる。たぷたぷと揺れている波を見つめたまま、おぼろな記憶をさぐりはじめる。
見つけたいのは和装の女性だ。うまくさがせない。着物を着ていた、という以上の情報が、さっぱりよみがえってこなかった。
江場小巻。三津にとっては大伯母に当たる人だ。
母方の祖母の、歳が離れたお姉さんで、今年で七十二歳になると聞いている。小学四年生のときに一度会ったきりで、以来、電話で話したことすらない〈遠縁のおばさん〉だ。大おばさんと呼ぶのが正しいのだけど、両親が小巻おばさんもしくはおばさんと呼んでいたので、三津にとっても小巻おばさん、おばさんが定着している。
そんな遠い親戚のもとに身を寄せることになったのは、粘菌の研究者である父親に、急な海外赴任が決まったからだった。ストックホルムにある研究所と、新たな粘菌の共同研究をすることになったらしい。少なくとも滞在期間は二年におよぶということで、父親が大伯母に相談した結果、あっさりと三津の場家之島ゆきは決まった。
一度だけ、『三津はどうしたい?』ときかれたけれど、『お父さんのしたいようにしていいよ』と答えただけだったので、その決定に三津の意思は反映されていない。
船が動き出した。白い波しぶきが、見る間に船のまわりを包みこんでいく。
これから少なくとも二年は、生まれ育った東京から遠く離れた離島──場家之島で暮らしていかなければならない。憂鬱といえば憂鬱な気もするし、見ている窓の眺めが変わるだけだから、と気楽に考えているような気もする。
いまはただ、圧倒されている。異界への入り口のような、底抜けの海の青さに。

3
島の玄関口に当たる船着き場が、ゆっくりと近づいてきた。
あれは……と三津は小さく首をかしげる。あれはたぶん、人力車だ。ぽつんと一台、岸に停まっている。黒光りする人力車のすぐ横には、法被姿の車夫らしき人もいた。
岸には、もうひとり。喪中のような黒いスーツを着た男性だ。
大伯母からは、宿の者が迎えにいく、とだけ事前に伝えられていた。人力車は観光客のためのサービスだろうから、スーツ姿の男性のほうが、自分を迎えにきた人なんだろうな、と見当をつける。
宿の者、というのは、宿泊先の従業員、という意味ではない。大伯母は、場家之島で一軒きりの旅館を営んでいる。スーツ姿の男性は、おそらく大伯母の宿で働いている人だ。
船に同乗していたのは、年配の男女が一組と、三津と同年代らしき制服姿の男の子だけだった。いずれも軽装で、荷物もそれほど大きくはなかったけれど、その中のだれかが観光客なのだろう。
ボストン型の旅行バッグを手にさげて、場家之島におり立つ。あとからおりてきた三人が、三津を追い抜いていった。だれも人力車のほうには足を向けない。あれっ、と思う。じゃあ、あの人力車は? と。
追い抜きざまに、制服姿の男の子が視線を向けてきた。とっさに三津は、顔をうつむかせる。すんでのところで目は合わせずにすんだ。ほっと息をつく。むかしから三津は男の子が苦手で、仲のいい女の子のうしろにかくれてばかりいた。いまだに目が合うのもこわい。
立ち止まったままでいた三津に、スーツ姿の男性のほうから歩み寄ってきてくれた。若いのか若くないのか、よくわからない風貌だ。四十四歳の父親と同じくらいの歳にも見えるし、大人っぽい二十代の若者にも見えた。
髪型は、いまどきあまり目にしない、艶のあるオールバック──よくいえば花婿さん風、悪くいえば映画やドラマで描かれるその筋の人風の──だ。背中に棒がさしてあるんじゃないかと思うくらい、姿勢がいい。
「お待ちしておりました。お世話させていただく多岐と申します。お荷物をおあずかりいたします」
多岐と名乗ったその人は、長い腕を伸ばして三津の旅行バッグを受け取ろうとした。
「あっ、いえ、自分で持ちます」
あずけるのがいやだったわけではなく、単に遠慮しただけだったのに、たいへんな失礼を働いたかのように、多岐はさっと手を引いた。さらには、「ご無礼を申しました」と頭までさげる。理由を説明したかったけれど、多岐はもう三津には背中を向けてしまっていた。行動に無駄がない。きびきびしている。
「あちらをお使いくださいませ」
そういって多岐が、黒光りする人力車を開いた手のひらでさし示した。自分のための人力車だったことに、三津は驚く。この島での移動は人力車? ふつうの車ではなく?
小学三年生のときにはじめて訪れた場家之島には、三日ほど滞在しているはずだ。そのときにも乗ったのだろうか。印象的な乗りものなのに、まるで記憶になかった。
やはり、特別な乗りものなのではないだろうか。だとしたら、この人力車も、多岐のかしこまった態度も、過剰な気がする。もしかすると大伯母の親戚だということが知らされていないのでは、と心配になってきた。一般の宿泊客としてもてなされているのだとしたら、誤解を解いておかなければならない。
「あの、多岐さん」
肩越しに顔をうしろに向けて、はい、と多岐が応じる。ふるまいと同じく、無駄な贅肉のついていない、すっきりとした横顔だった。
「わたし、お客さんじゃないんです。江場小巻の親戚で……」
「存じておりますが」
「存じ……ああ、そうなんですね」
だったらよかった、と思いかけて、大伯母の身内だと知っていてこの歓待ぶりなのか、とあらためて違和感を持った。自分が知らされていないだけで、大伯母はこの島ではちょっとした有力者だったりするのだろうか。
そういえば、と思い出す。小型フェリーのおじさんも、小巻さま、と〈さま〉をつけていた。だとしても、だ。だとしても、制服姿の十五歳の未成年者に、この分不相応なあつかいは居心地が悪すぎる。
「でしたら、どうぞお気遣いなく」
とりあえず、そう伝えてみた。
多岐は、浅くうなずくような仕草を見せてから、正面に向き直った。わかってもらえたようだ、と思い、ほっとする。ところが、
「よろしければ」
人力車の前まできたところで、多岐はなんの迷いもなく、地面に片ひざをついた。まるで外国人がプロポーズするときのような体勢になりながら、三津に向かって右側の肩をさし出している。肩を支えにして、あがってください、ということらしい。
ちっともわかってない!
内心で悲鳴をあげながら、三津はきっぱりと首を横にふった。そんな高貴な人にするようなことを自分にしないでください、というつもりでそうしたのだけれど、またしても多岐は、失態を恥じ入るかのようにきびきびと身を起こして、「ご無礼でなければ、こちらにおつかまりください」と直角に曲げた腕をさし出してきた。
これ以上、誤解はされたくなかった。その一心で、さし出された腕につかまる。よくわからないけれど、多岐にとっては腕をさし出すほうがなれなれしい行為になるようだった。
どうしてわざわざ身分の差があるような態度で接するのか。腑に落ちない思いを抱えながらも、三津は人力車に乗りこんだ。法被姿の車夫の男性が、かがめていた腰を身軽にあげる。ふわっと体が浮きあがる感覚に、思わず悲鳴をあげそうになった。
「《御殿之郷》にて、迎えの者たちがお待ちしておりますので」
そういって一礼した多岐は、この場に残るようだった。走って追いかけてこられてもこわいので、ちょっとほっとしてしまう。
腰を折ったままの多岐に見送られながら、三津を乗せた人力車は軽快に走り出した。
4
その道のりのほとんどがのぼり坂だったことから、三津は何度も、「あとは自分で歩いていけますから!」と叫びそうになった。
申し訳なく思う気持ちと戦いつづけた結果、頭の中だけがくたくたになった状態で、大伯母の営む老舗旅館、《御殿之郷》の正面玄関前に停まった人力車から三津はおりた。
「本当に、ありがとうございました」
せめてしっかりお礼を、と深く頭をさげた三津に向かって、車夫の男性は、ひええっと叫ばんばかりに、ぶんぶんと首を横にふった。
「やめてくだせえ。江場のお嬢さんにそんなことをされちゃこまりますぜ」
お礼も迷惑になるなんて、と三津がなかば呆然としているあいだに、車夫の男性は人力車を引いてさっさと去っていった。
「三津」
しゃんっ、と鳴る神具の鈴のようによく響く声が、するどく三津を呼んだ。
はっ、と体が揺れる。三津はあわてて、背中を向けたままになっていた旅館の玄関をふり返った。とたんに、凍りついたように動けなくなる。そこにあったのが、予想していたのとはまったく別ものの光景だったからだ。
一度だけ訪れたことのある《御殿之郷》を、どういうわけか三津は、きれいさっぱり忘れてしまっていた。いくら思い出そうとしても、記憶のどこにも《御殿之郷》の眺めが残っていなかったのだ。しかたがないので、離島のさびれた小旅館の風情をぼんやりと想像していた。
まっ先に目を奪われたのは、日光東照宮を思わせる豪華絢爛な玄関口だ。
瓦葺きの大屋根の下には、おびただしい数の極彩色の彫刻が飾りつけられている。開けはなたれた巨大な扉の奥には、ロビーに当たる部分がつらなっているようなのだけど、玄関口からではその全貌が見渡せないほど広大な空間のようだった。つきあたりの壁も天井も、まったく視界に入ってこない。
ここまでの眺めだけでもう、三津は完全に気圧されていたのだけれど、そろりと視線をあげて旅館全体の輪郭を目にしたところで、さらに息をのむこととなった。
荘厳な雰囲気を持つ白壁の建物が、建て増しに建て増しを重ねたような形で、ごつごつとした岩山に張りついている。ところどころに原色が見えていた。建物と建物をつなぐ渡り廊下の柱や欄干、屋根の下に飾られた彫刻の色のようだ。
どれだけ視線を上に動かしてみても、建て増しがつづいているように見える。一瞬、なにを目にしているのか理解できなかったくらい、それは奇怪な眺めだった。
これが……《御殿之郷》?
文字どおり狐につままれたような顔をして、三津は困惑していた。こんな光景を目にしていたのなら、忘れるはずがない。それなのに、いくら思い出そうとしても思い出せなかったなんて。
「いつまでそうして惚けたままでいる気なのですか、三津」
ふたたび名前を呼ばれて、今度こそ、はっきりと夢から覚めたようになる。「はいっ」と返事をして、声のしたほうに顔を向けた。
白銀の生地に金の菊を散らした豪奢な着物をまとった痩身に、豊かな白髪──白いというよりは銀に近い──をエイリアンの後頭部のような形に結いあげた女性が、まっすぐに三津を見ている。大伯母の、江場小巻だった。
仲居さんらしき着物姿の女性を三人、背後に従えている。欲しくもない贈答品を無理やり送りつけられたような顔をして、大伯母は三津を見つめていた。
「……ずいぶんと、俗世の垢をつけてもどってきたものですね。鼻が曲がりそう」
え? と息がとまった。『俗世の垢』『鼻が曲がりそう』という強い言葉に、たぶん、ショックを受けたのだ。そんな三津から目をそらすようにしながら、背後の女性たちに向かって、「清めの水を!」と大伯母は命じた。
女性たちのひとりが、手に木の桶のようなものを持って、するりと動く。直後、三津は大量の冷水を頭から浴びせられていた。
※
びしょ濡れになった三津を、たっぷりと枝葉を茂らせた木の陰から、こっそりと盗み見ている者たちがいた。
「きたね、江場のお嬢さん」
「きたね、きたきた」
「歴代の《江場家の娘》の面影が、ちょっとずつあるんじゃないか」
午後の木陰は、夜でもないのに暗い。その暗がりに完全に同化しながら、ぎゅっと寄り集まって話しこんでいる。子どものような声もあれば、しわがれた老人のような声も混ざっている。
「とはいえ、なんだかたよりなさそうなお嬢さんだ」
「だから、《寄託》なんてやっかいなもんに引っかかるのさ」
「いやいや、血さ。江場の家の血」
暗がりに溶けていくように、声は次第に小さくなっていき、やがて木陰は、ただの木陰にもどった。
(第2回へ続きます。3月15日ごろ更新です)
石川宏千花さんの新連載記念『YA作家になりたい人のための文章講座~十四歳のための小説を書いているわたしがお話しできる5つのこと~』はこちら!
(毎月1日、15日更新します)


















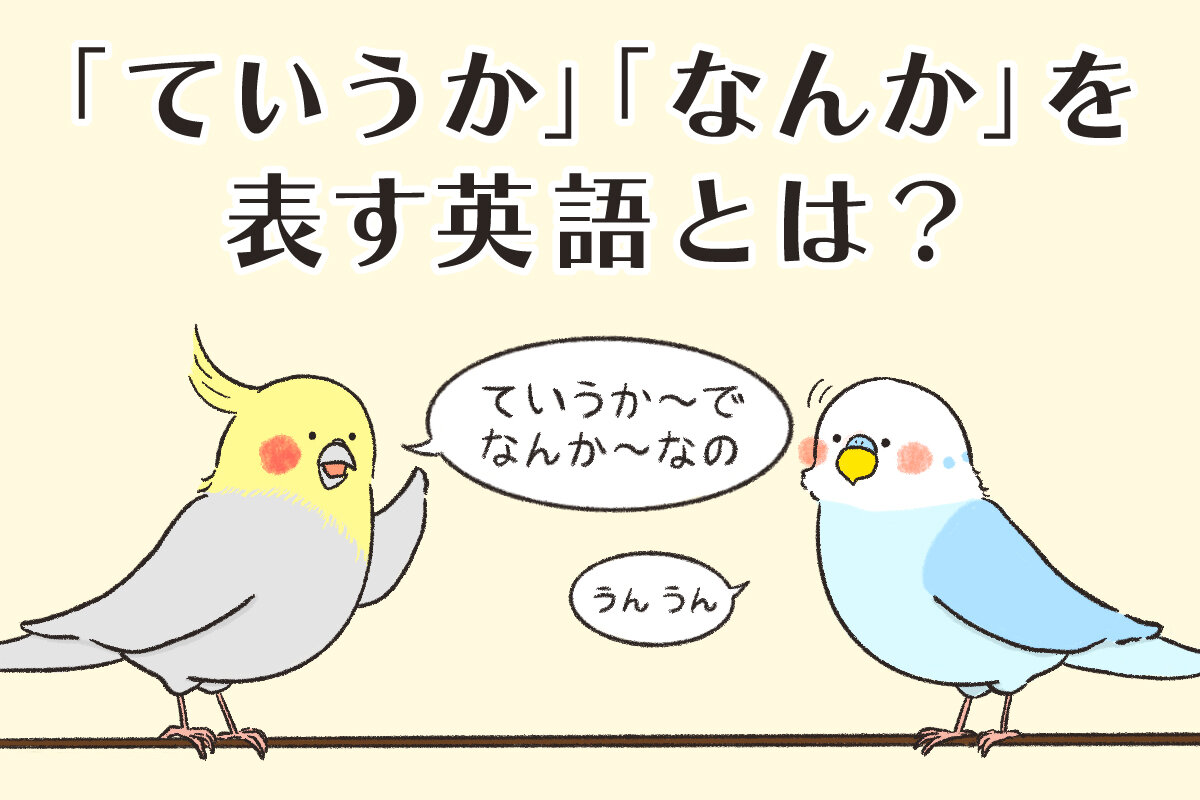



























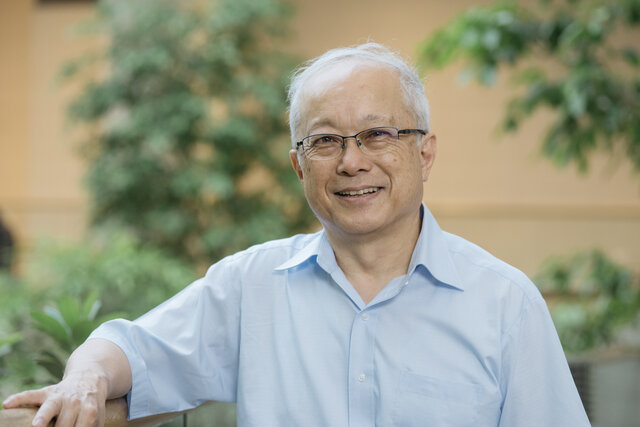


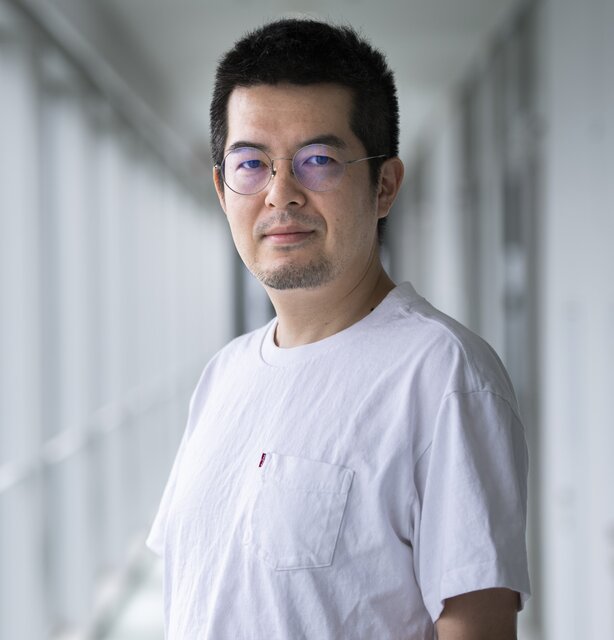






























































石川 宏千花
『ユリエルとグレン』で、第48回講談社児童文学新人賞佳作、日本児童文学者協会新人賞受賞。主な作品に『お面屋たまよし1~5』『死神うどんカフェ1号店』『メイド イン 十四歳』(以上、講談社)、『墓守りのレオ』(小学館)などがある。『少年Nの長い長い旅』(YA! ENTERTAINMENT)と『少年Nのいない世界』(講談社タイガ)を同時刊行して話題となった。『拝啓パンクスノットデッドさま』(くもん出版)で、日本児童文学者協会賞を受賞。
『ユリエルとグレン』で、第48回講談社児童文学新人賞佳作、日本児童文学者協会新人賞受賞。主な作品に『お面屋たまよし1~5』『死神うどんカフェ1号店』『メイド イン 十四歳』(以上、講談社)、『墓守りのレオ』(小学館)などがある。『少年Nの長い長い旅』(YA! ENTERTAINMENT)と『少年Nのいない世界』(講談社タイガ)を同時刊行して話題となった。『拝啓パンクスノットデッドさま』(くもん出版)で、日本児童文学者協会賞を受賞。