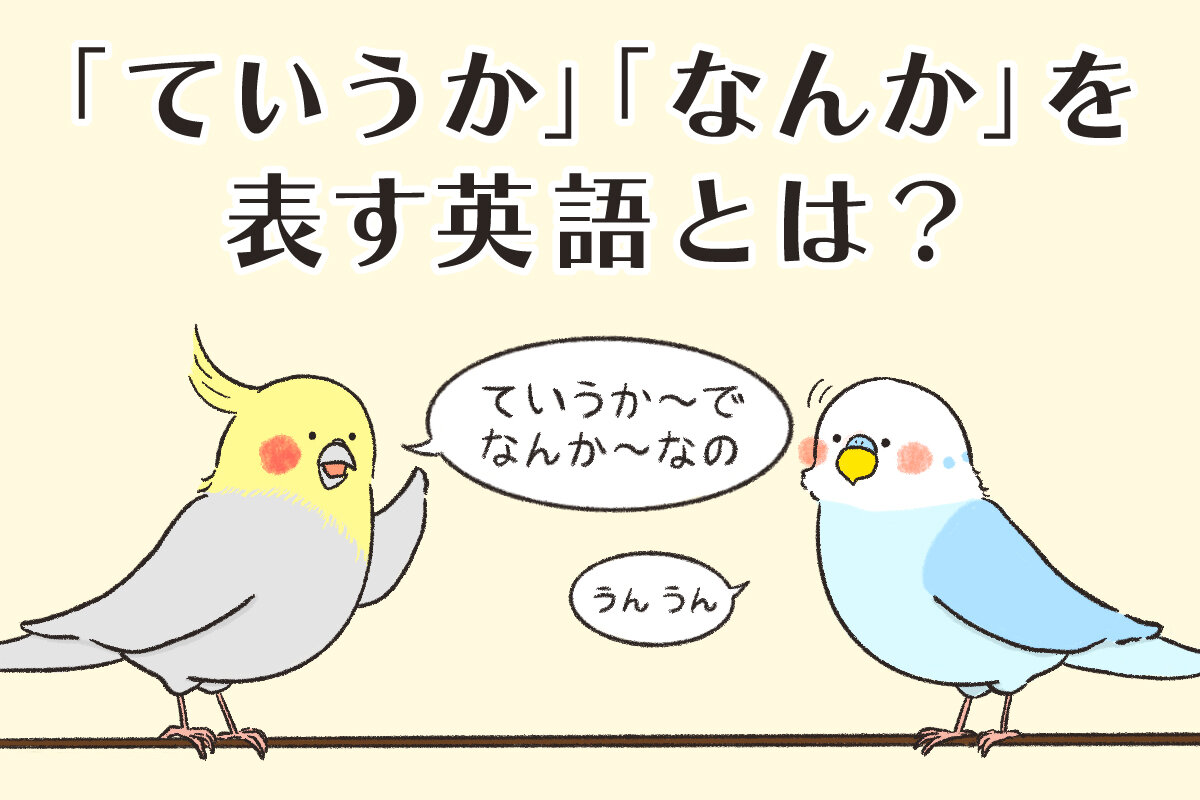

石川宏千花/著 脇田茜/画
【主な登場人物】
★ 淡島三津(あわしまみつ):この物語の主人公。15歳。
★ 江場小巻(えばこまき):三津の大伯母。72歳。御殿之郷を営んでいる。
★ 多岐(たき):三津の身の回りの世話をする、年齢不詳の男。
★ 遠雷(えんらい):大天狗。
★ 江場哉重(えばかえ):三津のいとこ。
★ 憧吾(どうご):三津が行くことになる高校に通っている。
★ たすく:つくもの会のひとり。基本は信楽焼のたぬき。
【主な地名、名称】
★ 場家之島(ばけのしま):東京から遠く離れた島。
★ 御殿之郷(ごてんのさと):島唯一の旅館。豪華絢爛で、全貌が見えないくらいまで建て増しをしている。
【これまでのおはなし】
父の海外赴任に伴い、淡島三津は遠く離れた場家之島で暮らすことになった。七年前に訪れてたはずなのだが、何一つ記憶にない。さらにその際、三津が無自覚な初恋をしており、一刻も早くその相手を探さねばならぬと聞かされる。一人あてがわれた部屋に、続々現れる妖しいものたち。「すきだらけなやつは、すぐに自我を奪われる」と注意されるが……。
失われた七年前の記憶
1
人力車は、《御殿之郷》がある小高い山の周囲をぐるりと半周し、やがて、ゆるやかな坂道をのぼりはじめた。
山道ではあるものの、きちんと舗装されている。カーブを描きながら人力車は山をのぼっていき、がらんとした展望スペースのような場所に入ったところで停車した。
「お疲れさまでございました」
「あっ、はい、ありがとうございました」
人力車から、そろりとおりる。見渡す限り、なにもない。ここまでのぼってきた山道と、海とのあいだにある街並みが、ただ眼下に見下ろせるだけだ。
軽い会釈をして車夫の男性が去っていくと、三津はぽつんとひとり、残された。あとからくるといっていた多岐の姿も、なかなかあらわれない。
突然、ふっくらと炊きあがったお米のにおいがしてきた。と同時に、
「お待ちしておりました。どうぞこちらへ」
声だけが、どこからか聞こえてくる。あたりを見回してみても、どこにもだれもいない。
「さあさあ、どうぞ」
声の聞こえる位置が移動した。ああ、聞こえなくなっちゃう、と足を前に進める。
「そうそう、こちらです、どうぞどうぞ」
声につれられて、三津はどんどん進んだ。景色は変わらない。なにもない場所のままだ。代わりに、もやが出てきた。あんなに晴れていたのに、見る間にあたりが白くなっていく。
それにしても、ずいぶん長く歩いているような気がする。そんなに広い場所だっただろうか。一向に山道にもどらないのが不思議でしょうがない。
気がつくと、声が聞こえなくなっていた。お米を炊いたにおいも消えている。戸惑いながら、まっ白になった視界に手を泳がせてみた。指先が、かたいなにかに触れる。きぃ、と木製の扉が開く音。ほうきで掃いたように目の前のもやが晴れる。そのときには三津はもう、別天地に立っていた。
どこまでも広がる緑の大地に、ところどころかたまって樹木が茂っている。実っているのは桃らしい。甘いにおいがかすかに漂ってもいる。
青く高い空。目を閉じたくなるようなそよ風。なんだろう、確かに心地のよさを感じているはずなのに、全身の皮膚がざわざわしているような感覚もある……。
人力車をおりたのが、遠いむかしのことのように思えてきた。ここからどちらに向かえばいいのか、さっぱりわからない。あたりを見回しているうちに、まばらに生えた桃の木の群れの向こうに、ちらりと赤が見えた。向かう途中で、橋だ、と気づく。水の流れが止まっているように見える不思議な川を、アーチ型のまっ赤な橋がまたいでいた。
ほとりでしばらく多岐を待ってみたけれど、こない。しかたがない、先にいこう、と橋を渡る。渡った先には、京都のお寺にありそうな日本庭園があった。白い砂が敷き詰められた上に、風情のある岩や灯籠、松の木なんかが見栄えよく配置されている。すでに屋敷の敷地内に入った……のだろうか。
三津が立ちすくんでいると、「ようこそおいでくださいました」と背後から声がかかった。ふり返っても、だれもいない。
また声だけ? と戸惑っていると、足もとの砂がうぞうぞとうごめいて、人の形を取りはじめた。見る間にそれは、三津よりも頭ひとつ分ほど背の低い、お雛さまのような着物を着た若い女性の姿になる。人の肌の質感を持つふっくらとしたほおに、ほのかな桃色を浮かべて、にこり、と女性はほほ笑んだ。
2
「そうですか……まったくご記憶がないのですね、七年前、この島を訪れた際の」
「そうなんです。《御殿之郷》のこともさっぱり覚えていなくて」
出されたお茶のおかわりを、三津は一気に飲み干した。女性にこれまでのことを話していたら、のどがからからになっていたのだ。
通されたのは、戦国時代が舞台のドラマや映画で見るような板張りの広大な大広間で、そのほぼ中央に、三津と女性は向かい合って座っていた。屋内に人の気配はない。お茶も、女性が運んできてくれた。
ふう、とふんわりやさしいため息が出る。
ふたりきりでいることに、ふにゃふにゃになりそうなくらいの安堵感があった。ずっとこうしていたいな、と思う。どこにもいかずに、いつまでもこの人とこうして──と、ここで三津は、はっ、と目が覚めたようになり、正座の腰を浮かしかけた。
「えっ? わたし、いつのまに?」
庭から建物の中に移動した記憶がなかった。気がついたらこの板張りの大広間にいて、砂から人間になった謎の女性を相手に、べらべらと身の上話をしていたのだ。
「おや、意外と〈化かされ〉から醒めるのがお早い」
口もとを着物のそでで隠しながら笑う目の前の女性に、三津はもう安堵どころか、落ち着いて向き合っていられる平常心すら持っていない。『この人、砂だったよね?』という警戒だけが、皮膚の上で騒いでいる。いったいこの中世のお姫さまみたいな人は……と思いかけたところで、「あ」と声が出た。
「もしかして、長壁姫……さまですか?」
「いいえ」
「いいえ……えっ、いいえ、なんですか?」
「わたくしはただの砂。ほら、このとおり」
たったいままで、中世のお姫さま然としてそこにいた女性が、一瞬でその輪郭をなくし、雪崩落ちていく砂になった。板張りの床の上に、こんもりと砂の山ができる。驚きすぎて悲鳴も出ない。
「わたくしが、長壁姫にございます」
気がつけば、右側のすぐ横に、別の女性が座っていた。顔をそちらに向けた途端、射るような視線に体がかちんとかたくなる。
見た目は、砂にもどったあの女性とそっくり同じだ。ふっくらとしたほおが特徴的な顔なのに、太っているわけではない。やさしげな目もとなのに、視線はするどい。なにひとつ、さっきまで目の前にいた女性とのちがいは見当たらなかった。ただ、なんといえばいいのか、気配のようなものがまるでちがっている。この人はホンモノだ、と直感した三津は、体ごと長壁姫に向き直り、丁寧に頭をさげた。
「淡島三津と申します」
「お話は拝聴させていただいておりました。江場家のご当主からは、初恋のお相手をさがすお手伝いを、と」

そろりと顔をあげる。
「さがせるんですか? 記憶にない初恋の相手を」
「わたくしが得意としているのは《先読み》ですが、《失せものさがし》もできます。ただ、このたびの初恋さがし、うまくいくかどうかは……わたくしの《失せものさがし》は、記憶の中からおさがしする形になりますので。お心の深いところに、沈みこんでいるだけならいいのですが」
唐突に、長壁姫が三津に向かって手を伸ばしてきた。あご先までの長さの三津の髪に触れ、首をかしげている。
「短い……」
「あ、切ったばかりで」
「なにか悪さでも?」
「いえ、切りたくなったので切りました」
「まあ、さすがは現代っ子。女の命を気分でお切りになりますか」
ひざを前に進めて、長壁姫がさらに近づいてくる。どきっとするほどの距離まで顔を寄せられた。なにをされるのか、まったく予想がつかない。真顔の長壁姫が、三津の髪をひとすくい、持ちあげる。その毛先を自分の鼻の下に押しつけたかと思うと、すんすんとにおいをかぎはじめた。悲鳴をあげそうになったのをすんでのところでこらえて、ぎゅっと目を閉じる。長壁姫が離れてくれるのを、ひたすら待った。
3
耳もとで、長壁姫がぼそりという。
「……ふむ、まったく見えない」
ひざでさがって、長壁姫が離れていく。
「やはり、この島でお過ごしになったときのご記憶が、三津どのの中にはまったく見当たりません。だいぶ深いところも見てみたのですが。こうなってしまうと、わたくしの《失せものさがし》ではどうにも……」
三津のほうが申し訳なくなるくらい、長壁姫はしょんぼりした様子になってしまった。
「で、でも、お目にかかれてよかったです!」
とっさに、そんなことを口走っていた。もちろん、まったくのうそではない。目が覚めたようになるまでは、ふにゃふにゃになりそうなくらい安心していたし、ずっとこうしていたいな、どこにもいかず、いつまでもこの人とこうしていたいな、と思っていたくらいなのだから。正気に返ったいまは、なんともいえない畏れのようなものも、感じてはいるのだけど。
にこり、と長壁姫が笑う。なにかを懐かしんでいるような目で、三津を見つめている。
「……江場家のご当主には、全面的に三津どのをお支えしますとお約束いたしました。おこまりのことなどがあれば、なんなりと」
ならば、と三津は居住まいを正した。
「ご質問を、いくつかさせていただいてもいいでしょうか?」
「おいくつでも。わたくしがお答えできることでしたら」
ふ、と肩から力が抜けるのを感じた。
「きたく……そう、まずは《寄託》について知りたいです。《寄託》とはなんでしょう? 七年前、この島でわたしが無自覚にしてしまったことらしいのですが」
まあ、と長壁姫は口もとに手をやった。
「そんなことも知らされないままここへ?」
はい、と三津がうなずくと、長壁姫はふるふると首を横にふった。
「姫さまからいろいろ教えてやってください、とたのまれてはおりましたが、ずいぶんとまあ、丸投げされたものですね」
丸投げ。長壁姫の口から出ると、妙にギャップを感じる言葉だった。まさか中身はふつうの現代人で、着物や長すぎる黒髪はただのコスプレ、ということはないのだろうから。
長壁姫が、小さくせき払いをする。
「わかりやすくお話ししますと」
「はい」
「この島ではごくまれに、初恋をした際に魂の一部が抜け出し、お相手の魂の中に住みつくことがございます。その状態のことを《寄託》と」
うん? と三津は思う。ここでまた初恋? 大伯母の話に出てきた『初恋』が、あまりにも脈略がなく意味を理解しがたかったので、いったん考えるのを保留にしておいたのだけど、それでは前に進めないらしい。念のため、頭の中で『初恋』以外の『はつこい』をさがしてみる。三津の知る限り、『はつこい』は『初恋』でしかなかった。
「えー……と、そのはつこい、というのは、初売りの初に、恋わずらいの恋と書く、あの初恋のことでしょうか」
「初売りの初……ああ、そう、その初恋でございます」
「意味もそのまま、ですか?」
「意味といいますと」
「この島では、はじめて人に迷惑をかけることを初恋という、みたいな……」
「文字どおりの意味しかございません。三津どのは、七年前にこの島を訪れた際、どなたかをお相手に、はじめての恋をされたのでございます」
大伯母も、同じことをいっていた。どういうわけか自分は、この島のだれかに初恋をしたと思われているらしい。なにがどうなってそんな誤解を、と思う。この島の人どころか、これまでに出会ったすべての人を対象にしたとしても、だれかを好きになったことなんてない。男の子も男の人も苦手だし、もっと広く考えてみても、女の子や女の人にだって特別な気持ちを持ったことはなかった。
恋というものが、三津の想像しているとおりのものだとすれば、そんなものはしたことがありません、とんだ濡れ衣です、と全否定したい気持ちでいっぱいだった。長壁姫の説明はつづく。
「今回の場合、《寄託》はまだ受領されておりません。つまり、三津どのの初恋は成就していない、ということでございます」
成就していない、という言葉に、思わず、ほっとする。
「成就していないのなら、まだなにも起きていないということですよね。だとしたら、特に問題はないのではないでしょうか」
「成就していないことが問題なのです。初恋をした時点で、三津どのの魂の一部はすでに、お体から抜け出してしまっています。それがお相手の魂の中に住みついていない──初恋が成就していないからこそ当時のご記憶がなく、深刻な状態になっているのでございます」
もしかして大伯母たちは、当時の記憶がないことを問題視しているのだろうか。だとしたら、これまで記憶がないことでこまったことはないし、たぶん、これからもないはずだ。それを早く伝えなければ、と三津が口を開きかけたところで、長壁姫は静かな声で、「七年……」といった。
「三津どのの魂の一部は、七年ものあいだ、宙に浮いたままだったということになります。よくまあそんなにも長いあいだ、欠けたお心のまま……」
その声が、表情が、それがどんなによくないことだったかを三津に教えた。とたんに、血の気が引いたようになる。頭ではなく、体が先に理解した。そんな感じだった。
大伯母も長壁姫も、おそらくおおげさに騒いでいるのではない。本当に、三津にとっては深刻なことが起きてしまっているのだ。
「……大伯母は、一刻も早く初恋の相手を思い出して、しかるべき対処をしなければならないといっていました。でも、長壁姫さまの《失せものさがし》では見つけられなかったんですよね。わたしには当時の記憶はまったくないし……」
いったいどうやって思い出せばいいのか。考えれば考えるほど、どうにもならないように思えてくる。そんな三津を安心させるように、長壁姫は、にこっと笑ってみせた。
「ご当主とは、さまざまな策について話し合っております。そうご心配なさらず。きょうのところはここまでといたしましょう」
やんわりとかけられたその言葉に、またしてもふにゃふにゃになりそうになる。
「多岐どの」
呼び鈴を鳴らすように、長壁姫が大きな声を出した。柱以外の仕切りがない廊下の暗がりから、黒いスーツ姿の多岐があらわれる。
「三津どのもおつかれのようです。《御道》を開きますから、どうぞお使いください」
「ありがたく使わせていただきます」
おんどう。なにやらまた、新たな耳慣れない言葉が出てきた。なんのことだろう、と思っていると、察したように長壁姫が説明してくれた。なにもわからずここにつれられてきたことを、よほど哀れに思ってくれたらしい。
「《御道》、というのは、わたくしの屋敷と《御殿之郷》のあいだをつなぐ抜け道のようなもののことです」
「抜け道……ですか」
「わたくしが開けると決めなければ、決して開くことのない抜け道です」
わかったような、わからないような、だった。
4
抜け道のようなもの、と長壁姫が教えてくれた《御道》は、正確には道ではなく、穴だった。
穴、というのもちょっとちがうかもしれない。長壁姫の屋敷の庭に、油を塗った透明な壁のような、ぬらっとして見える場所ができていて、ぬるん、とそこを通り抜けたら、立っていたそこはもう、《御殿之郷》にある大伯母の執務室の前だったのだ。
多岐が襖を開け、さらに奥にある観音開きの扉も開く。畳一枚分はありそうなサイズの執務机の前に、大伯母の小巻が背中を伸ばして座っていた。
その正面には、きのうと同様、背もたれの高い椅子が置かれている。三津に着席をうながすと、多岐はすぐさま小巻のもとへと向かった。耳もとで、短くなにかを告げている。長壁姫との《咫尺》の結果を報告したのだろう。見ていてわかるほど、小巻の顔色が変わった。
「……そうですか、やはり姫さまの《失せものさがし》ではさがせませんでしたか」
落胆した様子は見せつつも、小巻はすぐさま、新たな指示を多岐に与えた。
「例の手配を」
「承知いたしました」
一礼して小巻のそばを離れた多岐が、三津にも目礼してから執務室を出ていった。小巻とふたりきりになる。
「きのうの夜は──」
いきなり話しかけられて、びくっとなった。小巻が顔をしかめたのがわかる。ちょっと話しかけたくらいで、と思われたにちがいなかった。あやまりたくなる。そんなことをすれば、もっといやそうにされるのはなんとなくわかるので、ぐっとこらえた。
「……眠れましたか?」
「あ、はい」
「なにも問題はありませんね?」
遠雷のことが頭をよぎった。知らせておくべきだろうか。いや、話せばまたおばさんの顔がくもるだけだ、たいしたことじゃない、黙っておこう。気持ちはすぐに決まった。
「問題はないです」
そう、とうなずいてから、ふとなにかを思いついたように、小巻は卓上のレトロな黒い電話に手を伸ばした。
「哉重をこちらへ」
それだけ告げて、受話器を置く。
「多岐がもどるまで、館内を見学しておきなさい。哉重に案内させます」
はい、と答えた三津に、小巻は目線で扉のほうを示した。いきなさい、ということらしい。三津は黙ってしたがった。
5
板張りの薄暗い廊下に出てすぐ、「三津」と声をかけられた。まっすぐ伸びた廊下の先に、細長いシルエットを見つける。哉重だ。
手招きをされたので、小走りに駆け寄る。きょうの哉重は、細身の黒いデニムに襟つきの白いシャツを合わせている。すっきりとした顔立ちに、よく似合う服装だ。初対面のときには気がつかなかったけれど、左右の耳にけっこうな数のピアスが光っている。それもまた、哉重の雰囲気には合っていた。
「多岐はどうした? 小巻おばさんからなにか申しつけられたのかな」
内容にはふれず、「はい」とだけ答える。哉重にくわしく話していいのか、三津には判断がつかなかった。
先に立って哉重が歩き出したので、あわててとなりにならぶ。三津の身長も、高校一年生の女の子としてはそう低いほうではないのだけれど、哉重とならぶとだいぶ差があった。百七十四、五はありそうだ。
「どう? この島で暮らしていけそう?」
その質問に、三津は急に、はっとなった。
島に着くなり、人力車や多岐の態度に驚かされ、《御殿之郷》でも次から次へとよくわからない話をされ、すっかり置き去りにしたままになっていた問題を、電撃的に思い出したのだった。
「あの、哉重さん」
根本的に、自分が知っておかなければならないであろうことを、三津はたずねた。
「この島って……ふつうの島じゃないですよね?」
大伯母や多岐は、天狗がいることを当たり前のように話し、自宅として与えられた家の庭では、しゃべるたぬきの置物や、《つくもの会》と称する、これまたしゃべる雑多なものたちと遭遇した。携帯電話の電源が入らなくなる原因は袈裟羅婆裟羅だと教えられ、摩訶不思議なからくりを経て面会した長壁姫は、《先読み》や《失せものさがし》ができる超能力者のような人だった。
どう考えても、ふつうの状況ではない。
「そうか……三津は七年前のこの島での記憶がないから、そのとき教わったことも忘れてしまっているのか。もしかするとおばさんも、そのことは失念していたかもしれないな」
よし、というように、哉重が進行方向を変えた。まっすぐ進んでいた廊下を引き返して、途中にあった曲がり角を曲がろうとする。
「どこへいくんですか」
「布絵の部屋だ」
(第5回へ続きます。5月1日ごろ更新です)
第1話はこちら
第2話はこちら
第3話はこちら
『YA作家になりたい人のための文章講座 ~十四歳のための小説を書いているわたしがお話できる5つのこと~』はこちら
石川宏千花さんの新連載記念『YA作家になりたい人のための文章講座~十四歳のための小説を書いているわたしがお話できる5つのこと~』第1回はこちら!
(毎月1日、15日更新します)












![「卒園おめでとう」を伝える絵本3選! 門出を祝うプレゼントにぴったりな名作[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/879/large/fe3c9db7-2339-4abc-a2cd-c276cc46fa59.jpg?1772501924)





































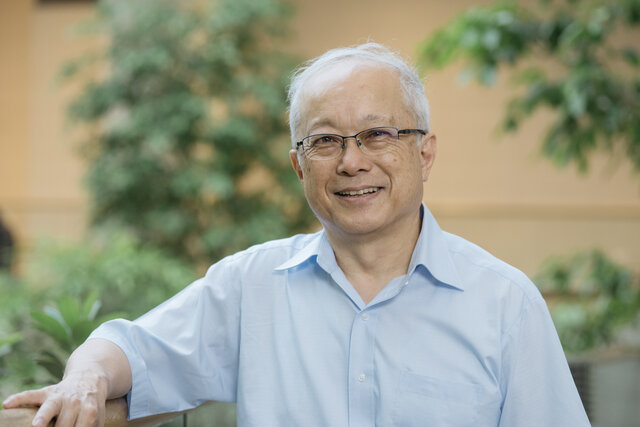


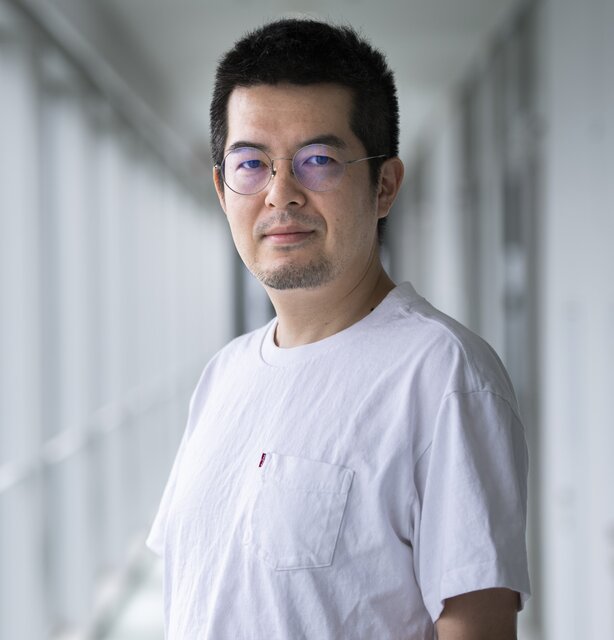




























































石川 宏千花
『ユリエルとグレン』で、第48回講談社児童文学新人賞佳作、日本児童文学者協会新人賞受賞。主な作品に『お面屋たまよし1~5』『死神うどんカフェ1号店』『メイド イン 十四歳』(以上、講談社)、『墓守りのレオ』(小学館)などがある。『少年Nの長い長い旅』(YA! ENTERTAINMENT)と『少年Nのいない世界』(講談社タイガ)を同時刊行して話題となった。『拝啓パンクスノットデッドさま』(くもん出版)で、日本児童文学者協会賞を受賞。
『ユリエルとグレン』で、第48回講談社児童文学新人賞佳作、日本児童文学者協会新人賞受賞。主な作品に『お面屋たまよし1~5』『死神うどんカフェ1号店』『メイド イン 十四歳』(以上、講談社)、『墓守りのレオ』(小学館)などがある。『少年Nの長い長い旅』(YA! ENTERTAINMENT)と『少年Nのいない世界』(講談社タイガ)を同時刊行して話題となった。『拝啓パンクスノットデッドさま』(くもん出版)で、日本児童文学者協会賞を受賞。