![「卒園おめでとう」を伝える絵本3選! 門出を祝うプレゼントにぴったりな名作[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/879/large/fe3c9db7-2339-4abc-a2cd-c276cc46fa59.jpg?1772501924)

石川宏千花/著 脇田茜/画
【主な登場人物】
★ 淡島三津(あわしまみつ):この物語の主人公。15歳。
★ 江場小巻(えばこまき):三津の大伯母。72歳。御殿之郷を営んでいる。
★ 多岐(たき):三津の身の回りの世話をする、年齢不詳の男。
★ 遠雷(えんらい):大天狗。
★ 江場哉重(えばかえ):三津のいとこ。
★ 憧吾(どうご):三津が行くことになる高校に通っている。
★ たすく:ため息が大好きな、信楽焼のたぬき。
★ 長壁姫(おさかべひめ):「先読み」や「失せものさがし」ができる姫。
【主な地名、名称】
★ 場家之島(ばけのしま):東京から遠く離れた島。
★ 御殿之郷(ごてんのさと):島唯一の旅館。豪華絢爛で、全貌が見えないくらいまで建て増しをしている。
★ 寄託(きたく):初恋をした時に魂の一部が抜け出して、相手の魂の中に住みつくこと
【これまでのおはなし】
父の海外赴任に伴い、淡島三津はかなり変わった島・場家之島で暮らすことになった。七年前に訪れてたはずなのだが、何一つ記憶にない。しかもその時、三津は成就しなかった無自覚な初恋をしており、魂の一部が宙に浮いてしまったままになっているらしい。大伯母の小巻は危機感を覚え、長壁姫に失せものさがしを頼むが、三津の初恋相手を見つけることはできなくて…。
場家之島が化け之島だったころ
1
その部屋に足を踏み入れた瞬間、背筋がびりびりっと震えて、何歩か進んだところで、三津は動けなくなった。
美術館を思わせる広大さの、まっ白な部屋。その壁一面に、〈切り取られた場面〉が整然と貼りつけられていた。
それらはすべて、畳一枚ほどの大きさの布に発色のいい絵の具によって描かれていて、まるでスケールの大きな紙芝居の様相だ。そして、布に描かれた〈切り取られた場面〉の一枚一枚は、その場の声や音が聞こえてきそうなくらいの臨場感にあふれていて──、
「七年前にも、きみはこの部屋を訪れている。覚えていない?」
哉重の声に、ふっ、と息を吐く。知らないうちに、息を詰めていたらしい。
「……覚えていません」
こんなにも圧倒される場所を訪れたのなら、記憶に残っているはずだ。それなのに、なにも思い出すことができない。突然、薄氷の上に立たされているような気がしてきて、三津は、ぞくりとなった。
「島の歴史が描かれている。あそこの、天井にいちばん近い絵を見てごらん」
いわれるままに、哉重が指さしている角の絵を見上げてみた。百鬼夜行という絵を見たことがある。一見、あれを模して色をつけたのかな、と思うような情景が、そこには描かれていた。
場所は、一本松の生えた砂浜だ。おでこに角がある小鬼の群れや、そのまわりを漂う無数の火の玉なんかが、一列になって進んでいる。体全体がぼうっと白く光った、鶴のようで鶴でない鳥が飛ぶその下には、猿なのか熊なのかよくわからない毛むくじゃらの巨体も歩いている。向かっているのは、夜の暗い海だ。そこにはすでに、大勢が乗りこんだ船が、何艘も何艘も浮かんでいる──。
「場家之島はもともと、化ける、の化けと書いて化け之島だった、といわれているんだ」
「じゃあ、あの絵に描かれているのは……」
「俗にいう、妖怪だね」
「よう……かい」
「江戸から明治へと時代が移り、彼らの居場所でもあった〈暗がり〉が失われたことで、日本全国からこの島に、多くの妖怪たちが移り住んだ時期があってね」
「どうしてこの島に?」
「もともと人と妖怪が、適度な距離感を保ちながら、のんびりと暮らしていた島だったらしい。時代が移っても、お互いの存在を認め合う関係に変化はなく、それが妖怪たちのあいだでうわさになり、移住を望む者たちがあとを絶たなくなった。そのころのことを描いたのが、あの絵というわけだ」
哉重の解説を聞きながら、〈切り取られた場面〉を順に見ていく。
「その下が、日本全国の妖怪たちが移り住んできてからの島の様子。ほら、大きなカボチャが道をころがってくるのに驚いて、腰を抜かしているおばあさんがいるだろう? あれは、《南瓜転がし》という広島出身の妖怪のいたずらだ。当時はこんなことが日常茶飯事だったようだけど、妖怪たちのすることだから、と目くじらを立てる島民もいなかった」
ところが、と声音を少し変えて、哉重が次の〈切り取られた場面〉に視線を移した。
「単なるいたずらでは済ませられないことをする者たちが、あらわれた。それが、クダンとサトリだ」
描かれていたのは、黒々とした巨大な牛と、毛の黒い雪男のような人型のなにか、だった。小高い丘の上から、里を見下ろしている。
「クダンは、疫病を予言する妖怪として知られている。サトリは、人の言葉を理解し、心も読む。そのため、捕まえようとしても心を読まれて逃げられてしまう。どちらも、人には害をなさない妖怪たちだといわれていたんだが……」
哉重が言葉を途切れさせたので、三津は顔を横に向けた。哉重はまだ、壁の上のほうに貼られている布の絵を見上げている。
「この島に渡ってきたのち、行動をともにするようになった両者は、どういうわけか喜々として、島民たちに混乱をもたらす行動を取りはじめた。されるとつらい予言をあえてしたり、身近な相手の知りたくもない本心を教えたりしたんだ」
哉重の視線の先に目をもどす。そこには、取っ組み合いの喧嘩をしている人たちや、強奪をしている人、女性を襲っている人、子どもを蹴りとばそうとしている人なんかが描かれていて、三津はすぐに、目をそらしてしまった。ひどい。あんまりだ、という思いがふつふつとわいてくる。それはまるで、絵の中の感情がそのまま三津の中に入りこんできたかのような、〈知っている〉怒りであり、悲しみであり、むなしさだった。
「この混乱を収めたのが──」
哉重が、さらなる〈切り取られた場面〉の解説をつづけようとしたところで、
「哉重くん!」
甘みのある高音の声が、背にしていた入り口から哉重を呼んだ。だれだろう、とふり返る。なぜだか哉重は、正面を見つめたままだ。
三津がふり返ったそこには、にらむようにこちらを見つめている少女の姿があった。まったく見覚えがない。恨みを買うようなことをした記憶も、もちろんない。あからさまな敵意や嫌悪をこめた視線をぶつけられている理由を、三津は見つけられなかった。
「さがしたよ、哉重くん。お茶しにいく約束、忘れてないよね?」
声の印象どおりの、甘い顔立ちをした女の子だ。二重の幅が広く、涙袋がぷっくりとしていて、あごが小さい。三津と同年齢か、もしくは少し下かもしれない。体格からすると、中学生にも見えた。
すぐ横の哉重が、ふっ、と短く息を吐いた。それで気持ちを切り替えた、とでもいうように、ぱっとうしろを向く。
「忘れてないよ、比那」
その声を聞いて、三津は思った。哉重さんはこの子のことを負担に感じているのか、と。
「ちょうどいい、三津を紹介しよう」
そういって哉重が、三津のほうに視線を向けようとしたとたん、比那と呼ばれたその少女は、「いい!」と叫ぶように答えた。
「どうせ今夜の歓迎会で会うもの。いまじゃなくていい」
ふいっと顔を横にそむけて、それきりこちらを見ない。
「哉重さん、いってください。わたしはもう少し絵を見ています」
「いや、でも……」
「だいじょうぶですから」
そこまでいわれては、という様子で、哉重が三津のそばを離れていく。そのうしろ姿に、かすかなこわばりが見えた。比那が、ちらっと三津に視線を向けてくる。甘みのある小さなその顔には、勝ち誇ったような薄い笑みが浮かんでいた。
2
ひとりになると、あらためて布に描かれた絵の迫力に圧倒された。それでも、すべて見てしまわなければ、という責任感のようなものがふつふつとわいてくる。
哉重が、クダンとサトリの絵だと説明した布の下には、すっかり荒れ果てた島の状況と、それを見つめるひとりの少女が描かれていた。着物に袴を合わせた出で立ちだ。〈切り取られた場面〉を順に追っていく。数枚の絵を経て、少女は単身、山の奥へと入っていき、荘厳な滝の前に立つ。滝には仏神の姿が浮かびあがっており、少女はなにかしらの契約を交わす。場面は移り、復興した島の様子が描かれる。
現在の場家之島はおもに、漁業と真珠の養殖、果実の栽培、あとは、希少な鉱石の発掘が、島民の生活の糧だと聞いている。そうした産業が興っていくまでが、何枚にもわたって記録されていた。人々が少しずつ明るさを取りもどしていくさまが、いきいきと表現されていて、見ているだけで楽しくなってくる。
途中、どういう場面なのか推察できない絵もいくつかあった。意味ありげに島を上空から見下ろす天狗の絵だったり、海や山が暴風雨に襲われている絵だったり、だ。
それでも、わからない漢字があってもなんとか読みとおすことができた小説のように、三津は最後の一枚まで、すべての布絵を鑑賞し終えた。
どっと疲れが押し寄せてくる。どこかに腰をおろしたい、と思った。部屋の出入り口に向かって歩き出そうとしたとたん、がくん、とひざが抜けたようになる。その場にへたりこんでしまった。全身が、重くてだるい。
脱力した状態で座りこんでいたら、急激な眠気を感じた。座っていることすらできなくなって、上半身がふらふらと揺れはじめてしまう。どうしよう、こんなところで眠くなるなんて……と思ったのを最後に、三津は力なく、床の上に横倒しになった。
3
「──い、だいじょうぶか、おい!」
激しく体を揺さぶられていることに気がついて、三津は、ぎくりとなった。
ぱちっと開いた目で、自分を揺さぶっている相手の顔をさがす。あっ、と思った。意外な顔が、すぐそばにあったからだ。
「桃の……人……」
今朝、桃を持ってきてくれた男の子だった。名前はたしか、憧吾、といっただろうか。いや、尉砂が名前だった? どちらが名字でどちらが名前だったか思い出せない。顔がやけに近いな、と思う。
「なんでこんなところで倒れてんだよ。具合が悪いのか?」
ああ、そうか、背中を支えられて、上半身だけが起きあがった状態なんだ、と気づく。気づくやいなや、三津は息を吹きこまれた空気人形のようになって、抱えられていた腕の中から、しゅるっと逃げ出した。急に動いたからなのか、背中にまだ手のひらの感覚が残っているからなのか、さーっと目の前が暗くなる。両手を床について、顔をうつむかせた。
「吐くのか? え、ちょっ……トイレか? トイレにつれてけばいいのか?」
動揺しているのが伝わってくる憧吾の声が、耳に近い。放っておいてくれればいい、と伝えたいのに、顔をあげられない。
「三津さま!」
よく通る声に、名前を呼ばれた。この声、多岐さんだ──駆け寄ってくる足音に、ふ、と正気がもどったようになる。やっと顔をあげることができた。
「どうされたんですか!」
憧吾をわきに押しのけながら、多岐が顔をのぞきこんでくる。自分でも驚くほど自然に、手が伸びた。その黒い上着の腕に向かって。
「ここから……出してください、多岐さん」
いい終わる前に三津の体は、ふわっと宙に浮いていた。三津を抱えて立ちあがった多岐は、一直線に出入り口へと向かっていく。体の重さやだるさが、ゆるゆると消えていくのがわかった。耳もとで、多岐がひとりごとのようにいう。
「布絵に当てられましたか……」
当てられた、というのは、どういう意味だろう、としばらく考えてみて、ああ、そうか、影響を受けすぎた、みたいなことかな、と気がついた。たしかに、長い年月を一気に過ごしたような感覚に、どっと体が重くなった気はする。当てられたのかもしれない。この島の歴史に。
「このままご自宅へおつれいたします」
「はい……でしたら、おろしてください」
廊下に出てもなお、多岐は三津を抱えあげたままだったし、歩く速度も変わっていなかった。
「おりる必要はございません」
「えっ? あります」
「なぜですか」
「もう歩けるからです」
「お言葉ですが、わたくしにはそのように思えません。このままおつれするほうが早いかと存じます」
丁寧な言葉に厳重に包みこまれてはいるけれど、その中身は、『おろす気はありません』だった。勝手におりようにも、多岐の両腕でがちっとホールドされたようになってしまっていて、身じろぎするのも難しい状態だ。
すっ、と頭が冷えたようになった三津は、なにをすればこの人は自分をおろしてくれるんだろう、と考えた。間近にある多岐の横顔が目に入る。見入っているうちに、思いついた。かなりの強硬手段ではあるけれど、確実におろしてもらえる方法を。
「多岐さん」
「はい」
「おろしてくれないなら、わたしはこれから多岐さんにあることをします。それはこの距離では避けられないことで、なおかつそれをされると多岐さんは、された側であるにもかかわらず、おばさんから責任を問われます」
「……責任を、ですか?」
多岐は、ぴんときていない様子だ。
「おろすなら、いまですよ」
「先ほどもご説明しましたが──」
三津は、強硬手段に出た。もとから近かった顔を、さらに近づけたのだ。あと少しでくちびるが触れる、という距離にまでせまったところで、多岐は、わっ、と声をあげた。連動して、三津を抱えあげていた腕の力がゆるむ。

そのすきをついた三津は、塀から飛びおりた猫が着地するように、すたっと床におり立った。
大伯母の小巻は、未成年に手を出すような人物ではない、と見込んだからこそ、多岐を自分の世話役につけたにちがいない。となると、なにが起きれば小巻の多岐への信頼がなくなるか、三津はそれを考えた。もちろん、本当にするつもりなんてなかったし、できるとも思っていなかったけれど、ふりならできる。ふりでも効果はある、と踏んで実行に移したのだ。
効果は覿面。三津は希望を叶え、多岐は、口もとを手の甲で押さえて立ちつくしている。
「いきましょう、多岐さん」
淡島さんは、怒らせるとこわい──。
クラスメイトから、何度かそんなようなことをいわれたことがある。普段がおとなしいだけに、怒ったときに取る行動が突飛なもののように思われるらしい。
自分では、よくわからない。ただ、どうせ怒るなら、最大限の効果が出せる怒り方をしよう、と考えているだけだった。
4
三津の母親は、ふわふわとしてつかみどころのない、クラスの中の変わり者みたいな人だった。
男の子のように短くした髪には不釣り合いなくらい、目の大きなアイドルっぽい顔。子どものように華奢で、色白な体つき。好んで着ていた白い服が、本当によく似合っていた。
三津のことは、わたしの娘さん、と呼んだり、みのつく人、と呼んだりで、まともに『三津』とか『三津ちゃん』と呼んだことはない。父親のことも、わたしの夫さん、と呼んだり、わたしの娘さんのお父さん、と呼んだり、だった。もしかすると、自分自身のことを母親だとも妻だとも思っていなかったのかもしれない。
そんな人ではあったけれど、家のことはきちんとしていたし、いつもきげんよさげだったので、いっしょに暮らしていてこまるようなことはなにもなかった。ただ、いつも少しずつ、さみしかっただけだ。母親にとって、自分はいちばん大切な存在ではないんだろうな、と常に感じていたし、だからといって、夫をいちばんに思っているようでもなかった。
自分の母親は、いつか遠いどこかにいってしまう人なのかもしれない。そんな不安が、幼いころから色の薄い影になって三津につきまとっていた。そして、それが現実のことになったのが、いまから二年前、三津が中学二年生になったばかりのころだ。
母親が、いつもとはまるでちがう黒ずくめのかっこうで駅前を歩いているのを、偶然、見かけてしまったのだ。だめだ、こんなことはしちゃいけない。そう思いながらも、あとをつけずにはいられなかった。
母親が駅の改札で待ち合わせをしていたのは、知らない若い男の人だった。当時の母親は三十代の後半にさしかかったばかりだったけれど、それよりもずっと若く見える人だったような気がする。
母親はうれしそうに駆け寄ると、迷うことなくその腕に自分の腕をからめ、改札の向こうに消えていった。それきり母親は帰ってきていない。連絡もない。きれいさっぱり、消えていなくなってしまった。
このときのことは、父親には黙っておくつもりだった。ただでさえ、妻の失踪に傷ついているにちがいないのだから。
それなのに──。
「おっ、出そうかな? 出そうですね?」
どこからか聞こえてきた、ちょっと震えている子どものような声に、はっ、と顔をはねあげる。
海の見える大きな窓に向けて置かれたふたりがけのソファに、三津はひとりで座っていた。すぐ横に、ちょこんとたぬきの置物が置かれているのに気づく。今朝、いきなりあらわれて、しきりにため息をほしがっていたあのたぬきの置物だ。置いた覚えはない。勝手にあらわれたのだ。
自宅まで三津を送り届けた多岐は、歓迎の宴は夜の七時からなので、その前にまた迎えにまいります、とだけいい残して帰っていった。文字どおり、逃げ去るように。
あのような〈脅し〉を三津から受けるとは、夢にも思っていなかったのだろう。今後もこの手は使えるかもしれない、と思いながら、リビングのソファに座りこんだところまでは覚えている。いつからもの思いにふけり出したのかは、覚えていなかった。
ぼんやりしていると、いつのまにか母親のことを考えてしまうのはいつもの癖だ。胸の死角で黒く光っている水ようかんが、ふるふると震えているのを感じる。
それにしても、ため息好きなこのたぬきの置物は、いつからとなりにいたのだろう。家の中にまで出没するなんて、と思いながらも、とぼけたその顔を見ていたら、なんだか気が抜けてしまった。
「きみ、名前はあるの?」
「そりゃあ、ありますよ」
「なんていうの?」
「たすくです」
「たすくちゃん」
名前があると知ったら、急に親しみがわいてきた。たすくのかぶっている麦わら色の笠に、そっとさわってみる。
「わ、しっとりしてる」
見た目は陶器そのものなのに、さわりごこちは濡れせんべいのようだった。
「お嬢さんのおかげですよ。今朝方、いい感じのため息をついてくれましたからね」
「もっとしっとりしたら、どうなるの? ホンモノのたぬきになるとか?」
「さあ、どうなるんでしょうねえ。それはぼくにもわかりませんよ」
「そうなんだ……」
話し相手がいるのっていいな、といまさらのように三津は思う。心につもったホコリの層のような思いを聞いてもらいたいわけではないけれど、だれかがそばにいて、気兼ねなく他愛ない話ができるのはいい。
ふ、と三津は笑った。
たとえ相手がたぬきの置物でもね、と。
(第6話へ続きます。5月15日ごろ更新です)
第1話はこちら
第2話はこちら
第3話はこちら
第4話はこちら
『YA作家になりたい人のための文章講座 ~十四歳のための小説を書いているわたしがお話できる5つのこと~』はこちら
石川宏千花さんの新連載記念『YA作家になりたい人のための文章講座~十四歳のための小説を書いているわたしがお話できる5つのこと~』第1回はこちら!
(毎月1日、15日更新します)



















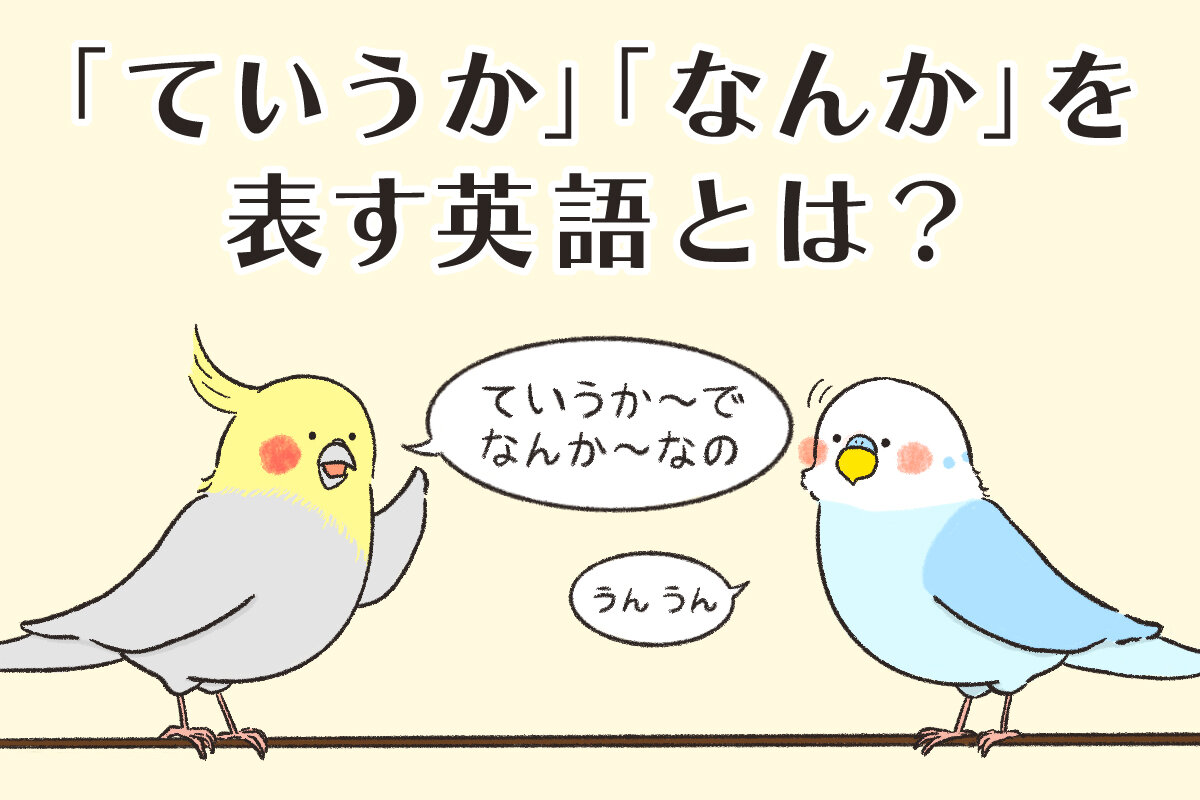



























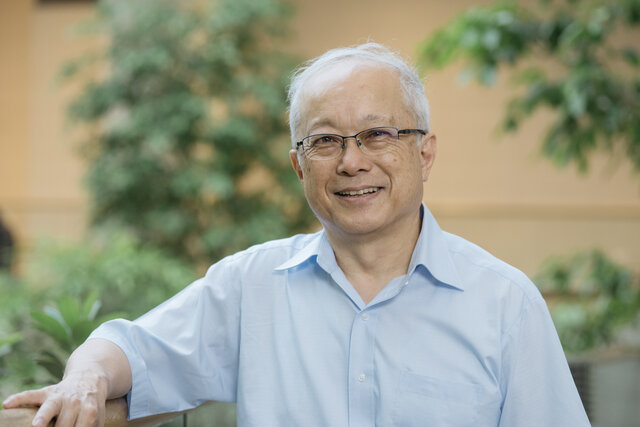


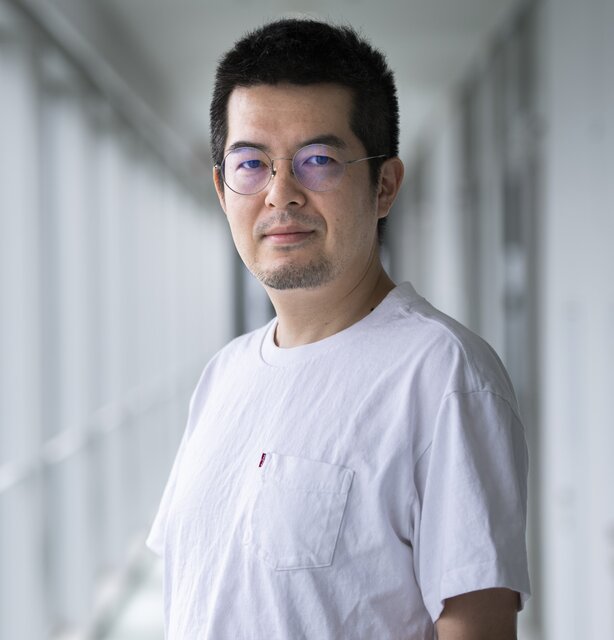



























































石川 宏千花
『ユリエルとグレン』で、第48回講談社児童文学新人賞佳作、日本児童文学者協会新人賞受賞。主な作品に『お面屋たまよし1~5』『死神うどんカフェ1号店』『メイド イン 十四歳』(以上、講談社)、『墓守りのレオ』(小学館)などがある。『少年Nの長い長い旅』(YA! ENTERTAINMENT)と『少年Nのいない世界』(講談社タイガ)を同時刊行して話題となった。『拝啓パンクスノットデッドさま』(くもん出版)で、日本児童文学者協会賞を受賞。
『ユリエルとグレン』で、第48回講談社児童文学新人賞佳作、日本児童文学者協会新人賞受賞。主な作品に『お面屋たまよし1~5』『死神うどんカフェ1号店』『メイド イン 十四歳』(以上、講談社)、『墓守りのレオ』(小学館)などがある。『少年Nの長い長い旅』(YA! ENTERTAINMENT)と『少年Nのいない世界』(講談社タイガ)を同時刊行して話題となった。『拝啓パンクスノットデッドさま』(くもん出版)で、日本児童文学者協会賞を受賞。