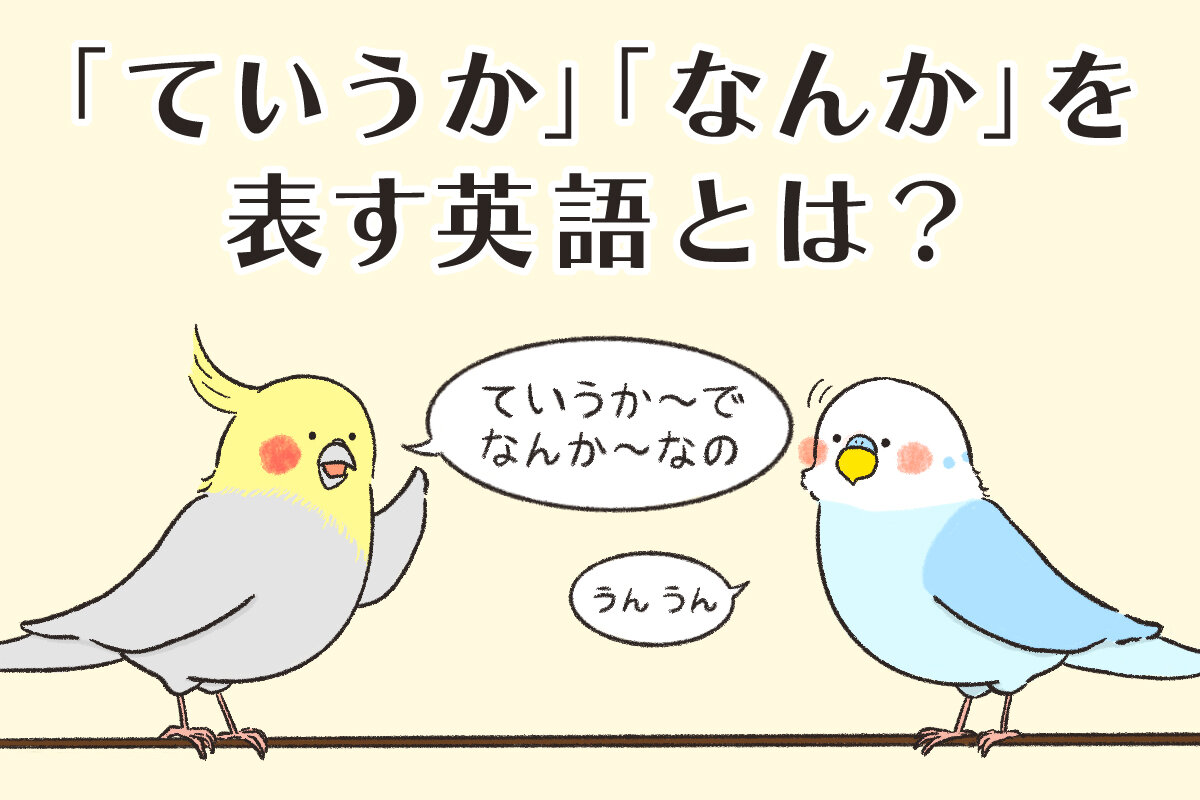

石川宏千花/著 脇田茜/画
【主な登場人物】
★ 淡島三津(あわしまみつ):この物語の主人公。15歳。
★ 江場小巻(えばこまき):三津の大伯母。72歳。御殿之郷を営んでいる。
★ 多岐(たき):三津の身の回りの世話をする、年齢不詳の男。
★ 江場哉重(えばかえ):三津のいとこ。
【主な地名、名称】
★ 場家之島(ばけのしま):東京から遠く離れた島。
★ 御殿之郷(ごてんのさと):島唯一の旅館。豪華絢爛で、全貌が見えないくらいまで建て増しをしている。
【これまでのおはなし】
父の海外赴任に伴い、淡島三津は遠く離れた場家之島で暮らすことになった。七年前に訪れてたはずなのだが、何一つ記憶にない。さらにその際、三津が無自覚な初恋をしており、一刻も早くその相手を探さねばならぬと聞かされる。状況も飲み込めぬ中、絶景の温泉で出会ったのは、麗しい大天狗。そこで「またね。見覚えがある気のするお嬢さん」と、言い残されて―!?
天狗除けのネックレス
1
父親とふたりで暮らすようになってから、大きく変わったことのひとつが食事だ。
父親は朝食をとらずに出勤し、帰りは決まって深夜、週末はほぼ一泊二日の出張に出ていたので、必然的に三津の食事は、ひとりで用意して、ひとりでとるものになった。
場家之島で迎えた最初の夜。
三津の食事は、やっぱりひとりだった。多岐いわく、『《咫尺》を済まされるまでは、外出を控えていただかなくてはなりません。歓迎の宴も、あすの夜になります。今夜のお食事は、こちらでおとりください』とのことだった。
和食と洋食、どちらになさいますか、という機内食の選択のような問いかけには、和食で、と即答はしたものの、正直、どちらでもよかった。そう答えればこまらせてしまうだろうからと、先に名前が出たほうを選んだだけだ。そうして運ばれてきた盛りつけ済みの皿を手際よく配膳し終えると、多岐は帰っていった。
黙々と食事を終え、片づけをし、入浴も済ませ、一階の明かりを消して回っていたときのことだ。海に面した大きな窓に、ふと目がいった。あっ、と声が出る。塗りつぶしたように暗い窓のすぐ向こうに、人がいた。目が合う。にこっと笑いかけてきた。あっけにとられる。浴場で会ったあの人だった。
あ、け、て、とくちびるの動きで訴えてきたので、三津はとっさに、こまります、と首を横にふった。天狗除けのネックレスに、自然と手が伸びる。これが与えられているということは、自分は天狗と関わってはいけないということだ。窓越しの相手は、あからさまにしょげた顔をしてみせている。
浴場で会ったときには、濡れて頭の形に撫でつけられていた髪が、いまは夜風に吹かれてそよいでいた。前髪を作っていないふんわりしたミディアムショートで、その髪型だけでも、ファッション関係の仕事をしている男の人を思わせる。加えて、くたっとした墨色のラグランスリーブシャツに細身の黒いパンツというかっこうも、雑誌のスナップ写真に載っていてもおかしくないくらい、さりげなくおしゃれだ。とても天狗になんて見えない。
本当にこの人は、天狗なのかな。多岐さんは、大天狗だともいっていたけれど……。
こんこん、と窓をノックする音が聞こえてくる。窓越しに、また目が合う。自分はいま天狗と向き合ってるんだ、と思ってみたけれど、不思議なくらい、こわいとは感じなかった。
もしかすると、この人からじゃないと聞けない話があるかもしれない──そんな考えが、ふと頭に浮かぶ。
三津は、窓のクレセント錠に手を伸ばした。外側から、窓が開かれる。
「こんばんは、お嬢さん」
「……こんばんは」
「遠雷といいます。遠い雷、で遠雷。お嬢さんは?」
「数字の三に、興味津々の津で、三津です」
「三津、ね。そう、三津か……」
遠雷、と名乗ったその人は、黒いビーチサンダルを脱いで裸足になった。指先にかぎ爪なんかはついていない。そのまま家の中に入ってこようとしたけれど、足先が床の上に触れた瞬間、いてっ、と声をあげる。
「天狗除けの結界か」
うっとうしい虫を見るような目で、遠雷はあたりを見回した。その視線が、三津の胸もとで止まる。
「……相変わらず、小巻は用心深いな」
ため息のまじった笑い声を、ふっ、と短くもらして、遠雷は三津の目をのぞきこんだ。
「オレは、そっちにいけない。三津がこっちにきてくれる?」
遠雷さんはこっちにくることができない。だから、自分が? いやいや、と思う。この状況には理由がある。大伯母の小巻が、必要だから、とこの状況を作っておいたのだ。それを無視して、こっちにきて、とこの人はいっている。三津の中から、急に迷いがなくなった。やっぱりこの人は天狗だ。人だと思って信用しちゃいけない相手なんだ、と。
遠雷の鼻先で、ぴしゃっと窓を閉めた。すぐさま施錠もしてしまう。驚いた顔でかたまっている遠雷をそのままに、ジャッとブラインドも閉めた。これでもう、だいじょうぶ。あの人は入ってこられない。
ほっとした三津は、その場にへたりこみそうになるのをぐっとこらえた。この家には、自分しかいない。へたりこんでも、助け起こしてくれる人はいないのだから、と。
2
寝坊した!
がばっと起きあがり、枕もとの目覚まし時計をさがす。ない。なにも手に触れない。がらんと広い部屋の様子が目に入った。ああ、そうか、とようやく安堵のため息をつく。
ここは、いつもの自分の部屋じゃない。仮住まいの、場家之島の家だ。学校は、夏休み明けから。寝坊はしていなかった。
寝室を兼ねたプライベートスペースになっている、と多岐が説明したとおり、二階は丸ごと一室になっていて、その分、一階以上に床の面積が広く感じられる。
置かれているのは、出窓の前のレトロな片袖机と、背の高い木製の本棚、それに、大きなドレッサーがひとつ。あとは、ダブルサイズはありそうなベッドだけだ。ゆるやかに湾曲した壁に、頭側が寄せられている。
三津の旅行バッグは、ドレッサーの前にちょこんと置かれていた。荷物がひどく小さく感じる。なんだか急に、どこかで乗り継ぎをまちがえて、別のだれかがくるはずだった場所にきてしまったような気がしてきた。多岐は親切だけど、ちゃんと言葉が通じている感じがしないし、たよりの大伯母は、あきらかに自分を疎んでいる。さすがに心細かった。自然と気分が沈む。昨夜の、遠雷のいきなりの来訪を思うとなおさらだ。
よろりとベッドを出た。なにはともあれ、着替えだ。
いまは、旅行バッグから出しておいた黒のロング丈Tシャツを着ている。パジャマは持ってこなかった。いざというとき外にも出られるもののほうが安心して寝られる気がして、部屋着を多めに持ってきたのだ。
海の見える出窓の近くまでいった。朝日を薄く溶かしたような色の波が静かに揺れている。
「人のいない世界の朝みたい……」
なんの気なしにそうつぶやいたとたん、ぞく、と背筋が震えた。本当に、自分しかいない朝を迎えてしまったような気がしたのだ。
早く着替えよう、と出窓に背中を向けようとしたその瞬間、視界のすみを、さっ、となにかがよぎっていった。えっ、と動きを止め、窓の向こうに視線をもどす。
なぜだか窓に手が伸びた。開けなくちゃ、と思う。開けると今度は、早く窓の外に出ないと、という気持ちになって、出窓の天板に片ひざを乗せた。窓の向こうに身を乗り出そうとしたところで、「おいっ」と、窓の下から怒声が飛んでくる。
ぐらっ、と体が前後に揺れた。
なにをしようとしてたんだろう? と三津はまばたきをくり返す。窓から身を乗り出したままの体勢で下をのぞいてみる。こちらを見上げている、同年代の男の子と目が合った。
「あんた!」
わっ、と漏れかけた悲鳴をなんとかのみこんで、はいっ、と三津は応じた。
「なんでそんなにすきだらけなんだよ。そんなんだからこんな小ものに化かされるんだ」
男の子の手には、猫に見える生きものが長くなってぶらさがっていた。小もの、というのは、あの猫らしき生きもののこと? と考えこんでいたら、ふたたび、「なあ!」と怒鳴られた。

「はいっ!」
「なんかぼうっとしてんな。だいじょうぶか? こいつにもうなんかされた?」
「いえ、特になにもされてないと思います」
「気をつけないと、あんたみたいにすきだらけなやつはすぐに自我を奪われるぞ」
「じが……あ、自我。はい」
よくわからないまま、三津はうなずいた。
「ちょっと玄関まで出てきてよ」
「わたしがですか?」
「ほかのだれかにいってるように見える?」
なんかすごく感じが悪い……と内心もやっとしながらも、旅行バッグの中から引っぱり出した黒のパーカをはおった三津は、玄関へと急いだ。
3
開いた扉の向こうで、むっとした顔をして立っていたその男の子には見覚えがあった。
場家之島に向かう船でいっしょだった、制服姿の男の子だ。いまは、制服は着ていない。着古した墨色のTシャツに、くたっとしたオーバーサイズのチノパンツを合わせている。そういえば、きょうは日曜日だ。
「これ、うちの親が持ってけって」
これ、といいながら、大きな紙袋をさし出してくる。伸びてきた腕にひやりとなりながら、反射的に三津は受け取った。中をのぞいてみる。白っぽい桃がごろごろと入っていた。
「ご近所さんからのおすそわけだけど」
「ありがとうございます……と、親御さんにお伝えください」
三津は紙袋を胸の前に抱えて、ぺこりと頭をさげた。そうしてしまえば、目が合わない。返事はなかった。少し待ってから、顔をあげる。五月人形のような黒々とした瞳が、三津の首もとをじっと見つめていた。
「その天狗除けは絶対にはずすなよ? それにかけてある〈呪〉は強烈だから、天狗には効果覿面だ。そう簡単にはやぶられない」
一気にそれだけのことをいい終えると、目の前にあった五月人形の顔は、くるりとうしろを向いてしまった。歩き出そうとしたところで、あ、というように、肩越しに顔だけを三津に向け直す。
「オレ、《御殿之郷》で働いてる尉砂の息子で、憧吾。あんたも通うことになってる海燕高校の一年生」
一方的に自己紹介をして、今度こそ足早に去っていった。芝生が敷きつめられた庭のようなスペースを横切って、岩肌に張りついている赤い階段へとそのうしろ姿が消える。
憧吾がいったとおり、三津は夏休み明けの二学期から、場家之島にある唯一の高校、海燕高等学校に通うことになっている。
東京在住だった三津は、オンラインでの筆記試験と面接を受けて、合格通知を受け取った。夏休みまで残り一週間を切っているので、初登校はきりよく二学期から、ということになっている。一学年一クラスだと聞いているので、同じ学年ということは、自動的に同じクラスになるということだ。
袋の中から、桃が香った。袋をさし出してきたときの顔を思い出す。親にいわれて、いやいや届けにきたにちがいない。申し訳なく思う気持ちと、また次もあるのかなと憂鬱に思う気持ちが、三津にため息をつかせた。
──ぱくっ。
口が大きく開いて、なにかを飲みこんだような音がした。なんの音? と周囲を見回す。
「もっとちょうだい」
今度は声が聞こえてきた。え? とさらに広範囲を見回す。だれもいない。朝日に染まった黄金色の芝生が、ただ広がっているだけだ。それなのに、
「ねえねえ、もっとちょうだい」
声はまだ聞こえている。小さな男の子のようだ。か細くて、ちょっと震えて聞こえる声だった。
4
「だれですか? どこにいますか?」
三津の呼びかけに、声の主はあっけなく姿をあらわした。ほいっ、というかけ声が聞こえたかと思うと、三津の足もとにたぬきの置物があらわれていたのだ。そば屋の店先によく置かれている、あの信楽焼のたぬき。きょとんとななめ上を見ている、あのたぬきだ。
かぶった笠のてっぺんが、三津のひざよりも上にある。背の高さは、五十センチくらい、というところだろうか。
「えっ? たぬ……き? たぬきですか?」
「うん、たぬき」
「置物、ですよね?」
「基本はね」
基本は、置物。たぬきの。
さっぱり意味がわからない。
「あのね、さっきみたいないい感じにしめったため息をいっぱい溜めこむと、ぼくもしっとりするわけですよ。そうするとね、置物っぽさがだいぶなくなるの」
ころんと丸い目は、ななめ上を向いたまま三津の顔を見ていない。口も、動いていない。でも、目が合っているような気はするし、声もちゃんと聞こえている。
「ねえ、もうつかないの? ため息」
「えっ、あ、ため息。またつくかもしれませんけど、いまはちょっと……」
「えー? もうおしまい? まだ出るでしょう。お嬢さん、なんだかいっぱい出しそうだもの」
ため息をいっぱい出しそう、といわれても、ちっともうれしくない。幸薄そうだといわれているようなものだ。
「申し訳ないんですけど、お引きとりいただいてもいいですか? わたし、きのうこちらにきたばかりで……」
「知ってますとも。江場家の三津さまでしょ。お嬢さんのうわさで持ちきりでしたから、ここ数日」
「うわさで持ちきり……って、どこで?」
「われわれのあいだで」
「われわれって?」
「あ、呼びます? 呼びますね」
呼ぶ? それはなんだかまずいことになるような……と思ったときには、もう遅かった。
たぬきの置物が、おーい、と呼びかけるやいなや、芝生の敷かれたスペースからあふれ出しそうな数のガラクタ──としか思えないようなもの──が、いっせいに出現した。
鍋、まな板、やかん、バケツ、下駄、傘、がま口のお財布、鞄、帽子、マント、三輪車、ガラスの戸棚、三面鏡……など。さながらゴミ回収所のようなありさまになってしまった。
「《つくもの会》のみなさんです」
たぬきの置物がそう紹介すると、ガラクタにしか見えない《つくもの会》のみなさんは、どこに口があるのかもわからないのに、どうもどうも、だとか、よくいらしてくださったねえ、だとか、口々にあいさつをしはじめた。あいさつされた以上は、返事をしなければならない。三津は、「はじめまして、淡島三津です」とくり返しながら頭をさげつづけた。
日はすっかり昇りきり、あたりは燦々とそそぐ朝の日差しに白く輝きはじめている。《つくもの会》のみなさんも、それぞれ光のベールを一枚ずつまとったようにうっすらと輝いていた。
「お、きますね」
唐突に、たぬきの置物がつぶやいた。
「だれがですか?」
「江場家の番犬ですよ」
ドーベルマンのイメージが三津の頭に浮かび、それはすぐに、多岐の黒いスーツ姿へと変換された。
「きたな、きたきた」
「退散しよう」
「あいつは苦手だ」
たぬきの置物につづいて、《つくもの会》のみなさんも騒ぎ出す。なんの前触れもなく、ふっとたぬきの置物の姿が見えなくなった。芝生の上いっぱいにあふれ返っていた《つくもの会》のみなさんも、こつぜんと姿を消してしまう。
「えっ……」
きょろきょろと左右を見回し、最後にうしろをふり返った。あ、と声が出そうになる。
多岐がいた。けわしい顔で、《つくもの会》のみなさんがついさっきまでいた芝生の上をにらみつけながら。
5
正装の必要がある、といわれたので、三津はいったん二階にもどった。
ドレッサーを開く。自分のものではない仕立てのいい服にまざって、アイロン済みの状態でハンガーにかけられていた制服を見つけた。三津が東京から着てきたものだ。
着替えを済ませ、玄関のドアを開けにいくと、閉めたときとまったく同じ体勢で多岐は待っていた。番犬。たぬきの置物がいっていたことを、つい思い出す。
岩肌に張りついた赤い階段をくだっていくと、五分ほどで、《御殿之郷》の正面玄関が見えてきた。広大な駐車スペースのすみに、見覚えのある乗りものを見つける。きのうの人力車だった。車夫も同じ人のようだ。目が合うと、目礼された。多岐にたずねてみる。
「どこへいくんですか?」
「長壁姫のお屋敷へまいります」
姫!
これまた思いがけないワードが出てきたぞ、と思いながらも、もはや三津は、多岐に説明を求める気にはなれなかった。これまでの経験上、丁寧に説明はしてくれるのだろうけれど、それで自分がなにかを理解できたためしがない。ならば、つれていかれた先で、自力で知ったほうが早い。
きょうの多岐は、肩も腕もさし出してこなかった。三津が望んでいないと理解してのことなのか、ただ単に、あれは初日限定の特別サービスだったのかは判断がつかない。
多岐は車夫に、「よろしくたのみます」と告げ、三津には、「わたくしはあとからまいりますので」といい添えた。
いったん坂をくだった人力車は、幅の広い海沿いの車道を走り出した。
車夫の男性は、規則的な呼吸の音を漏らす以外は口を開かない。三津は、右手に見えている海をぼうっと眺めた。細かな小波だけが、静かに揺れている。
そうだ、と不意に思い出す。場家之島にきてから、まだ一度もスマートフォンを使っていない。フェリーの上で電波が届いていないのを確認したのが最後だ。着いたよ、と連絡を入れる相手がいたとすれば父親なのだけど、ストックホルムまで電話をかける気にはなれなかったし、メッセージの文面を考える気にもなれなかった。もしかすると、父親からの着信はあったかもしれない。
通学用のバッグからスマートフォンを取り出してみる。画面が明るくならない。あれ? といいながら、首をかしげる。電源を落とした記憶はないし、バッテリーが切れるにはまだ早い。
「気まぐれですもんで」
突然、車夫の男性が話し出した。びっくりして、スマートフォンを落としそうになる。
「き、気まぐれ、というのは?」
「袈裟羅婆裟羅です」
「ケセ……ラン、パセラン?」
「電波をくっつけて遊びたがる日がありましてな。そういう日はもうだめです。スマホもテレビも、ぜーんぶ馬鹿になっちまう」
……スマートフォンの電源が入らないのは、袈裟羅婆裟羅が電波をくっつけて遊んでいるから? どういうことなのか、三津にはさっぱり理解ができない。
「ああ、ほら。そこ」
そこ、といわれたあたりに目をやると、宙にふわふわと、毛がすかすか気味のたんぽぽの綿毛っぽいものが浮いていた。よくよく目を凝らすと、その周囲には線香花火に似た微弱な火花がちらついていて、かすかに、あはは、あはは、という笑い声まで聞こえてくる。
とりあえず、この島でスマートフォンの電源が入らないときは、袈裟羅婆裟羅が電波で遊んでいるときらしい──ということは、学んだ。
(第4回へ続きます。4月15日ごろ更新です)
第1話はこちら
第2話はこちら
『YA作家になりたい人のための文章講座 ~十四歳のための小説を書いているわたしがお話できる5つのこと~』はこちら
石川宏千花さんの新連載記念『YA作家になりたい人のための文章講座~十四歳のための小説を書いているわたしがお話できる5つのこと~』第1回はこちら!
(毎月1日、15日更新します)












![「卒園おめでとう」を伝える絵本3選! 門出を祝うプレゼントにぴったりな名作[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/879/large/fe3c9db7-2339-4abc-a2cd-c276cc46fa59.jpg?1772501924)





































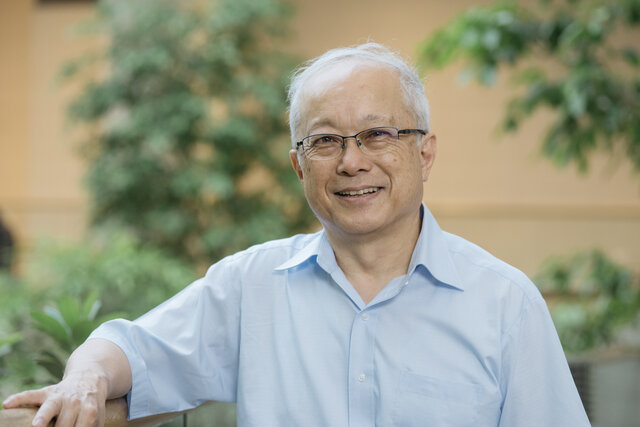


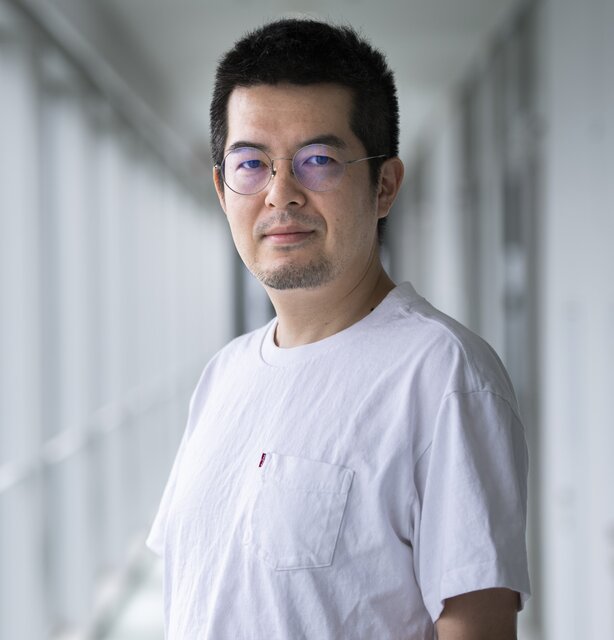























































石川 宏千花
『ユリエルとグレン』で、第48回講談社児童文学新人賞佳作、日本児童文学者協会新人賞受賞。主な作品に『お面屋たまよし1~5』『死神うどんカフェ1号店』『メイド イン 十四歳』(以上、講談社)、『墓守りのレオ』(小学館)などがある。『少年Nの長い長い旅』(YA! ENTERTAINMENT)と『少年Nのいない世界』(講談社タイガ)を同時刊行して話題となった。『拝啓パンクスノットデッドさま』(くもん出版)で、日本児童文学者協会賞を受賞。
『ユリエルとグレン』で、第48回講談社児童文学新人賞佳作、日本児童文学者協会新人賞受賞。主な作品に『お面屋たまよし1~5』『死神うどんカフェ1号店』『メイド イン 十四歳』(以上、講談社)、『墓守りのレオ』(小学館)などがある。『少年Nの長い長い旅』(YA! ENTERTAINMENT)と『少年Nのいない世界』(講談社タイガ)を同時刊行して話題となった。『拝啓パンクスノットデッドさま』(くもん出版)で、日本児童文学者協会賞を受賞。