

子どもの「自主学習」 つまずいたときのサポートや親の関わり方は? 現役小学校教師がくわしく解説
【後編】 ~つまずいたときと親のサポート編~ (5/5) 1ページ目に戻る
2025.02.19
桐朋学園 桐朋小学校教諭:伊垣 尚人
思いやりの心や失敗を許せる寛容さを
──私も見させていただきましたが、ディズニーについて調べていたり、イラストやマンガを描いている子もいましたね。知識や勉強にはつながらなさそうなテーマでもよいということでしょうか?
伊垣先生:自学には、学びに対する主体性が育まれたり、表現力や思考力、まとめる力がつくなどいろいろなメリットがありますが、僕はそもそも何か“能力”を高めるために取り組むものではないと思っています。
これまで日本人は能力主義に縛られてきました。努力して成長し続けることが幸せにつながり、能力で勝ち負けが決まると思わされてきた。事実、社会のあらゆる面で格差が広がっています。どれだけ努力しても常に比較や競争にさらされ、多くの人が生きづらさを抱えています。
そうではなく、子どもたちにはお互いの個性や興味関心を面白がりながら、周りの人と「一緒に生きていく」経験を積んでほしい。食いっぱぐれないように「一人で生きていける力」をつけるのではなく、どんな自分でも、どんな人とでも「一緒に生きていける」ことを学んでほしいんです。
自分を語り、相手を理解する言葉が、互いの持つ「能力」ではなく、「好き」や「大事」だったら、もっと生きやすい社会になり、思いやりの心や、失敗を許せる寛容さも育っていくのではないでしょうか。自学がそのきっかけになったらいいですよね。
何かを学ぶことは遊びの延長だと考えています。「好き」を探究することで、「学ぶって楽しい」「もっと学びたい」と感じてもらえたらうれしいですね。
───◆─────◆───
実際のノートを見せてもらい、伊垣先生のクラスの子どもたちが自主学習を「好き」の延長として楽しみ、学び、成長している様子がうかがえました。自主学習そのものは一人で進めるものですが、それを共有し合うことでさらに意味のある取り組みになることもわかりました。子どもが興味を持って学んでいることを、大人も一緒に楽しみながら見守っていけるといいですね。
取材・文/北 京子
撮影/森﨑一寿美
自主学習の記事は全2回。
前編を読む。



北 京子
フリーライター。 藤沢市在住。食の月刊誌の編集者を経て独立。食を中心に、SDGs、防災、農業などに関する取材・執筆を行う。 3児の母。自然の中で遊ぶこと、体を動かすこと、愛犬とたわむれることが好き。
フリーライター。 藤沢市在住。食の月刊誌の編集者を経て独立。食を中心に、SDGs、防災、農業などに関する取材・執筆を行う。 3児の母。自然の中で遊ぶこと、体を動かすこと、愛犬とたわむれることが好き。





















![お年玉と一緒に贈りたい“お正月の絵本”3選[絵本専門店の書店員が選出]](https://d34gglw95p9zsk.cloudfront.net/articles/images/000/045/022/large/68833581-f835-4688-a9fe-33fa7156917c.jpg?1764905096)




























































































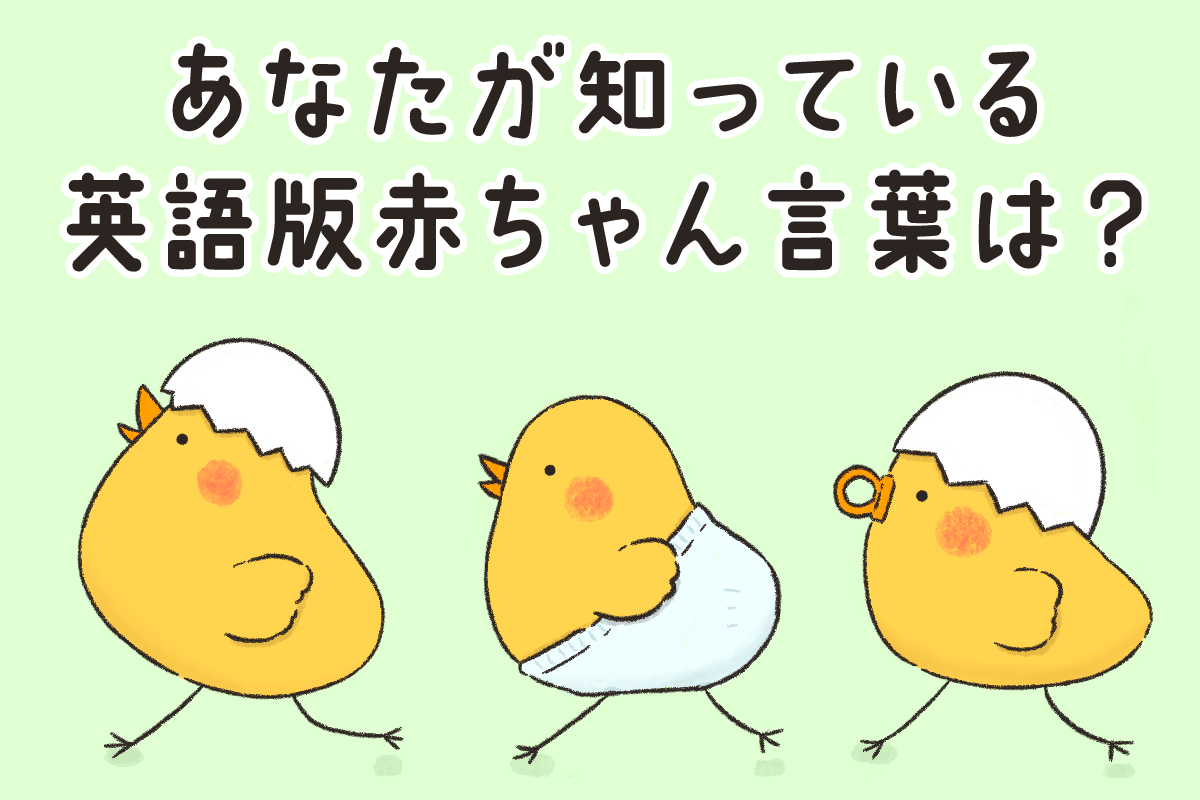





伊垣 尚人
1977年生まれ。YMCAのキャンプリーダーや不登校児童・生徒の学校復帰の支援活動などを通じて学校現場に興味を持ち、通信教育で教職の道へ。カウンセリングやファシリテーションを活かしたクラス経営により、子どもがオーナーシップを持ち、学ぶことを楽しむ授業づくりに取り組んでいる。 NPO法人Educational Future Center理事、西脇KAI代表幹事、Learning Association of Facilitative Teachers主催、日本イエナプラン教育協会会員。 主な著書に『子どもの力を引き出す自主学習ノートの作り方』(ナツメ社)、『子どもの力を引き出す自主学習ノート 実践編』(ナツメ社)他がある。
1977年生まれ。YMCAのキャンプリーダーや不登校児童・生徒の学校復帰の支援活動などを通じて学校現場に興味を持ち、通信教育で教職の道へ。カウンセリングやファシリテーションを活かしたクラス経営により、子どもがオーナーシップを持ち、学ぶことを楽しむ授業づくりに取り組んでいる。 NPO法人Educational Future Center理事、西脇KAI代表幹事、Learning Association of Facilitative Teachers主催、日本イエナプラン教育協会会員。 主な著書に『子どもの力を引き出す自主学習ノートの作り方』(ナツメ社)、『子どもの力を引き出す自主学習ノート 実践編』(ナツメ社)他がある。